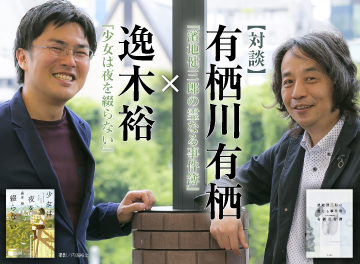【連載小説】その日、少年は〈力〉を受け取った。少女の死の真相とは? 青春ミステリの最新型! 逸木裕「空想クラブ」#1
逸木 裕「空想クラブ」

※本記事は連載小説です。
第一章 少女の死
1 8年前
雷がとどろく。
朝からずっと、空が壊れたんじゃないかと思うくらいの強い雨が降り続けている。普段住んでいるマンションは台風がきてもほとんど揺れないけれど、いまいる木の家は風が吹くたびにガタガタと鳴る。雨は銃弾のように降り注ぎ、屋根や壁を壊しそうな勢いで打ち続ける。
ぼくは廊下から、窓ガラス越しに空を見ていた。
ぼくはそこに、空想を描いた。
黒い空に、じわじわと一頭のキリンが浮かび上がり、その横にベンガルトラとマンドリルが現れる。三頭の動物は適度に距離を保って、嵐の中でくつろいでいる。ぼんやりと浮かび上がる動物たちを見つめていると、口元がゆるんでくる。だって、全部ぼくの好きな動物だから。
──あんまり自分の世界にこもるのはよくないよ。
自分の部屋や、出かけた先で空想をしていると、父さんや母さんに怒られることがある。でも、今日はそんな心配はない。だってみんな、ぼくに構っている暇なんかないもの。
と思ったところで、隣に
「
宮古島の
ぼくの父さんはここ宮古島の出身で、年末から正月にかけて毎年遊びにきている。空港に降りるたびに、埼玉では吹かない暖かい風に乗って、甘い匂いが漂ってくるのにびっくりする。あの匂いが果物のものなのか花のものなのか、何回きてもよく判らない。宮おじぃーに聞いても「
「
宮おじぃーは普段ぼくと話すときはそこまででもないのだけれど、酔っ払うと地元の言葉が強く出てくる。でも直接話していると普通に伝わるから、言葉って不思議だ。ぼくは首をぶんぶん振って、空を見上げた。
「雷がそんなに珍しいかい」
「ううん」
「お空がそんなに好きなのかい」
「ううん」
「じゃあ、何をしてるんだい」
「動物を見てるの」
「
そうだよと言って、ぼくはさらに空想を描いた。マンドリルの隣に、白いヤギがぼんやりと浮かび上がってくる。
宮おじぃーの家では昔から何頭かのヤギを飼っていて、庭の
その出来事があったのは、四歳のころだった。
一頭のヤギを、宮おじぃーが裏につれていくのを見た。お散歩でもするのかなと思ってついていったら、宮おじぃーは物置から大きな刃物を持ってきて、白い首にいきなり突き立てたのだ。
真っ赤な血が噴きだすのを見た瞬間、ぼくは気を失ってしまった。気がついたら翌朝になっていて、何も食べなかったからか、おなかがギュウギュウと悲鳴を上げていた。
宮おじぃーと父さんがやってきて、ふたりでぼくを諭してくれた。あんな場面を見せてしまってすまない。もっと周りを見ておくべきだった。でも、この家では何かお祝いごとがあると、ヤギを殺して食べるんだ。お前が普段食べている肉や魚もそうやって食卓に並んでるんだよ。
そのときはショックで言葉が素通りするだけだったけれど、それから一年くらいかけてだんだん受け入れられるようになってきた。翌年にきて見てみると、ただ優しいと思っていたヤギの目の中に「やれやれ仕方ないから食べられてやるぜ」というどこか悟ったような色を見ることができて、だから、空に浮かぶヤギも「やれやれ」という表情でぼくを見下ろしている。
「お空に動物が見えるのかい?」
「見えるんじゃないよ。空想してるだけ」
「空想するのが好きなのかい?」
ぼくは
物心ついたときには、ぼくはもう空想をしていた。欲しいものが買ってもらえなかったり、幼稚園で同級生に
晩ご飯を食べてから寝るまでずっと空想していることもあるので、さすがに父さんと母さんもおかしいと思ったらしい。変な子だと思われるから、表ではあまり空想のことを話すな。外の世界に、もっと目を向けなさい。よくそんなことを言われる。
でも、宮おじぃーなら大丈夫だろう。
と思っていたら、話が終わったときの宮おじぃーは、怖い顔になっていた。
「いつから、そういうことをしてるんだい?」
「うーん……判んない」
「気がついたら、空想ばかりしていたの?」
「うん、そう」
「一日、どれくらいそういうことをやってるの?」
「判んない。ずっとやってるときもある」
「そうか」
宮おじぃーは、硬いものを
「これは大事なことを聞くんだけど……もっと色々なものを、見てみたいかい?」
ぼくは首をかしげた。色々なもの?
「お前は見るのが好きなんだろう? 例えば、世界中のあらゆるものがもっとこう、くっきりと見えたら、いいと思わないか?」
どういうことなんだろう。もっとくっきりと見る? ぼくの空想とは違うんだろうか。
「難しく考えることはない。いまのままでいいのか、もっと色々なものを見られたらいいのか、自分にとって、どっちが楽しいと思うか、考えてみてごらん」
「じゃあ……見えたらいい、かな」
よく判らないけど、そっちのほうが楽しそうだ。
宮おじぃーは少し怖いくらい真剣な表情で、何かを考えている。そして、さっき嚙んだ硬いものを、飲み込むみたいに言った。
「お前はやっぱり、おじいちゃんの孫なんだな」
宮おじぃーは立ち上がり、廊下の向こうから折りたたみ椅子を持ってきた。ひときわ大きく雷の音が鳴って、廊下の蛍光灯がちかちかと瞬いた。
「おじいちゃんも、お前と似てた。子供のころから考えることが好きで、時間があったら色々なことを空想してた。おじいちゃんは、世界中を旅行してみたくてね。ピラミッドとか、ストーンヘンジとか、サハラ砂漠とか、行きたい場所がたくさんあった」
「旅行で行かなかったの?」
「行けなかったのさ。おじいちゃんがお前くらいのころ、この島は戦争でそれどころじゃなかった。いや、戦争が終わってからも、貧しくて、忙しくて……とてもそんな余裕はなかったなあ」
宮おじぃーは自分の右手を撫でる。中指の先が欠けていて、手の甲には水をこぼしたような形の大きな傷がある。なんでできたのかは聞いてはいけないと、父さんに言われていた。
「二十歳くらいのころ、おばあちゃんに会った。お前は、ユタって知っているかい?」
「ううん、知らない」
「沖縄には、ユタと呼ばれる人がたくさんいるんだ。お祈りをしたり、霊を
宮おじぃーは目を細める。
「おばあちゃんは、世界中にあるものをなんでも見ることができた。万里の長城だって、自由の女神だって、南極だって……出会って結婚するまで、おばあちゃんにそんな〈力〉があるなんて知らなかったから、びっくりしたよ。もっとびっくりしたのは、その〈力〉をおじいちゃんにくれるって言いだしたことだ」
「あげられるの?」
「おばあちゃんも、もともとはお母さんからもらったと言っていた。〈私はあんたと違って、そこまで見るのが好きじゃない。あんたなら、悪いことには使わないだろうし〉って言ってくれてね。信用してもらえて、
宮おじぃーの言葉が、象みたいに重くなった。
広間のほうから、大人たちの声が聞こえてきた。哀しいはずなのに、それを隠すためにわざと笑っているみたいな、明るくて暗い声。それをかき消すみたいに、雷が鳴る。
今日は、宮おばぁーの葬式だった。
宮おばぁーは昨日死んだばかりで、埼玉から急にきたのはお葬式に出るためだった。生まれて初めて着たブレザーのパリパリと固い感じが、まだ身体に残っている。
「〈力〉をもらうとき、おじいちゃんはおばあちゃんと一緒に、ひとつの空想を見た」
宮おじぃーは、遠くを見るような目になる。
「おじいちゃんが一番見たかった、
そのときの光景が、見えているみたいだった。
「空想が終わるとき、おばあちゃんはおじいちゃんのおでこに手を当てて、目を閉じろと言った。その通りにしたら……〈力〉が、使えるようになったんだ。それからは、本当に楽しかったなあ。毎日見たいものばかり見て、いい人生だった」
〈ひとつの空想を見た〉というのが、よく判らない。すぐに判るよという感じに、宮おじぃーはぼくの頭を撫でる。
「おじいちゃんも、そろそろ死ぬ」
「おじぃー、どこか悪いの?」
「もう年なんだ。この〈力〉は、それと一緒にこの世界から消えると思ってた。お前の父さんにあげようと思ったこともあったんだが、いらないと言われたしな。でも、お前の話を聞いて、気が変わった」
また、頭を撫でられる。宮おじぃーの手は枯れ葉みたいにかさかさしていて、撫でられると気持ちいい。
「いまからお前に、あげよう」
「いまから?」
「こんな日には、一緒に空想を見ることができるんだ」
「こんな日?」
「こんな、大変な日にはね」
雷が
「おじいちゃんと、手をつないでごらん」
ぼくは宮おじぃーの手を握った。いつの間にか汗で
「いま、何か見たいものはあるかい?」
「なんでもいいの?」
「ああ。それを見たいと、心の中で強く願ってごらん」
アフリカのサバンナが見たいと思った。
岩場にいるライオンの群れと、広い草原を歩き回るサイやカバやシマウマ。はるか遠くに広がる地平線と、大地と空が真っ赤に染め上がる、アフリカの夕焼け。
「目を閉じるんだ」
宮おじぃーの声が、少し怖い感じになった。ぼくは慌てて目を閉じる。
「普段、人間は、現実しか見ることができない。でも、本当は違うんだ。おじいちゃんもお前も、どんなものであっても見ることができる」
「この世界のあちこちには、たくさんの〈窓〉が隠されてる。そこを開くことができれば、お前は色々な世界を見ることができる」
魔法みたいに、その声が響いた。
「見えないものが見える。聞こえないものが聞こえる。そういう世界を空想できるかい?」
うん。
「見たいものを見たいと、願い続けるんだ」
サバンナを見たい。サバンナを見たい。
雨の音と、宮おじぃーの声に導かれるように、ぼくはその思いを唱え続けた。
雷が鳴った。
世界が裂けるほどの、巨大な雷の音が。
その瞬間──どこか遠くで、〈窓〉が開いた気がした。
ぎゅーんと、自分の手が伸びていく。いや、実際に伸びているわけじゃない。見えない手が、遠くにある〈窓〉に向かってするすると伸びていく、そんな感覚。
どこまでも伸びていった手は、やがて〈窓〉に触れた。その瞬間、視界に光が
何も見えなくなるくらいの、強い光だった。でも、太陽を見たときみたいに
光で真っ白になった視界に、少しずつ何かが見えはじめる。色や線が、世界が、あぶりだされていく。
そこで、ぼくが見たものは──。
▶#2へつづく
◎前編の全文は「カドブンノベル」2020年8月号でお楽しみいただけます!