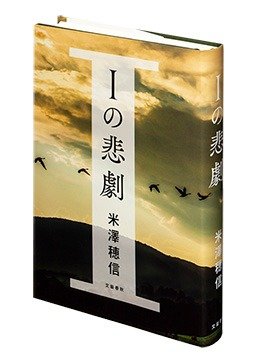【集中掲載 米澤穂信「花影手柄」】 城の東に織田方の陣を見つけた荒木村重は……。 堅城・有岡城が舞台の本格ミステリ第二弾!#1-7
米澤穂信「花影手柄」

>>前話を読む
6
勝ちであった。大津の陣は乱れ、荒木勢は思うさま手柄を挙げた。夜討ち勢は屋敷の庭に集められ、縁側に立った村重が「えいえい」と声を上げれば、ほかの者が「おおう」と音を伸ばして
武士は手柄を挙げそれを土地や名声に換えることで生きており、戦いが終わったのならば、誰がどのような手柄を挙げたのかを速やかに
雑兵足軽の類をいくら討っても、手柄にはならない。矢戦、鉄炮戦で上将を討っても、誰の矢玉が当たったかなど検めようがないため、手柄にはならない。戦で手柄を挙げる術は、まずは一番鑓や一番乗りを果たすこと。そして何といっても、おのが手で兜首を取ることだ。良き兜は身分ある武士の持ち物であり、兜を
陣幕のうちに
首実検が終わる頃、東の空は白みかけていた。
雑賀衆が取った首は、年寄りの首が一つ、若者の首が一つ。高槻衆の首もまったく同じ、年寄りと若者の首が一つずつであった。村重は、伊丹一郎左衛門が報せた大津勢百人たらずのうち、武士はさしずめ十人、多くとも十五人ということはあるまいと読んでいた。兜首四つはまずまずである。
本来首実検では、討ち取った武士の名前を書き取らなくてはならない。しかしあいにく、首が誰のものかはわからなかった。ふだん大津伝十郎は戦場に出ることが少なく、大津家中の顔や名前を知る者がなかったのである。このような場合に備えて
「存じませぬ。お許しを」
と繰り返すばかり。それで生虜は解き放ち、首帳には「兜首」とのみ記して、夜が明けたら城内に触れを出して大津勢の顔を知る者がいないか募ることになった。
首実検の後は、
手負帳が作られるあいだ、村重は屋敷の一室で酒を飲み、
「一郎左は気の毒なことでした」
千代保が落ち着いた声でそう言うと、村重は低く
「そうよな」
と応じた。
「儂をかばって死んだ」
「一郎左を討ったのは、素肌の武者であったと聞きました」
素肌とは鎧を身につけないことである。村重は黙って頷き、千代保は床に目を落とす。
「なにやら、
「……見ておったのか」
「はい。まざまざと」
村重は
いまを去ること五年、尾張国との境目にほど近い伊勢国長島で、多くの者が死んだ。長島城には一向門徒が立て籠もり、長年にわたって織田と戦っていたが、その年とうとう籠城衆は開城を申し出た。
千代保の父は、大坂本願寺の縁者だ。加勢として長島に入った父に従い、千代保はこのとき長島城にいた。素肌武者の戦いぶりを、千代保はおのれの目で見たのだろう。
「死に物狂いとは恐ろしいものだとつくづく思い知りました」
「まさにな。死兵ほど
村重はそれを承知であったから、大津の陣を四方から囲むことはしなかった。逃げ道が残っていれば兵は決死の覚悟を固めることはなく、まず逃げようとするからだ。たまたま村重の目の前にさまよい出た武者ひとりが死兵と化したのは、一郎左にとってまことに不運なことだった。しかし村重は、そうしたいきさつを千代保には語らない。手は打っていたのだと言えば、あまりに言い訳めく。
「一郎左は良き武士でした」
「良き武士であった」
御前衆は村重の身のまわりを警固するため屋敷に上がることも多く、千代保とも顔を合わせることがある。戦で人が死ぬのは当たり前だが、それで愛別離苦が消尽するわけもない。村重は勝ち戦を祝い、同時に、千代保の心痛を思う。
障子の外で鎧が鳴る。
「申し上げます」
郡十右衛門の声であった。
「何事か」
「雑賀衆下針、戻りましてござります。殿に言上仕りたき儀があると申しておりますが」
「わかった」
村重が盃を置いて立ち上がる。千代保は頭を垂れ、村重を見送った。
下針は額と肩に布を巻かれていた。血が滲み、庭に置かれた戸板に寝そべっている。同輩の雑賀衆はもちろん、高槻衆、それに御前衆も、下針を遠巻きにして様子を見守っていた。村重が縁側に現われるとかれは苦しげに半身を起こそうとするが、村重に「そのままでよい」と言われ、ばたりと体を横たえる。それでも気丈に、
「不覚を取り申した。鉄炮は斬り合いに向きませぬな」
と
下針の傍らでは、鈴木孫六が膝をついている。孫六はいつも通り苦虫を嚙みつぶしたような顔で、ちらりと下針を見て言った。
「この者が敵陣に躍り込んで兜首に鉄炮を撃ちかけた後、横合いから額を切られるところを見た者がありまする。
村重は頷いた。
「わかった。下針、よう働いた」
それを聞き、下針は真顔になって言う。
「直々の御言葉、かたじけのうござる」
「お主、儂に言いたいことがあるとか。許す、言うてみよ」
「さればその事」
傷が痛むのか顔をしかめ、下針は声を励ます。
「それがしが目を覚ますと、敵陣は蜂の巣をつついたような騒ぎにござった。見つかってはかなわじとしばし葦の中に身を潜めており申したが、その間にそれがし、御大将お討ち死にと言い交わす声をしかと聞いてござる」
おお、というどよめきが上がった。村重も太い眉をぴくりと動かし、我知らず、
「なに」
と聞き返す。
「間違いござらぬ。敵方の
御大将と言えば大津伝十郎長昌のことであろう。夜討ちの中で大津を討ち取っていたとなれば、これは望みもしなかった大勝である。老武者が退き陣の指図をしていたというのも、討ち死にした大津に代わって命を下していたのだと考えれば筋が通る。村重はすぐに十右衛門の名を呼んだ。駆けつけ
「聞いたか。敵陣を
十右衛門は夜通し戦った疲れも見せず、かえって
「かしこまってござりまする」
と答え、ぱっと駆け出した。
下針は養生のため天守へと運ばれていく。残った兵たちが囁き合う声が村重の耳にも届く。
「まことか」
「われらは敵大将を討ったのか」
「首は四つであったが」
「大津殿は若年、二つは
「ならば……」
村重も、心のうちでは同じことを考えていた。若武者の首は雑賀衆が一つ、高槻衆が一つ挙げている。本当に夜討ち勢が大津伝十郎を討ったのであれば、そのどちらかが大将首であろう。
どちらか。大手柄を挙げたのは、雑賀衆か、高槻衆か。
首は未だに、首実検を執り行った陣幕の中に残されている。村重が何となくそちらを見ると、居並ぶ将卒もつられて同じ方を向く。白みゆく空の下、陣幕は月の残光に照らされてそこにあった。