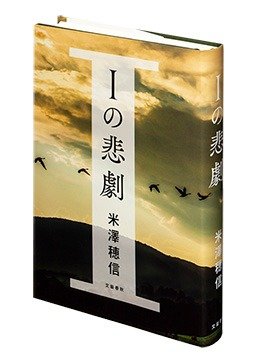【集中掲載 米澤穂信「花影手柄」】 城の東に織田方の陣を見つけた荒木村重は……。 堅城・有岡城が舞台の本格ミステリ第二弾!#1-8
米澤穂信「花影手柄」

>>前話を読む
7
長い夜が明けた。
本曲輪の門が開き、雑賀衆、高槻衆、御前衆から選りすぐられた夜討ち勢は各々のねぐらに戻っていく。それと入れ替わりに本曲輪には中間どもが戻って、馬の世話や屋敷の掃除など日々の雑務に取りかかる。
村重はひとり、陣幕の中で首と
皺首は考えに入れない。首の主はいずれも名のある武士ではあったのだろうが、大津伝十郎長昌ではない。雑賀衆が挙げた首は地を睨み、細面で唇薄く、眉は細く、鼻は高かった。高槻衆が挙げた首は天を睨み、頰はふっくらとして唇厚く、眉は濃く、鼻が大きい。信長は自らの側に美童を置く癖があり、いまこの二つの首を比べれば、雑賀衆が挙げた首の方が見栄えがする。しかし同時に、大津伝十郎は一手を率いる将であった。高槻衆が挙げた首は首まわりが堂々と太く、生前はさぞ武士らしい体つきであったのだろうと思わせる。どちらの首も、死に臨んで潔く覚悟を決めたのか、穏やかと言っていいような形相をしていた。それぞれの首にはうっすらと髭が生えており、男の首であることは間違いない。それで、どちらが大津の首か。村重はじっと首を睨む。
郡十右衛門はまだ戻らない。村重はやがて屋敷に戻り、少し眠る。
村重は夢を見た。
夢の中でかれは小さな舟の中にいた。千代保もその舟に乗っている。見れば鈴木孫六も、高山大慮も、郡十右衛門も、伊丹一郎左衛門も乗っている。舟はいま伊勢長島城を出たところであった。織田との和睦が成り、村重たちは城を出て落ち延びるところなのだ。
「難しい戦にござりましたな。されど、それももう終いにござる」
そう言って笑った船頭は、上津山太夫であった。舟は海を渡り、どこへ行くのだろう。見まわせば何十
そして、そうなった。波打ち際に並んだ鉄炮衆がいっせいに火蓋を切る。あたりはいつの間にか日が落ちて、火縄の火がさしずめ蛍のように揺らめいている。鉄炮奉行は大津伝十郎である。村重はその顔を見ねば、と舟から身を乗り出すが、どうしても見ることが出来ない。それなのに、大津がにやりと笑ったことだけははっきりとわかった。
鉄炮が放たれ、たちまち海は阿鼻叫喚の地獄と化す。十右衛門が胸に穴を開けて斃れた。一郎左が首から血を吹きだして斃れた。上津山太夫はいつの間にか総身に刀と鑓を受け、それでも笑って舟を漕いでいた。千代保はどうしたか、と村重は首を巡らせる。千代保は舟の中で正座し、幾十発もの銃弾を浴びて、微笑んで言った。
「なにやら、長島を思い出しまする」
城が燃えている。見ればそれは長島城ではなく、摂津国伊丹の有岡城ではないか。燃える城から首が笑いながら飛んでくる。鈴木孫六は数珠を繰り、高山大慮は十字架を掲げて、あの首を挙げたのはわれらだと言い争う。首は村重の喉元に迫っている。
「殿。……殿」
部屋の外から中間が呼んでいる。村重はふっと目を覚まし、額を拭って言う。
「何か」
「郡十右衛門様、お戻りにござります」
村重は我に返り夢を忘れた。半身を起こし、障子を開けて外に出る。日はまだ東にあった。
広間で十右衛門に会う。十右衛門は、昨日の伊丹一郎左衛門そのままに泥まみれであった。一郎左は陣夫に化けたため土に汚れるのはもっともだが、十右衛門の姿は合点がいかない。村重は眉を上げ、
「その姿はいかがいたした」
と訊く。十右衛門は平伏し、「申し訳ござりませぬ」と
「鎧剝ぎに遭い、斬り合いましてござりまする。三人ばかり斬り申したが仲間を呼ばれ、しばし葦原に隠れておりました。この汚れは、葦原に伏せたため」
「そうか」
死者の武具を剝いで売る落ち武者狩りは、合戦が終わればどこからともなく現われる。しかし大津の陣が健在であれば、落ち武者狩りは出てこられまい。十右衛門が襲われたという一事をもって、村重は十右衛門の口上が半ばわかったような気がした。
「それで、敵陣はいかに」
「下針の申す通り、敵方は陣を引き上げてござりまする。武具兵粮もずいぶん残ってござれば、よほど急いで退いたものかと」
「大津は」
「兵粮を盗まんとしておった陣夫を見つけ聞きただしたところ、たしかに大津勢は、大将お討ち死にと言い合って引き上げた由」
万に一つ、下針の話は戦場から逃げた言い訳の作り話という考え方もなくはなかったが、十右衛門の復命でそれも消えた。夜討ち勢が大津伝十郎を討ち取ったことは、もはや疑いない。
「よし」
下がれと命じかけて、村重はふと、十右衛門ならばあの首をどう見るかを聞きたくなった。
「十右衛門、ついて参れ」
と命じ、中間に草履を出させて庭に下りる。桜の下の陣幕へと向かいながら、村重は訊く。
「大津の首は、ほかの首とどう違うか」
主が尋ねていることの意を悟り、十右衛門は慎重に答える。
「さ。……大津殿は前右府の
「む。兜か」
兜の善し
首がかぶっていた兜が首実検に持ち出されることはなく、ゆえに村重はそれを見ていない。兜は分捕品として雑賀衆と高槻衆それぞれの誰かが持っているはずで、見せろと命じることは出来る。村重は十右衛門に兜を持ってこさせようとして、やめた。十右衛門は全く休んでいない。使番には別の者を立てるべきだろう。
村重が陣幕に近づくと、十右衛門がそれをまくって開ける。首台の上に首が四つ、村重たちに後ろを向けて据えられている。
「内側の二つは老武者の首よ。大津の首は右端か、左端。十右衛門、心して見よ」
「は」
村重主従は首台をまわり込み、四つの首の前に立つ。その途端、郡十右衛門が「あっ」と叫んだ。村重もまた目を
村重が最後に見た時、若武者の首はどちらもたしかに尋常の顔つきをしていた。しかしいま、若武者の首の一つは
戦には様々な吉凶がある。日取りにも食にも、落馬の仕方にさえ吉と凶がある。討ち取った首の形相にもそれはあり、両眼を穏やかに瞑っている首が吉とされる。異相の首を凝視し、十右衛門が声を震わせる。
「殿、これは、この首は……大凶相にござる!」
村重の目には、首がにやりと笑ったように見えた。
(この続きは「カドブンノベル」2020年2月号でお楽しみください)