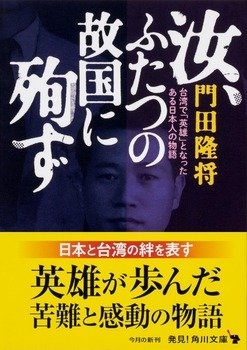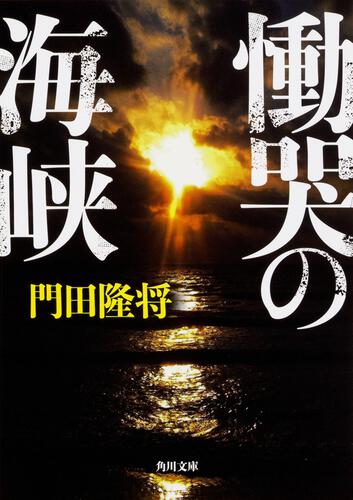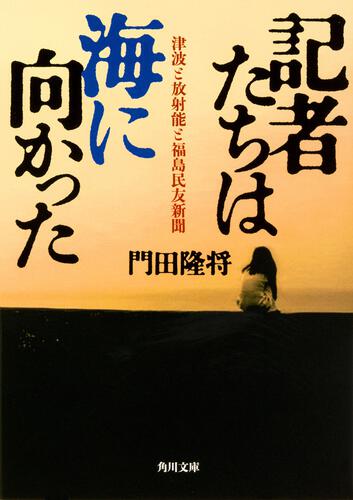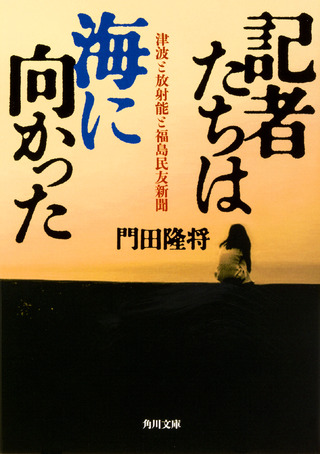文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(評者:
たしか2016年の暮れか、年が明けてすぐのころだったと思う。上海市内の小さな事務所で僕は、この本を手にしてページをめくりながら、不覚にも涙が
僕は2018年まで10年にわたって、上海を拠点に香港やマカオも含んで中国全土をカバー範囲にした新聞社の特派員だった。
目撃し、写真を撮り、記事を書いた現場で、心をえぐられたのは、2010年と2012年に各地で、日本人や日本関係の施設が次々と襲われた反日デモ、そして2014年に香港で起きた学生らの民主化要求デモ「雨傘運動」だった。
根源をたどればいずれの出来事も、民主社会に
徳章の時代、台湾を支配した中国国民党の強権による惨殺、知識人の粛清、1987年まで実に半世紀近く続いた戒厳令による自由の
厳格な警官だった日本人の父、美しくも気高かった台湾人の母のもとに生まれた徳章は、まぎれもなく民主社会の一員であった。
その社会に生きる人々を守り抜くための頑強なる信念と、
戦後台湾を統治した中国国民党という存在は、中華人民共和国を現在、統治している中国共産党とは「双子の政党」と称される。
表面的なイデオロギーこそ異なれど、人権意識の欠如や剝きだしの残虐性、すべてを私物化し、自己正当化しようとする
台湾の元総統、
だが、彼らが銃を手に統治者となってしまった現実がある。強大な軍事力を備え、民主社会を力でねじ伏せようと試みている現在の中国を思い出すがいい。
上海の事務所には中国人の女性スタッフが1人だけ勤務していた。中国の公安当局とも連絡のある、事実上の監視員に近い存在といえたが、すこし離れた席にいた彼女に気づかれないようにページをめくった。
この本は中国への入境時にみつかれば、没収の対象だろう。手荷物で
それでも僕が涙を止められなかったのは、このシーンだ。中国国民党の横暴に耐えきれなくなり、
「会場は、ざわざわとし始めた。学生たちが一直線に目指している政権打倒など、はかない夢にすぎず、為政者である中国人が、想像をはるかに超える危険な体質を持っていることを、経験者である弁護士が告げているのである」
「この為政者のもとで『人権』というものをどう守っていくか。それがいかに大切か、
「絶対に軍の介入を許してはならない。国民党軍の精鋭が台湾に大挙、やって来ることはなんとしても避けなければならない」
このシーンに僕は、ふたつの映像が重なった。徳章と李登輝、そして台南の学生と香港の学生の姿だ。
徳章が生まれた16年後に台湾の北部、
あの台南の学生のほとんどは当時、日本統治時代の日本教育を受けたはずだ。
李登輝はこれを、
徳章が筆者の
「政府転覆など到底無理であることはわかっている。現行政組織の下で台湾人の人権を確立することが、当面の課題なのだ。今回不幸にも起こってしまった騒動に対する『報復』だけは回避しなければならない」
徳章の
香港で2014年の「雨傘運動」に身を投じた学生も、2019年に香港警察に人権
歴史の偶然で李登輝が中国国民党という統治者の中から、握った権力とカネを使って独裁政権を内側から
日本人も台湾人も、あるいは香港人も実際、お人よしだ。「誠意」ある「話し合い」さえあれば、中国共産党も分かってくれる、あるいは分かってくれるはずだ、と考えている。もちろん「対話」によって衝突を回避できることが、最高の外交であり、日本も台湾も戦後必死に、綱渡りで対話を繰り返してきた。これからもそうなのであろう。
だが、国連にも登録された中英共同声明に明記された「一国二制度」で保障した香港の高度な自治や言論の自由、民主制度などを次々と
本書に描かれた戦後台湾の2・28事件や白色テロは、中国共産党と双子の政党である中国国民党の人々が、わずか数十年前に現実に引き起こした惨状だ。日本にも明らかに「文明の衝突」の危機が迫りくる。
香港が陥落し、台湾が中華人民共和国に併合される事態となれば当然、中国共産党の狙いは沖縄に、九州に移る。「そんなはずはない。国際社会の監視がある中で、中国共産党だってそんな恐ろしいことはできやしない」と思う日本人が95%かもしれない。香港が白色テロの時代に進まないことを強く祈っている。
2019年12月7日のこと。台南市内で映像会社が12月10日の「世界人権デー」を前に、こんなシーンを撮影した。人権弁護士の湯徳章が「坂井徳章」と書かれた細長い板を背負わされ、中国国民党軍のトラックに乗せられて「
徳章は中国国民党の兵には理解できない地元の台湾語で、天まで届こうかという大声で叫んだ。「私を縛りつける必要はない! 私には大和魂の血が流れている!」。集まってきた台南の人々の魂が震えた。最後に日本語で「台湾人、バンザーイ!」と叫ぶ。ふたつの故国に殉じた徳章の気迫はこの瞬間、神になった。
父親の坂井
壮絶な拷問を受けながらも徳章は、中国国民党に立ち向かった台南の若者らの名をひとりとして口に出さなかった。台南において台北や高雄などに比べて知識人への殺戮が少なかったのは、徳章の気迫によるところが大きい。徳章の心にはずっと父の徳蔵が寄り添っていたはずだ。この日の撮影シーンを徳章の息子である、
▼門田隆将『汝、ふたつの故国に殉ず 台湾で「英雄」となったある日本人の物語』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321909000203/