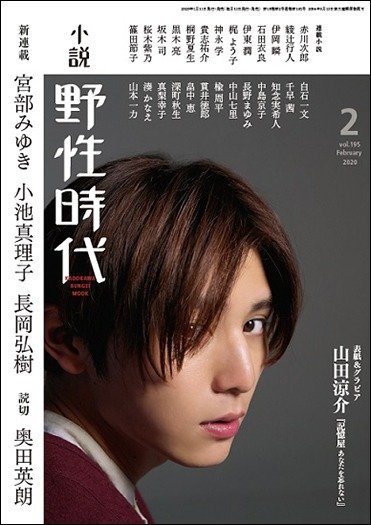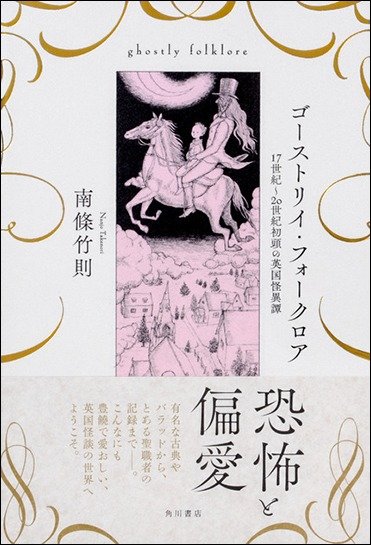1 月 11 日(土)発売の「小説 野性時代」2020年2月号では、小池真理子さんの新連載「アナベル・リイ」がスタート。
その冒頭を公開します!
……月照ればあわれ
麗しのアナベル・リイは私の夢に入る。
また星が輝けば、
私に、麗しのアナベル・リイの明眸(ひとみ)が見える。
エドガー・アラン・ポオ「アナベル・リイ」より。
(阿部保・訳 彌生書房刊)
[序]
これからここにまとめようとしているものは、単なる手記ではない。
少なくとも私は手記を残そうとする者にありがちな自己陶酔、隠しきれない自意識をひとつも持ち合わせてはいない。少しでもそうしたものがあったのなら、どれほど救われていただろう。
たった一日、いや、わずか数時間とて忘れていられたためしがなかった。何かに夢中になっていたり、楽しい冗談を口にし、親しい人と笑い合っていたりしている時ですら。眠っている時でさえ、それは意識の奥底にこびりついていた。忘れられずにいること、怯え続けることが私の人生だった。
そんな人生を手記にまとめてどこかに発表するなど、想像しただけで恐ろしい。私は何も、他者に向かってとっておきの秘密を打ち明けたいと思っているわけではない。できることなら、私は私自身の身におこったことから永遠に逃れていたいのだ。
にもかかわらず、私は今、こうして書き始めている。手記とも記録ともつかないものを。現代ふうに言えば、長く果てしなく続くツイート(つぶやき)を。一部の人にとっては、ばかばかしい世迷い言、愚かな錯覚にしか過ぎないかもしれないことを。
とうに還暦を過ぎた。生きた時間よりも、残された時間のほうが圧倒的に短くなった。いずれ私が死ねば、脱け殻と化した私の肉体と共にこの奇怪なできごともきれいさっぱり焼き尽くされる。私の記憶……いつ果てるともなく続いてきた怯え、恐怖、不安に苛まれた日々にも幕が下ろされる。ジ・エンド。そうなれば、私にも長い間、待ち望んでいた平穏が訪れることだろう。
どのみち、人に気軽に打ち明けることができるような話ではない。もし私がこのことを人に話したら、ということは数えきれないほど何度も想像してみた。
相手は眉をひそめ、沈鬱な表情をしながらも、とりあえずは最後まで聞いてくれるだろう。気の毒な人間を見るような視線を投げてくるだろう。やがて私は悲しげな口調で言われるのだ。あなたは心を病んでいる、自分で作り出した錯覚から逃げ出せなくなっているだけなのだ、と。
私は必死の形相で、違う、違う、これは事実あったことなのだ、私はまぼろしの話をしているのではない、本当のことを言っているだけ……と繰り返し、叫び、相手ににじり寄っていったあげく、泣きだしてしまうかもしれない。
それが怖くて、これまで誰にも話せなかった。本当に誰にも。
私が死ねばすべては無に帰す。何もかもが、痛くもかゆくもなくなる。忘れるも忘れられないもなく、すべての記憶は一切合切、消滅する。
だが、同時に、この説明のつかない事実もまた簡単に、塵芥のようになって消えてしまうのだ。どうにも説明がしにくいのだが、そのことが私には悔しい。口惜しくてならない。
私の死後、何年かたって、この文章に目をとめてくれる人が現れる可能性がある。その「誰か」は、もしかすると、この一連の不可解な出来事を客観的に分析し、うまくいけば科学的な立証を試みてくれるかもしれない。長く私を脅かしてきたものが、恐れるに足りないものであったと、あの手この手で証明してくれるかもしれない。なんだ、そういうことだったのか、とわかる時がくるのかもしれない。
だが、運よくそうなったところで、その時はすでに、私自身は冷たい石の下の冷え冷えとした骨壺の中に詰めこまれた、無機的な物質と化している。わかったとしても何もできやしない。しかし、それでも、ひょっとして「あの世」があれば、私は「そうか、そうだったのか」と得心できるではないか、という、馬鹿げた、幼い、しかし、私なりに真剣な夢を捨てきれずにいる、というわけなのだ。
▶このつづきは「小説 野性時代」2020年2月号でお楽しみください!
https://www.kadokawa.co.jp/product/321901000096/
※リンク先:「野性時代」2月号 KADOKAWAオフィシャルページ
関連記事
- 小池真理子『異形のものたち』インタビュー 甘く冷たい恐怖が本能を歓喜させる、大人のための怪奇幻想小説。
- 【レビュー】怖いけれど温かく、懐かしい。恐怖小説の名手による最新傑作集。『異形のものたち』
- (レビュアー:小池真理子)凍った月の冷たい光 『月』