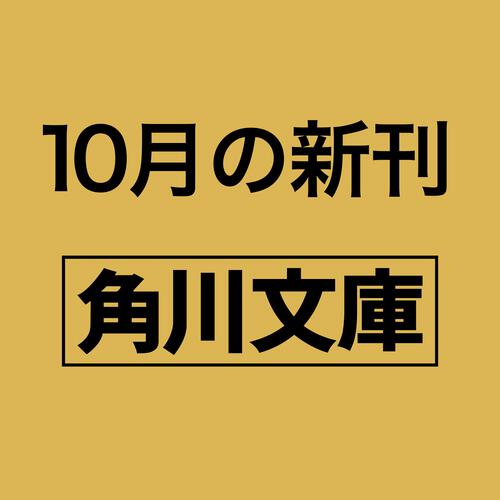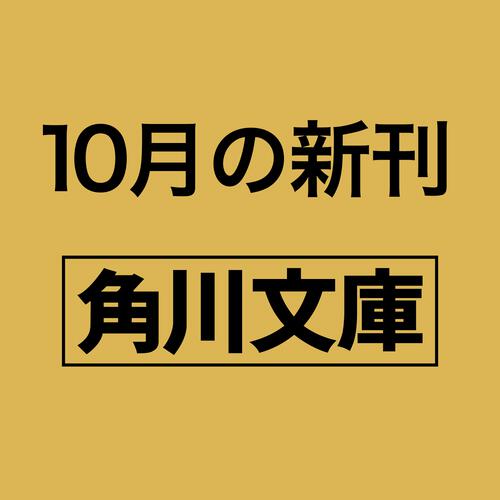火坂雅志『臥竜の天』上・下(角川文庫)の刊行を記念して、下巻の巻末に収録された「解説」を特別公開!
火坂雅志『臥竜の天』文庫巻末解説
解説
圧倒的なパワーを備えた物語である。長大な物語であるにもかかわらず一気
書評や解説の仕事をしていると、デビュー作との出会いが、作者との縁を取り持ってくれることがある。そのデビュー作が斬新な着想と、豊かな物語性を備えていればなおさらである。まさに作者の『花月秘拳行』(一九八八年)との出会いはそうであった。
八四年に
しかし、二作目の『花月秘拳行2 北斗黒帝篇』(一九九三年に『続・花月秘拳行』に改題)と三作目の『骨法秘伝』を見ると作者がスーパー伝奇ものに活路を
理由がある。作者はデビュー作から執筆の舞台がノベルスであった。ノベルスはハウツーものを除けば推理小説によって支えられてきた。しかし、文庫がジャンルの拡大を図るに及んでノベルスのポジショニングは極めて不安定なものとなった。活路を求めたのがスーパー伝奇であった。スーパー伝奇とはSF、推理、冒険、歴史、格闘、チャンバラなどの要素をごった煮にしたエンターテインメントである。作者はデビュー当時から時代小説の新しい書き手としての独自性をどう打ち出すかという命題を抱えていた。この問いの答えがスーパー伝奇の書き手としてひた走ることであった。
八八から九八年の十一年間ノベルスを書き続けることで、物語性の豊かさと、起伏を付ける展開の技術を体得し腕を磨いてきた。特筆すべきことは、『西行桜』、『利休椿』、『桂籠とその他の短篇』(二〇〇二年に『桂籠』に改題)で、短編の名手であることも証明したことである。確実に成熟の一途を
『全宗』については、『臥竜の天』で重要な位置づけを持った作品なので改めて解説するが、『全宗』以降の活躍には目を見張るものがある。戦国時代を独自の価値観を持って駆け抜けた
興味深いのは作者を“時の人”として全国的な有名人にした『天地人』と並行して連載されていたことである。周知のように同書は二〇〇九年にNHK大河ドラマとして放映され人気を博した。“愛”をトレードマークとした
「僕は、泳ぐことを止めたら死んでしまう回遊魚と同じなんだよ。小説が書けなくなったら、もう生きている意味がない」
という強烈な印象を与える言葉を紹介している。作者自身が古今東西の歴史を回遊していた回遊魚そのものであった。長く留まり精魂を尽くして書き継いだのが、時代のはざまで、向かい風をものともせず
本書の読みどころを紹介する。
第一は、政宗の成長過程を、大胆な柄と細やかで
ちょうど手元にあった朝日新聞社編『朝日日本歴史人物事典』を引いてみたら、全宗のことを次のように紹介している項目を見つけた。
施 薬 院 全宗 戦国・安土桃山時代の医者。本姓は丹 波 、号は特運軒、近江国(滋賀県)甲賀郡に生まれ、幼くして父を失い比叡山薬樹院の住持となる。織田信長の叡山攻め後に還俗して曲 直 瀬 道 山 の門に入り、医を学んで豊臣秀吉の侍医となり、施薬院の旧制を復興、京都御所の一画(烏丸一条通下ル中立売御門北側)に施薬院を建て、施薬院使に任ぜられて、庶民の救療に当たった。子孫は施薬院を家姓とした。秀吉の側衆としても重用され政治にも参画した。京都で没し比叡山に葬られたが、現在は施薬院家代々の葬地十 念 寺(京都市上京区)に墓がある。
独自の解釈を施し特異なキャラクターに仕立てることを得意とする作者は、戦国時代
最も重要なのは、秀吉の誇大妄想によって多くの将兵が命を落とした朝鮮出兵の無意味な失敗から、武力で人々を屈服させることの限界と虚しさを学び、領民が安心して暮らせる平和な国作りこそ、これからの自分の仕事だと会得したことだ。
第二は、政宗の生涯に
秀吉と
「そなた自身が、生きて考えることだ。けっして、生き急いではならぬ。そなたはまだ、二十五であろう。水は曲がりくねりながら、なおも流れる。そのこと、心にとどめておかれるとよい」
この言葉は政宗の心に刻み込まれる。
関白秀次の動向を凝視する政宗の行動と心情はすさまじい気迫に満ちている。政宗は、秀次との交わりを深めることで、天へ駆けのぼる
大久保長安は金銀山の開発に成果を挙げ、徳川幕府財政基盤の拡充に貢献し、経済政策の担当者であった。敵の弱点をいち早く察知し、
政宗の生涯の大半は戦場が舞台であった。それだけに戦場で渡り合った宿敵とのエピソードは、リアルで迫真性を
第三は、魅力的な脇役の存在である。筆頭は
歴史上の著名な人物を、斬新な着想を駆使して新たな解釈を施し、歴史の行間を渉猟させるという手法は作者の独壇場といえる。本書に登場する
作者の奔放な想像力に脱帽である。
作品紹介
書 名: 臥竜の天 上・下
著 者:火坂雅志
発売日:2025年10月24日
著者没後10年、『虎の城』に比肩する歴史巨編!
著者没後10年、『虎の城』に比肩する歴史巨編!
「圧倒的なパワーを備えた物語である」(解説より) 文芸評論家 菊池 仁
天下統一をなした豊臣政権は栄華を極め盤石に見えたが、朝鮮出兵や継嗣問題をめぐり翳りが射し始めた。やがて秀吉亡き後、石田三成と徳川家康によって天下を二分する戦いが勃発。東北の地から中央を見据えていた伊達政宗は、その隙をつき、さらなる領土拡大を図る。だが関ケ原の戦いで早期の決着がつき、次の天下人となった家康に不興を買ってしまう……。戦国の世をしぶとく生き抜き、最期まで天下を見つめた政宗の苛烈な生涯!
上巻詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000516/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
下巻詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000517/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら