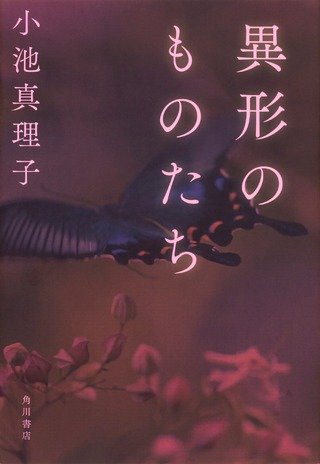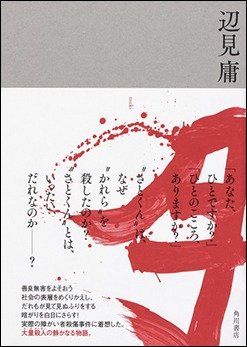インタビュー 「本の旅人」2017年12月号より

小池真理子『異形のものたち』 甘く冷たい恐怖が本能を歓喜させる、大人のための怪奇幻想小説。
撮影:ホンゴ ユウジ 構成:朝宮 運河 取材・文:東 雅夫
自身初の怪談作品『水無月の墓』を発表してから二十年余り。怪談を書くのは、仕事というよりも趣味、と語る小池さんの最新作『異形のものたち』について、怪談専門雑誌『幽』の編集顧問を務める東雅夫さんが切り込みます。
怪談は昔から大好き、仕事というより趣味です。
── : 最新作の『異形のものたち』、夜中に読んでいて震え上がりました。小池さんの怪談は初期からずっと拝読していますが、近年の『怪談』あたりからいよいよ怖さが増しているような気がします。
小池: ありがとうございます。幻想怪奇もののオーソリティにそう言っていただけるのは嬉しいですね。わたしにとって怪談を書くのは、仕事というよりも趣味なんです。他のジャンルの作品だと書き上げてからも、あそこはもっと上手く書けたかな、と反省点が浮かんでくるんですけど、怪談はただただ書いていて楽しい(笑)。日本的な怪談に初めてトライした『水無月の墓』から二十年以上も経ちますし、人生の大波小波を経て書き手としての腕も多少は上がっているんでしょうけど、書きたいものを好きに書いているというスタンスは変わっていないですね。
── : 本当にこのジャンルがお好きなんだなということは、拝読していてよく分かります。
小池: そうですね。夏目漱石や内田百間が書いていたような不思議な味わいのある短篇、それと英米の怪奇幻想小説と呼ばれるものは、昔からとにかく好きですね。
── : 『異形のものたち』は六篇を収めた短篇集ですが、このタイトルにこめられた思いとは?
小池: 「異形のものたち」というタイトルの作品は収録されていないんですが、考えてみれば六篇すべてになんらかの異形が登場していますし、総タイトルとしてしっくりくるんじゃないのかなと。怪談やホラーのファンには、一目でどんな本なのか伝わりますしね。もともと「異形」や「異界」といった言葉の響きが好きで、タイトルに使いたいとは考えていたんです。
── : 異形というのは、お化けや幽霊に近いようなニュアンスですか?
小池: この種の作品を書くときに意識しているのは、この世ならざる存在を出そうということ。そうはいっても妖精や怪獣、怪物が出てくるような作品は、わたしの資質とはどうも合わないみたいで。だから結局は幽霊ということなんだろうと思いますね。生者のすぐ隣にいるこの世ならざる存在。イコール異形のものたち、という感じですね。

死者たちに感じる、「身近さ」と「懐かしさ」。
── : 収録順に作品内容についてうかがいます。巻頭作「面」は、遺品整理のために田舎町の実家に帰ってきた中年男性が主人公。小池さんの怪談において、〝家〟は重要なモチーフですね。
小池: ええ、いつも何かしらの形で出てきますね。父が転勤族だったもので、子供の頃から全国を転々として、暮らした社宅や借家がたくさんあるんです。引っ越すたびに家が変わって、毎回違う匂いや空気に触れていた。そういう子供心に刻まれた印象や関心が、いまだに強く残っているんだろうなと思います。以前書いて評判のよかった「命日」という短篇も、高校時代に父の転勤で引っ越した家が舞台なんですよ。あまりに妙な雰囲気が漂っていて、とりわけ母が耐えられなくなって、荷物も解かないまま、すぐに引っ越してしまいました。
── : 最近お出しになったエッセイ集『感傷的な午後の珈琲』にも、「死者と生者をつなぐ糸」と題して、不思議な実体験を紹介されていますね。日暮れの別荘地でいるはずのないお母様をご覧になったというエピソードは、まさに「面」の一場面のようです。
小池: 亡くなった母に関しては、本人がいわゆる〝見える〟人だったというのもあって、本当にいろんなエピソードがあります。作品にもずいぶん使わせてもらいました。
── : 続く「森の奥の家」は別荘地が舞台です。主人公の女性が訪れるいわくつきの山荘が、居心地のよさそうな空間として描かれているのが印象的です。
小池: たとえ荒れ果てた廃屋であっても、死者たちにとっては懐かしく、心安らぐ空間であるかもしれません。わたし自身も死んだら懐かしい場所に居座って、生前親しかった人たちを呼び集めて、ゆっくり体を休めたいなと思っているんです(笑)。そんな願望が表れた作品ですね。このパターンの作品はこれまでにも何度か手がけていますが、たぶん自分でも好きなんだと思います。
── : 死者が安らぐ場所といえば、小池さんはお墓好きでもあるんですよね。
小池: 大好きです。外国に行くと必ずその国のお墓を訪れるようにしています。生者と死者が共存している空間というのが好きなんですよ。死者をどう弔うかは国や文化によって違いますし、外国の墓地は美術的にも見応えのあるところが多いんです。現地のガイドさんには「お墓ですか?」と呆れられますけど(笑)。
── : 三話目の「日影歯科医院」では、住宅街にたたずむ古風な歯科医院が舞台となります。
小池: 昔の歯医者さんって独特な雰囲気でしたよね。普通の住宅を改装したような造りで、洋風の扉を開けると昼間でも薄暗くって。そういう歯医者さんに子供時代よく通ったので、舞台にしてみたいと思いました。一種のノスタルジーですね。「日影歯科医院」というタイトルは、突然頭に浮かんできたのをそのまま使ったんです。
── : 主人公は離婚によって傷つき、東京から地方に越してきた女性です。毎回、主人公のプロフィールはどのように決めているのですか?
小池: わたしの好む主人公のタイプっていうのがあるんですよね。孤独をよく知っていて、一人になることをいとわず、世間とうまく折り合っているように見えて、自分がどこか世界とずれているという感覚を持ち続けている。明るくて元気いっぱいという主人公は、男女問わずまず出てきません。これは他のジャンルでも基本的には同じです。怪談だから特別なパーソナリティを作りあげている、というわけではありません。
── : 「ゾフィーの手袋」は海外赴任していた日本人を追ってオーストリア人女性の幽霊が東京郊外の住宅地に現れるという、小池版『舞姫』とでも呼ぶべき作品。
小池: いえいえ、そんな高尚な動機ではないんです(笑)。短篇の締め切りが迫ってきて、いいアイデアはないかと頭を悩ませていた時に、ちょうど軽井沢駅の新幹線のホームで痩せた外国人女性を見かけたんですね。病気をしているのか隣の男性にずっともたれかかっていて、春なのに白い手袋をつけていた。その姿が印象に刻まれたので「よし、これで一本書いちゃおう」と。
── : 珍しいタイプの怪談でありながら、しっかり怖いのがお見事ですね。クライマックスの箪笥のシーンのおぞましさといったら!
小池: そもそも仏壇にお線香をあげているような日本家屋に、オーストリア人の幽霊が出てくるのかっていう話ですけど。こういう書き方をすれば違和感がなくて、ちゃんと怖くできるんだというのが自分でも発見でした。古い箪笥を描いたのもノスタルジー。昔はどこの家にも大きな洋箪笥がありましたけど、何かが潜んでいそうで子供の頃は怖かったものです。
── : 五話目は旅館が舞台となる「山荘奇譚」。怖さでいうと、間違いなくこの作品が白眉だと思います。
小池: 実はこの作品は、実際に見た夢をほぼそのまま書いているんです。昔の文豪はよく夢を作品化していますが、そういう書き方をしたのはこれが初めて。山奥の旅館に泊まりに行って、宿の主人から幽霊の出る地下空間の話を聞かされる……という異様な夢で、目を覚ましてからも「今の夢、何?」という感じで怖かった。その旅館の名前が、作中にもある〝赤間山荘〟ですね。字面がはっきり頭に残っているので、気になってネットで検索してみましたが、下関に赤間神宮という神社があるだけで、どうも赤間山荘は実在しないみたい。どこから出てきた名前なのか、自分でも分からないんです。
── : 幽霊の着物の柄を再現しようとする主人とか、その布が貼りつけられた地下室の様子とか、理屈のつかないディテールが怖いですよね。
小池: そのあたりもまったく夢の通りなんです。だから自分でもどういうことか分からない(笑)。一般の小説だとしっかり理屈を作らないといけないんですけど、怪談の場合は不条理な展開であっても許される。その発想の自由さが、書いていて一番楽しいところですね。
── : そして最終話が「緋色の窓」。隣家の窓から亡くなったお妾さんの幽霊が覗いているという、美しいイメージをもった恐ろしくも哀切な作品です。
小池: 収録順は担当編集者の方が考えてくれたんですけど、ラストに綺麗な話が置かれたことで、うまくまとまったなと感じています。幽霊というのはわたしにとって、身の毛がよだつほど恐ろしいものである一方、どこか懐かしい存在でもあるんです。人生の流れのなかで遠ざかってしまって、二度と会うことのできない人たち。それにふとした瞬間、異なる次元が繋がって会うことができる気がする。死者たちに感じる身近さや懐かしさというのは、このジャンルを書いていくうえで一番大切なファクターかもしれません。

怪談には人を哀しみから救い出す不思議な力がある。
── : 全六作、いずれ劣らぬ傑作揃いですがもっとも思い入れの深い作品は?
小池: みんなそれぞれ愛着があるんですが、あえて選ぶとするなら「山荘奇譚」かな。それなりに枚数がある作品なんですけど、突き動かされるようにして一気に書き上げてしまった。会社を立ち上げ、現実社会で右往左往している合理主義者の主人公が、少しずつ不穏な世界に巻きこまれていく感じは、我ながらうまく出せたかなと思っています。
── : しかも単に怖いだけではなく、怪異を通して人生の深みに触れられる。どの作品にも小池さんの死生観が刻み込まれているように感じました。
小池: 人はどうして怖い話を読むんだろう、とよく考えるんですよ。たとえば耐えきれないほどの悲しみや絶望、虚無感に打ちひしがれている人がいて、何気なく手に取った怪談に思わず夢中になる、ということがあると思うんです。恐怖って人間の根源的な感情のひとつなんでしょうね。だからそこに強く引き込まれている間は、現実的な悩みや苦しみを、束の間、忘れ去ることができる。極端なことを言うと、これから自殺しようと思っている人でも、震え上がるほど怖い話を読むことで、もしかすると死のうという気がなくなるかもしれない。フィクションがもたらす恐怖だからこそ、怪談にはそういう不思議な効能があるような気がするんですね。
── : 二〇一七年は「小池真理子幻想怪奇小説集」と銘打って『怪談』『夜は満ちる』『水無月の墓』の三作も集英社文庫より連続刊行されました。まさにベストのタイミングで世に出る『異形のものたち』をきっかけに、若い読者にも小池怪談の魅力に触れてほしいですね。
小池: 怪談はミステリーのように背後がすべて説明されるわけではありません。読む人によっては「どこが怖いのか分からない」ということがあるかもしれませんね。ただこういう怪談には独特の割り切れない面白さがありますし、お好きな方にはきっと喜んでもらえるだろうと思います。
── : では最後に怪談方面での今後の抱負を。
小池: これからも考え込まず、好きなように書いていくでしょうね。たとえば「幻想文学とはなんぞや」という分析から入っていけば、これまでにない怪談が書けるのかもしれないけれど、多分それは一生やらない(笑)。発表の場を与えてもらえるうちはぽつぽつと、楽しんで書いていきたいと思います。やっぱり仕事というより趣味、なんですね。