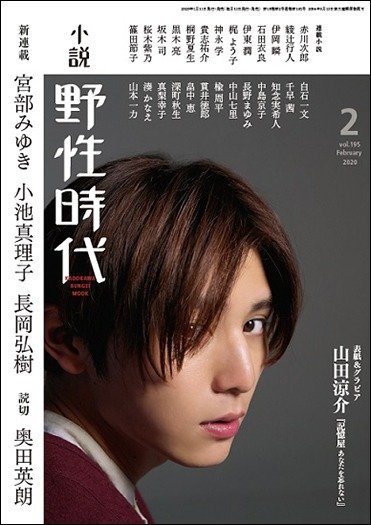本日 1 月 11 日(土)発売の「小説 野性時代」2020年2月号では、宮部みゆきさんの新連載「火焔太鼓 三島屋変調百物語七之続」がスタート。
その冒頭を公開します!
序
江戸は神田三島町にある袋物屋の三島屋は、風変わりな百物語をしていることで知られている。人びとが一夜一間に集って順繰りに怪談を披露するのではなく、語り手一人に聞き手も一人、一度にひとつの話を語ってもらって聞きとって、その話はけっして外には漏らさず、
「語って語り捨て、聞いて聞き捨て」
これが三島屋の変わり百物語の趣向である。
三年余り前、彼岸花の咲く季節に、主人・伊兵衛が招いた来客の身の上語りが振り出しとなったこの変わり百物語は、最初の聞き手を務めた姪のおちかが近所の貸本屋へ嫁いだあと、次男坊の富次郎が引き継いでいる。いささかの遊び心と絵心がある富次郎は、語り手の話を聞き終えると、それをもとに墨絵を描き、〈あやかし草紙〉と名付けた桐の箱に封じ込めて、聞き捨てとする。
若いうちは買ってでもするべき苦労をしにいった奉公先で思いがけず大怪我を負い、生家へ帰ってきて、療養がてらのぶらぶら暮らし。変わり百物語の聞き手としても新米の富次郎には、怪談語りが呼び込む怪異から三島屋を守る禍祓いの力を持つお勝、富次郎を子供のころから世話してきた古参のおしま、この二人の女中が強い味方だ。
人は語りたがる。嘘も真実も、善きことも悪しきことも。
気さくで気が良く、旨いものが大好きで、今の気楽な身の上に、自ら「小旦那」と称して剽げてみせる富次郎。しかし、変わり百物語に臨むときはいつも真剣勝負だ。そんな聞き手の待つ三島屋に、今日もまた一人、新たな語り手が訪れる。
第一話 火焔太鼓
水無月の朔日、鐵砲洲稲荷へ富士参りに行く母・お民のお供をした富次郎は、本物の霊峰富士の溶岩を使ってこしらえたという高さ十一間(約二十メートル)もあるお参り用の富士山のそばで、懐かしい「師匠」とばったり会った。花山蟷螂という絵師である。
背が高く手足が長く、痩せぎすで顎がとんがっており、ちょっと飛び出し気味の目玉ばかりがぎょろりとしている。そんな見てくれが雅号の由来だというこのかまきり絵師は、人柄は優しくて教え上手だった。
富次郎は十五の歳に、「他所の釜の飯を食って来い」という父・伊兵衛の言いつけに従って、新橋尾張町の木綿問屋〈恵比寿屋〉に住み込みの奉公に出た。先様では富次郎を三島屋からの預かりものとして丁寧に遇し、木綿問屋の商いを一から教えてくれたのだが、それに加えてもう一つ、富次郎に学びの機会を与えてくれた。それが絵を描くことである。
恵比寿屋の主人は、外に女をつくって子を産ませ、その子をお店に入れて奉公人として追い使うという酷い一面のある人だったけれど、気の多い趣味人でもあった。謡いに三味線、鼓などの芸事はもちろん、朝顔を育ててみたり、メジロを飼ってみたりといろいろやっていたが、そのなかの一つに絵を描くことがあり、その師匠が花山蟷螂だったのだ。
蟷螂師匠はしばしば恵比寿屋に通ってきて、奥の一間で絵描きのいろはを主人に教えた。当時の富次郎は奉公を始めて半年足らずで手代格になり、何かと主人のそばについていることが多かったので、自然と蟷螂師匠とも顔馴染みになった。あるとき、実は自分も子供のころから絵が好きなのだが、きちんと習ったことはないと話してみると、師匠の方から恵比寿屋に掛け合ってくれて、富次郎も主人と一緒に習えることになった。
絵師がそんな計らいをしてくれたのは(もちろん富次郎がただの奉公人ではないことを知った上ではあるが)、恵比寿屋の主人がむら気な上、素人のくせに絵の鑑識眼があることを吹聴するので、教えがいがなくってつまらなかったからだと、あとで本人がこっそり教えてくれた。
富次郎の絵心は生まれついてのものらしく、最初から筋がよかった。振り売りから三島屋を興した伊兵衛にもお民にも、美しいものを見る目はあるわけだから、その血筋の力なのかもしれない。
恵比寿屋の主人が次の習い事に気を移すまで、二年ほどのあいだ、蟷螂師匠は熱心に教えてくれたし、富次郎はよき弟子であった。そのように親しくなってからわかったのだが、蟷螂も小さな商家の生まれだった。どうしても絵を描きたくて、十二のときに家を飛び出し、小石川の御家人で絵師でもあった花山松治郎(雅号は美松)に弟子入りして、下働きしながら絵を習ったのだそうだから、富次郎に少し似たものを感じてくれたのだろう。
当時は三十代半ば、今は四十路を超した花山蟷螂は、富士参りの場で再会してみれば、鬢に白いものがちらちらとまじり、洒落た刺繍の花紋付きの黒羽織をさらりと着こなしていた。
二人で再会を喜び合った。絵師は富次郎が恵比寿屋から三島屋へ帰ったことを知っており、今も絵を描いているかと問うてくれた。
「ほんの手慰みでございますが」
変わり百物語の聞き捨てのためだとは言えず、そう答えた富次郎に、花山蟷螂は連れの男を紹介してくれた。日本橋通町四丁目にある筆墨硯問屋「勝文堂」の手代頭で、名前は活一。歳は蟷螂と富次郎のあいだくらいだろう。空豆に目鼻をつけたような顔で、にこにこと愛想がいい。
「私は筆や墨ばかりか、画材はみんな活一さんに頼っているんですよ。この人だけの伝手を持っていて、いいものを安く仕入れてくれるから、ぜひ便利にお使いなさい」
活一も「どうぞよろしくごひいきに願います」と言ってくれたので、富次郎も「こちらこそ」と愛想を返しておいた。
帰り道、厄除けの麦わら蛇をぶらぶらさせながら、お民に絵師との縁を話して聞かせると、この働き者のおっかさんは素朴に驚いた。
「あんたはそんなに絵が好きだったのかえ」
「いえ、下手の横好きですよ。蟷螂さんのあとは、これという師匠についたわけじゃありませんし」
「近ごろも、ときどきうんうん唸りながら何か描いておいでだよね」
「はあ」
「道具や画材はどうしておいでなんだ。お愛想じゃなく、さっきの勝文堂さんにいろいろ頼んだらいいんじゃないの」
「本物の絵師が使う画材なんぞ、わたしにはもったいないですよ、おっかさん」
花山蟷螂はかつても名のある絵師ではなかったし、今もそうなのだろう。だが、好きな絵を描いて、そこそこ良い暮らしをしているように見えた。富次郎とは居場所が違う。
ところが、それから数日後、
「近くまで届け物に参りましたので、ご挨拶だけでもと思いまして」
と、活一が三島屋を訪れた。
富次郎は慌ててしまった。出商いの商人には縁先で会えば充分なのだが、客間に通して丁重にしたのは、やっぱり元師匠の顔を思い浮かべたからである。
富次郎は正直に、今の自分の「手慰み」は本当にそこらの半紙に墨絵を描くことで、子供が板塀にいたずら書きをするのと大差ないと話した。活一は嫌味のない商売人で、富次郎の汗顔をやわらかく受け流した。
「お騒がせしてあいすみません。ただ、富士参りでお目にかかったあと、蟷螂師匠がたいそう嬉しそうに富治郎さんの話をなさいましてな」
――私が教えたときにはまだ小僧の面影が残っているような年頃だったが、あの人には独特の才があった。これまで出会った弟子のなかでは、いちばん光るものがあった。
――今も描いているなら幸いだと思ったが、三島屋さんほどのお店の倅が、それを放り出して絵の道に進めるわけもあるまい。つくづく惜しい。きちんとした師匠について腕を磨けば、花を咲かせる才だと思うのに。
これを聞いて、富次郎は耳が熱くなった。花山蟷螂が本当にそこまで言ってくれたかどうかは怪しい。活一が話を盛って、勝文堂の商売に繋がればいいと恃んでいると踏んだ方が正しかろう。
それでも嬉しかった。自分には光るものがあったのか。二年ばかりの師匠と弟子でも、今も覚えていてもらえるほどに。
活一が引き揚げていったあと、しばらく客間でぼうっとしていた。
今の富次郎が描く絵は、変わり百物語の聞き手としてのものである。もとより永くとっておくものではなく、〈あやかし草紙〉の桐箱のなかで、自然に古びて薄れて消えてしまうことをこそ望んで描いている。
――そうじゃなくて、ホントに本物の絵を描いてみたらどうなるだろう。
それ以前に、描けるだろうか、自分に。
――きちんとした師匠について腕を磨けば。
考えてみたこともなかった。
長男である兄の伊一郎がいるのだから、この先、富次郎が両親の商いを継ぐにしても、それは暖簾分けの形になる。伊一郎が受け継ぐこの三島屋を助けつつ、競い合えるような分店を立てられるならば、それ以上の親孝行はあるまい。
今はまだ、かつての富次郎と同じように「他所の釜の飯を食って修業中」の伊一郎だって、遠からずうちに帰ってくるのだから、今後のことはそのとき相談すればいいのだと思っていた。今のぶらぶら暮らしは、それまでの楽しい幕間だ。ほかの人生を選ぶなんて、頭の隅をかすめたこともない。
富次郎は二十二歳、次の正月が来れば二十三歳になる。父・伊兵衛が母・お民をめとった歳だ。夜なべで袋物をこしらえては、日中は振り売りに励む暮らしのなかで、いつか二人でお店を持とうと誓った歳だ。
これからまるっきり違う道へ進むなんて。商人ではなく、絵師になるなんて。
――遅すぎるよな。
呟いて、独りでふっと笑いをもらした。
「合歓の花は、昼間はうつらうつらしておりますわね」
黒白の間の床の間に、お勝が合歓の花を活けている。薄暮に花を開く合歓は、昼前の今は確かに半開きである。
「小暑のころがいちばんの見頃でございますから、今はまだつぼみも若うございます。今日お見えになるお客様がお若い方でしたら、ちょうど釣り合いますが」
百物語に次の語り手を迎えることになり、支度をしているところである。人選びは口入屋の灯庵老人に任せているので(おちかが聞き手をしているころには、飛び入りもあったそうだが)、いざ語り手と顔を合わせるまでは、富次郎はその人物風体を知らない。しかし、勘のいいお勝がそんなことを言うのだから、本日の客人は若者なんじゃないか。
掛け軸に真っ白な半紙を吊すとき、勝文堂の活一とのやりとりが頭をよぎった。麻紙や鳥の子紙や絹地に、顔料や岩絵の具を用いて美しい色合いの絵を描く――それは趣味として楽しいだろうけれど、語り手の話を聞き捨てにするためにしては、ちょっと贅沢に過ぎるように思うのだ。
これまでに、墨絵ではなく、色も差せたらいいなと思う折がなかったわけではない。蟷螂師匠の下で習っていたころに使っていた水干絵の具ならば安価なので、試してみようかと思ったこともある。
しかし、〈あやかし草紙〉の絵は、やっぱり白地に黒い線だけであるのがふさわしいのだと思い直した。語り手の話は、そっくり全て過去のことだ。今、この世で起きていることと同じように色鮮やかではない方がいい。
一度、何気なくそんなことをお勝に話したら、こう返された。
――そのようにお考えになるということからして、小旦那様は絵師の心をお持ちなのだと、わたくしは思います。
悪い気はしなかった富次郎である。
本日供する茶菓子には、上品な練り切りを用意してある。旬のない菓子だが、富次郎ひいきのこの菓子屋のものは、夏場は水鳥の形になっており、目にも涼しい。香ばしい麦湯とよく合うはずである。
さて、約定の昼間の八ツ(午後二時)に、おしまの案内で黒白の間に通ってきた語り手は、長身で筋骨たくましい侍であった。
歳はいくつぐらいか。三十路には達してなかろうが、富次郎よりは年上に違いない。だから「若者じゃないか」という読みは外れた。しかし、若々しく清々しい人だ。身体に清冽な気が漲っている。目尻がきりりと上がり気味で、鼻が高く、口元は引き締まっている。やや面長で、額が秀でているので釣り合いがよく、つまりは、
――美丈夫とはこういうお方のことよ。
髷は細く、刷毛先が小ぶりの銀杏の葉のように少し開いている。これが武士の結う銀杏髷の特徴だ。ほのかに薫る髪油。薩摩の紺がすり上布を着ているが、これは夏の略式ながらも外出着である。平織りの角帯に、さすがに羽織はなしの着流しだが、白足袋がすがすがしい。
三島屋にはおそらく徒歩で来たのだろうから、この出で立ちに網代笠をかぶっていたのだろう。その姿も見てみたかった。
語り手が武士であっても慌てぬよう、黒白の間には黒漆塗りの刀置きを備えてある。が、この客人は両刀を外すと傍らに置いた。無駄のない、無造作にも見える所作。袖口からちらりと覗いた腕の、がっちりした肉付き。
――剣術の腕も立ちそうだ。
おしまがしずしずと盆を捧げてやって来て、麦湯と練り切りを並べる。いったん次の間に引き返し、今度はお代わりの麦湯を満たした大きな土瓶を載せた盆を、富次郎のそばに置いてゆく。その手つきを見るに、おしまはいくらか上がっているらしい。
富次郎も同じ心地だった。この語り手に対して粗相があってはならない。武士の怒りが怖いからではなく、恥ずかしいのだ。
おしまが無事に下がり、次の間との仕切りの唐紙が閉まる。呼吸を計って、富次郎は丁重に畳に指をつき、挨拶を始めた。
「ようこそ三島屋の変わり百物語においでくださいました。手前は聞き手を務めます当家の倅、名を富次郎と申します」
こうして向き合うと、上座の美丈夫殿も、ちょっぴり肩がいかっている。頬が上気しているのは、この方も緊張しているからだ。それに気づくと少しだけ気がほぐれ、滑らかに口上を続けることができた。
「まず、手前が先んじてまくしたてるご無礼をお許しください。と申しますのは、この変わり百物語には、お客様のお名前やご身分を明らかにされぬままお話を伺ってもよいという決まりがございますからでして」
相手が町人なら、真っ先にこれを言わなくてもかまわない。しかし、今はいの一番に申し上げておかないと、こちらが落ち着かない。
「これからお話を頂戴します上で、ご不便がありましたら、どうぞ仮名をお使いください。またお話の内容についても、差し障りのあるところは伏せていただくなり、変えていただくなり、お客様の裁量に全てお任せいたします。お話は、語って語り捨て、聞いて聞き捨て、一から十までこの場限りのことでございます。どうぞお心を安らかに語っていただけますよう、あらかじめお願い申し上げる次第でございます」
富次郎がもう一度平伏すると、美丈夫殿は、形のいい(ほんの少しいかつい感じがなおさら好ましい)顎を引いて、軽くうなずいた。
「こちらのしきたりの委細は口入屋から聞き置き、心得ております」
丁寧語である。身分を脇に置き、語り手としてここにいると示しているのだ。おまけに、声もよかった。この顔から出てくるならこの声だよ、という声音。
およそ男と生まれつくなら、こういう漢に生まれたい――と思うよりも、描きたいなあと思ってしまうのは、やっぱり蟷螂師匠との再会があったからだろう。富次郎の絵心が浮ついて騒いでいる。
「みどもは、江戸市中の人びとが浅黄裏と笑うという勤番者でござる」
白い歯を見せて、美丈夫殿は笑った。
「殿の出府に付き従い、江戸に上るのはこれで三度目でござるが、裾を払えば土の匂いのたつ田舎者。ただ国許の出来事を、国許では語れぬ故に、こちらの珍しい趣向の場で吐き出したく、今日の機会を得たものでござる。何卒よしなにお願い申し上げる」
富次郎はもう惚れ惚れとしてしまって、ああ描きたい、この方の肖像を描きたい、立ち姿も、馬上の姿もよかろうなんて思って、驚きはあとから追っかけてきた。
え? 勤番武士? お国訛りがなさ過ぎる。野暮ったい浅黄裏なんてとんでもない、この方にそんなふざけた言葉をぶつけたら、罰が当たる。
「お、お、お」
畏れ入りますとつっかえながら申し上げて、額に汗が浮く。背筋にもつうっと汗が走る。
富次郎ののぼせぶりを、素直に受け取ってくれたのだろう。美丈夫殿はまた爽やかな笑みを浮かべた。いかっていた肩もゆるんだ。
「こちらの店先には、五年ほど前に初めての勤番を終えて帰国する際に、土産物を探しに参ったことがござる。評判以上に、どの品もきらびやかで垢抜けており、目が迷うばかりで、結局何も買わぬまま、這々の体で逃げ帰ってしまったのですが」
その謙譲な口調、言葉の選び方、富次郎に向ける表情。全てが一定の教養に裏打ちされている。
富次郎は深く感動した。この方の故郷、主君の領地がどこにあるにせよ、そこがどんな辺鄙な場所であろうとも、けっして「田舎」と貶められる場所ではない。
「お客様のお心を乱すばかりで、お気に召す品物を揃えておけなかったのは、手前どもの手抜かりでございます」
三島屋ばかりか、袋物屋ぜんたいを背負うつもりで、富次郎は頭を下げた。
「もしや、そのとき限りで、袋物屋にはすっかり懲りてしまわれましたか」
美丈夫殿は、いいえ――と軽く手をあげ、そのままその指先で秀でた額をかいた。
「空手で帰国しては、江戸土産を心待ちにしている母にも妹にも泣かれます。日を改め、藩邸詰めの胞輩に頼んで同道してもらいました。そうして選んだ品物のなかにこちらで買い求めた懐紙入れがあり、妹が今も大切に使っております」
おお! よかった。
「たいへん光栄なことでございます。お買い上げありがとうございました」
この方には母上と妹御がいらっしゃる。奥方はまだもらっていないのかな。いや、初出府・初帰国のころは独り身だったけれど、今は妻帯しているのかもしれない。だったら此度の出府からの帰国の際には、ぜひうちのとびっきりの品物を奥様のお土産にしていただきたいものだ。
聞き手をしているのか売り子をしているのかわからなくなってきた富次郎は、やっぱり興奮しているのである。
幸い、美丈夫殿が先に麦湯に口をつけてくれたので、富次郎も喉を湿した。今日はふと気が向いて、麦湯の器にとっておきの白磁を使わせてもらったのだが、それでよかった。今、目の前の美丈夫殿の厚みのある手の中にすっぽりと収まっている華奢な白磁の湯飲みは、涼やかな夏の花のようだ。
富次郎の考えが伝わったのか、美丈夫殿は手にした白磁に目を落とし、しげしげと見回した。それから言った。
「このように美しく儚げな風情のものとは比べようのない無骨なものですが、みどもの国許でも焼き物が盛んに作られております」
名高い窯元のある場所は限られているから、迂闊に問い返すと、美丈夫殿のお国を言い当ててしまう。富次郎は口をつぐんでうなずいていた。
「但し、名産物ではござらん」
美丈夫殿も、すぐに断りを入れてきた。
「はるばる江戸市中にまで流通するほどの焼き物ではないのです。みどもの国許と、せいぜいそのまわりの国々の日々の暮らしのなかで使われ、脆く壊れ、また新しいものが使われては壊れる。さすがに素焼きでは不便だから釉薬ぐらいはかけておこうというほどの、工芸品とも呼べぬ代物でござる」
ずいぶんとへりくだっている。
「その、焼き物に」
富次郎は慎重に、ゆっくりと問うた。
「呼び名はついておりましょうか」
瀬戸焼、備前焼、有田焼、砥部焼――そういうのとは違うのだとしても、名称はあるだろう。
果たして、美丈夫殿は詰まった。
「ある――のですが」
それを聞いてしまうと、美丈夫殿の名前やお国の見当がついてしまう。
「では仮名をつけましょう。先ほど手前が申し上げましたのは、こういう場合のことなのです」
「なるほど。どうするかな」
思案する美丈夫殿の眼差しは真剣だ。
「こうした事柄は、いざ偽ろうとすると、難しいものでござるな」
「偽るというほど厳めしいことではございません」
それでも美丈夫殿が考え込んでいるので、こちらから「三島焼でいかがでしょうか」と言おうとした寸前、その口元がやわらぎ、目元が笑みに緩んだ。
「では、〈かじやき〉でお願いしよう。〈かじ〉には加持の二文字をあてます。この焼き物を始めたところが、加持村と申すので」
もちろん、それで富次郎には何の障りも不満もないが、不思議だった。なぜ、この仮名を思いついて微笑んだのだろう。秘密や皮肉の苦みの混じらぬ、思い出し笑いみたいな素直な笑みだった。
「みどもは――ああ、これも重苦しい」
美丈夫殿は進んで打ち消すように言って、かぶりを振った。
「ここからは、〈私〉で通しましょう。この話はもう二十年も昔、私が十歳の洟たれ小僧であったころの出来事でござる。国許では語れぬというのは、この話が我が家中のごく限られた者どものあいだだけの秘事であるからですが」
「秘事」という強い言葉の響きを確かめるように、そこでいったん言葉を切ったが、得心がいったのか吹っ切れたのか、すぐとこう続けた。
「左様、秘事ではござるが、今の私自身は、家柄の上でも家臣としての役務の上でも、この秘事を守るべき立場にはない。そのような秘事があったことさえ忘れた顔をして過ごしております」
だから全ては思い出話だ、と言う。
「私がかつて見聞きしたこと、出会ったものが、今もあのとおりであるかどうかはわからぬ。それを今さら誰かに問うて確かめることもかなわぬ。そういう類いの話でござる」
あいわかりましたと、富次郎は応じた。
「手前どもの百物語は、まさにお客様の思い出話のようなお話のための場でございます。どうぞ、どこからでも存分にお語りください」
「かたじけない」
また顎を引き、美丈夫殿はつと瞼を閉じた。心を静め、あらためて富次郎の顔を見る。
「私は中村新之助と申します。ただ、これから語る出来事があった当時は、元服前の幼名で小新左と呼ばれていました」
お話の舞台である小新左の国は大加持藩、お城は大加持城、中村家が仕える主君は大加持風之守加持衛門――と決めて、語りが始まった。
▶このつづきは「小説 野性時代」2020年2月号でお楽しみください!
https://www.kadokawa.co.jp/product/321901000096/
※リンク先:「野性時代」2月号 KADOKAWAオフィシャルページ
関連記事
- 【解説】誰かに聞いてほしい話はありませんか――? 宮部みゆきの大人気「三島屋」シリーズ、待望の新作『三鬼』
- 《『あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続』刊行記念対談 宮部みゆき×若松英輔》稀代のストーリーテラー宮部みゆきのライフワークにして江戸怪談の真骨頂!