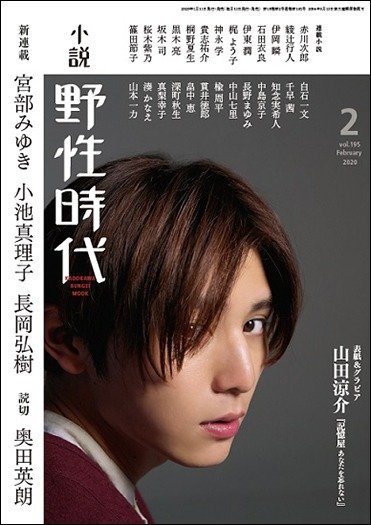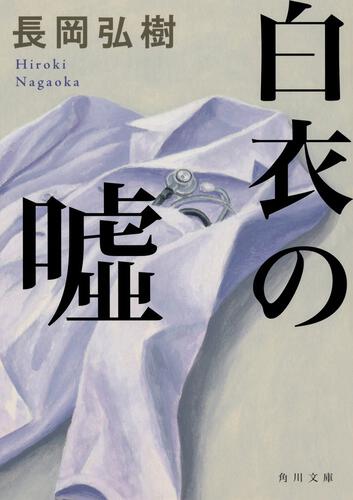1 月 11 日(土)発売の「小説 野性時代」2020年2月号では、長岡弘樹さんの新連載「死人の家」がスタート。
その冒頭を公開します!
1
患者の頭は三点固定器に挟まれていた。
固定器の太いピンは、こめかみの皮膚に深くめり込んでいる。
これぐらい強く締め付けてもまだ不安だった。いまから脳に手術の器具を入れていくのだ。首から上が少しでも動いてもらっては困る。
患者の体から伸びている、血圧と心拍数を計測するためのコード類や、尿を排泄する管。それらが手術中に邪魔にならないよう、そっと足でよけた。
モニターが発している規則正しい心音が、緊張で研ぎ澄まされたこの耳には、実際以上に大きく聞こえている。
筋弛緩剤が注射され、自発呼吸を止められている患者の体は、蝋でできた精巧な人形のようでもあった。
手術中に彼の命を繋ぐのは人工呼吸器だ。そこから伸びた気管チューブが、患者の口に少しずつ挿入されていく。
奥まで入ったチューブが、念入りにテープで固定されたあと、看護師の一人がバルブを開いた。
純酸素と笑気ガス、そして麻酔剤を混合した空気が、少しずつ患者の肺に送り込まれていく様子を、束の間じっと見守る。
そうこうしているうちに、もう一人の看護師が、バリカンで患者の頭髪を刈り、手術野である側頭部を、慣れた手つきで剃りあげていった。
剃毛の次には、茶色の消毒液にたっぷりと浸しておいたブラシを使い、強めに頭皮を洗っていく作業が待っている。この薄い皮膚の向こう側は人間の中枢部だ。少しの雑菌も侵入させてはならない。
消毒も済むと、感染防止用の薄いセロファン膜を貼りつけた。
患者の手足に視線を移せば、甲の静脈部分に、点滴用の針が深く挿し込んである。手術中に万が一容態が急変した場合に備え、すぐに輸血ができるよう、もしくは薬物を投入できるようにするための、欠かせない措置だ。
患者の頭部に目を戻した。
指先で頭蓋骨の形をゆっくりと数回なぞったあと、手術用の油性ペンを手にし、切開線を描き込んだ。術後にできるだけ早く傷跡が隠れるよう、毛髪の剃り跡が濃い場所を選んだことは言うまでもない。
そのU字線だけが見えるようにして、他の部分はそっと布で被う。
ここが動脈瘤への入口だ。
――さてと。
これで準備は整った。
手術室の中央で、無影灯のスイッチがオンになり、患者の頭部が煌々と照らし出される。
ここで尾木敦也は目を開いた。
2
いつの間にか、また眠りに落ち、夢を見ていた。
内容は例によって自分が執刀する手術。毎回同じだ。何も睡眠中にまで仕事をすることはあるまいに、と思う。
病院であくせく働いているときには、手術室にいる夢など見たことがなかったのに、休職した途端にこれだ。不思議というより皮肉と表現した方が正確だろう。
眠りを破ったのは、耳障りな騒音だった。ブーンというこの低い唸りは、蠅の羽音でなければ、スマホが発している着信音に違いない。
敦也はベッドから起き上がることなく、首だけを捻った。
カーテンを閉め切った薄暗い部屋。このどこかにスマホがあるはずなのだが、一見しただけでは、そのありかが分からない。衣服や雑誌、コンビニのビニール袋などが散乱していて、床が見えていないせいだ。
そうこうしているうちに、呼び出し音が止んだ。コール音の回数はきっちり十だったから、病院からの連絡に違いない。
休職して自宅に籠って以来、スマホが鳴ったのは三回目だった。
同時にメールも来ているかもしれなかったが、端末を確認しなくても用件には見当がつく。
――《これから来てもらえないか》
前二回の電話が思い出された。少し嗄れているものの、よく通る声。どちらも東崎だとすぐに分かった。
――《さっきも隣から急患の依頼があったよ。きみに手術をしてほしいんだがな》
東崎院長の依頼は二度ともそうだった。自分が勤務する医療法人明浄会S病院には、病院スタッフが「隣」と呼び習わしている場所から、ときどき患者が運ばれてくる。
もちろん、「いまは休職中ですから」と、きっぱり断った。結局、手術は外部から招聘した他の医者が担当したようだ。
別の物音を聞いたのは、もうひと眠りするかと目を閉じようとしたときだった。
階下だ。
誰かが入ってきたらしい。玄関の鍵はかけていたはずだが……。
空き巣狙いか。そのおそれは十分にある。にもかかわらず、それでもベッドから起き上がろうとしない自分がいた。
やがて、みしりと木の軋む音も耳にした。階段を上ってくる足音に違いなかった。
ほどなくして、部屋のすぐ外に人の立つ気配があった。
L字型のドアレバーがゆっくりと下に動き、扉がこちら側に向かって開いた。
部屋の入口に誰かが立っている。
女だ。白い服を着ていた。
彼女は鼻をひくひくと動かし、小さな声でひとこと呟いた。
「臭い」
ほっとけ。敦也はそう言おうとしたが、ねばついた唾液のせいで口が上手く動かず、言葉にならなかった。
「兄さん」
その女――菜々穂は顔をしかめながら言った。
「もう何日になる?」
「どういう意味だ」今度は不明瞭ながら発語できた。
「だから、もう何日入浴していないのよ」
菜々穂は母から譲り受けたバッグを持っていた。病院に出勤するときにいつも使っているものだ。仕事に行く途中でここへ立ち寄った、ということらしい。
「知るか」
風呂には、休職した日からずっと入っていない。だから一週間ということになるが、面倒臭くてきちんと答える気になれなかった。
「これから入る気は?」
「ない」
そ、と応じた菜々穂は、一歩も部屋に足を踏み入れることなく、姿を消した。
風呂場の方でガタガタと音がし始める。かと思うと、またすぐに彼女は戻ってきた。今度は、両手に何か持っている。バケツとタオルだ。
「休職している間、毎日何をしていたの」
そう訊きながら、菜々穂が部屋に入ってきた。足取りが慎重なのは、なみなみとバケツに汲んできた湯をこぼさないように、との配慮のせいだ。
「別に」
「ちゃんと答えて」
「ちゃんと答えたさ。何もしちゃいなかった」
これは本当だった。カーテンを閉め切ったこの部屋で、酒壜を抱え、ベッドで横になっていただけだ。
目蓋が重くなってくると、抗うことなく目を閉じたが、訪れるのは浅い眠りばかりだった。
目が覚めれば、ずっと天井を睨んでいた。
それ以外のことは、やった記憶がない。
尿意があれば尿瓶で用を足した。固形物は何も口にしていないせいか、便意を覚えたことは一度もなかった。寝ても覚めてもベッドの上にいた。
「いまの気分はどう」
「最高」
本当のところは、もちろんその反対だった。
▶このつづきは「小説 野性時代」2020年2月号でお楽しみください!
https://www.kadokawa.co.jp/product/321901000096/
※リンク先:「野性時代」2月号 KADOKAWAオフィシャルページ
関連記事
- 【「教場」対談 吉川英梨×長岡弘樹】『警視庁53教場』刊行記念!「警察学校小説」対談が実現!
- 【解説】精緻なトリックと意外な結末! 生と死が交差する“病院”で繰り広げられる、心温まるミステリ『白衣の噓』