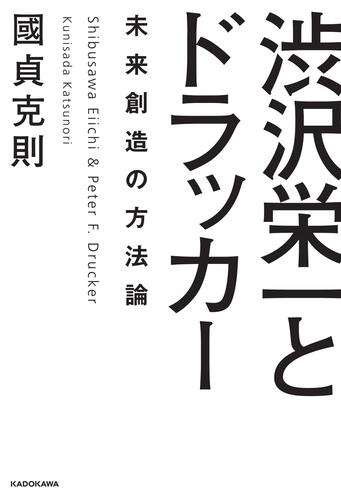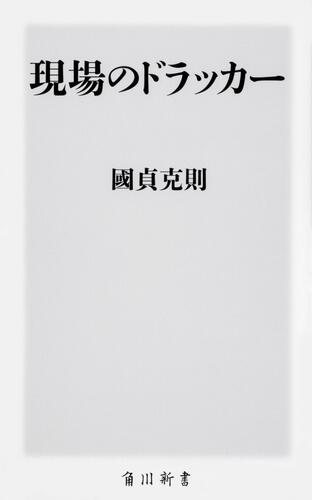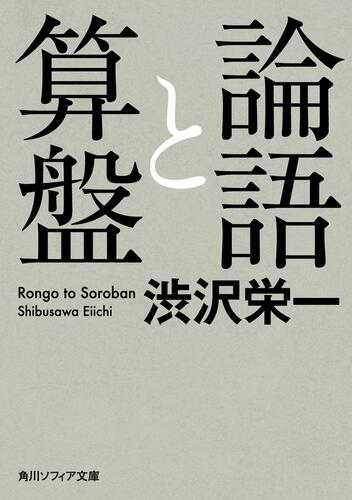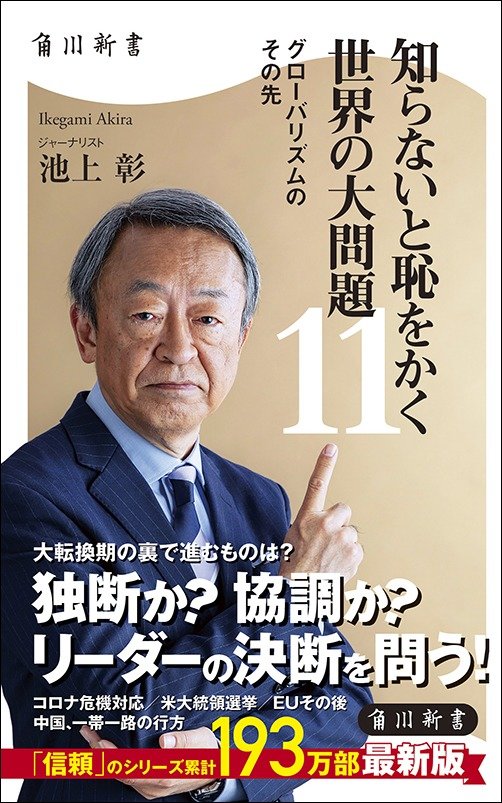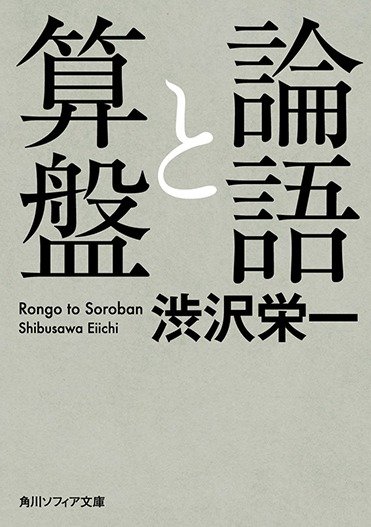渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論
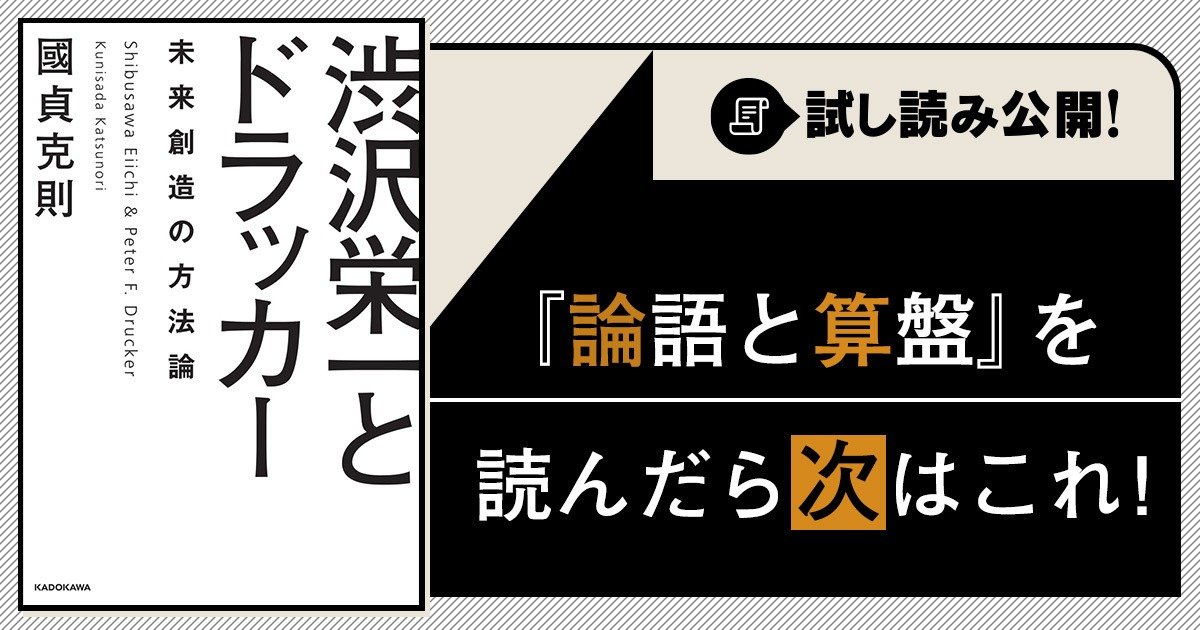
『論語と算盤』を読んだら次はこれ。ドラッカーが称賛した渋沢栄一の「本質を見抜く眼」を身につけよう!②
好評を博しているNHK大河ドラマ「青天を衝け」の主人公であり、新一万円札の肖像にもなる「日本資本主義の父」渋沢栄一。その渋沢の業績を『マネジメントの父』ピーター・ドラッカーは大いに賞賛し、授業でもたびたび言及したといいます。ドラッカーの授業を受けたこともある大ベストセラー『財務三表一体理解法』シリーズの著者・國貞克則氏が、渋沢そしてドラッカーの思想や行動原理から、コロナ禍により先の見えない時代に身につけるべき考え方を教えるのが『渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論』です。
アフターコロナのビジネスで試される「本質を見極める力」
渋沢栄一とドラッカーに共通する2点目は、「本質を見極めていた」ということである。これまで説明してきた「高く広い視点で時代が要請するものを見極めていた」というのもその1つだろうし、ドラッカーが渋沢を評価したのも、渋沢の基本的な考え方や鋭い洞察力だった。
さらに、渋沢が500社もの会社を設立できたのも「本質を見極めていた」からに他ならない。彼は事業において極めて重要なのが「専門的経営者」であることを見極めていた。
渋沢は彼の著書『
例えば、大阪紡績という事業を立ち上げる際には、
一方ドラッカーは、社会生態学者として社会の本質を見極めることに天賦の才があり、社会の本質を見極めることを仕事としていた。ドラッカーはマネジメントの全体像とその本質を整理したことによって「マネジメントの父」と呼ばれるようになった。
ドラッカーはマネジメントの全体像とその本質を整理しただけでなく、変化の本質、未来の本質、そしてその未来の本質から導き出される未来創造の本質についても整理してくれている(そのことについては『渋沢栄一とドラッカー』第2章以降で詳しく説明している)。
渋沢栄一とドラッカーに共通する3点目は、ある時点で「だれもやっていない新しい道を歩むことを決意した」ということだ。
渋沢栄一は、ただ単に民に出て事業を始めることを決意したのではなく、論語の道徳観をベースに、民に品位と才能のある人材を育てることを決意したのだった。
渋沢は若いころから高い志を持っていた。彼の志の高さは論語や陽明学といった東洋思想の影響だったと思われる。ただ、渋沢栄一の心の奥底にあったのは、官尊民卑への憤りだった。
渋沢は農民だった若いころに、地元の代官から
渋沢が民に出ることを決意した際には、民に出ても「世間から軽蔑を受けて一生役人にあごで使われるだけだ」と慰留されるが、渋沢は決意を変えることはなかった。渋沢栄一、33歳の時である。(『渋沢栄一「日本近代資本主義の父」の生涯』今井博昭著、幻冬舎新書)
一方、ドラッカーはマネジメントを研究することを決意する。彼をマネジメントに向かわせたのは、前述したように、人類の多くが組織で働くようになったからだった。
ドラッカーのマネジメント研究は、アメリカの大手自動車メーカーGMの調査から始まった。それは
その調査を元に出版した『企業とは何か』は、GMの経営陣から否定され無視され続けた。また、ドラッカーが当時
しかし、ドラッカーは自らの方向を変えることはなく、マネジメントの研究にさらに突き進んでいった。ドラッカーのマネジメントに対する強い想いはどこからくるのだろうか。
ドラッカーは次のように述べている。「組織が成果をあげられないならば、個人もありえず、自己実現を可能とする社会もありえない。(中略)自立した組織に代わるものは、全体主義による独裁である。(中略)成果をあげる責任あるマネジメントこそ全体主義に代わるものであり、われわれを全体主義から守る唯一の手立てである」(『マネジメント 課題、責任、実践』P・F・ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社)
さらに、次のようにも述べている。「そもそも私が、一九四〇年代の初めにマネジメントの研究に着手したのは、ビジネスに関心があったからではなかった。今日でもそれほどの関心はない。しかし私は主として第二次大戦の経験から、自由な社会の実現のためにはマネジメントが必要であると確信するようになった」(『[新版]断絶の時代』P・F・ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社)
ドラッカーは第一次世界大戦と第二次世界大戦を目の当たりにしている世代である。オーストリアの貿易省事務次官の息子だったドラッカーは、第一次世界大戦後で職の見つからないオーストリアを離れ、職を転々とする。第二次世界大戦でヒトラーが実権を握ると、ヨーロッパ大陸を離れ、イギリスに移りその後アメリカに移った。
ドラッカーはユダヤ系オーストリア人である。第二次世界大戦後、ヒトラーやスターリンが行った残虐な行為が明らかにされるにつけ、それは「私の想像をはるかに超える悪辣さだった。そして、そのあまりのことに私は人間に絶望した」とドラッカーは述べている。(『すでに起こった未来』P・F・ドラッカー著、上田惇生+佐々木実智男+林正+田代正美訳、ダイヤモンド社)
読者のみなさんも想像してみていただきたい。一人の独裁者のために、家族と別れ、母国を離れ、いろんな国を転々としなければならなかったことを。そして、たくさんのユダヤ人の同胞が虐殺された事実を知ったドラッカーの心情を。
ドラッカーのマネジメント研究の奥底には、人間への絶望、独裁に対する憤り、不条理に対するやり場のない感情があったことは間違いない。
渋沢栄一とドラッカーの強い想いを、志とか使命感とかといった言葉にするのは軽すぎるような気がする。人はだれも口には出さない様々なものを抱えて生きている。彼らの強い想いは、彼らのそれぞれの憤りや絶望といった人間存在に根ざしたものだったのだ。
そのような人間存在に根ざした強い想いが、その人を持続的な行動に向かわせ、成果につなげさせるのだ。強い想いがないところで人は何も生みだせないと思う。
(第3回へつづく)
▼國貞克則『渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322008000234/