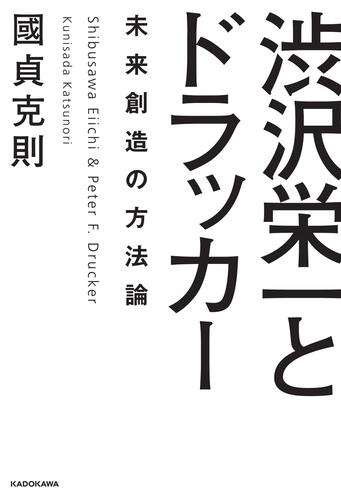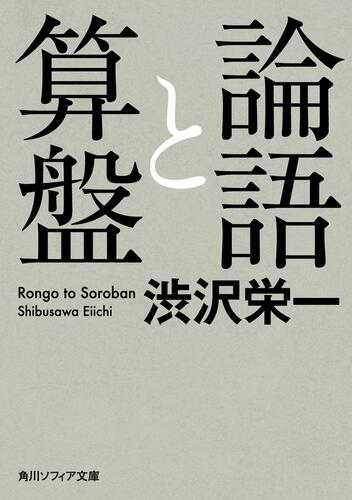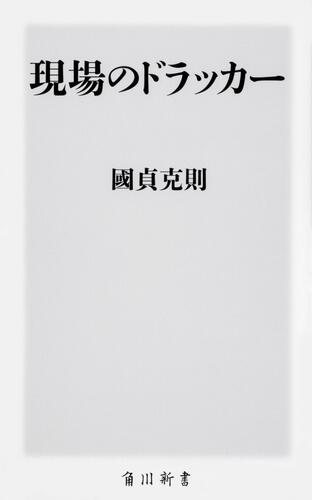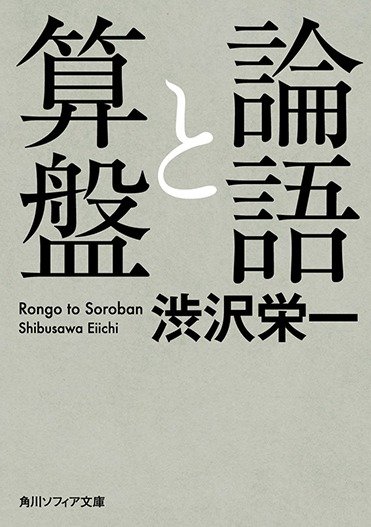渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論
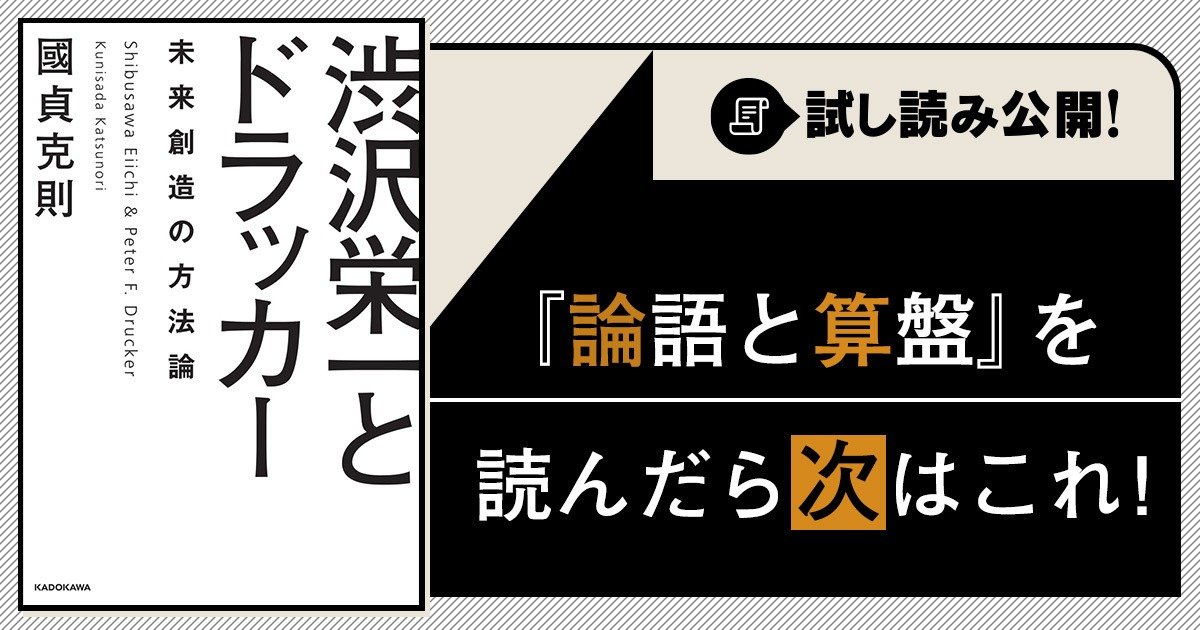
『論語と算盤』を読んだら次はこれ。ドラッカーが称賛した渋沢栄一の「本質を見抜く眼」を身につけよう!③
好評を博しているNHK大河ドラマ「青天を衝け」の主人公であり、新一万円札の肖像にもなる「日本資本主義の父」渋沢栄一。その渋沢の業績を『マネジメントの父』ピーター・ドラッカーは大いに賞賛し、授業でもたびたび言及したといいます。ドラッカーの授業を受けたこともある大ベストセラー『財務三表一体理解法』シリーズの著者・國貞克則氏が、渋沢そしてドラッカーの思想や行動原理から、コロナ禍により先の見えない時代に身につけるべき考え方を教えるのが『渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論』です。
「変化を嫌がる人」たちを動かした渋沢栄一の方法論
これまで渋沢栄一とドラッカーの共通点をとおして、未来創造の本質について考えてみた。次は、具体的に未来の事業をいかに創造していけばよいかという観点から、渋沢栄一の未来創造の方法論と彼の偉業の本質について考えてみたい。
未来創造の考え方や方法論はいくつもある。渋沢が未来創造のために使った方法は、ドラッカー流の方法論から言えば「他の産業、他の国、他の市場」で起こっていることを自分の国で実現するという手法である。
渋沢は、日本にはなかった西洋のカンパニーという会社形態を日本という国で実現し、社会的イノベーションを起こしたのだ。
未来創造の方法論として、「他の産業、他の国、他の市場」で起こっていることを活用するという方法を使ってビジネスを成功させている例はたくさんある。例えば、ユニクロやニトリがこの方法を使って成功している。
ユニクロやニトリの成功の本質は、アパレル業界や家具業界に他の産業で行われていた「製造小売」という新しい事業スタイルを持ち込んだことである。元々アパレル業界や家具業界の事業スタイルは、メーカーが造ったものを百貨店や家具店が販売するというものだった。つまり、「製造」と「小売」が分かれていた。
しかし、他の産業では「製造小売」という事業スタイルは広く用いられている。街のラーメン屋さんは製造小売が基本である。そんな小さなお店だけでなく、日本の自動車業界も基本的に製造小売だ。法人形態は別々かもしれないが、例えばトヨタが造った車をトヨタの販売店で販売している。ユニクロやニトリは他の産業で行われていた「製造小売」というスタイルを自らの業界に持ち込んで成功したのだ。
コンビニやホームセンターも同じ方法論で成功している。コンビニやホームセンターは元々アメリカにあった業態を日本に持ち込んだ。その後、日本のセブン-イレブンは元々の導入元であったアメリカのセブン-イレブンを買収した。日本は他の国のものを持ち込んで、日本に合ったものに作りかえ、元々あったものより素晴らしいものにしてしまう。
ドラッカーは「あなた方日本人は、自分たちが必要なものを取り入れて日本の制度に合うようにつくりかえてしまうという点で、天才だと思います」と言う。(『NHKスペシャル 明治1 変革を導いた人間力』NHK「明治」プロジェクト編著、NHK出版)
では、渋沢栄一は西洋のカンパニーという会社形態を日本に持ち込んで500社に及ぶ会社を設立したから高く評価されているのだろうか。もちろん、それだけではない。渋沢栄一が高く評価され続けるのは、世界的に見てだれよりも早く「企業と国家の目標、企業のニーズと個人の倫理との関係という本質的な問いを提起した」からであり、そのことが20世紀の日本の経済大国としての興隆に大きく寄与したからなのだ。
渋沢は『論語と算盤』の中で次のように述べている。「『一個人の利益になる仕事よりも、多くの人や社会全体の利益になる仕事をすべきだ』という考え方を、事業を行ううえでの見識としてきた」渋沢が書いた本の中には、国富とか国益とかという言葉が頻繁に出てくる。(『現代語訳 論語と算盤』渋沢栄一著、守屋淳訳、ちくま新書)
多くの企業は一企業としての利益や個人の利益のことを考えている。渋沢の偉業の本質は、企業は社会の一員であり、企業は国家社会のために貢献しなければならないという、企業人に一企業の利益を超えた高く広い視点を与えたことなのだ。
ちなみに、この考え方はドラッカー経営学におけるドラッカーの基本的な考え方でもある。企業が社会の中に存在する以上、企業の目的は企業の外にある。企業は社会に貢献するために存在するというのがドラッカーの考え方だ。
話を元に戻そう。渋沢栄一の偉業の本質のもう1つは、道徳をベースにしたビジネスという考え方を提起したことだった。それは、『論語と算盤』に出てくる「道徳経済合一論」や「士魂商才」といった考え方である。道徳をベースにしたビジネスという思想こそが、長きにわたって多くの人々から支持されている理由なのだ。
ただ、道徳をベースにしたビジネスという考え方は渋沢の偉業の本質ではあるが、未来創造の方法論ではない。未来創造の方法論という観点からいえば、道徳をベースにしたビジネスという考え方は、当時において大きなパラダイム・チェンジだったと思われる。
ちなみに、パラダイムとは、ある時代に支配的になっている物の見方や考え方のことである。パラダイム・チェンジの象徴的な例としては、天動説から地動説への変化があった。昔の人は天が動いていると思っていた。人間は既成概念を疑いもせず、それが当然であると思って生きているのだ。
渋沢が生きた時代は、
ユニクロやニトリもそれぞれの業界のパラダイムを変えた。多くの人は、これまで行われてきたことが当たり前であり当然であると思っている。このパラダイム・チェンジは、未来創造において重要なキーワードである。
既存のパラダイムを疑ってみることは大切である。大きな変化の時代においては、既成概念から離れて、「0」ベースで考えることは重要だ。ただ、新しいものを創りだす上で、何から何まで「0」からスタートすればよいかといえばそうではない。
渋沢が鋭かったのは、ドラッカーが指摘したように「新しい日本は、古い日本の基盤の上に築かなければならないことをよく認識して」いたということだった。つまり、渋沢は西洋のカンパニーという仕組みを、ただそのままに日本に移植したわけではない。渋沢は西洋のカンパニーという組織を、藩の時代の「家」の意識としてのコミュニティと、それへの忠誠心といった、日本の過去の文化の上に移植したのだ。
ドラッカーは「外国文化を受け入れ、それを日本化してしまう能力は、日本の歴史に織りなされた絶えざる縦糸である」と言う。この、新しいものを導入し、持っているものを
これまで渋沢栄一の偉業の本質について見てきたが、忘れてはならない重要なことは「変化を機会としてとらえる」ということである。江戸から明治にかけてだれもが大きな変化に直面した。しかし、多くの人は変化を嫌った。不安に思った。変わりたくなかった。
多くの人が変化に抵抗するのはいつの時代も同じである。人は変化を嫌がる。特にこれまでの世界で大きな成果をあげてきた人は現状を肯定する。現状のままであることを望む。自分が生きてきた世界で気持ちよく生きていきたいと思う。しかし、渋沢栄一がそうであったように、変化を機会としてとらえた人が未来を創造するのだ。
(このつづきは本書でお楽しみください)
▼國貞克則『渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322008000234/