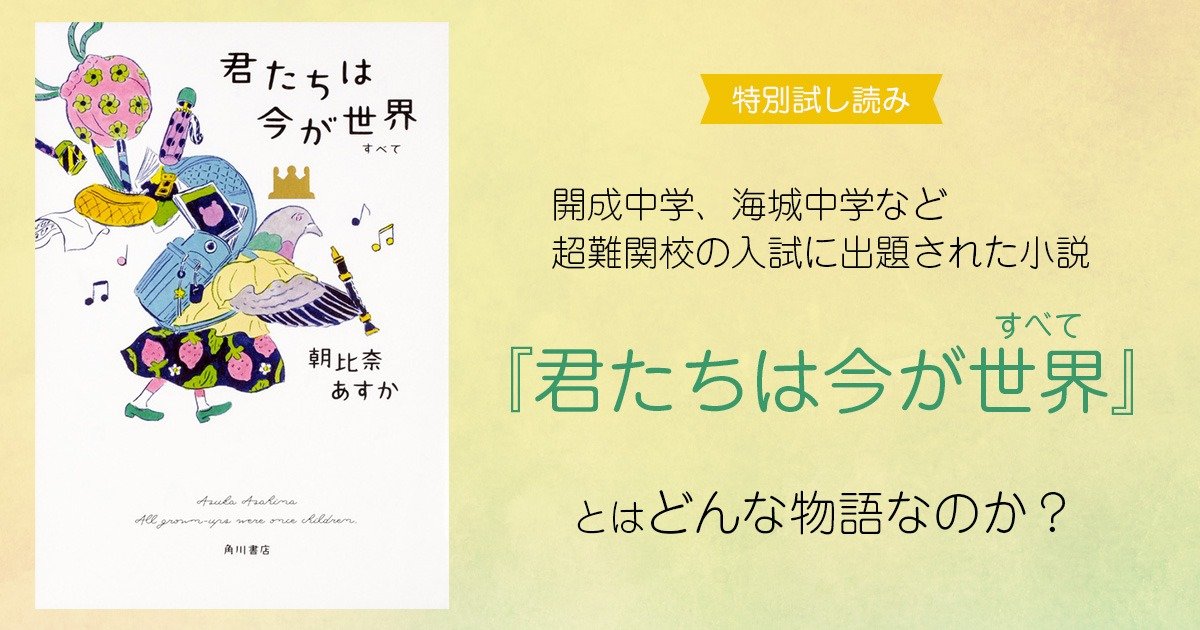開成中学校、海城中学、サレジオ学院中学校など、
2020年度の超名門校の入試問題に続々取り上げられた小説、『君たちは今が世界』。
「国語の入試問題は、学校の先生が入学する生徒に読んでほしい物語」とも言われます。
著者の朝比奈あすかさんが、小学校6年生の教室を舞台に
4人の主人公の目線で描き出す学校=世界とはどんな場所なのでしょう?
今回は特別に、各章の冒頭部分を試し読みいただけます。
>>第1章「みんなといたいみんな」
>>第2章「こんなものは、全部通り過ぎる」
>>第3章「いつか、ドラゴン」
◆ ◆ ◆
第四章
泣かない子ども
小学六年生の見村めぐ美は、今朝も「まっすぅ」こと増井智帆との朝の待ち合わせに遅刻した。
遅刻といっても、五分足らずだが、朝の五分は長い。せめてもの誠意を示すため、めぐ美はエントランスから、まっすぅが待っているマンションの門前まで十メートルほど走る。
「おはよう」
まっすぅはいつもと同じ笑顔で出迎えてくれる。ちいさな目と丸いほっぺたの彼女は、不満そうな表情を見せたことがない。めぐ美は、走ったのだからいいやという感じで、遅刻の謝罪を省き、かわりに、
「リボン、かわいいね」
と、まっすぅを褒める。両サイドの髪を
「そうかな。なんか、変じゃない? ちょっと子どもっぽいっていうか」
まっすぅはリボンに手をやり、早口で言った。
「そんなことないよ。超かわいいじゃん」
マンションの隣の小さな公園前を歩く。茶黄色に枯れた
公園を過ぎると、しばらく戸建てが並ぶ平べったい住宅地が続く。空気が臭くなくなると、ふたりは話題を失い、黙って歩いた。
入学した頃には登校班があった。マンションの子たちは全員そろって通学していた。その中には、今同じ三組の、小磯利久雄もいる。昔は男女入り交じって、隊列を組んで登下校していた。
上級生がどんどん卒業していく一方、小学校に入学する子の数が減り、去年ついに登校班は解散した。
学区域の端にあるマンションだから、学校までは歩いて二十分近くかかる。途中の道で痴漢が出たという情報が出回ったこともあり、登校班解散後もふたりで行き帰りをしてほしい、とまっすぅのお母さんからめぐ美は直接頼まれた。まっすぅのお母さんはめぐ美のママにも同じことを依頼したようで、
──あそこの親、やばいね、心配性。受ける。
ママは、めぐ美の五つ年上の「ミイ姉」ことみな
ふたりの笑い声を聞いて、めぐ美も自然と笑っていたが、登校班がなくなった後もまっすぅと学校に通えるということに、内心ほっとしていた。
まっすぅとは一年生の時からずっと一緒に行き帰りをしていたから、何となく気心が知れている。流行に疎く、スマホも持っていないし、友達の噂話や先生の悪口にもノッてこないタイプのまっすぅは、話し相手としては退屈だけれど、そういう性格だと分かっているから、会話が途切れても焦らずにいられる。並んで歩きながら、ぼーっと気を抜くことができる相手だ。
住宅地の途中で通りを曲がると、痴漢が出たと噂される細い道に出る。片側が駐車場で、片側がレンタル倉庫だ。見晴らしはいいが、いつもひとけがない。
ふたりは沈黙のまま、少し早足になって、次の曲がり角まで行く。その先の大きな道路まで出れば、安心だった。車が通っているし、人も多い。
「めぐちゃん」
人通りの多さに安心したのか、沈黙に耐えかねたのか、まっすぅが声をかけてきた。
「何」
あちこちの道や路地からランドセルの小学生たちがこの道に合流してくる。入ったことはないけれど、スーツの店や薬局なども連なっていて、朝も夕も
まっすぅは、どう話そうか迷うように「うんとね」と言葉を泳がせた。
「何、何」
めぐ美がせっつくと、
「算数の、……大丈夫?」
と
「はー?」
めぐ美は不愉快になって、声を
「えっと、ごめんね、だって、昨日、先生が……」
まっすぅは慌てたように声を裏がえらせる。横を見なくても、彼女の頰が赤くなって、
「あんなの藤岡の脅しに過ぎないって。なんとかなるに決まってるじゃん。義務教育なんだからさー」
ことさら軽薄な調子でめぐ美は言った。
「うん。だよね。良かった。わたし、受験とかしないし、五中だから……」
まっすぅが言うのを聞いて、
「わたしも五中だから、一緒に通おう」
めぐ美は言った。「うんっ」と、まっすぅの声が跳ねた。
そんなこと心配してたのか。
めぐ美は思った。
第五中学校は小学校よりさらに遠い。この大通りを、さらに五分ほど歩かなければならないのだ。お互い、心のどこかで登下校要員だと思っている。それでも、さっきのひとけのないレンタル倉庫の前の道で、隣に同級生がいてくれるのはありがたいことだった。
昇降口で靴を脱ぎ、上履きに履き替えると、それきりまっすぅとは下校時まで話さない。まっすぅにはまっすぅの友達がいるし、めぐ美はカナ、リッチー、まやまやとの、かっちりした四人組に所属していて、すべての行動は四人でしている。教室の女の子は数人ずつのグループに分かれていて、まっすぅのグループとめぐ美のグループは交わらない。
もしも、知らない誰かがこの教室を
めぐ美はたまにそんなことを考える。
きっと、誰もがぴたりと言い当てるだろう。女王はカナだ。カナこと前田香奈枝は、見目かわいらしく、手足が細くて、ティーン雑誌のモデルみたいな服を着こなしている。運動神経も良く、ダンスもうまい。そして何より彼女に女王の風格をもたらしているのは、人に遠慮なく命令できる
「おはよー、めぐ」
今日もカナがめぐ美の腕を取る。カナはスキンシップを好むし、そのスキンシップの対象は、主にめぐ美、時々まやまやで、リッチーにはあまりしない。カナに信頼されている順序のように、めぐ美は思った。
「算数のテストの解き直し、やってきた?」
カナに訊かれ、「やるかっ」とめぐ美はツッコミ風に返した。
「マジ? やば。『このままでは卒業させられないわ』」
カナが藤岡の真似をする。似ていたので、めぐ美は笑った。
ちょうど教室に現れたまやまやを、カナが大声で呼びつける。
「まやまやー、この子マジでやばいから、昨日の算数のテスト見せてあげてー」
楽しそうに騒ぎ立てる。その流れにノッて、めぐ美も「お願い~まやまや様ぁ」と、そんなこと恥でもなんでもないという顔をして両手を合わせた。
「ごめん、わたしテスト家に置いてきちゃった」
まやまやがすまなそうに言う。
「え。まじ。直し無かったの? 百点か」
「……うん、そんな感じ」
「すごい! 天才! あ、リッチー来た。リッチー、リッチー!」
次に登校してきたリッチーに、カナが同じことを頼んでくれる。テストの直しをしてきたリッチーは、答案を見せてくれたけど、点数のところだけ、恥ずかしそうに折り曲げていた。それでも答案にはたくさんの丸がついている。「わー、ありがとー」礼を言いながら、餌にぱくつく鳩のように、めぐ美は知らない数字を必死でかき集めた。その横で、ちゃっかりカナも自分の答案と見合わせて、答えが違っていたものを直しながら、
「よかったね、めぐ。やっぱ、持つべきものは天才的な友達だね!」
と言う。
「まじ、サイコー!」
めぐ美も言う。
朝の会を始めるチャイムが鳴った。
昨日、担任の藤岡から、
──見村さん。さすがにこのままでは卒業させられないわ。
と、皆の前で言われた時、めぐ美は「えー、なんでですかあ」と笑って返した。算数のテストを返却していた時だった。
──六年生をもう一回やりたいんですか。
こんな意地悪な質問をされて、「いやでーす」とふざけるしかなかった。だってクラスの皆は、めぐ美が、落ち込んだり反省したりするタイプだとは思っていないのだ。そうした受け答えが、藤岡をさらに
案の定、藤岡はそれ以上は怒らなかった。かわりにため息をついた。わざとらしい、「はあ……」を聞いて、どうせ
──とにかく、このテスト、明日までに解き直してきてください。そうじゃないと……
そこまで言ってから、もう一度大きな「はあ……」。
──そうじゃないと、なんですかー?
──あのね、あなた、本当に中学に行ってから、困りますよ。
──めぐー、どんまい!
離れた席からカナが茶化し、教室が静かな笑いに包まれた。その笑いのおかげで、
それなのに、今朝まっすぅに心配されたせいで、またしても心がひりつく。卒業なんて、できるに決まっているじゃないか。
自分は藤岡に嫌われているのだとめぐ美は思う。原因は分かっている。一学期にカナと一緒に川島さんの算数の宿題の答えを写させてもらったのが、ばれたのだ。以来、目をつけられている。
あの後、一緒に答えを写したカナは、うまいこと反省したふりをして、全問解き直して、藤岡に言われた通りの反省文までちゃんと書いて、提出していた。だけどめぐ美は、言われた解き直しをしなかった。
したくなかったからではなくて、本当は、問題の意味すら分からないくらいにちんぷんかんぷんで、最初の数問くらいしか自力で解けなかったからなのだけど、それがばれるのは恥ずかしいので、やる気がなかったことにして、藤岡の追及をへらへらとかわした。すると藤岡は静かにめぐ美を見て、前田さんは提出したのに、と言った。
藤岡からの報告の電話を、めぐ美のママは「はい、はーい」と明るく受けていた。電話を切ってからも、ちょっと首をひねって、
──めぐは昔は頭良かったんだけどねー。
と言っただけで、特に叱ったりはしなかった。
だけど、カナの親は違ったのだ。即、補習塾の申し込みをしたらしい。カナは不満そうだったけど、お母さんが申し込んだ補習塾のおかげで、今ちょっとずつ、算数ができるようになってきている。昨日返されたテストの点は、めぐ美よりずっと良かった。それが
──めぐって頭良かったの?
ママの言葉を聞いたミイ姉が、からかうように訊いた時、
──頭良かったんだよ、この子。図書館に連れてっても、あんたと
と、ママは言った。
──マジで?
──字を覚えたのだって、三人の中で、一番早かった。
──マジか。
──やっとあたしからパパ似が生まれたって、思ったんだけど。
──今こいつ、本なんか全然読まないじゃん。
──どこでどうなっちゃったのか。
ママとミイ姉がげらげら笑うのを聞いていた。
どこでどうなっちゃったのか。ふたりの会話を聞いていて、めぐ美はうっすらと、本が
絵本に慣れた彼女に、次のステップはごく自然に訪れた。本棚を眺め、華やかな文字の、わくわくしそうな題名の、その背に指をひっかけた。
だけども次へのステップを、彼女は逃してしまうのだ。本を読んでいると、ミイ姉に「ネクラ」とか「キモい」と言われたり、読んでいた本を取り上げられて隠されたりしたせいだとも言えるが、それだけでなく、めぐ美自身が性格を変えたかった。
小学三年生の新しいクラスで、同じ班になった「ひなっち」という子と仲良くなった。運動神経抜群で、男子より足が速いひなっちは、本など読まなかった。休み時間を告げるチャイムが鳴ると、真っ先に教室から飛び出してゆくような子だった。ドロケイでも脱走ゲームでもいつも大活躍のひなっちは、クラスの人気者だったから、そんな彼女に声をかけられて、嬉しかった。
ひなっち、めぐ、と呼び合うようになった頃、めぐ美も彼女と同じく「人気者」というポジションの、端っこにいた。ひとりで本を読むのは寂しいこと、実際寂しくなくても、寂しそうに見られることだという考えを、めぐ美は自分に植えつけた。低学年の頃の自分は、大人数でわあっと盛り上がるノリには気後れした。だけど、ひなっちに引っ張られて遊んでいるうちに、友達は自然と増えていったし、盛り上がることも楽しめるようになってきた。めぐ美は鬼ごっこやドロケイで活躍したし、友達から、友達の多い子だと思われるようになったら、学校が楽しくなった。その自信は、本からでは、得られないものだった。
ひなっちとめぐの間にカナが入り込んだのはいつ頃だったろうと思う。カナは当時の彼女のグループ内で色々と
そして、そのまま、今もカナとめぐ美は「親友」だ。
長い付き合いだから、カナの口癖が「でも」だというのは知っている。誰かが目立つと「でも」と必ず否定せずにはいられないカナの、あまりに大きな自尊心を、めぐ美は間近で見続けてきた。「でも」を言いたい相手は、髪型を変えた同級生の時も、朝会で
カナの自尊心の強さを、めぐ美は見て見ぬふりをする。実際、なんでも強気で向き合っていくカナの「でも」には、説得力があるようにも思った。
▼続きは本書でお楽しみください▼
▼朝比奈あすか『君たちは今が世界』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321903000384/