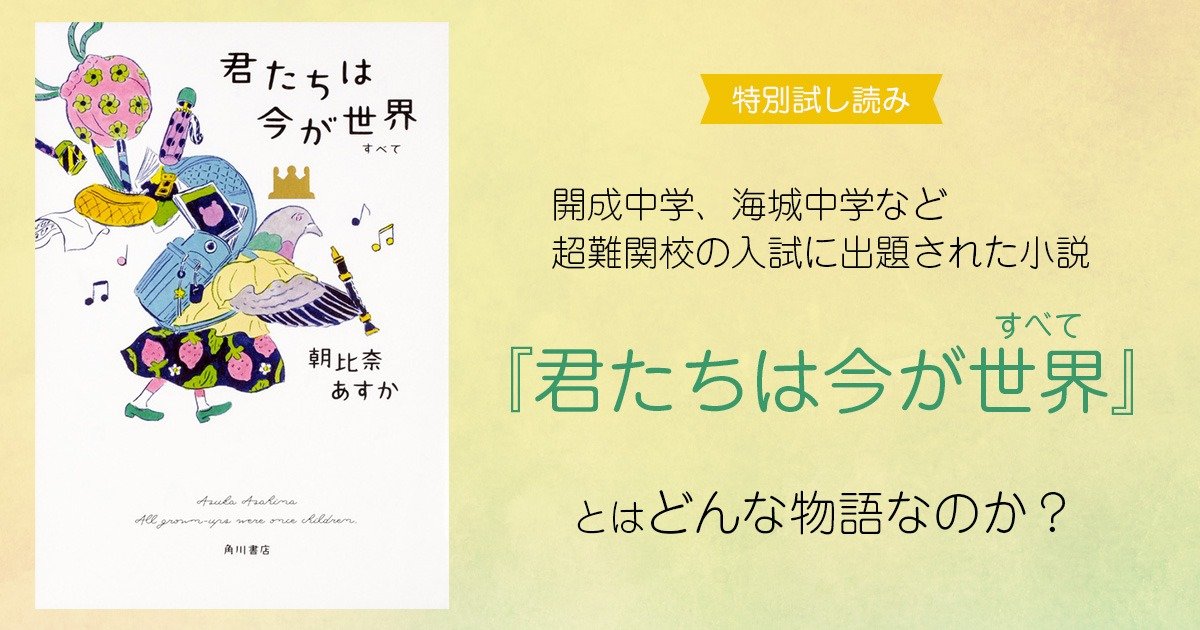開成中学校、海城中学、サレジオ学院中学校など、
2020年度の超名門校の入試問題に続々取り上げられた小説、『君たちは今が世界』。
「国語の入試問題は、学校の先生が入学する生徒に読んでほしい物語」とも言われます。
著者の朝比奈あすかさんが、小学校6年生の教室を舞台に
4人の主人公の目線で描き出す学校=世界とはどんな場所なのでしょう?
今回は特別に、各章の冒頭部分を試し読みいただけます。
>>第1章「みんなといたいみんな」
◆ ◆ ◆
第二章
こんなものは、全部通り過ぎる
こんなものは、全部通り過ぎる。
小学六年生の川島杏美は、そのように考えることが、ほとんど習い性のようになっている。
こんなもの。今、背中からおろしたランドセルも、杏美がそう思ううちのひとつだ。牛革製の濃い赤色のもので、ずいぶんと質が良かったらしく、小学校に入学してから雨風に
そのランドセルから筆箱やら教科書やらを取り出して、机の中の道具箱に入れていると、目の前に人の立つ気配があった。
「ねえねえ、川島さん、宿題やってきた?」
前田香奈枝と見村めぐ美がにこにこしながら、杏美を見下ろしている。
「音読の宿題のこと?」
眼鏡のブリッジを鼻にかけ直し、わざとゆっくり、杏美は問う。
「違う違う」
「算数の宿題」
「計算のやつだよ。ドリルの」
「川島さん、やってきてるでしょ?」
口々に言うふたりの笑顔に若干の
「うん。やってきたよ。見る?」
杏美は自らノートを差し出す。
「えっ、いいの?」
「めっちゃうれしい」
香奈枝とめぐ美は驚いたような顔をして、それから満足気な笑みを浮かべる。
「助かるぅ」
「川島さん、超優しい」
やっていないと答えたところで、どうせ先生には提出しないとならず、噓がばれたらどんな悪口を言われるか、考えたくはなかった。学校の計算ドリルの宿題なんて、たいした手間もかかっていないのだから、見せてあげても何の損もない。この子たちに従わされているんじゃなくて、自ら見せてあげているんだ。
始業前の短い時間に必死になって杏美の答えを写している香奈枝とめぐ美の、ふたつの小さなつむじの向こうで、男子たちがふざけている。
女子ほどはっきりとグループに分かれているわけでは無いけれど、気の合う子どうしで緩やかにつるんでいる男子たちは、声が大きく、言葉が荒い。うるせえとか、変態とか、死ねとか。一組の山形先生が聞いたら怒鳴りつけてくれるだろう言葉も、学期途中で担任教師が変わった「学級崩壊気味」といわれる三組では、休み時間に平気で飛び交っている。
「サンキュー、川島さん」
「助かったあ」
写し終えたふたりが顔をあげて口々に言い、ノートを手に、そそくさと離れていった。
蛍光ピンクのゴムできゅっとまとめたポニーテール。黒いTシャツに白いひらひらしたスカートとグレーのハイソックスを合わせた香奈枝の姿は、後ろから見ても隙がなくまとまっている。
香奈枝は書道の時間に、将来の夢を「バックダンサー」と書いていた。
書道といっても、ゲスト講師を招いて単発で開かれた「アート書道」の授業のことだ。ゲスト講師は、書道アーティストという方で、英語でもカタカナでも何でもあり、いっそ絵でもいいから、自分の字体で、自分らしく半紙に夢を書こうという授業だったのだ。
他の子たちはというと、例えば鈴木結は丸いちまちました文字で「パティシエ」の、「パ」の〇の部分を♡に変えていたり、増井智帆は彼女らしい角ばった生真面目な文字でシンプルに「先生」、三組で一番体の大きな高嶋律子は体格に似合わぬ小さな文字で「オリンピック選手!!」とビックリマークに個性を込めようとしたり、小磯利久雄の「YouTuber」は英語だから目立ちそうなものだが他に三人同じことを書いている子がいたので話題にはならず、瀬野敏は「サッカー選手」の横にボールの絵、尾辻文也は「ゲーム・デザイナー」の「ゲーム」までを大きく書き過ぎて「デザイナー」が
別に、そんなことはどうでもいい。書道アーティストの先生に文字を認められたところで、夢がかなうわけじゃない。
杏美は偏差値の高い私立中学に入って、しっかり英語を頑張ろうと思っている。国連職員は世の中のために役立つ立派な職業だ。バックダンサーなんて、と思う。誰かの
香奈枝とめぐ美はもう、教室の後ろの方の窓辺にいた飯田麻耶や高嶋律子といったクラスの中でも特に目立つタイプの女の子たちと合流し、きゃらきゃらと弾むような声をあげている。そのうち彼女たちは体を揺らして踊りだす。有名なK─POPのグループの、
教室の、その一角だけ、明るく光が射しているみたいに華やぎ、皆が見るともなく気にしている。
やがてチャイムが鳴って、香奈枝はダンスをやめた。
六年三組の教室に、担任の
先月まで、幾田先生がこのクラスの担任だったけれど、今は休職中だ。あんなことがあったのだから、仕方がないと杏美は思うけれど、多美子は「六年生の子たちをほったらかすなんて、無責任だ」と憤慨していた。
五年三組の担任として初めて杏美たちを受け持った時の、幾田先生の小さな目を思い出す。ゾウみたいだなと思ってから、そんなふうに感じるのは女の先生に対して失礼だと思い直したけど、やっぱり最後まで、幾田先生はゾウみたいだった。
「休職」ということは、いつか復帰するのかもしれないが、それはきっと、自分たちが卒業した後になるのだろうなと思う。そして、そのほうが幾田先生にとっては良いことだろうとも思った。
「おはようございます」
教壇に立った藤岡先生の
宝田ほのかの大きな声を聞くたび、感心する。
「日直さんは誰ですか」
藤岡先生が皆に問うた。
「はぁーい」
間延びした声をあげたのは香奈枝だった。杏美から一列おいて斜め前方に座っている。
香奈枝相手だと先生が若干
「名前を書いてないですよ」
先生が言うと、香奈枝はもう一度「はーい」と言ってから、もうひとりの日直の尾辻に、行ってこい、というふうに
「きりーつ」
香奈枝がわざとみたいに、ゆっくりと声をだす。みんな、のろのろと立ち上がる。立ち上がっても、くにゃりと背骨を緩めている。立ち上がらない子もいる。
この教室はしまりがない。
みんな、先月のあの出来事を、もう忘れてしまったのだろうか。
ほのかみたいにいい子ぶる気もないけれど、それでも、クラスの子たちのだらしなさにはいらいらする。
先月、児童のひとりが家庭科の調理実習で食品に洗剤を混ぜるという「事件」がおこった。家庭科の先生や学年主任の先生もおおいに怒って騒ぎになり、その勢いで、当時の担任だった幾田先生が、
──皆さんは、どうせ、たいした大人にはなれない。
と言った。
大人が、あんなことを言うなんて、びっくりした。先生が休職したのは、あの発言が理由だという噂もある。
だけど杏美は、幾田先生の言うとおりだと思っている。この教室にいる奴らは、皆、どうせ、たいした大人にはなれない。
学区の公立小学校だから、仕方なく通っているだけ。こんなものは全部通り過ぎる。
「きをつけェー。れェい。ちゃくせきィー」
香奈枝の声は完全に、先生を、教室を、ばかにしている。ばかにしていることを先生にも思い知らせようと、わざと
「では宿題の計算ドリルノートを回収します。後ろから回してください」
藤岡先生の声もどこか投げやりだ。問題を起こして前任の先生を休職に追い込んだクラスだ。なるべく実害を被らずにやりすごそうとしているのかもしれない。
列の後ろからノートが回ってきたので杏美も自分のノートをのせて回す。
回収したノートは放課後に返される。いつも、大きな丸がつけられて、左下に「よくできました」のハンコが押されている。
以前、返されたノートの大きな丸をつけられたそのど真ん中に、自分がやらかしていた細かな計算ミスを見つけた。採点ミスだ。先生はわたしを信用しすぎているのかもしれない……と思ってから、ふと、先生はこのノートをちゃんと見ているのだろうかと疑った。
それで、いつもより気をつけて先生の行動を見ていたことがある。給食は教室で食べているし、昼休みも校庭の見回りをしている。授業の合間に職員室に戻ることはあるけれど、たったの五分休みだから、ノートの採点がはかどるとはとても思えない。図工や音楽といった専門の先生が受け持つ授業の時に、図工室や音楽室から姿を消す時があるから、きっとその時間帯に採点しているのだろう。だとしても、図工や音楽がない日でも、計算ドリルの宿題は集めている。三十人以上いる子どものノートをきちんと見る余裕が、全くない日だって、きっとある。
杏美は藤岡先生に同情した。
去年、算数少人数教室の専任教員をやっていた時は、もっと、頑張っている感じがした。六年三組を受け持つことになってから、少しずつ目がつりあがってきて、緊張していて、同時にとても疲れている。丸つけくらい手を抜きたくなるのも当然だと杏美は思った。
日直の香奈枝と尾辻が立ち上がり、前列に集まったノートを回収して藤岡先生に渡した。
「ありがとう」
先生が二人に礼を言う。香奈枝も尾辻も何も言わず、目も合わせず、そそくさと席に戻ってゆく。無視や嫌がらせではなく、役割を終えたらそれで終わりといった
子どもにはこういうところがある、と杏美は、自分も子どもだけれど、同級生を見ながら思った。
自分以外の人間に心があると思っていない。その単純さ。
朝の会が終わって先生が教室を出てゆくと、あたりは一斉に騒がしくなった。めぐ美や麻耶たちと集まって、ふたたび踊りだす香奈枝のポニーテールが揺れていた。
香奈枝はばかだから全部忘れちゃうんだなと思った。
杏美は、香奈枝が「はじゅちゃん、はじゅちゃん」と言いながら自分の後ろをついてきた日々を、はっきり覚えている。
舌足らずの香奈枝が「あずちゃん」と呼ぶと、それは「はじゅちゃん」と聞こえたのだ。
保育園で、杏美は香奈枝と「仲良し二人組」だった。
思えば、家が近くて母親どうしが顔見知りだったというだけの理由だったが、赤ちゃんの頃から一緒にいて、周囲からも先生からも「仲良し二人組」として扱われると、ちいさな園の中で、その関係はほぼ固定化された。
四歳になっても、香奈枝は「はじゅちゃん」と、舌足らずに呼んだ。
そのころ杏美は保育園の同じ学年の子たちの中で、一番背が高かった。自分でもよく覚えている。リトミックでも体操でも、何をやってもいちばん上手で、みんなができないのが不思議なくらいだった。お絵描きの時間は大得意だった。他の子たちがどうにかして人間を描こうとしても全部お化けみたいになっちゃう時に、杏美は前髪も
ある時香奈枝が、大きくまるを描いて、その中にぐりぐりと目玉らしきものをぬりこんでいた。できあがったものをみんなに向けて言った。
──これ、はじゅちゃん。
にこにこしている香奈枝を見て、カッとなった。
──わたし、そんな顔じゃないよ!
自分でもびっくりするくらい、険しい声が出た。その声に、目の前の香奈枝が固まった。
香奈枝は無言で消しゴムを探し、ごしごしと絵を消した。消して消して、その指先が真っ赤になるくらいに力を込めて消しているうち、紙が破けてしまったから、さすがに申し訳なくて、杏美は焦った。けれど、優しい言葉を香奈枝にかけることが、どうしてもできなかった。
あの時のことを、香奈枝は忘れてしまったのだろうか。杏美ははっきり覚えている。あんなに強く反応してしまったのは、同じころ母親の多美子が香奈枝の写真を見ていて、
──この子は将来、美人になるわ。
と言ったからかもしれない。
ため息のこもったようなその声には、深い実感があった。
──でも、かなちゃんは何にもできないんだよ。
なぜか杏美はそんなことを言った。
──いいのよ。あれだけ可愛いんだから。
多美子はさらっとそう言ってから、
──あなたは不器量だから、しっかり勉強して、みんなの役に立つ仕事に就かないとね。
と、杏美に言った。
それからしばらくして香奈枝が保育園を退園した。
わたしが絵のことで怒ったから、香奈枝を傷つけてしまったのだろうかと、子どもながらにはらはらと後悔した。そのことを多美子に言ったら怒られそうな気がして、杏美はずっと黙っていた。
実際は、香奈枝の母親が仕事を辞めたために、幼稚園に転園したというだけのことだったのだが、幼い杏美にそんな事情は分からなかった。だから、小学校の入学式で香奈枝が満開の笑顔で近づいてきてくれた時、世界が一気に輝いたように感じた。ふたりが再び、「二人組」になった。当たり前のことだけど、香奈枝はもう「はじゅちゃん」ではなく「あずちゃん」と、呼べるようになっていた。
秋になり、学芸会で『
配役が発表されると、
「あずちゃん、何の役やる?」
香奈枝に
「ナレーター」
と言った。
「かなちゃんは?」
「あたし白雪姫に立候補する」
きっぱり言う香奈枝の目はみずみずしい野心に満ちていた。
すでに杏美と香奈枝の力関係は変わりつつあった。香奈枝はクラスで一番背が低く、発想も幼く、絵や字もへたくそで、計算も遅い。何もかも杏美に負けているのに、一向に気にしていないようだ。気が強くわがままで、そのわがままを通す力を持ち始めていた。
「白雪姫なんて、セリフ全然ないじゃん」
香奈枝のまっすぐな物言いが
「だって、ドレス着れるの、白雪姫だけでしょ。それに」
と、香奈枝が思いがけないことを言った。
「あずちゃんも一緒に白雪姫やれば、一緒に練習できるよ」
▷次回は「第三章 いつか、ドラゴン」をお届けします。
▼朝比奈あすか『君たちは今が世界』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321903000384/