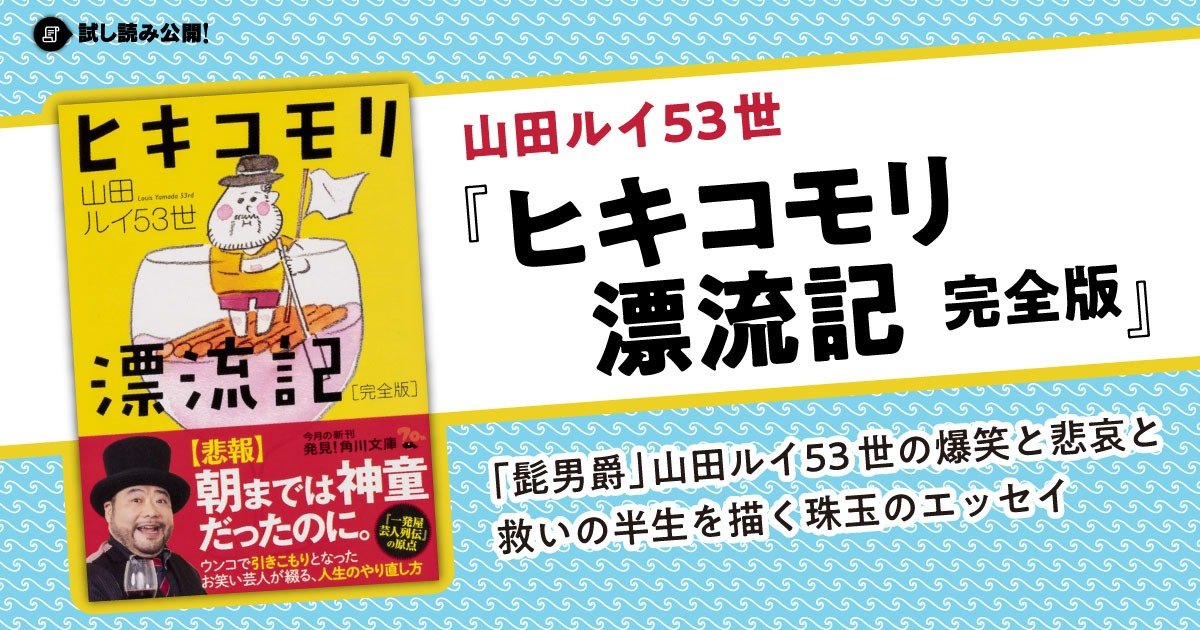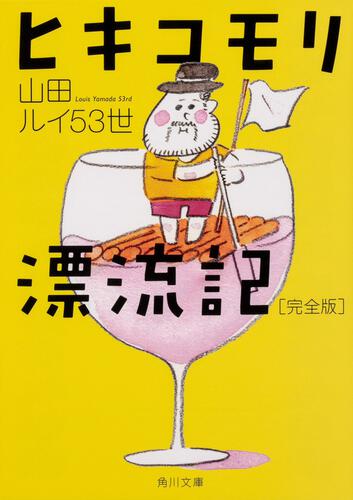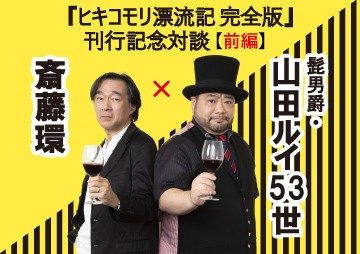かつて神童と呼ばれたお笑い芸人は、なぜ突然引きこもりになったのか? 渾身のルポ『一発屋芸人列伝』も話題の髭男爵・山田ルイ53世の半生を赤裸々につづった衝撃のエッセイ『ヒキコモリ漂流記 完全版』の電子書籍化を記念し、序章と第1章を試し読み全文公開! ヒキコモリ……その暗黒に足を踏み入れる序曲それはまさに“恐怖の胎動”!
なお、電子版には特典として、ヒキコモリ問題を分かりやすく分析した精神科医・斎藤環さんとの対談も収録。この機会に是非お読みください!
第1章 神童の季節
姑息な朝顔のつる
小さな頃は、後々「引きこもり」になるなんて想像もつかないような、活発でやんちゃな子供で、よく度が過ぎたいたずらをやらかしては、親が先生に呼び出されたりしていた。
誕生日が四月で、いわゆる遅生まれだったからだろうが、小学校低学年くらいまでは、
幼稚園の時なんかも、トイレに行けない子がいると、手を引いて連れて行ってあげたり、落とし物を一緒に捜してあげたり、泣いている子がいると職員室に人を呼びに走ったり……そういう兄貴的振る舞いを先生も見ていたようで、ある時、「級長」に任命された。級長は、先生から渡された、サクランボの形をしたボンボンを胸元につける。大人からの信頼の
夏休みに入る少し前、みんなで朝顔の種をまいた。園児一人に一鉢、朝顔を育てさせる。自分の朝顔は責任を持って世話をしなければならない。僕も、皆と同じように、キチンと水をやり世話をした。にもかかわらず、僕の朝顔だけ大きくならなかった。
他の子の朝顔は順調に大きく育っていく。
ふたばが出て、本葉が出て、気が早いのは、つるが伸び始めているものさえあった。
なのに、僕の朝顔は、小さな小さな「ふたば」が出たのを最後に、それ以上まったく大きくならなかった。
そうこうするうちに夏休みに入った。何日かある登園日の度に様子を見てみるのだが、僕の朝顔の上にだけ時間が流れていないのか何の変化もない。僕に落ち度はなかったはずだ。それなのに、現実にこれだけの差が出ている。
単純に種の当たり外れだろうが、
(なぜ、自分だけがこんな目に……)
人生とはなんて理不尽なんだ。これを解決するには、もう実力行使しかない。
追いつめられた僕は幼稚園に忍び込んだ。
朝顔は、各教室のベランダにズラッと並べられている。
教室とベランダは大きな「掃き出し窓」で隔てられている。夏休み中なので、そのガラス戸はもちろん、教室のドアも何もかも、すべて施錠されていた。つまり正規の侵入ルートはない。
僕のクラス、「バラ組」の教室は二階にあった。しかし、都合良く、バラ組のベランダすれすれに大きな木が生えており、それをよじ登って、ベランダに飛び移れることを僕は1年前から知っていた。
無事ベランダに降り立ち、周りをうかがうと、相も変わらず、貧相な「ふたば」止まりの姿で僕の朝顔がそこにあった。
せめて、枯れてなくなってしまえばせいせいするのだが、空気も読まずに、ふたばのまま青々としている。まったくもって忌々しいヤツだ。
「僕は元々こういう種類ですけど?」といわんばかりに、開き直った様子の僕のふたば。隣の鉢には、土に挿された三本の支柱に、しっかりとのびた〝ツル〟を絡ませた素晴らしい朝顔がある。
他の子のものと比べても、それが一番大きく育っているように見えた。
僕は、そのNo.1朝顔を慎重に引き抜いて自分の鉢に植え、貧相なふたばを身がわりに隣の鉢に植え替えた。
それからしばらくして、また登園日がやって来た。久しぶりに会った友達と、夏休み中の出来事を報告し合う。
それらが一段落して、子供達が落ち着くのを見計らい、先生がお話がありますと言って、みんなを集めた。その先生は若い女の人で、幼稚園に勤め始めてまだ日の浅い新人ではあったが、とても熱心な方だと親達の評判は良かった。
そんな彼女の
僕にはすぐに分かった。この泣いている女の子は、先日、僕が勝手に行った朝顔のトレード、その相手に違いない。しかし、自分が手を染めたあの悪事がばれたとまでは、毛ほども思っていなかった。女の子の頭に優しく手を置きながら、体育座りをした子供達を前に、先生が話し始める。
「○○ちゃんの朝顔が、突然小さくなってしまいました……皆さん、どう思いますか?」
えっ? 小さくなった? どういうこと?
ざわざわと戸惑う周りの子供達を、慎重に目の端で観察しつつ、自分だけが浮かないように、リアクションの温度調節をしながら、僕は、「えらいストレートに聞いて来たな!」などと思っていた。我ながら、
ふと先生を見ると、
「バチーン!」という衝突音が聞こえたかと錯覚するくらい、しっかりと目が合い、先生と僕の視線は、ギッチギチの固結びにされた。
再び先生が、「皆さん、どう思いますか?」と呼びかけた。
勘違いではない。「皆さん」と言いながら、彼女は僕のことしか見ていなかった。ロックオンされている。ばれた。それでも往生際の悪い僕は、「なんでそんな不思議なことが起こったのかな? っていうか、○○ちゃんかわいそうだねー!?」的な表情を浮かべ、しらばっくれていた。
すると先生、今度は、「山田君は、どう思いますか?」
包囲網が狭まっていく。
周りの子供達は、おそらく、「サクランボの級長さんだから、先生は山田君に聞いているんだ」なんて思っていたに違いない。
答えに窮して、「キョトーン」の芝居をいまだ続ける僕に、
「山田君の朝顔は、急に大きくなりました……どう思いますか?」
その若い女の先生は、
子供らしく、泣きながらすべてを白状する山田君。それを、寛大な心で許し、何か子供達のその後の人生に影響を与え、心に刻み込まれるようなメッセージを述べるわたし。改心し謝る山田君。他の子供達からの拍手。めでたしめでたし……しかし、現実は違う。
子供は噓をつく。特にこの姑息なガキは。現実の世界では、大人の方が単純かつ、メルヘンチックであり、子供の方が複雑でリアリストなのだ。
先生の目は語っていた。
「お願い!! 山田君、お願いだから、自分から言って。先生をガッカリさせないで。先生、信じてるよ……お願い!」
先生の目をまっすぐに見つめながら僕は答えた。
「分かりません」
急速に、先生の目から光が失われていくのが分かった。花火を途中でバケツの水に「ジュッ!!」とつけたかのように。
情熱を持って幼稚園の先生になり、つい先程まで、子供達に注がれていた、熱く優しい
そしてある日、一人の園児の朝顔が急激に巨大化する一方で、別の園児の朝顔は、時間を巻き戻したかのように小さくなっているのを目撃する。
今まで、自然界で確認されたことのない、学会でも報告されていないであろう超自然現象が、自分の職場で起こったのだ。
さぞ、驚いたことだろう。
もちろんそれは、世紀の科学的大発見にではなく、純真
結局、その場では、それ以上の追及はなかった。が、その後すぐに職員室に呼び出される。ガラス玉の目で無言でしばらく僕を見つめたあと、先生は、僕の胸のサクランボをむしりとった。母に糸でしっかり縫いつけてもらっていたので、僕の体は先生の方へとグラッともっていかれたが、彼女はまったく意に介さなかった。「ブチーン!!」という派手な音がした。
「分かるよね? 山田君にこれを付ける資格はありません!!」
姑息なヤツは失敗する。
産地偽装の詩
小学校二年生の時。
国語の宿題で書いた「詩」が、地元新聞に取り上げられた。それは、「小さな目」という欄で、「子供ならではのまっすぐな目線で紡がれた文章や詩を紹介する」というのがその趣旨だったと思う。
地方紙とはいえ、僕の住んでいた町では、大体、どの家庭でも取っている新聞だったので、自分の子供の作品が載って、親も随分と鼻が高かったようである。その証拠に、息子の詩が掲載された新聞を、
「何をそんなに
「順君(僕のこと)はほんまえらい子やねー! うちの○○にも読ませたわー!!」などと大いにちやほやされた。
詩の内容から、皆が僕に、「兄弟想いの心の綺麗な少年」との印象を受けたようだった。しかし、事実はその逆。全ては計算ずくだったのである。
第一に、僕は知っていた。
というのも、家が近所でよく遊んでもらっていた上級生のお兄さんから、
「この時期に出る国語の詩の宿題は、新聞社に送られて、出来の良い作品は掲載される」という情報を入手していた。そして何より、
先生は随分「大根」だったようだ。
とにかく、それを敏感に
「これは、いつもの宿題ではない」
そう確信し、全力で「
それにしても、なぜ小学校二年生の自分がそんなにも新聞に載りたかったのか? たまたま何かで目にした新聞記事に、アンモナイトか恐竜の歯か忘れたが、何かその手の「化石」を発見した少年の話が載っていたのだ。自分と同じような年齢の小学生が、新聞に載っている。そしてそれを周りの大人が手放しで褒めている。
本来なら、自分と変わらない年齢の子供が、独学で恐竜や化石のことを勉強し、それを発掘するに至った、その情熱の方に刺激されるべきなのに、「新聞に載った」という部分にのみ感化されてしまったのである。
すべてを知った上で考えた。
「どのようなテーマが大人ウケするのだろう?」「どんなワードを使えば小学生っぽく見えるだろう?」
「っぽく」もなにも正真正銘の小学生である。
書いては消し、書いては消しを繰り返した。
「駄目だ駄目だ……大人達は少し足りない感じを好むはずだ……言い過ぎちゃ駄目だ!」「もっと、子供らしい舌っ足らずな感じを出すんだ!!」
そんな、およそ子供らしからぬいやらしい計算の下に出来上がった詩が新聞に載った。
親も、学校の先生も、新聞社の大人達も、そして、もちろん、それを読んだ人達も先述の通り、
「この作者の子は、とっても優しい子なんだなー!!」などと思ったことだろう。
しかし、大人達が舌鼓を打って召し上がった、「天然物の子供らしさ」は、その実、偽物の、意図的につくられた養殖物だったのである。
「産地偽装」である。
やらしい悪癖
「産地偽装」で作られた、そんな詩がこちら。
『ぼくのランドセル』
ぼくのランドセルはおにいちゃんのおふるだ
おにいちゃんがつかったからペッタンコだ
ぼくもだいじにつかって
おとうとにあげる
実にいやらしい。特に、平仮名の意図的な多用は、胸焼けがしそうだ。
当時、大人向けの本も大量に読んでいたので、小学二年生にして「
ただ、ひとつ言っておきたいのは、実際、僕が使っていたランドセルは、兄のお下がりだった。そこに噓はない。元々は黒いピカピカのランドセルだったはずなのに、全体的に色落ちして灰色になっていた。あちこち傷だらけで、おそらく、何度も座布団代わりにでもしたのだろう、型崩れが激しく、ペッタンコになっていた。一体、どんな荒々しい使い方をすれば、これほどの「風格」をランドセルごときが
当然、本当はそんなボロボロのランドセルが嫌だった。それを背負って学校に行くのが、恥ずかしくて仕方がなかった。
小学校入学時、他の皆は、ふっくらとして、ボリューム感のある「焼き立て食パン一斤」のような綺麗なランドセルを背負って登校する。文字通り、ピカピカの一年生だ。なのに自分のそれは、「カビの生えた八枚切り食パン一枚」くらいの感じだった。実際ちょっと生えていた。おかげで僕は、小一にして、「さすらいの小学生」と表現してもしっくりくるくらいの、あたかも数々の修羅場をくぐりぬけ壮絶な武者修行を経てきたような、
本心では、
「なんで自分だけ、こんなランドセルなんだ?」
と不満タラタラだったのに、褒められたい欲にかられて書いた偽りの詩(うた)。
最近親に聞いたところ、さすがに僕のランドセルが、ボロボロで汚すぎると気になっていて、そろそろちゃんとしたのを買ってあげようとなっていたらしいのだが、詩を読んで感動し、子供の気持ちを尊重して買うのをやめたと言っていた。
結局僕は、小学校の六年間、そのボロランドセルを背負う羽目になる。
ちなみに五歳年下の弟は、新しいランドセルを買って
策士策に
謎の見せ本
我が家は、別に由緒ある家柄でも名家でも、地元の有力者でも、資産家でもなんでもなかった。父はただの平凡な公務員である。なのに、妙にお堅い家で、何年もの間、「くだらない、馬鹿になる」という、それこそくだらない、馬鹿な理由で、我が家にはテレビがなかった。
僕が小学校高学年の頃にようやくテレビが家にやってきたのだが、それでも観て良い番組は時代劇かNHKだけで、いわゆる民放のバラエティー番組とかは禁じられていた。刑務所みたいな方針の家である。
テレビは見させてもらえなかったが、本……というより、書籍といった方がニュアンス的には近いヤツが大量に揃えられていた。スタンダールの『赤と黒』とか、ドストエフスキーの『罪と罰』とか、ゲーテの『ファウスト』とか、ハードカバーの古典作品がところ狭しと本棚に並んでいた。
子供の
どうやら僕しか読んでいなかったようである。
そんな本がなぜ我が家にあったのか?
漫画本も禁止。ただ、歴史物、偉人伝系の漫画は許されるという、暗黙の了解というか、抜け道があった。なので、小学生の僕は、自転車に乗って電車で駅四つ程離れた街にある図書館に通い、他の子供達が『少年ジャンプ』や『なかよし』なんかの漫画雑誌を読むのと同じテンションで、「
親が意図的にそうしていたのか、それは定かではないが、世間で普通に
当時、流行っていた、ゲーム&ウオッチや、ファミコン、キン肉マン消しゴム……とにかく、ありとあらゆる娯楽が我が家にはなかった。
ライラライ♪
父には自分の趣味に
キャッチボールが好きで、僕が小学校3年生くらいまでは、何かというと相手をさせられた。
近所の公園、日曜日の小学校のグラウンド、我が家から自転車で小一時間ほどの神社の境内、家の前を通る道路……とにかくありとあらゆる場所でキャッチボールをした。
一見、良い父親である。しかし、おかしなことに、毎回、僕は座っていた。キャッチャー役ばかりさせられていたのである。
通常、父と子のキャッチボールと言えば、〝ボール〟のやりとりより、〝会話〟のそれが重視されるもの。
しかし、我が家では違った。ただ黙々とやる。
父は小学校低学年の子供に、大きく振りかぶって、ビュンビュン球を放り込んでくる。手加減は一切ない。本気も本気である。
別に、若かりし頃、高校野球で惜しい所まで行ったとか、当時、役所の草野球チームに入っていて、週末大事な試合があるとか、そんな伏線も全くない。
ただただ、本気。厄介である。
一度のキャッチボールで、百球近く投げ込むことも珍しくなかった。
メジャーリーガーなら契約違反だが、父は一介の公務員……肩の消耗を心配する必要などない。
最初におかしいなと思ったのは、友達とキャッチボールをしているとき、他の子達が持っているグローブを見た時である。
彼らのグローブは野手用で、〝シュッ〟としたフォルムなのに対し、僕のは閉じるとたらこ唇のようになる、もっさりとしたキャッチャーミット。
しかも、かなり使い込まれたボロボロの代物で、何箇所か、本来〝結んである〟ような部分も
丁度、ボールを受け止める部分、一番インパクトが強い
どうも父の球を僕が受けた時、いい音がするように細工してあったらしい。
ほとんど、素手で球を受けているような状態。痛かったが、僕も父とのキャッチボールは嫌いではなかった。
そんな少年が、野球に興味を持つのは自然な流れ。
ところが小学校高学年になり、部活を始める際、
「野球部に入りたい!!」
と両親に申し出ると、あっさり駄目だと言い渡された。
野球は用具が多くて、お金が掛かるし、休みの度に親が駆り出され、色々邪魔くさいというのがその理由だった。
だったら、なぜあんなにキャッチボールをしたのか。あれだけ、野球に子供の興味を〝誘導〟しておいて、急に「
これまた今でも、謎である。
父は、音楽も好きだった。
特に、クラッシック。
ドボルザークやベートーベン、チャイコフスキー等々、オーケストラが演奏したレコードを沢山持っていて、休みの日になると大事そうにとりだし、プレイヤーにセットして、そーっと針を落として聴いていた。
たまに付き合わされたが、普通の小学生の子供は、クラッシックなんかに興味はない。
さらにそういうオーケストラの演奏もののレコードは、基本的に〝長尺〟なので、その時間は苦痛以外の何ものでもなかった。
僕は当時から、父はクラシックが好きなのではなく、クラッシックを好きな自分が好きなんだと思っていたので、そういう時は大概、
「はいはい、分かったから……高尚な趣味持ってんのはもう分かってるから」
などと心の中で毒づいていた。
寝る前には必ず父がチョイスした音楽を「子守
洋楽も好きだった父の選曲で、一番良く聴かされたのが、サビの部分が「ライラライ、ライライライラライライー♪」という歌詞のヤツで、こう言っちゃ悪いが、とても陰気な曲だった。
健やかな睡眠を考えるのであれば、お得意のクラッシックの方がまだ効果的だろうと思うのだが、何故か寝る時は必ずこの「ライラライ♪」を聴かされた。
毎晩、英語で意味も分からない、陰気な曲をBGMに眠る……一種の洗脳である。
しかし、父はお構いなしである。
当時の僕が、かなりのストレスを感じていた証拠に、関連こそ証明できないが、ほぼ毎晩悪夢を見た。寝言も
さらには、数カ月に一回、夜中に飛び起き、二階の自分の部屋から階下に下りて、玄関まで走って行き、ドアを開け、
あのままいっていたら、早晩、ブリッジで階段をバタバタと下りる羽目になっただろう。
とにかく当時、「ライラライ♪」が、父のお気に入りのナンバーだった。
大人になって調べてみたら、「ライラライ♪」は、「サイモン&ガーファンクル」の「ボクサー」と言う有名な歌だった。
歌詞の内容を、はしょってザックリ記す。
「夢見て、都会に出て来た1人の男が、現実に打ちのめされ、なんの希望もなく、彼女すらいなくて、しかしどんどん年だけ食って行く……それでも〝生活のため〟にリングに上がり、殴り合いをしないと駄目だ……もう嫌だ!! 故郷に帰りたいよー!!」
恐怖で震えあがった。
「故郷に帰りたいよー」はさて置き、
たとえ、バイリンガルでもなく、歌詞も理解出来ない子供だとしても、その脳や
「パブロフの犬」の〝条件反射〟さながら、〝負け〟を目の前にすると
あんな歌を子供に毎晩聴かせていたら、科学的根拠はないが、少なくとも、他の児童より一発屋になる確率は格段に跳ね上がりそうである。
妙に合点がいき、怖くなった。
笑えない。
この呪いを解くには、「能天気で何のメッセージもないお気楽ソング」を向こう十年間は聴き続けないと駄目だろう。
誰の曲とは言わないが、それはそれでまた拷問である。
頑固で、厳格な父
父は、
「昨日、なんで帰らへんかったん?」と尋ねると、
「張り込みや」なんて答える。
税関職員も、港で不審な船舶などの張り込みをするそうな。
「刑事みたいで格好良いなー」と思った。
張り込み以外にも、船に乗り込んで行って、不審な物がないか捜索することもあったらしく、晩ご飯の時なんかに、武勇伝を話してくれた。
そういう話の中には、「ロシア人船員と格闘の末投げ飛ばした」みたいな威勢の良いエピソードもあり、小学生の僕は、「おとん、かっこえ~な~!」と素直に尊敬したものだが、中学生の時分、一度父と取っ組み合いの
そういう、税関職員としての、仕事道具のひとつだと思うのだが、我が家には、「伸び縮みする指し棒の先端に、角度が自在に変えられる鏡が付いた器具」があった。
もし仕事道具じゃなかったのなら、あんなものが何故家にあったのか……聞くのも怖い。
おそらく、本来は、税関の仕事で、外国の船舶に立入検査をする
が、我が家においてはもっぱら、兄や僕が隠し持った漫画本や、奇跡的に入手できたちょっとエッチな本などを「捜索」するという、しょうもない用途に使われていたようだ。
学校が終わって帰宅し、自分の部屋に行くと、隠していたはずの漫画本や、エッチな本が、勉強机に「ドンッ」とこれ見よがしに置いてある。
どれだけ巧妙に隠しても、数日もすればその場所からは消え、自分の机の上に出現するのだ。
天井裏に隠しても駄目、カーペットの下に忍び込ましても駄目、雨で
伝書鳩並みの帰巣本能がエロ本にあるわけはないのだから、父の税関職員としての「捜す能力」を褒めるしかない。ロシア人を投げとばせなくてもさぞかし「腕っこき」の職員だったに違いない。
ある日、僕は父の書斎を物色していた。
特に何か入り用で、捜し物をしていたわけでもない。明確な目的はなかった。僕はただ、「人の部屋を物色する」という浅ましい行為に興奮し、魅了されていた。勝手に子供の部屋を物色するような親の背中を見て育つと子供もそうなる。
「物色のDNA」はここに受け継がれていた。
父の仕事机があった。なんとなく……本当になんとなくなのだ。その机の一番下の引き出しの、奥の方を探っていると、VHSのビデオテープが出て来た。ビデオテープという代物の存在は、学校でも理科の授業なんかで使われていたので知っていたが、我が家には、それを再生するビデオデッキもなければ、そもそもテレビ自体がない。
いったい何のビデオかなと、おもむろにそのテープの背中を眺める。
父の名誉のためにも詳細は避けるが、タイトルを見て、僕は
それは、人生で初めてお目にかかった「AV」だった。
最初、「これはきっと、お父さんの税関の仕事のヤツだ。押収物とかいうヤツじゃないか?」と思った。思いたかった。よく考えれば、そんな「証拠品」を自宅に持ち帰るのもおかしな話なのだが。そもそも何の証拠だ。
だが、子供とはけなげなもの。心が、厳格な父のイメージを反射的に守ろうとしたのだろう。それが崩れるということは、それに従って生きてきた自分をも否定することになる。
「例のロシア人船員からとりあげた物かも」
そんな風にも考えてみた。
大体、これをどうやって見るというのだ。何度も言うが、我が家にはそもそもビデオデッキもなければテレビもないのだ。よって、父がこれを鑑賞しようと思って所持しているわけがないじゃないか……必死で考えを巡らし、自分の中で何か大事なものが崩壊しそうになるその瀬戸際で、なんとか踏みとどまった。
その週末、我が家に新品のテレビとビデオデッキが届いた。
あれだけ、子供に教育上の観点からテレビを禁止していた父が、結局AV見たさにテレビ、及び周辺機器までまとめて揃えたのだ。ただ、そのことで、父を
むしろ、ここまでいとも簡単にあの父親の心を溶かすAVなるものに尊敬の念を抱いた。おかげで我が家にも人様並みにテレビやビデオがやって来たのだ。AVには感謝である。自分でも意外だったが、今まで頑固で厳格で恐ろしいだけの存在だった父が、実は同じ人間なんだと思えてどこかホッとしていた。