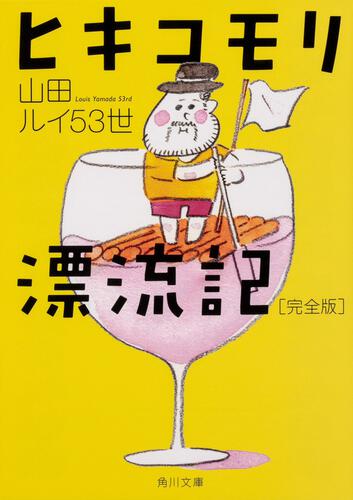その秀才ぶりからかつて「神童」と呼ばれた髭男爵・山田ルイ53世が、突然引きこもりとなり、苦悩、葛藤の末、引きこもりから脱出する半生を描いた話題の書『ヒキコモリ漂流記』が完全版となってついに文庫化。その発売を記念し、引きこもり問題の第一人者である精神科医の斎藤環氏との対談が実現。著者の引きこもり体験を、専門家の視点で分析、果たしてその結果は?
――単行本の『ヒキコモリ漂流記』の発売は2015年ですよね。
山田ルイ53世(以下、山田):そうですね。3年ぐらい前ですね。
斎藤環(以下、斎藤):『ヒキコモリ漂流記』は、引きこもりの経緯もさることながら、中学に入る前から始まったという「強迫」の描写がすごかったですね。勉強の前に掃除をしないといられないという「こだわり」の描写が。
山田:あれやっぱり、そういう名前付く行為ですよね。
斎藤:付きます。十分付きます。几帳面のレベル超えてますよね。
山田:ああ、やっぱりそうや。当時は「俺だけ変やな」と思ってたんですけど、大人になってこれ書いてるときになって、コレ何か、ナントカ症みたいな名前付くなあと思って(笑)。
斎藤:筆圧が強過ぎて、折れて飛んだシャーペンの芯を捜さないと、勉強が始まらないってすごいですよね(笑)。見つかります?
山田:多分これは前に飛んだやつやな……みたいなのが見つかっても、これでとりあえず納得するとか。なんせこの、「見つけた」「取った」「捨てた」っていうのがないと次に行けない。今でもちょっと「こだわり」の名残りがありますよ。
斎藤:あるんですか?
山田:あります、あります。角が揃ってなきゃイヤだとか。
斎藤:だけど、それは普通の几帳面なレベルという感じですね。
山田:まあ、いいところにおさまったということですかね。でも、それって一時的におさまっただけで、またバーッとぶり返すことってあるんですかね。
斎藤:引きこもっちゃった人って、結構な割合でそういうふうになるんですよね。だから、どちらかといえば、そういう傾向があったのかな、という気もしましたけど。ちなみに、その当時治療は受けてらっしゃらないですよね。
山田:ないです、ないです。昔はそういう専門治療受けるの恥やみたいな空気があって。僕は全然治療を受けたほうがよかったな、と思いましたね。そのほうが楽ですよね、絶対。
斎藤:そうしていたら、親御さんの当たりも少し柔らかくなっていたでしょうね。
山田:確かに(笑)。
斎藤:ただね、山田さんレベルの「強迫」だと、かなりどっさり薬飲まされるんですよ。医者から見たら完全に「強迫性障害」と診断されるレベルなんで。
山田:やっぱりそういう投薬治療みたいのがあるんですか。
斎藤:「強迫」って6割ぐらい薬で治るんで、出しちゃうんです、やっぱり。
山田:そうなんですか。いや、お話を聞いてスッキリしました。
斎藤:薬を使わない治療をする人も最近は増えてます。
山田:それはどうやってやるんですか。
斎藤:それは「認知行動療法」といって、こだわりをまず自覚させるんです。
山田:これに君は「とらわれてるんだよ」という。
斎藤:そうですね。それと、行動記録もつけてもらうんですよ。
山田:俺、それ書いてたなぁ。
斎藤:あ、書いてました?(笑)
山田:よかったのか悪かったのかちょっとわからないですけど、僕、確かに全部書かんと気が済まん時期があったんですよ。
斎藤:何を書いてました?
山田:朝起きてとか……今でもちょっと名残りがあって、手帳のスケジュール表あるじゃないですか。で、その日の仕事の出来、不出来みたいなのとかを、1日の終わりにOKかダメかみたいなん書いて、書かないとなんか気持ち悪い。ただ、ノートにその日あったこととかを全部書くことで、僕の中でちょっと安定する部分はありましたね。
僕、ベタなんですね。よくあるパターンなんですね? (山田)
――いろいろなところでお話しされているとは思うんですけども、どういう経緯で引きこもりになってしまったかというのを改めてお聞かせいただけますか?
山田:もう僕は今、当時の自分を先生に診てもらいたい気持ちでいっぱいなんです。いらっしゃったんでしょうかね、当時。30年近く前、僕が13、4、5歳ぐらいのときって、先生みたいな専門家の方って。
斎藤:80年代ですか。いないですね。「引きこもり」って言葉がメディアに出始めたのは90年代の半ばなんですよ。2000年代にブームになるんですけど、全然その頃は何だかわかんなかった。
山田:それ以前は「登校拒否」とか、そういう言い方ですもんね。
斎藤:そうですね。「登校拒否」とか「不登校」とか言っていた時代で。だからルイさんの場合、不登校という括りに入っていたんじゃないかと思いますね。
山田:保健室登校みたいなパターンもちょっと経験しましたし。いや、だから、当時……何でしたっけ、ご質問。
――あ、きっかけです。
斎藤:(笑)
山田:きっかけは、やっぱりウンコ漏らしたっていうのが一番大きかったですけど。これ逆に聞きたいんです。「引きこもりのきっかけトップ3」みたいなの、ないんですか(笑)。
斎藤:ルイさんの場合、すごく典型的なのは、漏らしてにおいが充満しても、誰にも言わなかったんですよね?
山田:言わない。僕も言われなかったですから。
斎藤:つまり、直接「ウンコ漏らしやがった」とか言われたわけじゃない。
山田:はい。「ウンコマン」とも言われてないです。
斎藤:言われてないですよね。でも、自分で言われることを予期して学校に行かなくなったじゃないですか。これ非常に典型的なんですよ。
山田:ベタなんですね(笑)。
斎藤:そうですね。いや、ウンコ漏らす(笑)……
山田:すみません。立派な先生に何度も「ウンコ漏らす、ウンコ漏らす」って言わせて申し訳ないですけど(笑)。
斎藤:「失敗の予感」だけでこもっちゃう人がけっこういるんですよね。そのへんがある種、典型かなと。
山田:実際に何か粗相をしたり、やらかしたりしなくても、「こうやって、こうやって、こうしたら、俺、多分こうなるやろな」……で、もう行かへんという。
斎藤:そこからは雪だるま式なんですよ。この本ではそのあたり非常にリアルに書かれているので、すごく共感呼ぶと思いますね。
山田:もう少し早く先生とこういう話をしたかったなと。当時先生と話ができてたら、ものすごくよかっただろうなと思う反面、今になると僕がやってきたことは、引きこもりの過程とか、そのときの症状とか、折れたシャーペンの芯見つけなもう先に進まへんとか、角揃えなあかんとか、「イーッ!」となってしまうみたいなことが、実は「あるある」だったというね……じゃ、僕、ベタなんですね。よくあるパターンなんですね?
斎藤:あと、もともとすごく秀才というところもパターンです。
山田:先生、僕、この本書いてるときは、「けっこう俺って変わってるなぁ」みたいな、そういう変な高揚感も多少ありながら書いてたんですけども、けっこうベタなやつだったという。これは恥ずかしいですよ(笑)。
斎藤:いやいや(笑)。ある時期までは、そういう人、本当に多かったんですよ。昔は不登校から引きこもる人がほとんどだったので。ちなみに、最近は就労後にこもる人も増えましたね。
山田:なんかすごい年齢が上がっているという。
斎藤:上がってきてるんですよ。あと、不登校から引きこもる子の中にかなりの割合で、「出来がすごくいい子」がいます。プライドが高い子。
山田:僕です、僕です(笑)。
斎藤:そういう子が、「つまずき」とか、その「予感」で、こもっちゃう。
山田:じゃ、逆にいうと、「あるある」というかベタなパターンが今はわかってるから、そういう子が引きこもっちゃった場合の対処方法は、けっこう進んでるんですか。
斎藤:そうですね。私の場合、まずやることはほとんど家族会議なんですよ。
山田:へぇー。
斎藤:ルイさんのご家族の反応もベタなんで(笑)。
山田:俺のことはいいです。親までベタ呼ばわりするのはやめてください(笑)。
じゃ、けっこう子どもが急に引きこもって、戸惑ってしまって、ああいう感じになるという。
斎藤:まともな親御さんなら、こう反応するという典型的なパターンですね。
――ルイさんのケースは、対処しやすいパターンだったのでしょうか?
斎藤:そうですね。対処するとしたら親御さんにまず私が会って、「これは引きこもり的な状況なので、もうちょっと違う関わり方をしてください」みたいなことを言いますね。
山田:なるほどね、じゃ、僕たちはベタ家族だったんですね(笑)。

――家庭環境とか家族構成とか、引きこもるケースに何か傾向ってあるんでしょうか?
斎藤:ありますね。普通はご長男のケースが多いんです。
山田:ああ。僕、次男です。
斎藤:次男ですよね。だから、ルイさんの場合、そこは「典型」じゃないんです。なんで長男が多いかっていうと、やっぱり期待されるからっていうのがあるんですけど、そのへんはどうだったんでしょうね。この本を読むと、受験は全然期待してなかったみたいじゃないですか、親御さんは。「受験したきゃすれば?」みたいな感じで。
山田:僕もでしたけど、親も中学受験という発想がそもそもなくて、細野君という友達が勉強してるの見て「何これ?」と思って、カッコええなと、これやったら俺もちょっと褒められるな、みたいな、もうそんなことから急に受験って言い出したことなんで、親も全然そういうのなかったんです。
ただ、僕、中学受験やる前も、ずっと成績はよかったんです。3段階ぐらいの通信簿でしたけど、小2ぐらいのときにすごくよくて、そこからなんか次の年もそうでないとダメやなみたいな、そういうプレッシャーは僕にもあったし、親も「成績がいい子ども」という状態に慣れ過ぎてて、それが当たり前みたいにはなってた感じはしますね。
斎藤:慣れてくると親としては、上昇志向というか「いずれ東大に」みたいな感じにならないんですかね。
山田:東大とは言いませんでしたけど、親父はよく「下を見るな、上を見ろ」みたいなことは言うてましたね。
斎藤:具体的に中学受験という提案はしてこなかったんですね。
山田:それはなかったです、確かに。ただやっぱり、勉強も運動も頑張らなあかんみたいなことはありましたし、大晦日、正月とかは、うちの近所というか何キロか離れたところに「雌岡山」みたいな名前の山があって、必ずそこまでマラソンして、甘酒飲んで帰ってくるという行事とか、けっこうスパルタっぽい感じはあったんですね。
斎藤:キャッチボールの件も(笑)。
山田:キャッチボール……あれは多分親父が投げたかっただけだったんですけど(笑)。
斎藤:あれだけ投げ込んておいて野球部は反対というのはね(笑)。
山田:そうなんです。いや、あれはお金かかるからです、絶対。
斎藤:お金かかる(笑)。ああ、なるほど。
山田:地域のコミュニティで、とくに親父のほうは若干浮いてたんですよね。ちょっとキレやすい人で。だから、家建てるときも、生け垣の木の植え方とかで職人とすごい揉めたっていうのを母親がもうずっと言うてましたから、けっこうすぐ揉めちゃう人なんです。
斎藤:そうなんですか。ちょっとそこは典型的じゃないところですね。一般的には、期待に押しつぶされてとか、非難されたりとか、挫折したりとかってことがけっこう多くて。そこはすごいところですよね。ルイさん、自分で行動に出ますし。
山田:そうなんです。セルフなんです。そういう人もいるんですよね、おそらく。
斎藤:いや、そこは珍しいと思います(笑)。
山田:そこはベタじゃないんですね。変わってる、俺、変わってるわ(笑)。
――そして6年間引きこもって、脱出するきっかけが成人式。
山田:はい、そうですね。
――つまり自分の力で脱してるわけですよね。これはレアなケースですか。
斎藤:レアですね。自力脱出ってほとんどないんですよね。
山田:レアなんですか。ちょっと怖い話になりますけど、1回引きこもったら、何らかの助けがないと出てこられないもんですか。
斎藤:推定ですけど、毎年数万人の人が新たに引きこもってるんですよ。
山田:えぇー、そんなに?
斎藤:脱出できてる人は、1000人いないんじゃないかというぐらいですね。
山田:何パーですか。ちょっと先生、パー、パーだけ教えてください。
斎藤:パーって(笑)。2万人いるとしたら、本当0.5%とかそんなんですね。
山田:少ないですね。ほとんどがそのまま続行ってことですもんね、引きこもると。
斎藤:入学する人はいっぱいいるけど、卒業する人はほとんどいない。ダムって、100年経ったら大体土砂に埋もれるらしいんですけど、それは土砂が流れ込んでくるけど流出していかないからなんですよね。「引きこもり」でも同じ現象が起こっていて、たまる一方。毎年平均年齢が上がってるのは「たまる」からなんですよ。ちなみに引きこもりの平均年齢、20年前は21歳だったんですけど、最近の統計では34歳なんです。
山田:ぐっと上がりましたね。
斎藤:今は、30代後半になってると思います。
――それこそ10年以上とかってケースも?
斎藤:平均155か月です。10年なんてもんじゃないです。
山田:その20歳から30いくつまでの10年ちょいの間に、社会に出ていくきっかけがないってことなんですか?
斎藤:そうなんですよ。ただ、抜け出した人たちにおおよそ共通してるのは、お友達とか家族以外の人と接点があることなんです。それがけっこう大きい。
――接点が家族だけだと、対応はより厳しくなるものでしょうか。
斎藤:ていうか、無理ですね。
山田:無理なんだ……。
斎藤:同居してるともっと難しくなりますね。ちなみにルイさんは、アパートに出られたでしょう?
山田:僕、途中で何度かアパートに……あの、このあいだ脱走犯がいた向島っていうのがありますけど、僕、あそこなんです。
斎藤:なるほど。
――脱出できるというその0.5%は、呼びかける友達がいたということでしょうか。
斎藤:抜け出せって言うんじゃなくてもいいんですよ。たまに「つるむ」相手がいるだけでも違う。
山田:うん。それは絶対違うと思う。ただ、心がもう何も受け入れない感じになってしまってるケースってあるじゃないですか。そういう場合は、どこから切り崩していったらいいというか。
斎藤:本当に自暴自棄になっちゃって「もう生きてる価値ないから死ぬしかない」みたいになってしまうことも多くて、そういうときはどんな説得も通用しないですよね。でも、説得という形で関わると、否定しか返ってきませんけど、行動の中に「なんとかしよう」という意志が見え隠れするもんなんですよね。だから、ルイさんでいえば、例えば、筋トレとかするじゃないですか。
山田:します、します。してました、はい。
斎藤:あと、ジョギングとかもされたでしょう。
山田:夜中の2時、3時とかですけども。
斎藤:それってなんとかしようとする前向きな行動ですよね。
山田:そうなんです。まあでも、そうすると安心するみたいなんもあったんで。みんな、本当はしたいんですよね、絶対。
斎藤:どこかに向上心はあるんですよ。それを少しずつ拾っていくと、だんだんと前向きになって、どこかできっかけがつかめるんです。
山田:なるほど。じゃ、例えば「ちょっと外に出る」でも積み重ねれば、だんだん大きなモチベーションになってくるということなんですね。
斎藤:そう思いますね。ただ、やっぱりそこで家族がダメ人間扱いすることが多くて、そうされると、本当にがんじがらめになっちゃうんですよね。
山田:今、6歳の娘を叱るときとかでも、ちょっと「陥ってる」みたいなときがあって……。例えばゲームやってて、約束の時間過ぎてるのにやめへん。「やめなさい」と言ったら、ギャーってなる。なったときに、「それやったらもうこのゲーム捨てるわ」とか、「それやったら、遊びに行く言うてたけど、もうやめるわ」みたいな言い聞かせ方してしまうときがあるんですけど、それって多分よくないですよね?
斎藤:痛いほど気持ちはわかりますけど、よろしくはないですね。
山田:でも、これね、うちの親の典型的なやり口やったんです(笑)。

――そういうとき、どういうふうな対応をしたらいいんでしょうか。
山田:そう、それ知りたい。
斎藤:一つのコツは、親も苦痛を味わうというのがあるんですね。例えばゲームをやめない場合、ペナルティ与えますよね。与えるときに、子どもだけに与えないで、親も一緒に何かを我慢するとか、そういうことをセットでやると、けっこう効くといわれてますね。
山田:へぇー。じゃ、子どもにゲームやめさせよう思ったら、「じゃ、パパもウイスキー飲むのちょっとやめるから」みたいなことですか。
斎藤:そんな感じです。自分だけ罰せられたら、なんかアンフェアみたいな感じになりやすいんですよね。そういうニュアンスをちょっと加えると違うみたいです。
山田:へぇー、勉強になるなあ。
――ルイさんの親御さんはどんな感じだったんですか。
山田:うちの親も基本的にもう、「言うこと聞かへんのやったら、もう知らん」パターンが一番多かったです。とくに親父が。
斎藤:あのドロップキックがすごかったですね(笑)。
山田:あれはよっぽどやと思いますけど。いや、多分もう、わからんようになったんでしょうね。
斎藤:初めての反抗ですか、あれは?
山田:と思います。だから、何ていうんですかね……例えば、明智光秀とかも普段からちょっと垣間見えてたと思うんです。信長に対する気持ちとかね。
斎藤:チラチラとね、ありますよね。
山田:だから、秀吉も周りものちのち対処できたと思うし、信長も攻められながら、「でもまぁ、よう俺も言うてたもんな」みたいな気持ちも多分あったと思うんですけど、僕の場合、もう完全にいい子やったんで。むしろ、親が気分よくなることをするのにちょっと快感を覚えてたぐらいの感じやったんです。
斎藤:いや、そのいい子って、めちゃくちゃ気遣いをしてるわけですよね。
山田:気遣いしてます。
斎藤:親の顔色といえば、印象的だったのはあれですよ、『ぼくのランドセル』という詩。
山田:新聞載ったやつ(笑)。
斎藤:あらゆる大人の感想を予測して、計算ずくで、大人ウケする文章を書いて。
山田:そうですね。これ好きでしょ? というところを(笑)。
斎藤:いやな子だ(笑)。
山田:先生、初対面ですよ(笑)。
斎藤:ただ、喜ばせる快感が一種の承認欲求みたいなものだとすると、けっこう脆いというか……。
山田:あ、その脆さってすごくわかりますね。もう、引きこもる前後で全部なくなりましたもんね、なんか。
斎藤:そうですよね、一気に失いますね。
山田:一気になくなっても、そんだけ何年も築いてきた関係性やったら普通やったら、土台がちょっと残るとかあると思うんですけど、まったくなくなったから、それがやっぱりしんどかったですね。
――実際引きこもり始めると、どんどん身動き取れなくなっていくような感覚になるのでしょうか。
山田:そうですね。でも、先生、ちょっとおっしゃいましたけど、やっぱり積もり積もっていく。1日休めば、もうその1日分行きにくくなる。
斎藤:実はきっかけがない人もいるんですよね。
山田:いや、それ怖いですね。
斎藤:そう、怖いんですよ。大した出来事もなかったのに、1日休み、2日休みしたら、もう行けなくなっちゃったみたいなパターン。
山田:僕の場合は、そのウンコ漏らしましたっていうのが大きなトリガーではありますけど、その前からめちゃくちゃしんどかったのはしんどかったです、勉強と運動が。通学もしんどくて。そもそも、宿題に手つけんかったというのが多分、引きこもりの始まりなんかなとは思うんですよ。
斎藤:相当限界に来たと思うんですよね。症状名付くレベルの強迫症状だったんですから。
山田:先生にお会いして、もう何年越しでやっと診断がつきましたけど(笑)。シャーペンの芯捜すとかあれも全部、強迫……。
斎藤:強迫性障害というんですけど、逆にいうと、私はそのレベルでも自然に回復するんだという勉強になりました。
山田:新しい症例として(笑)。
斎藤:新しい症例として(笑)。でも、強迫って、そういう周囲のストレスとかに対する反応として起こることもあるので、だとすれば自然治癒しても不思議じゃないんですよね。その点はラッキーというか、よかったですよね。
山田:よかったですね。だから、さっきも言いましたけど、たまたま同世代の成人式のニュースをテレビで見て、ものすごく焦ったっていう。このままやったら同期が完全に射程圏外に行ってまうなという、その焦りで動きましたからね。
斎藤:それがうまく作用したんでしょうね。焦って奮起できたんで、ルイさんはよかったですけど、焦りつつも「決定的に遅れちゃったからもう無理」と思っちゃって、ますます引きこもってしまうパターンもありますから。
山田:あと、僕のこのメソッドが正しいか先生に分析してほしいんですけど、今までそのルーティンみたいなのがブワーッとどんどん自分の周りにできて、全然外に出れなかったんですけど、その焦りを利用して、とりあえずやる、頑張る、とりあえず何かやるという、この「とりあえず」というワードをすごく強く意識してたんですよ。
斎藤:「とりあえず」って、実はすごいいいことなんですが、これがなかなかできないんですよ。「とりあえず」って、今この場のこれだけやっとけばいいということですよね。
山田:そうです、そうです。
斎藤:それができなくて、常にトータルで考えるから、全然身動きが取れなくなる。
山田:いや、でも、その「とりあえず」ができなくて6年無駄にしたと思ってるんで。
斎藤:でも、6年経ってもできない人が多いですよ、どっちかというと。
山田:今、30歳、40歳とかになってきて、まだ引きこもってる人って、多分めっちゃしんどいやろなと思うんですよね。あのしんどさがそんな長期間続くっていうのは。
斎藤:すごくしんどいですよ、それは。だんだん欲もなくなってくるみたいですしね。
山田:ええ、わかります、わかります。僕、賢く思われたくてゲシュタルト崩壊って言葉にハマってるんですけど……。
斎藤:(笑)
山田:本当になんか、スイッチというか脳のギアが変わるというか、今まで意味があったものがもう消失していくというか、取っ掛かりがなくなっていく感覚がすごいあったんです。
>>《後編》高齢化でより深刻となる「引きこもり」。この社会問題に対する処方箋とは? そして、出口はあるのか?