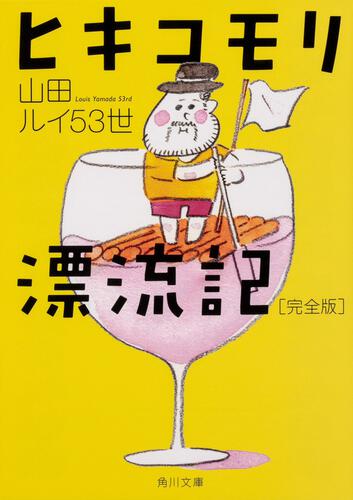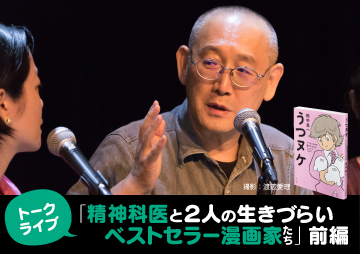秀才中学生が、引きこもりになった経緯を精神科医が分析する対談の話題は、「引きこもり問題」そのものへ。高齢化が進み、より深刻となるこの社会問題に対する処方箋とは? そして、出口はあるのか? 光と闇の引きこもり対談、完結編。
>>《前編》著者の引きこもり体験を、専門家の視点で分析、果たしてその結果は?
本当にキツいときって、ネットする気にもならない。ネットできる人って、かなりましなレベルの人です。(斎藤)
――斎藤さんは引きこもりという言葉がない80年代から研究されていますけれども、時代の変化によって定義とか状況が、変わったと思うことはありますか。
斎藤環(以下、斎藤):定義として唯一変わったのは、以前書いた本には、「引きこもり」は20代までに始まるって書いたんですけど、もうそれは取っ払いました、意味ないんで。年齢は上限なしにしました。
――それ以上の年齢でも始まるときは始まる、ということですね。
斎藤:今、若者の定義って、日本では39歳までなんですよ。
山田ルイ53世(以下、山田):けっこう上(笑)。
斎藤:上なんですよ。だから国が統計とっても39歳までだから、ちょっとしか出てこないんですね、54万人とか。
山田:へぇー。
斎藤:でも、もう40代以上もゴロゴロいるので、100万人以上間違いなくいるはずです。それから最近「8050問題」というのがあって、80歳の年老いた親が50歳の引きこもりの息子の面倒を見るという問題があり、当たり前になってきています。
山田:いや、大変ですよね。
――ネットの登場については、どのようにお考えでしょうか。疑似的にも外とつながれると思いますが。
斎藤:うーん、『社会的ひきこもり』を書いた当時は、僕はネットの登場でなんとかなると思ったんですけど、意外となんともなってない。
山田:いい方に行くと思ったんですか、先生は。
斎藤:「家にいても友達作れるじゃん」と思ったんです。でも、友達ってやっぱり得難い存在だから価値があるんですよ。ネットで誰とでも出会えちゃうと、そこにはあまり価値がなかったりするんですよね。
山田:ああ、でも、なんとなくわかる、それ。いろんなケースはあるでしょうけど、ネットやSNSでつながってる人間に体重預けられないですよね、心理的に。
斎藤:そういう感じですよ。ただですね、最近、ボイスチャットとかニコ生とか、あれはちょっとだけプラスになることがあります。
山田:やっぱり、声ですか。
斎藤:声を介してしゃべってると、会話の練習になるんですよね。ルイさんはどうだったかわかりませんけど、長く引きこもってると、声が出なくなっちゃうんですよね。
山田:あ、俺、すっげえ、独り言を言ってたんで。
斎藤:それ健康法ですよ。独り言というのはすごい自己治療なんです。
山田:健康法なんですか⁉ いや、ほんま、お笑い始めたての古いタイプのコントの導入部ぐらいしゃべってました、俺。完全におかしなってきてると思ってた(笑)。
斎藤:でも、それすごく大事です。それがないと、本当声が出なくなっちゃうらしいんです。コンビニに行って何か買おうと思ったけど、声が出なくて買えなかったみたいな話があるぐらいで。
山田:それは何ですか。肉体的に気管が弱るとかじゃなくて精神的な?
斎藤:声帯が弱っちゃうんでしょうね。あと、声の出し方を忘れちゃうみたいですよ。本当に長い引きこもりの一つの典型的な特徴といわれてます。

――同じような立場の人と話しているという「共感」がプラスに働くということでしょうか。
斎藤:ニコ生だと書き込んでくれるじゃないですか、いろいろ感想を。あれが承認になるみたいで。あれをきっかけに、引きこもりから脱したという人、3人ぐらい知ってますけどね。
山田:なるほど。ちゃんと自分を見てもらえた、認められたっていう。
斎藤:そうですね。
山田:若い人に「6年ぐらい引きこもってました」って話すると、「ネットもないのに、よう引きこもれましたね」みたいなこと言われます。僕らのとき、なんにもないから。
斎藤:でもね、本当にキツいときって、ネットする気にもならない。ネットできる人って、かなりましなレベルの人です。
――斎藤さんは著書で「引きこもりは無気力ではない」と書かれていますが、年月を重ねると無気力になってきてしまうものなのでしょうか。
斎藤:無気力とちょっと違って、焦ってるんですよ、常に。ずっと焦りが心の中を占めてるので、まず退屈にはならない。それから、焦ってる状態を私は無気力と呼びたくないんですよね。なんとかしたいという気持ちはある。そういった意味で、動けなくなっているけど、いわゆる無気力状態とは少し違う。
山田:取っ掛かりが、プールでいうたら蹴る壁がないというか……なんかそういう感じやと、自分のときは思いました。
斎藤:だから、さっきおっしゃった、とりあえず何かするってことが解決策なんですけど、その段階まで持ってくるのが難しい。「引きこもりというのは早起きすれば治る」と言った心理学者がいまして、これは、まあ、おっしゃるとおりとしか言いようがないんですけど、要するにそれって、「ニートは働けば治る」と言ってるようなものなんですよ。そこまで持ってくるのが大変なのに。
山田:あ、なるほどね(笑)。そもそも早く起きれない。そのためには昼夜逆転をまず治す。治すためにはどうすんねや! という。
斎藤:早起きしてもらうというのがまず難しい。昼夜逆転を治すのも難しい。そこの方法論がないまま、そこだけポンと言われても解決にならないんですけど、でも逆に言えば、何か取っ掛かりになることをちょっとするだけで変わるんです。私が診た人によく言うのは、「3分外に出てください」ということ。1日3分、それでいいと、とりあえず言うんです。ちゃんとやってくれた人はかなりよくなります。ほとんどの人は、なかなかそれすらやってくれませんが。
山田:それも確かに、当時の自分がもしそれを言われたらって考えると、たぶん「そんな3分だけ出て、どないなんねん!」みたいな、それを打ち消すことを、山ほど考えるんですよね。
斎藤:そうなんですよね。
山田:で、そこに行かないと。でも、「とりあえず」っていう発想があったら、「とりあえず先生も言うてはるから、やっとこ」という。でも、そこに身を預けられる、考えずにそれをやるっていうところに到達するのは確かに難しい。
斎藤:そこが難しい。方法論はわかってますけど、一番肝心な動機づけがわからないので、そこをどうするかということですよね。
山田:ああ、すっごいわかりやすいです。私、当時それ聞きたかったです(笑)。
斎藤:(笑)。でも、自己治療でけっこう頑張った。
山田:ありがとうございます(笑)。
「親は絶対俺の面倒見てくれへんな」と思ってたので。(山田)
――引きこもり問題は、昔よりさらに解決が難しくなっていると思われますか?
斎藤:高年齢化してより自暴自棄になってる人が多いという難しさの反面、一方では、けっこう就労支援の動きが国レベルで改善してきてるので、昔だったらありえないような、「50代で初診で就労に成功」みたいなケースが出てきてますから、そういう点ではよくなってる面もありますね。
山田:へぇー。いろんな人が助けてくれて就職決まったら、外に出るんですか。
斎藤:深刻な話ですけど、50歳過ぎて親御さんが亡くなっちゃうんですよね。もうやっていけないとなって初めて病院に来て、どうしますかってなって「いや、しょうがないから就労します」と。今、障害者枠がすごく充実しているので、通院している人はほとんど障害者手帳が取れるんですよ。手帳取って就労移行支援という制度を利用すると、年齢問わず就労に乗っけてくれるので、その点はだいぶやりやすくなってる面もあります。当事者は追い詰められてますから。
山田:多分僕、成人式のニュースでそれぐらいの焦りがあったんでしょうね。
斎藤:そして、どこでその焦りを行動に移せるか。ほとんどの人は無理なんですよ。そういう成人式を見ても。
山田:いや、でも確かに僕、当時もう、「親は絶対俺の面倒見てくれへんな」と思ってたので。

斎藤:そこなんですよ。そこが一番違うところで、ルイさんの中で一番典型的じゃないところなんです。ルイさんのお母さん、同居を嫌がるじゃないですか。あれは普通の親御さんと違う反応なんです(笑)。
山田:普通は同居したがる。
斎藤:家から出したがらない。
山田:それは恥だ、みたいなこと?
斎藤:恥もあるし、それからやっぱり、愛と言っていいかわからないけど、とにかくそばに置いておきたいというのがあるんです。
山田:うち、基本的にちっちゃいときから、何かしたら外放り出すという躾やったんです。ほんま真冬でも。真夜中に放り出されて……。
斎藤:今なら確実に虐待通報されてますね。
山田:いや、ただ、その前に僕は、ヤクルトを1本盗み飲みしたんです。そのヤクルト1本盗み飲みで、大体それぐらいの罰が来るんです(笑)。
斎藤:それは厳しい(笑)。
山田:絶対親は俺、面倒見てくんないわっていうのがすごくあったから。
斎藤:それはけっこう大きいんですよ。やっぱり引きこもってる人のほとんどは、親がなんとかしてくれるっていう気持ちがどこかにあるから。これはなかなか大っぴらには言いにくいんですけど、ときどき聞く話に、「引きこもり」から抜け出した人の中に一定の割合で、「親には一切期待できないと思った」という人がいて、「何もしてくれないと思ったんで、引きこもれませんでした」って言うんですよね。
山田:ああ、なるほど。いや、わかりますね、それ。僕、ちょっと気になるんです。引きこもってる子と一蓮托生になり過ぎる親御さんって、なんかよくない。
斎藤:そうそう。でもそちらのほうが多いんですよね。まさに、だから一蓮托生で生きてきたからこそ「8050」になっちゃうんです。でも、その親も実は自分たちが死んだらどうするかってことを、あんまり考えてなかったりするんですよね。目の黒いうちは一生懸命支えるけれども、そのあとはわかりませんみたいな。
山田:僕は親に申し訳ないなという気持ちもちょっとあって。子どもって、親ってもう人生終わってるみたいにちょっと思いがちじゃないですか。もうその先がないみたいに思いがちやけど、自分がこの年で6歳ぐらいの子どもの親になってみると、いやいやいや、まだ2、30年楽しませてくれよって気持ちが全然あるから、やっぱりその親御さんも、子どもが引きこもってるからといって、ママ友の集まり行かへんとか、あるいは子どもが引きこもってて恥ずかしいからテニスサークル行かへんとか、そういうのやめたほうがいいかもしれない。
斎藤:いや、本当にそう思います。親御さんが自分の人生を楽しむ余地を残しておかないと、子どもはそれに罪悪感を感じますんで。そうならないように、外に目を向けてほしいというのもありますよね。
――やはり引きこもりになる方は、今でも女性のほうが相対的に少ないのでしょうか。
斎藤:いや、そうでもないことが最近わかってきたんです。要するに、男性は大学卒業したら、すぐ就職しなかったらもう非難轟々じゃないですか。「何やってるんだ」みたいな。その点女子は、家事手伝いという名目がまだ立つので、何年かはお目こぼしになるというか。
山田:へぇ、今でもですか。
斎藤:今でもで相対的にはそうです。女子である当事者は焦りますけど、世間の目はまだぬるいというか、社会参加すぐしなくても、まあ、それほど目くじら立てないみたいなところがありますよね。男子に比べればっていう意味ですよ。昔よりは厳しくなりましたけど。
山田:なるほどね。でも、女性は女性でそのあと、今でもやっぱり、やれ結婚がどやとか、孫がどやとか、みたいな変なプレッシャーもありますもんね。
斎藤:逆に結婚のプレッシャーがあったりするわけですけど、それも今、晩婚化で、30過ぎにならなければ、そんな遅くないって感じですから、そういった意味では女子のほうが問題化する時期が遅くなりがちで、気がついたら40近くなっていて、やっと焦りだすみたいなことがあります。男子はもっと早くから焦らされちゃいますけれどもね。
山田:僕の知り合いの男性学の先生が「達成と逸脱」て、よう言うてます。やっぱりそれも引きこもりの入口と関係してる……。
斎藤:多いでしょうね。挫折をするか、挫折を予期するかの違いはありますけど、どちらも入口になりやすいということですよね。
コミュニティが崩壊したときに彼らは元気になるんです。(斎藤)
山田:僕、先生にこれは聞いときたいなと思ったことがあるんです。
斎藤:どうぞ、どうぞ。
山田:僕は引きこもってるときに、本当に前向きな曲が大嫌いだったんですよ。
斎藤:(笑)
山田:それは「あるある」ですか? けっこうみんなそういうのあるんですか? ちょっとポジティブな感じの、夏だから飛び出して海に行こうぜみたいなやつが苦痛でしょうがなかったです。
斎藤:コンビニで流れてるJポップ、全部前向きの応援歌みたいなのばっかりで、いやになっちゃうみたいな。
山田:とくに90年代、それ多かったんですよ。
斎藤:多かったですよね。いや、もちろん私も大嫌いですよ、当然。
山田:(笑)
斎藤:もちろんダメですよ、あんなものは。
山田:あれダメですか、やっぱり(笑)。
斎藤:はい。とても聴けないですよね。
山田:引きこもりの方、そういう傾向あります?
斎藤:もう、モロありますよね。
山田:じゃあ、そこもベタだった。よかったぁ……。
斎藤:応援されてもしょうがないですもん、だってねえ。
山田:(笑)。いや、そうですよね。本当にもう焼け石に水というか、何の意味もないです。
――日本社会は圧が強いというか、プレッシャーというか、やっぱり日本独特の空気があるのでしょうか。
斎藤:いわゆる同調圧力ですよね。だからね、成人式もそうですけど、同じ年齢で同じことしてないと、落ちこぼれ感がハンパないという。
山田:成人式なんて本当そうですよね。
斎藤:なんであんな儀式がいまだに残ってるのか。同窓会という機能があるかもしれませんけど、もうじき成人年齢引き下げになって、たぶん成人式は崩壊するだろうと思ってますけれども。
山田:多分うやむやになるでしょうね。
斎藤:なりますよ。だって18歳で成人してもねえ、祝えないですよ。
山田:そうですよね、確かに(笑)。
――ちょっと不謹慎な話かもしれないんですけど、震災のときに被災地で鬱が減ったという話があります。
斎藤:同じパターンですよ。私は東日本のときにボランティア行ってきましたけど、引きこもりは、みんな「引きこもる場所」がなくなっちゃいますから、出てきますよね。
――社会、階層というか、コミュニティが一回まっさらになって……。
斎藤:コミュニティが崩壊したときに彼らは元気になるんです。要するに世間が消えるんですよ、そこで。世間が消えたときは生き生きとして、避難所でお手伝いとか頑張ったりするんですけど、避難所の中でも、すぐに世間は出てくるんですよね。そうするとどうしたかというと、パーティションの中にこもっちゃうんですよ。
山田:ああ、体育館の中の。
斎藤:ビックリしました。腰までしかないパーティションしかないのに、そこから出てこなくなっちゃうんですよね。丸見えなのに。
山田:でも、すごく気持ち的にはわかりますね。
斎藤:私も驚きながら、なんとなくわかりました、それは。
山田:俺はそれスマホの画面やと思ってます。スマホの画面見たら、もう部屋入ってんのと一緒でしょ、あれ、なんか心理的に。
斎藤:はい。もう密室感ありますよね、眺めてるときってね。
山田:ね。だから、あれ「引きこもりのモバイル化」と僕は呼びたいと思ってます(笑)。
斎藤:周りを目に入れないためのね。電車の中なんて、いっぱい個室が並んでる状況ですよね。
――引きこもり問題、どうしたら軽減されるでしょうか。
斎藤:ただですね、これは必然でもあるんですよ。ルイさんが特別なのは、ホームレスなさったでしょう、一時的に。ホームレスっぽい経験。
山田:はい、ぽい経験をしてますね。
斎藤:引きこもりとホームレスって実は同じような現象で、要するに若い世代で社会に馴染めなかった人が行く場所って、家の中か路上しかないんですよね。で、日本や韓国は家族が優しいというか面倒見ちゃうんで、引きこもれるんですけど、イギリス、アメリカは、大人になったらもう家から出ろというのが普通なんで、引きこもりたくても引きこもれないんですよね。そういう国ではホームレスがすごく増える。アメリカはヤングホームレス400万人とかなっちゃって。日本ってホームレスがすごく少ない国で、1万人いないんですよね。
山田:え? 日本全国ですら1万人いないんですか。
斎藤:厚生労働省が統計とってるんですけど、いわゆる野宿者は1万人いないんです。減ってるんです、だんだん。
山田:いや、確かに池袋とかも、あんま見なくなったもんな。
斎藤:減りつつあるんですよ。ヤングホームレスはもっと少ないんですよ。これは異常なくらい少なくて。
山田:その人たちはどこに行ってるんですか。
斎藤:家の中にいるんです。実家にこもってるんです。
――それはそれでどっちが問題なのかという話ですね……。
斎藤:どっちが問題か一概に言えないんですけど、はっきり言えることは、ホームレスは平均寿命が短い。50歳切ってます。引きこもりは間違いなく長生きするんで、福祉財源に対する負担度から長期的に見ると、引きこもりのほうが問題としては大きいかもしれない。
――今、在宅で働くことも増えてきました。引きこもってること自体がマネタイズできたら、問題が問題でなくなるんじゃないかという考えもありますが。
斎藤:それは難しくて、実は昔、名古屋でテレビ塔から、100ドル札をばらまいた青年がいたんですよ。その人は、引きこもってデイトレードやってものすごい儲かったんです。でも、一人も人間関係がなかったらしいんですよね。だから、儲かってたけど、人とつながりのない虚しさに耐えかねてやったんじゃないかと私は見ていて。やっぱり、どこかそのマネタイズだけでは虚しくなってしまうという局面があるのかもしれない。
山田:まあでも、一助にはなる可能性ありますよね。引きこもってて稼げる手段というのがバリエーションあれば。
斎藤:今は本当いっぱいあって、とくにメルカリが出来てから、身のまわりのものをすぐ何でもお金にできるようになりましたよね。あとネットで、イラストがうまいとか、自分のちょっとした技能を買ってくれる人と自分とを仲介する「ココナラ」ってサービスがありますよね。ああいうのを利用したりとか、あと、もっと極端にいえば、自分の口座をネットにさらしておくと、お金入れてくれる人がいるんですよ。
山田:え、それ実例としてあるんですか(笑)。
斎藤:あるんです。「生活苦しいんでここへ入れてください」とか言うと、けっこうな確率で振り込んでくれるらしい。
山田:面白いと言うたら不謹慎かもしれませんけど、へぇー。
――路上で「恵んでください」というのと一緒ですよね。
斎藤:同じ、同じ。ネット物乞いみたいな感じですよね。でもまあ、違法行為ではないということで。だから、今、ネットを活用すれば稼げる手段はいくらでもあると言えるんですけど、本当に絶望してる引きこもりはネットすらやらないんで、そこまで持っていくのがなかなか難しかったりするんです。今、本当にネットを活用すれば稼げるんですよ。一人ぼっちでもよければ。
山田:それはいいこととお考えなんですか。
斎藤:いいことですね。私が見てる引きこもりの人でも、ある製品のブログを作って、そこでその製品に関する質問に答える掲示板を作って、で、その製品を売ったら、まあ、売り上げだけですけど300万円行っちゃったりとか……。
山田:えぇー。
斎藤:そういう人がいたりするんですよ。起業してる人もいるし、あと、FXやったりとか。
山田:そもそもユーチューバーもずっと家おるわけですからね。毎日動画上げよと思ったら。
――FXで稼いで、引きこもりを脱した人はいるのでしょうか。
斎藤:FXって勉強しないといけないから、勉強会行ったりとかいろいろ、人と接する機会はありますよね。やっぱり手広く稼げるようになってくると、必然的に社会とのつながりが生まれてくるんで。
――そういうことをやること自体前向きな行動なんですね。
斎藤:かなり前向きな行動ですよね。あとは、自分の中にあるその「前向きの芽」に、どう気づいて伸ばしていけるかということだと思うんですけど、ルイさんはそこをすごく上手にされたと思うんですよね。
山田:なんか奇跡的に、多分奇跡的にうまく、たまたまうまくいったんでしょうけどね。
斎藤:いや、自己治療のメソッドがすごいです、やっぱり。
山田:野生の狼みたいなものです。自分で傷舐めて治す(笑)。
斎藤:それを治療者が言っても、やろうって気にならないんですけど、ルイさんが伝授するときっとね、当事者目線だから、真似してやろうと。
山田:いや、それでね、うまいこといく人が何人かいたらね……。
斎藤:一定数いると思いますよ。
山田:全然、僕、やりたないと思いますけどね。あと、この『ヒキコモリ漂流記』出してから取材をけっこうしていただくんです。専門家でもないのに偉そうに語るのは気が引けるんですけど。そのときに、やっぱりそのインタビュアーの人が、僕の統計上8割方が話のゴール決めてて、「でも、その6年間があったから今の山田さんがあるんでしょう?」みたいな、あのパターンなんですね。
斎藤:はいはいはい(笑)。
山田:僕はその取材を受けてるとき、タレントとしてありえないなと自分でも思うんですけど「いや、あの6年、完全に無駄やったと。何の足しにもなってない。少なくとも僕の場合はそうだ」という答えを必ずするようにしてるんです。すると、やっぱり相手がちょっと戸惑う。
斎藤:そうでしょうねぇ。
山田:最終的にはちょっと美談っぽくしたいから、向こうは。でも、僕の実感としてはそうやから。「とはいえ、やっぱりその年月があったから?」みたいなこと、また言うてくる。どんだけね、この無駄が許されへんねんというか、なんか結局、ハードル上げてない? って感じがして……それどうなんですか、先生!
斎藤:これは不登校カルチャーの中で生まれた発想で、不登校から成功した人って、不登校経験が素晴らしい経験だったと言いたがるんです。
山田:そうなんです。そうなんです。
斎藤:不登校ぐらいだったらいいですよ。でもね、10年引きこもって、それ全部意味があったかって、それはなかなか言いづらい。
山田:そうなんですよ。少なくとも僕の場合は本人が言うとるわけですから、無駄やったっていう。その無駄も許してくれへんねやというか、「友達と勉強したり部活行って遊んだりとかのほうが絶対人生充実してたから、無駄やと思てます」って言うても、「ん?」ってなるんですよ。その後悔もさせてくれへんっていうことの感じが、すごくしんどくないかなっていうのはあるんですよね。
斎藤:たぶん聞くほうも成功者バイアスを期待して、うまくいっちゃった人は全部過去を肯定するものだというようなストーリーで。
山田:「下積み」のパターンやと思う。「下積み苦労、これがありまして、今ポンと花咲きました」っていう、この味好きなんです、やっぱりみんな。
斎藤:でも、逆にちょっと伺いたいんですけど、その間、普通に過ごしていたら、今があったと思われます?
山田:普通に過ごしてたら、シルクハットはかぶってなかったなっていうのは絶対ありますよね。
斎藤:それを期待したんじゃないですかね、どっちかというと。無駄だったけど、その無駄でも意味があったから、みたいな。
山田:ああ。いや、ただ僕自身が、シルクハットをかぶった漫才師というものをそんなに好きじゃないんです(笑)。そりゃやっぱり、スーツびしっと着て、センターマイクしゃべり一本でやりたいですよっていう。
斎藤:あ、そうなんですか(笑)。
山田:結局、「別に現状の自分に満足してないのはあかんの?」って思うし、「もういいやん、それしかできへんねんから。いやなことも、しんどいことも、屈辱的なこともあるけど、まあ、たまにええこともあるし」くらいの状態でええなって思うから。「いや、でも、それがあったから」と言う人は、もはや、それ、自分のストーリーを守りたいんでしょ?
斎藤:そうですね。全肯定してほしいという。
山田:その押しつけ感がやっぱり、世の中はすごいなって。
斎藤:元引きこもりって二つタイプがあって、一つは全肯定タイプですよ。「俺も立ち直ったんだから、おまえも頑張れ」という。
山田:ヤンキーと一緒なんです(笑)。
斎藤:そうなんです。そういう人が支援者に回ると難しいんですよね。
山田:引きこもり経験を、喧嘩しました武勇伝みたいな感じで言うてる人いるでしょう? その人だけで言うてるんやったらええけど、みんなにそうなれって言うのは違うんじゃないかなと。
斎藤:そうそうそう、すごく困っちゃうんですよね。
山田:絶対的に自分のノリとか考えが正しいと思ってるやつに力預けるのって、ほんま怖いですよね、そう考えると。
斎藤:そうなんです。ちょっと懐疑的な人のほうが上手な支援ができると思うんですよね。
山田:うん。いや、それ1万人おったら、何人かそれで治る人もおるとは思うんですけど、それで全部がうまく行くとは到底思えない。
斎藤:また、そのパターンでなんともならなかった場合のコケ方が酷いんですよ。だから、無駄で無意味だったという考え方も(笑)、大事だなと思いますね。
山田:いや、先生、これに関してやっと専門の人の意見を聞けました(笑)。
ナンバーワン・オンリーワンって、考え方によっては罪な歌やなって思って。(山田)
斎藤:私から最後にもう一個聞きたいんですけど、引きこもってる人って、抜け出しても、もう一回引きこもっちゃうんじゃないかみたいな不安がしばらく続くんですけど、ルイさん、そういう不安ありましたか。
山田:大検取って大学入ったぐらいのときはちょっとありました。家に何日かいたりすると、ちょっともう出るのが億劫やって気持ちがすごく大きくなってきて、「ヤバいヤバい、これはまた、また同じことになる」みたいなのはちょっとありましたけど、それよりも、一回ちょっと売れてご飯食べれるようになるまで、社会に入れてないって気持ちのほうがずっと大きくて。学歴もボロボロやし、就職とか絶対できへんなっていうのがあったから、仕方なしに芸人してたぐらいの感じなんで。全然社会の歯車になれてないっていう劣等感のほうが大きかったですね。
斎藤:そこを脱却できたというのは何か要因が? やっぱり成功ですか?
山田:いや、これ正直、全部解決してくれたのは金です。
斎藤:(笑)。売れてからってことですか、やっぱり。
山田:結局そうですね。いろんなもん、家賃から何からきちんと整理して払ってとか、借金も全部きれいにしてとか、やっと真っ当にやれるわってなったのが30過ぎだから。
――娘さんの存在は、ルイさんにどのような影響を与えたのでしょうか。
山田:娘が生まれてからは、余計その「無駄やったけど、ええやん」って気持ちがすごく強くなって。いや、この人間を二十歳まで育てなあかんなっていう責任感の部分ですね。もう43になりますけど、考えたら結局自分の中から起こる衝動では何も動いてないなっていう。まあでも、そういう人間なんやなっていう、自分に対する諦めみたいのはあります。でも、別に、悪い気分ではないです。
斎藤:そこで謙虚さがポイントかもしれないですよね。
山田:そ、そうですか?
斎藤:抜け出しても繰り返しちゃうもんなんです。やっぱり就職していじめられたりとか、人間関係に躓いたりとかで、前よりも酷い引きこもり方になっちゃったりすることがあるんで、消えないんですよ。だから、就労ぐらいじゃなかなか解消できない。
山田:就職だけでもダメなんですか。
斎藤:ダメですね。結局やっぱり家族ですよ。家庭持って「もう大丈夫」、子どもができたから「大丈夫」ってやっと言える。
山田:でも、そうですね。親としてちょっと情けない部分かもしれませんけど、子どもがストッパーになって頑張るっていうところはありますね、正直。
斎藤:今ね、就職して結婚して子どもを持つというのは、かなりすごいことなんですよ。引きこもってる人見たら、見上げるような高さのハードルですよね。
山田:そうですね。僕もほんま、たまに夢心地になるときありますもんね。「あんな感じやったのに、娘にランドセル買うの?」とか、そういう気持ちはあります。当時を思い返して今にファッと戻ってくると、そのギャップというのはすごくありますね。
斎藤:ギャップは昔より開いたような感じがしますね。
――どうして、そうなってしまったのでしょうね。
斎藤:やっぱり、経済的なものは大きいと思います。若者はどんどん弱者化してますからね。それから、承認欲求に依存する度合いが強まったおかげで、ますます人からの承認を得られにくくなってしまっているという感じが強くありますね。
山田:だからナンバーワン・オンリーワンって、考え方によっては罪な歌やなって思って。あれによって逃げ道がなくなったと思うんです。
斎藤:そうなんですよ(笑)。
山田:ナンバーワンじゃなくてもええけど、オンリーワンであればいいという。いや、オンリーワン、ハードル高いでっていう。素晴らしい歌ですけども、考えようによってはしんどいなと。
斎藤:ものすごくしんどいです。あれはまさに社会の縮図で、80年代ぐらいまでは、偏差値教育といわれてて、要は成績よければいい子になれたんですよ。90年代に入ってから、エリートは成績だけじゃダメなんですよね。コミュ力と人間力、そういういろんなスキルがないといけない。ハイパー・エリート、ハイパー・メリトクラシーみたいな世界になってきて、エリートのハードルがどんどん上がってきてるんですよね。学校の評価基準も変わってきていて、新指導要領の中では、成績はもう単純に評価できないんですよね。勉強の姿勢が大事なんです(笑)。
山田:スキージャンプみたいな(笑)。
斎藤:そうそう。本気じゃないとか、無気力とか、「姿勢を問うな」って言いたいですね。
山田:なるほどね、姿勢を問うなと(笑)。これはいただきました、先生のお言葉を。
斎藤:いや、本当にね(笑)、姿勢を問う社会はまずいですよ。成績は基準があるけど、姿勢は基準ないですから。極端な話「俺が気に入るかどうか」しかないですから。
山田:やっぱりなんかちょっとキラキラしとかな、ちょっと変わってないとあかんとか。
斎藤:そうですね。
山田:いや、ほんまもう、大人はやっぱり嘘つくから本当のことを言わなダメやと思うんですけど、正直、何も得意じゃない人っていると思うんですよ。でも、何か特別じゃない、何でも得意じゃなくても、本人が責められてる気分にならへんような空気感のほうが真っ当やと思うんですけどね、俺は。
斎藤:今、本当にそうなんですよね。あと、取り得もそうですけど、しゃべんないといないことになっちゃいますからね。昔のクラスには、1人か2人は1年間ほとんどしゃべんないやつが必ずいましたからね。それでもなんとなく一目置かれたりしちゃうんです。でも今日ではもうダメなんです。カースト下位になっちゃって相手にされない。コミュ力至上主義ですから。でも、ある意味、今の若い世代のロールモデルって、お笑い芸人さんなんですよ?
山田:へぇー。どういう?
斎藤:つまりですね、若者の中で、まずキャラが大事といわれている。これ、お笑い用語ですよね。あとグルーピングするときに、「キャラかぶっちゃダメ」とか言うわけですよ。これお笑い用語ですよ。
山田:キャラがかぶる、ああ。
斎藤:それから、「これはいじめてません。いじってます」とか言うんです。「いじる」もお笑いなんです。大体ね、お笑いの言葉を導入してコミュニケーション作っちゃってるんで。
山田:いや、ちょっとバラエティ批判じゃないですか、それ(笑)。
斎藤:そうなんですかね(笑)。でもいい面もあって、キャラを立てると、けっこうコミュ力のハードルが下がるんです。しゃべりやすくなる、つながりやすくなる。ちなみに悪い面は、そこに参加できないやつは、はじかれてしまう。
山田:キャラがない。
斎藤:キャラがないというか、そういう「キャラ空間」に入ってこれないやつは、はじかれてしまうというのがあって、いい面、悪い面、両面あるんですよね。いい面をなんとかもっと広げたいんですけど、悪い面の副作用が最近ひどくなってきていて、そこから外れて引きこもっちゃう人もけっこういるんです。ルイさん、引きこもっていたときに、バラエティ番組見てましたか。
山田:いや、家に一時テレビがなかったんで。
斎藤:なるほど。引きこもってる人は見ないんですよ。嫌いなんです(笑)。
山田:あ、見ないんですか。
斎藤:見ない。辛いみたいです。
山田:あ、でも、僕、わかりますわ。2008年にバーンて売れて、2009年夏ぐらいこう落ちて一発屋ってなってから、僕、CS放送しか見なくなったんです。地上波見るのがつらくなって(笑)。
――地上波のリア充感が耐えられない。
山田:そう。その分、海外ドラマにめっちゃ詳しなったという(笑)。
斎藤:海外ドラマは見れるんですよね。
山田:自分の周りの関係ないことやから。それはでもね、ちょっと共通してるとこあると思う。しかし先生は面白い漫談をいっぱい持ってますね。
斎藤:いや、漫談じゃないですけど(笑)。
――最後に、身近なところで引きこもりに悩んでいる方、ひょっとしたら、引きこもっている本人が読まれるかもしれないという中で、引きこもっている方に向けての一言と、あとご家族に対して何か一言をいただけますでしょうか。
斎藤:私の決めの一言は、よく言ってる言葉なんですけ「胸を張って脛をかじれ」。
山田:ああ、いいっすね(笑)。
斎藤:つまりですね、当事者も家族も、あるフェーズでは引きこもりを一旦肯定しないと前に行けないんですよ。全肯定は無理ですよ。さっきもルイさんおっしゃったように、無意味な経験になってしまうこともありますから。でも、そこに足がかりを作るのは、とりあえず現状肯定しかない。そこをくぐり抜けないと先に進めないということをご家族にもぜひ認めてもらいたい。引きこもり支援は、少なくとも引きこもりを否定しない人じゃないとできないんですよね。
山田:なるほど。僕はさっき言いましたけど、やっぱり親御さんもテニスとか壷作りみたいな趣味の陶芸教室とか行ったほうがええと思うっていうのがまずひとつありますよね。
あんまり一緒になって暗くなるっていうのは、誰も得せえへんやろなと思うし。あと、引きこもってるときってすごく惨めで、罪悪感みたいなものもあるんですけど、生き方として下手やし間違ってるかもしれんけど、「悪」じゃないよねっていうことをすごく思うので、自分を追い詰めないでほしいなと思いますね。あと、最悪、髭男爵にはなれるっていう。
斎藤:(笑)
山田:これ常々言ってます。最悪、なれますから。
――最後に良いお言葉をいただきました。本日はどうもありがとうございました。
>>山田ルイ53世『ヒキコモリ漂流記 完全版』