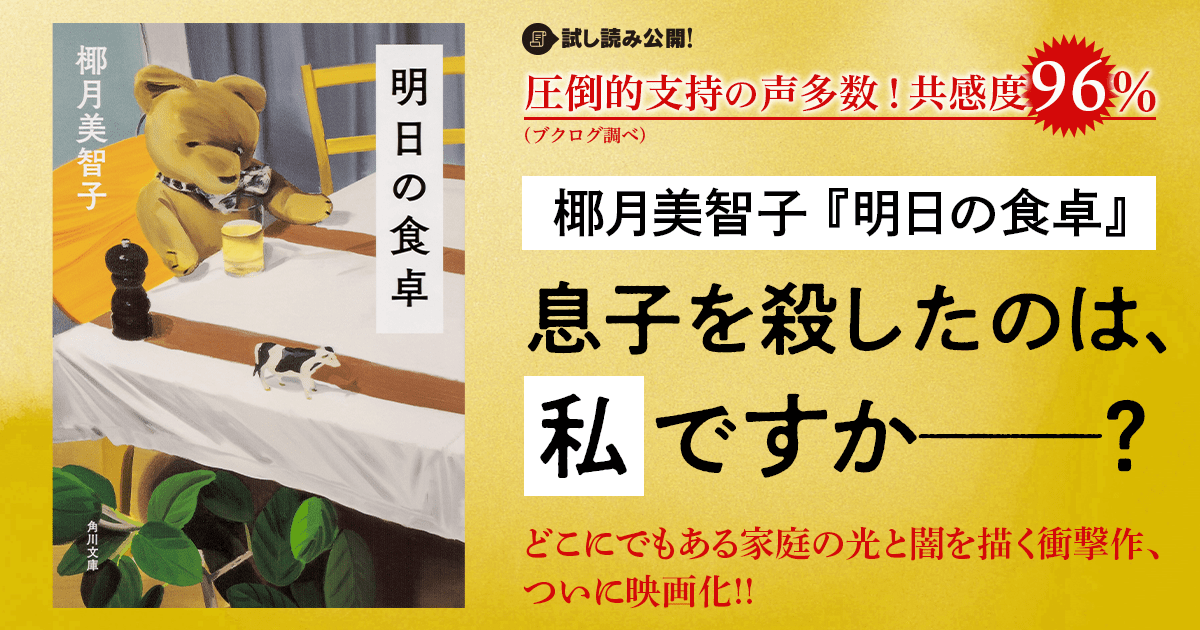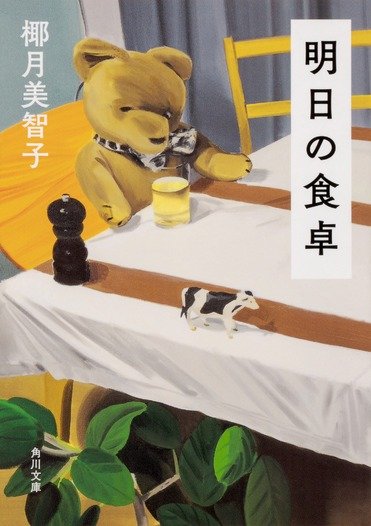単行本時に共感度96%(ブクログ調べ)を叩き出し、圧倒的支持を得た椰月美智子さんの『明日の食卓』。どこにでもある普通の家族に起こり得る光と闇を描き切った本作が、満を持して映画化されます!
フリーライターの石橋留美子を菅野美穂さん、シングルマザーの石橋加奈を高畑充希さん、専業主婦の石橋あすみを尾野真千子さんが熱演。それぞれ小学校3年生の「石橋ユウ」を育てる母たちの行く末は――?
5月28日からの映画公開に先駆け、3つの「石橋家」が良くわかる冒頭部分を公開します。
>>第4回へ
◆ ◆ ◆
*
─
裏面が白紙の折り込みチラシに書いたものをテーブルの上に置き、
「つめたっ!」
そう言いながら、少しでも早く着こうと立ちこぎをする。なだらかな上り坂が続く。
首元から雨が入ったのか、パート先のコンビニに着いたときには、肩までぐっしょりと濡れていた。
朝の五時五十分。
「おはようございます。お疲れさま」
深夜シフトの学生アルバイトに声をかける。眠たそうな目で、あくび交じりに「おはようございます」と返ってくる。加奈はタオルでごしごしと顔と首を拭いて、ユニフォームを着た。
「お先に失礼しまーす」
学生が頭を下げて、加奈の前を通り過ぎる。関西
「お疲れさま」
学生は覇気のない顔で店を出ていった。二十二歳と聞いている。加奈が勇を産んだ年齢だ。
加奈は、届いた商品の検品作業に入った。おにぎり、サンドイッチ、パックに入ったお
降り続いている雨のなか、空はいつの間にか明るくなっている。そうこうしているうちに、通勤、通学のお客さんで店内が混んでくる。レジの前にお客さんが列を作る。加奈はバーコードを読み取り、お弁当を温め、釣り銭を渡しながら、勇のことを考える。
ちゃんと起きられただろうか。朝食は食べただろうか。長靴を履いて、学校に行けただろうか。
ちらと時計を見ながら、レジをこなしていく。
「いらっしゃいませえ」
「ありがとうございました」
ポケットに入れた携帯電話に、小学校からの着信はない。勇は無事に行ったのだろう。
九時からのアルバイトの女の子が来たのと入れ替わりに上がり、加奈はそのまま大急ぎで自転車を走らせる。雨が小降りになってきたのがありがたい。
九時半からは化粧品会社での仕事が待っている。いつもギリギリになってしまって申し訳ないが、みんななにも言わないでくれる。
九時二十八分にタイムカードを押して、大急ぎで着替え、ライン作業に入る。
交替の時間になり、お昼休みとなった。長時間立っていることには慣れたが、同じ体勢での作業なので身体中が凝り固まっている。加奈は腕と首をゆっくりと回し、前屈と後屈をする。ふわーと、血液が身体じゅうを巡っていくのがわかる。
「石橋さん、お昼にしようや」
パート仲間の
「加奈ちゃんの弁当は、いつも男前やなあ」
小林さんが大きな声で笑う。加奈の昼食は、六枚切り食パン二枚とゆで卵二個とトマト丸ごと一個。勇の朝食と同じメニューだ。朝は時間がないので、今日はじめての食事だ。
「そやろ。父親代わりまでやってるから、男らしねん」
加奈も笑いながら答える。五時に起きて身支度をし、洗濯物を干すだけで精いっぱいだ。自分の弁当など、お腹が膨れさえすればなんでもいい。
勇の今日の給食はなんだろう。給食のありがたさを感じているわりに、加奈は献立表をろくに見ていなかった。今日こそは見ようと思っても、慌ただしさでつい忘れてしまう。
「キャラ弁とかアホらしなあ!」
小林さんがひときわ大きな声で言い、まわりの人たちが笑う。
「あんなん、食材こねくりまわして不潔やん。おいしなさそうやしな」
そう言う小林さんは、大きなおにぎりを頰張っている。パートの人たちは、みんなやさしい。年配の人が多いこともあり、一人で子どもを育てている加奈のことを娘のようにかわいがってくれる。
「加奈ちゃん、新聞持ってきたで」
「おおきに。助かるわあ」
ひと足先に食べ終わった五十代の
「資源ゴミに出さんでええから、こっちも助かるわ。まとめてくくるだけで、ひと仕事やもんな」
加奈は再度礼を言って、大和田さんから新聞を受け取った。
「加奈ちゃんは明るくて働きもんで、見てて気持ちええなあ。うちの娘に、加奈ちゃんの爪の
そう言って大和田さんは、加奈と同年代の独身の娘について、ひとしきり嘆いた。
加奈の家では新聞はとっていない。読みたいとも思わないし、読む時間もない。なによりお金がかかる。
勇が図工や習字の授業で新聞紙を使うときは、これまでコンビニで買っていたが、その話をしたところ、大和田さんがこうして前日の新聞を持ってきてくれるようになった。折り込み広告も一緒にくれるので、近所のスーパーの特売品もわかるし、広告でくず入れを作ったりメモ用紙に使ったりと、なにかと助かっている。
「さぁてとっ、お腹もいっぱいになったことやし、午後もがんばらんとなあ!」
小林さんが言って太鼓腹をぽんっと打ったので、みんなで笑って席を立った。
その後、加奈は十七時半まで黙々と仕事をこなし、勇の小学校へ向かった。学童保育のお迎えだ。一人で帰ってきてほしいが、十八時までに保護者が迎えに行かなくてはならないという決まりがある。
空は灰色の雲に覆われていたけれど、雨は止んでいた。顔に当たる風が気持ちいい。
校舎の裏門のチャイムを押す。はーい、と学童保育の指導員の声が届く。
「三年三組の石橋勇です」
インターホンに口を近づけて、子どもの名前を告げる。はーい、とまた返事があり、「勇くん! お迎えが来たでえ」と雑音に交じった声が聞こえる。しばらく待っていると、勇と年配の女性指導員さんが出てきた。
加奈の顔を見た勇が、はにかんだように笑う。勇は今日はじめて、加奈の顔を見たことになる。
「勇くん、おかえり。お疲れさん」
加奈が言うと、「お疲れさん」と勇も返す。
「いつもギリギリになってしもて申し訳ありません。おおきに。どうもありがとうございました」
指導員さんに笑顔を返され、封筒を渡される。来月の学童保育のおやつ代、千五百円の集金だ。
「ほなな、勇くん。また明日な」
勇は手を振ってバイバイと言って、かけ出した。
「あー、あんた。長靴履いてへんやん!」
勇は素知らぬ顔で水たまりを飛び越えている。
「スニーカー、それ一足しかないんやからな。明日
「もう、きついねん」
「きつい? 長靴が?」
「みんなや」
「もうきついんか! ものすごい成長やなあ」
スニーカーも長靴もきついということは、当然、上履きもきついのだろう。そういえば、週末に持ち帰る上履きのかかとはいつも踏んである。
「ほな、土曜日に買いに行こかー。日曜はサッカーの練習試合やもんな」
加奈が声をかけると、勇は振り向かないままで、こくんとうなずいた。
「さあ、急いで帰るで。ランドセル、自転車のカゴに入れたるから、勇くん、走り」
勇はランドセルを加奈の自転車のカゴに入れ、走り出した。加奈がこぐ自転車に必死でついてくる。下り坂なので、ブレーキをかけつつ車輪の動きに任せていたら、あっという間に勇に追い越された。
「危ないでえ。気い付けてな」
前を行く勇が、手を上げる。
「勇くん、速いなあ」
走りでは、自分は勇に追いつけないと加奈は思う。小さい頃、道路に飛び出した勇を、慌ててつかまえたことがあったけれど、今ではもう間に合わないだろう。
「あっという間に大きなってもうたなあ」
大きな声でそう言ってみたが、勇はもうずっと先に行ってしまい、加奈の声は聞こえないようだった。
アパートに着いて、加奈は大急ぎで夕飯の支度をした。冷凍ご飯を解凍し、キャベツと豚肉の
「できたでー」
勇は学校で借りてきた本を、夢中で読んでいる。
「勇くん、お母ちゃん、先に食べるでえ!」
大きな声でそう言うと、勇は本を置いて、テーブルに着いた。小さな二人用のテーブル。リサイクルショップで二千円だったが、作りがしっかりしていて気に入っている。
「いただきます」
加奈の声のあと、勇も「いただきます」と言って
「じゃあ、行ってくるな。勇くん、ちゃんと風呂入って先に寝ててな」
「うん」
口をもごもごさせながら、勇が手を振る。
外に出て、勇が
勇が三年生になってからは、平日はだいたいこのシフトで働いている。朝六時から九時までコンビニ。九時半から十七時半まで化粧品会社。十九時から二十二時までコンビニ。一日十三時間労働だ。身体は楽ではないが、慣れてしまえばどうということはなかった。夜はぐっすり眠れるし、規則正しい生活なので、以前より体調もよかった。
品出しをし、商品の発注をし、レジを打つ。仕事帰りであろう、疲れた顔をしたサラリーマンがお弁当やビールを買っていく。なかには毎日見かける人もいる。
お金を受け取って商品を渡すだけの店員と客の関係だが、加奈はときどき、この人たちはどんな家に住んで、どんな生活をしているのだろうかと考えたりする。家族はいるのだろうか。一軒家だろうか、マンションだろうか。帰ったらすぐにテレビをつけるのだろうか。湯船には
勝手な想像をするのは、店員同士の上滑りなおしゃべりよりも、はるかに気休めになった。
二十二時。暗い夜道を自転車で走り、家に向かう。もうすぐ今日も終わる。そして、すぐに明日がやってくる。
アパートに帰ると、勇はまだ起きていた。
「なんや、まだ起きてたんか。九時には寝なあかんて言うてるやろ。どないしたん」
加奈が問うと、勇は難しい顔をして、
「白の絵の具がないんや。言うの忘れとった。明日図工で使うねん」
と言った。
「もうこれっぽっちもないんか」
加奈がたずねると、ない、と小さな声で返ってきた。きっと、加奈がコンビニのパートに行っている間に絵の具のことを思い出し、明日の図工が気になって眠れなかったのだろう。
誰かに貸してもらい、と言おうとして、思いとどまった。友達から、ものをもらったり借りたりするんやないで、といつも言っているのは加奈のほうだった。
「隣町に二十四時間の百均あったなあ。しゃーない、お母ちゃん、ちょっとひとっ走り行ってくるわ」
時刻は二十二時十五分。一時間もあれば行って帰って来られる。勇が泣きそうな顔で加奈を見る。こんな時間になって絵の具のことを思い出した自分を責めているのだろう。勇は、泣きそうな顔はするけれど、実際に泣くことはない。
「大丈夫や。すぐや。お母ちゃん
「……うん」
伏し目がちに勇がうなずく。
「心配せんでええ。すぐやからな。おやすみ。鍵ちゃんと閉めといてや」
加奈はそう言って、外に出た。雲が流されたのか、星がいくつか見えた。
「勇くん、きっとギリギリまで言えへんかったんやなあ。白い絵の具をちびちび節約して
大きくひとり言を言いながら、加奈は自転車を走らせた。勇はとても我慢強い子だ。家計が苦しいことをわかっているから、欲しいものがあっても自分から口に出すことはめったにない。学校で使うもんはなんでもすぐに言うんやで、と言ってあるが、それでも遠慮している。
「堪忍やでえ、堪忍やでえ、勇くん」
こうして勇に謝らないでも済むように、勇をうしろめたい気持ちにさせないように、しっかりと生活を支えていきたいと思いながら、加奈は強く強くペダルを踏んだ。
(つづく)
▼椰月美智子『明日の食卓』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321806000298/