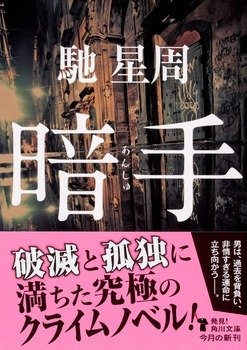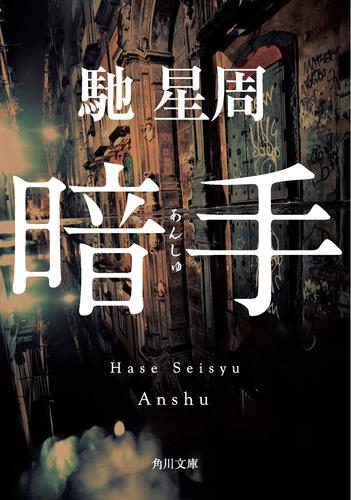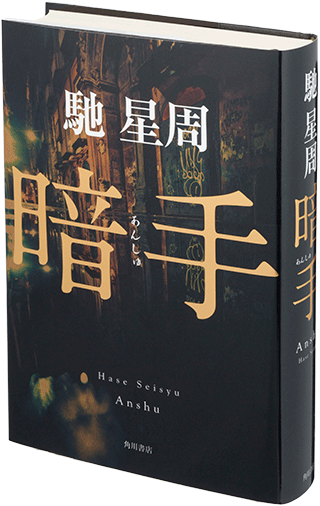『不夜城』で鮮烈なデビューを飾った馳星周さん。その二年後に発表された『夜光虫』の「その後」を描いた本書は、最悪な状況下でも「生きる」ことを決断する主人公の姿を描き、読む人を物語世界に引きずり込みます。今回は文庫化を記念して、冒頭部分を3回にわたって公開します。
>>第1回を読む
◆ ◆ ◆
2
「貿易商ってやつですね」
大森が言った。スパークリングウォーターの入ったグラスを傾ける。酒はいける口だが、シーズン中は飲まないらしい。
「そんなに
おれは赤ワインを啜り、生ハムを口に運ぶ。味はしない。台湾にいた頃、おれは味覚を失った。ある日突然、なにを食べても飲んでも味を感じなくなったのだ。味がしないだけで、
フロアスタッフが大森の頼んだズッパを運んでくる。ここは大森の行きつけのリストランテ。オーナーシェフは、ロッコの選手たちの栄養士を自任しているらしい。
バルで男に紹介された後、大森
「普段ミラノにいるんなら、田舎の料理は口に合わないんじゃないですか」
「ミラノで旨いものを食おうと思ったら、それなりに金がかかる。田舎の方が安くて旨いものの宝庫ですよ」
「いつか、ミラノでプレイしたいなあ」
大森の耳におれの声は届いていない。
「ミラン? インテル?」
おれはミラノを二分するビッグクラブの通称を口にする。ACミランにインテル・ミラノ。どちらもここ数年は低空飛行を続けている。
「どっちでもいいです。おれを認めてくれるなら。ユーベでもいい」
トリノに本拠を置くユベントスこそはセリエAの盟主だった。
「チャンピオンズリーグに出たいんすよ、おれ」
チャンピオンズリーグはヨーロッパ主要国リーグの上位チームがしのぎを削る大会だ。名のあるチームはみな、自国のリーグとこのチャンピオンズリーグを制することを各シーズンの目標に置く。サッカー賭博で動く金も膨大だ。
「いつか出られるさ。焦ることはない。大森君はまだ若いんだし」
「もう二十五ですよ。キーパーだから、最低でもあと十年は現役でいけるだろうけど、十年しかない。給料だってたかが知れてるし、ロッコ辺りでちやほやされても日本代表に呼ばれるにはきついし」
日本代表にはアンタッチャブルと呼ばれる正ゴールキーパーがいる。もう四十歳に近くパフォーマンスも落ちてきているが、その人気は絶大で、代表監督が彼をレギュラーから外そうという動きを見せるだけで世間から
「失礼だけど、給料はいくらもらってるの」
おれは
「五十万ユーロっす」
日本円にして六千万というところか。Jリーグの給料よりはましだが、ヨーロッパでなにかと苦労を
「ロッコのような田舎の弱小クラブがそれだけ出すとは、君の将来性を買ってるんだろう。二、三年後にはビッグクラブからオファーが来て多額の移籍金が手に入ると踏んでるんだな」
「ベルギーにいた時は二十万ユーロっすよ。こっちで名をあげて、いつかチャンピオンズリーグに出てやる。その夢がなかったら、絶対断るオファーだったんすから」
「フォワードやミッドフィルダーなら数試合活躍すれば注目を浴びるけど、キーパーはね」
「高中さん、結構詳しいっすね」
大森がまじまじとおれの顔を見つめている。反射的に顔を伏せたくなる衝動を抑え、おれは微笑む。
「ミラノに住んでると、いやでもサッカーに詳しくなるよ」
「もしかして、インテルかミランに知り合いがいたりとかしません?」
「知り合いの知り合いならいるけどね」
釣り
上昇志向が強すぎる。キーパーというポジションも焦りに拍車をかけているのだろう。
フォワードは試合中にどんな
キーパーはどんなに素晴らしいセーブを連発しても、最後に失点を食らえば戦犯扱いされる。
脚光を浴び続けるには常に自分をアピールしなければならないのだ。
おれのリゾットが運ばれてきた。大森はおれと同じリゾットの他にパスタも頼んでいる。メインはふたりとも肉料理。
大森がパスタを食べ終えたところで提案した。
「シーズン中は飲まないと言っていたけど、一杯だけでもだめかい」
「だめってことはないですけど」
「次はふたりとも肉料理だろう。赤ワイン、ボトルで頼みたいんだが、ひとりじゃ飲みきれない。お近づきのしるしに一杯か二杯だけどうかな」
「わかりました。次の試合は日曜だし、だいじょうぶでしょう」
「ありがとう」
おれは店の人間を呼び、ワインの銘柄を告げた。男の顔色が変わった。
「もっと手頃なワインも用意してありますが」
「レオのために注文するんだ。わかるだろう?」
ウィンクしてやると、男の顔がほころんだ。
「そういうことなら喜んで」
「なに
大森が口を挟んでくる。
「なんでもないよ」
おれは答えた。去り際に、店の男が大森の耳になにかを
──一本千ユーロのワインだぞ。いいパトロンになってくれるかも。大事にしろよ。
大森は間違いなくこの田舎町に愛されている。
「高中さん、今度、ミラノで飯
大森が言った。
「いいとも。ミラノで試合がある時は連絡してくれよ」
おれは答える。
* * *
結局、大森はワインを四杯飲んだ。
肉を食べ、デザートを食べる間にも会話は弾んだ。
大森は日本に恋人がいたが、長く続く遠距離恋愛の果てに破局した。今はフリー。時々無性にやりたくてたまらなくなる。そんな時は
もっと有名になって、有名な女とやりたいから。
大森はそううそぶく。
自分が日本人じゃなければ、とっくに中堅以上のクラブから声がかかっていたはずだ。
大森はそう嘆く。
有名どころのキーパーの名を挙げ、その連中に負けないだけの才能が自分にはあるのだと演説をぶつ。
大森の話に耳を傾けながら、既視感に襲われる。
どこかで聞いた言葉、どこかで見た表情。
不意に気づく。
大森は似ているのだ。昔のおれに。どんな大スラッガーだろうがおれのスライダーを打つことはできない。そう確信していたおれに。
金と女と境遇への不満。
手札は揃っている。焦りさえしなければ、大森は落ちるだろう。
かつて、おれが落ちたように。落ちぶれて台湾に行き着いたおれ。金が必要で、ある女をどうしても手に入れたかった。八百長に手を染め、自分を慕っていた弟分を殺した。
大森もおれと同じ道を歩むだろうか。
知ったことではなかった。
* * *
翌日、ロッコからミラノへ戻る。大森のチームメイトであるジャンルカ・アブルッツェーゼが八百長組織からの呼び出しを受けて、ガッレリアにあるバルへやって来る。
「あんたがマノかい」
ジャンルカはおどおどした顔と
ジャンルカは今年三十二歳になるセンターバックだ。二年前まではイタリア南部の弱小クラブにいて、八百長に手を染めていた。
一度でも八百長に関われば、一生逃げることはかなわない。試合中、自陣ペナルティエリア内でファウルをしろと言われればやらざるを得ない。チーム内のだれかの買収に手を貸せと言われれば貸さざるを得ない。
ジャンルカは頭のてっぺんから
「レオと仲がいいそうじゃないか」
おれはいきなり切り出した。ジャンルカはチーム内に信望がある。そんな男が口利きをすれば狙った相手は落ちやすくなる。
ランナー──八百長に関わる人間は、ジャンルカのような人間をそう呼ぶ。
「レオだって? あいつは日本人だぞ。八百長なんか、死んだってするもんか」
「声が大きいぞ、ジャンルカ。自分が八百長に関わっていると知られてもいいのか」
「レオは無理だよ」
「おまえだって最初に声をかけられた時は、死んでも八百長なんかはしないと見得を切ったそうじゃないか」
おれの言葉にジャンルカの
ジミー・チャンからの情報──ジャンルカはチームメイトの女房とねんごろになった。
金。女。脅迫。だれだって最後には心が折れる。
「あいつは金じゃ動かないぞ」ジャンルカが言う。「素晴らしい才能を持ったキーパーだ。順調にやっていけば、いずれ中堅クラブから声がかかる。その先は、チャンピオンズリーグに出るようなクラブだ。夢があるんだ。金じゃ動かない」
「やつの女の好みはどうだ」
おれはジャンルカのたわごとを聞き流した。
ジャンルカはおれを見た。おれの
「なあ。ロッコの試合で八百長を仕組みたいなら、おれがやる。なにもレオを巻き込まなくても──」
「やつの女の好みは?」
ジャンルカの肩が落ちる。
「小柄な女が好きみたいだ」
「肌と髪の色は? 白か、黄色か、黒か。金髪か、赤毛か、黒い髪か」
「白と黄色。髪の毛の色には特にこだわりはないと思う。小柄だけれど、出ているところは出ている。そんな女によく声をかけてるよ」
「付き合っている女は?」
「今はいない。日本にいた恋人とはベルギーでプレイしている頃に別れたと言っていた」
「どこで遊ぶことが多い?」
「ミラノだ。練習がオフの日にみんなでミラノに繰り出してクラブへ行ったり、女を買ったりする」
「よく行くクラブの名前と女を買う場所は」
おれはジャンルカが口にした名前を頭に刻みこんだ。メモは取らない。そんなことをするのは馬鹿だけだ。
「なあ、レオはいいやつなんだ。練習熱心で、なによりカルチョを愛してる」
カルチョというのはイタリア語でサッカーを示す言葉だ。
おれはエスプレッソを啜った。
「おれはいつかあいつがチャンピオンズリーグの舞台でプレイする姿を見たいと本気で思ってる。あいつはロッコの……いや、弱小チームでしかプレイできないカルチャトーレの希望の星なんだよ。そっとしておいてくれ」
カルチャトーレはサッカー選手のことだ。おれは笑った。
「ゴールキーパーだぞ。おれたちが真っ先に目をつけるポジションだ。レオは悪い時に悪いチームに所属していた。運がない。それだけだ。おまえが気にすべきは、浮気の写真が女房の目に入らないようにするってことだけだろう」
ジャンルカは唇を
「また連絡する。レオに余計なことは言うな」
おれは懐から取りだした封筒をジャンルカに渡す。中に入っているのは五千ユーロ。ジャンルカはすんなり受け取った。
エスプレッソの代金、一ユーロをテーブルに置き、おれは席を立つ。ジャンルカは受け取った封筒を
3
スマホが鳴る。発信者の番号を確認し、電話に出る。
「なんの用だ」
ぶっきらぼうに声を吐き出す。
「そんな声を出すなよ。びびっちまうじゃないか」
ジミー・チャンの声が耳に飛び込んできた。
「
「依頼を引き受けてからまだそんなに経ってない」
「なにをするにしてもあんたは迅速に動く。みんな知ってることじゃないか、暗手」
おれは返事をしなかった。
「実はな、暗手。お偉方のひとりがあんたと会いたいと言ってるんだ」
「だれだ」
「
ジミー・チャンが口にした名を聞いて、おれは
自ら天の王を名乗る男。サッカー賭博の帝王。中国大陸から東南アジア、オセアニア、ヨーロッパまで手広く稼いでいる。
「なぜ、やつがおれに」
帝王は玉座に座っているだけだ。下々の相手などはしない。
「今、ミラノに来てるんだ。あんたの話をしたら、会いたいと言って聞かないのさ」
鼻の奥で
「会う必要はない。引き受けた仕事は全うする」
「わかってるよ、暗手。だけど、おれも王天には逆らえない。あんたも王天に逆らうべきじゃない」
溜息を押し殺す。
「ヴィア・サルピ。
ミラノの中華街、パオロ・サルピ通り。龍華飯店は
「ああ、わかる」
「そこで午後一時に。店の人間におれと待ち合わせをしていると伝えてくれ」
「わかった」
電話を切る。左の肘を揉む。古傷──台湾で受けた銃創が痛む。
鼻の奥に硝煙の匂いが残っている。硝煙に血の匂いが混ざる。
死ねばいいじゃないか──時々、そう思う。おれには夢もない。希望もない。生きる意味も失った。
それなのになぜ生きているのか。他人の血を啜りながら生き長らえているのはなぜか。
いつも答えを探している。
おまえがおまえだからだ──いつも頭に浮かぶのはそんな答えだった。
* * *
パオロ・サルピ通り──ミラノの中華街は世界中のどんな中華街とも似ていない。目につくのは飲食店ではなく、衣料用品店ばかりだ。
ミラノの中国人は、ファッション業界の下請けとしてこの地に招かれた。だから、飲食店ではなく、衣料用品店が乱立する特異な中華街として発展した。
もちろん、街を仕切っているのは黒社会の連中だ。元々この地に住んでいたミラノっ子たちから土地を買い、ビルを買い、それを中国人たちに高値で貸し付ける。
通りを数メートル歩くだけであちこちから様々な中国方言が聞こえてくる。
それとなく前後左右に視線を走らせる。この中華街に台湾出身の人間はそれほど多くない。だが、なにかの縁でこの街に
台湾の黒道には、今なおおれを殺したがっている連中がいる。
やつらに殺されるのが運命ならかまわない。だが、黙って殺されるには、おれは
龍華飯店はパオロ・サルピ通りの西の外れに位置する。味は一流だが、店構えは凡庸だ。
店の前にポルシェ・カイエンが停まっている。運転席に座った男が鋭い視線を通行人に向けている。カイエンの外にもひとり。地味なスーツにくわえ
男たちの視線を無視して店に入り、近づいてきた若い女にジミー・チャンに会いに来た旨を告げる。若い女が
「こちらへどうぞ、
先生──ミスターと呼ばれることなどまずない。王天の客だから敬称がつくのだ。
男は厨房に向かっていく。その後を追う。炎が舞う中、数人の料理人が
扉の向こうは狭い通路だ。通路の先に階段があり、それをのぼると広々としたエリアに出た。
VIP
男が個室のドアをノックした。ドアが開き、ジミー・チャンが顔を出す。いつものにやけた顔ではなく、どこか緊張した面持ち。おれを認め、手招きする。
男が無言で立ち去っていった。
部屋に入る。十五人は座れそうな円卓に、三人の男が掛けている。料理が載ったいくつもの皿とワインボトルにグラス。吸い
「ボス、こいつが暗手です」
ジミー・チャンが葉巻を吸っている男におれを紹介した。他のふたりが
王天と護衛たち。
「よく来てくれた。座るといい」
王天は自分の向かいの席を指差した。ジミー・チャンの右隣。下々の者は
「好きなものを食べて飲んでくれ」
王天は葉巻をくゆらす。四十代半ばの
「結構です。昼飯は済ませてきました」
目に留まったバルでパニーニを食べ、エスプレッソを飲んだ。夜も同じように目に留まったバルでパニーニを食べ、エスプレッソを飲むだろう。
「噂通り、陰気くさい男だな」
おれは口を閉じた。王天はおれを
「
普通話というのは北京語のことだった。
「福建です」
おれは言った。福建と台湾は海を隔てた隣同士。言葉の訛りもよく似ている。
「なるほど。福建の田舎者が、なぜミラノにいる? なぜこんな仕事をしている?」
「話せば長くなるし、話すつもりもありません」
おれの答えに、護衛たちが目の色を変える。帝王にそんな物言いをする人間はいない。
「おまえたちは静かにしていろ」
王天が護衛たちを
「いいだろう。仕事さえきっちりやってくれれば、おまえの過去などどうでもいい。どうだ、日本人は落とせるか」
「落ちない人間はいません」
王天が笑った。おれの答えが気に入ったのだ。
「酒は飲まないと聞いたが、一滴もやらないのか」
「気が向けば、飲む時もありますよ」
「一杯どうだ。おまえと乾杯したい」
「一杯だけなら」
王天が目配せする。護衛のひとりがワインボトルを
「乾杯」
王天がグラスを掲げる。同じくグラスを掲げる。
「乾杯」
香りを嗅ぎ、ルビー色の液体を少しだけ啜る。香りも味もわからない。
「若い時に調子に乗って、王天と名乗るようになった。天の王になってやる。本気でそう思っていたんだ」
王天はワインを啜り、葉巻をくゆらせる。
「必死でのし上がってきたが、いつだって上には上がいる。今もそうだ。天の王になるにはまだまだ階段をのぼっていかなきゃならない。わかるな?」
おれはうなずく。
「おれがサッカー賭博で動かすのは、自分の金と、おれより上にいる連中の金だ。何倍、いや、何十倍に増やして返さなきゃならん。八百長が成功しようが失敗しようが連中には知ったことじゃない。おれに預けた金が何十倍になって戻ってくる。重要なのはそれだけだ」
おれはうなずく。
「おれも同じだ。おまえがあの日本人を落とすかどうかは、おれの知ったことじゃない。おれの関心は、おれが望む試合で、あの日本人がミスをすることだけだ。おれの金が何十倍に増えることだけだ。わかるな?」
おれはうなずいた。
「おれの望む通りになれば、おまえは報酬を得る。望む通りにならなければ、おまえは自分の命で償うことになる。わかるな?」
「もう何十年もこの世界で生きてるんですよ、王天先生」
おれは口を開いた。また、護衛たちの目の色が変わった。
「わかっているならいい。おそらく、今シーズンの末には、とてつもない大金が動く。おれたちの望む通りにならなかったら、地の果てまで追いかけてでもおまえに償わせるぞ」
「その時はお好きなように」
おれは腰を上げた。
「お、おい、暗手……」
ジミー・チャンが
「それでは、失礼します」
「よろしく頼んだぞ、暗手。期待を裏切るなよ」
王天の声を背中に聞きながら個室を出た。そのまま厨房へ向かう。ドアが開く音に続き、足音が聞こえてくる。
おれは手近にあった中華鍋を手に取った。
「おい、待て」
護衛のひとりだろう。おれの態度に腹を立て、お
立ち止まり、待つ。
「暗手だかなんだか知らねえが、ボスにあんな態度を取るやつがどうなるか、思い知らせてやろうか」
声が充分な近さに達したところで振り返る。中華鍋を護衛の顔に叩きつける。
衝撃。
男がもんどり打って倒れ込む。
中華鍋を放り投げ、おれは厨房を横切った。
護衛が聞いて
おれは殺し屋──いや、殺戮者だったのだ。
年は取ったが、チンピラにしてやられるほど衰えてはいない。
* * *
目に留まったバルでパニーニを頰張り、エスプレッソで胃に流し込む。食べ終えるとねぐらへ戻る。
おれはコル・ディ・ラーナ通り沿いのアパートメントの一室を借りている。ミラノの中心から南に下ったところにある、旧市街と呼ばれるエリアだ。運河も近い。一時期は
近隣の人間はおれをヴィトと呼ぶ。ヴィト・ルーというのが、おれの今の名前だ。スイス南部で生まれ育った中華系で、市内の中華レストランで働いていることになっている。そのレストランで仕事をしたことはないが、給料はもらっているし、税金も納めている。
だだっ広い部屋にあるのはベッドとクローゼットにライティングデスクだけ。食器棚どころか冷蔵庫すらない。帰宅する都度、ミネラルウォーターのボトルを買い、夜中に飲み干して、朝、出かける時に空のボトルを捨てる。
食事は常に外食。酒は飲まず、コーヒーも外で飲む。洗濯はコインランドリー。ネットに繫いで仕事の連絡に使うノートパソコンが一台。
それ以外に必要なものはない。
シャワーを浴び、パジャマに着替え、ライティングデスクに立てかけてある写真立てを手にとってベッドの端に腰掛ける。
女の写真──かつて心の底から欲した女の写真。
この女を手に入れたくて、おれはおれを慕っていた男を殺した。煉獄へと突き進んだ。
なにも考えず、なにも想像せず、ただ、写真を眺める。
飽きることはない。おれは今でもこの女を欲している。
だから、死ねないのだ。だから、意味もなく生きている。
おれは欲深い人間だった。今では欲はほとんどない。しかし、
空が白みはじめるまで写真を眺め、夜明け前に短い睡眠を取る。
それがおれの日課だった。
(つづく)
▼馳星周『暗手』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000665/