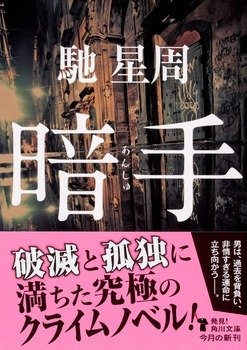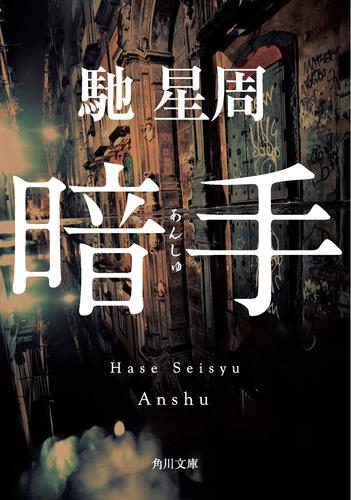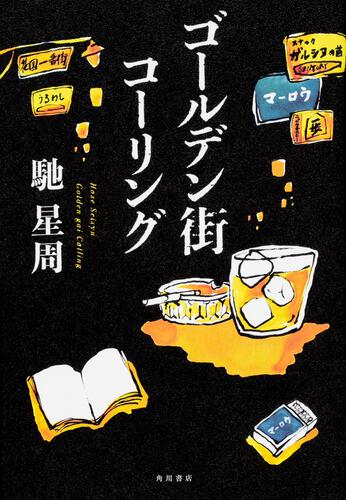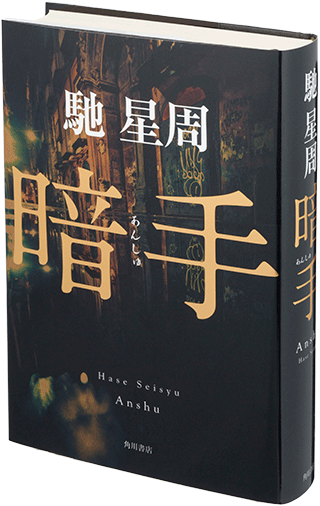『不夜城』で鮮烈なデビューを飾った馳星周さん。その二年後に発表された『夜光虫』の「その後」を描いた本書は、最悪な状況下でも「生きる」ことを決断する主人公の姿を描き、読む人を物語世界に引きずり込みます。今回は文庫化を記念して、冒頭部分を3回にわたって公開します。
>>前話を読む
◆ ◆ ◆
4
来月早々、ロッコはミラノに遠征してインテル・ミラノと試合を行う。キックオフの時刻は未定だが、おそらく午後三時だろう。
金のあるクラブは、クラブハウスに集合して専用バスに乗り込んで遠征先、あるいは空港まで移動する。試合終了後もスタジアムからそのままバスで帰るのだ。
しかしロッコのような田舎クラブは選手を移動させるバスをチャーターする費用にも苦労する。ミラノへの遠征なら、選手たちは個々の車でミラノへ来て、ロッコへ帰ることになる。
大森とは試合後にミラノで食事をする約束を交わした。
女を調達しなければならない。大森好みの小柄だがプロポーションのいい女。身体だけではない。頭もそこそこ回らなければ使えない。
シニョリーナ・バレッリに連絡を取る。
アドリアーナ・バレッリ──ミラノの高級売春クラブのマダムだ。シニョリーナは未婚女性に対する敬称で、アドリアーナは
「シニョリーナ・バレッリ。ヴィトだ。少し相談したいことがあるんだが」
アドリアーナの携帯の番号を知る者は少ない。おれはアドリアーナに気に入られ、番号を教えてもらった。
「あら、ヴィト。久しぶりね。わたしのことなんか忘れちゃったのかと思ったわ」
アドリアーナの少女じみた声が鼓膜を震わせる。
「貧乏暇なしというやつでね。いつも仕事に忙殺されているんだ」
「知ってるでしょうけど、わたしを買うのは高いわよ。もう半分引退しているようなものだもの。それでもわたしを買いたいというお客様にはふっかけることにしてるの」
「知ってるだろうが、おれは必要な金はケチらずに使う」
アドリアーナが笑った。
「相変わらずね、ヴィト。いいわ、食事を奢ってちょうだい。それでチャラにしてあげる」
アドリアーナは夜の住人だ。食事と言えば、ランチを指す。
「アリーチェっていうリストランテを知ってるかしら。ガリバルディ門のそばにあるの。最近、評判がいいみたい」
「聞いたことはないが、調べるよ。いつがいい?」
「明日のお昼。一時過ぎなら空いているわ」
「了解。おれの名前で予約を入れておく」
「楽しみにしてるわ」
電話が切れた。おれも電話を切る。プロフェッショナルとの会話は気分がいい。
パソコンを開き、アリーチェというリストランテを検索に掛ける。ウェブサイトにアクセスし、予約を入れようとして満席になっていることを知る。
なるほど、評判がいいというのは本当のようだ。
おれは電話をかけた。
「はい、アリーチェでございます」
「明日の昼、予約を入れたいんだが」
「お客様、申し訳ございません。明日の昼はすでに予約で満席になっております」
「五百ユーロ」
おれは言った。
「なんとおっしゃいました?」
「席を用意してくれれば、君に五百ユーロを渡す」
「そのようなことをおっしゃいましても──」
相手の声が揺れた。
「君の名前は?」
「カルロ……カルロ・ファヌッチですが、それがなにか?」
「カルロ。店は関係ない。おれと君との契約だ。明日の一時、ふたり。席を用意してくれれば、君に直接五百ユーロを渡そう。あぶれた客には、新入りがオーバーブッキングをしたとかなんとか言い訳すればいい」
「お客様のお名前は?」
「ヴィト。ヴィト・ルー。素敵な女性を連れていく。いい席を用意してくれ、カルロ。頼んだぞ」
「かしこまりました、シニョーレ・ルー。明日のご来店をお待ちしております」
おれはまた電話で挙げた成果に満足し、スマホをそっとデスクに置いた。
* * *
アドリアーナは深紅のタイトスーツに身を包んで現れた。身長は百八十センチ近く。ブルネットの髪の毛に緑の瞳。スーツの下はランジェリーしか身につけていないに違いない。ぱっくり開いたスーツの胸元からは双丘の膨らみと、それを包み込んでいるレースの一部が覗けている。
まるでランウェイを歩くスーパーモデルだ。店中の男ども──客からスタッフまでがアドリアーナを凝視している。
「待たせたわね」
椅子を引くおれに微笑みながら、アドリアーナは腰掛けた。
「予想していたよりは早い」
時刻は午後一時二十分を回っていた。
「それに、あなたは目立つのが嫌い」
「そういうのが君のスタイルだということは承知している。嫌なら、最初から声はかけない」
「相変わらずね」
アドリアーナは口元を押さえて笑った。五十歳を超えているはずだが、三十代前半にしか見えない。薄い化粧を施しただけの顔の肌は
「ちょっと待って」
おれが口を開きかけると、アドリアーナが制した。
「あなたの声を聞いたのは二年ぶりなのよ。まずは食事をしながら旧交を温めましょう。仕事の話はそれから。いい?」
「了解した」
おれはそう言って、メニューに目を通した。
メニューに記載されているのは間違いなくイタリア語だった。だが、おれにはちんぷんかんぷんだった。インテリアから想像はつく。ここはフレンチ、和食、バスク料理といった各国料理の影響を色濃く受けた
「お手上げだ。おれの分もオーダーしてくれないか」
おれは言った。
「相変わらずパニーニかピッツァしか食べないのかしら」
彼女の言葉におれはうなずいた。
「じゃあ、ズッパとパスタぐらいかしらね」
おれはまたうなずいた。
「ワインは?」
おれは首を横に振る。
「思い出したわ。あなたとの食事、とっても退屈だった」
「決めたわ」
彼女が言った。相変わらず、決断が早い。おれは手をあげて店の人間を呼んだ。男がやって来て、彼女がオーダーを告げた。
男が去ると入れ替わるように女がやって来た。両手にワインのボトルを抱えている。トスカーナの赤だった。
「ひとりで一本飲むのか」
おれは訊いた。
「あら、二本でも三本でも平気よ。あなたの
「それはありがとう」
アドリアーナはワインをテイスティングし、夢見るような目つきになった。
「素晴らしいわ。あなたも飲めばいいのに」
「おれは水が好きなんだ」
おれはガス入りのミネラルウォーターを口に含む。
料理が運ばれてくるまでの間、料理を食べている間はアドリアーナがひとりで喋りまくった。おれは相づちを打つだけだ。
アドリアーナのとめどない話に耳を傾けながら、ズッパを数口啜り、次に運ばれてきたショートパスタを数口食べた。それで満腹だった。
「昔よりさらに少食になったんじゃない」
アドリアーナが言った。
「そうかな。自分じゃよくわからん」
「ベネデッタを覚えている?」
「ああ」
二年ほど前、とあるサッカー選手を脅迫するネタを作るために協力してもらった女だった。
「彼女、あなたのことをヴァンピーロと呼んでいたわ」
ヴァンピーロというのは吸血鬼のことだ。
「あまりにも食事を取らないから、きっとどこかで人間の血を吸ってるんだわって」
「腹が減ったらパニーニかピッツァを食べている」
「その
「おれのことは気にせず食べてくれ。話も聞いている」
「わたしはあなたに会うたびに、ヴァンピーロじゃなくファンタズマを想像するけど」
吸血鬼に幽霊。いずれにせよ、女たちがおれから受ける印象はそう変わらない。
アドリアーナはその見事なプロポーションからは想像もできない
「夜は食べている時間がないから、昼食が重要なの」
「このリストランテは気に入ったのかい」
「まあまあね」
アドリアーナは食後酒を飲み干すと、テーブルに両肘をついた。
「さ、仕事の話をしましょう」
「女が
おれは単刀直入に言った。アドリアーナは、こと仕事の話になると無駄話を嫌うのだ。
「どんな女? どんな男をカモにするの?」
「小柄だがグラマー。白人か黄色人種。相手はジョカトーレだ」
「髪の毛と目の色は?」
「何色だろうとかまわない」
「ジョカトーレは白人?」
「日本人だ」
「ああ、ロッコにいるゴールキーパーね」
仕事の相手が男である場合、女もサッカーに詳しくなる。それがイタリア人というものだ。
「小柄でグラマーで頭の回転が速い……ちょうどいい子がいるわ。日本人よ」
「日本の女がミラノで娼婦をやっているのか」
「服飾デザインで一旗揚げようとミラノに来たの。でも、いつまで経っても日の目を見ず、かといってそのまま日本に帰ることもできず、日々の暮らしに窮して。よくあるパターン。最近、中国人の客が多いの。彼らは白人の女を抱きたがるけど、日本人がいると聞くと食指を動かすのよ」
「使えるのか」
「客あしらいも上手。きっと、あなたは気にいると思う。今夜、会う
「よろしく頼む」
「じゃあ、いつものホテルで待ってて。午後九時に行かせるわ」
アドリアーナは
* * *
ミラノ中央駅に近い五つ星ホテルに部屋を取り、そこでしばらく横になった。眠るわけではない。眠りたくても眠れない、寝つけない。ただ横たわり、頭の中を空っぽにして休むだけだ。
午後八時に電話が鳴った。相手は名乗りもせずに用件だけを告げた。
「女の名前はミカ。約束通り、九時に」
電話が切れた。
シャワーを浴び、水を飲み、待つ。
九時ちょうどにドアがノックされた。
覗き穴から外の様子をうかがう。ショートヘアの若い女が立っている。挑むような目が印象的だった。
ドアを開けた。
「こんばんは。ミカよ」
素っ気ない口調だった。
「入れ」
イタリア語でミカを招き入れ、ドアを閉めた。
「もうシャワーは浴びたのね。わたしも浴びてくるから待ってて」
発音はぎごちないが文法的には
「その必要はない」
おれは言った。
「そういうのが好きならどうぞ」
ミカはバッグをソファの上に放り投げ、ブラウスのボタンを外しはじめた。おれはミカのするがままに任せた。
ブラウスとミニスカートを脱ぐと、挑発的なランジェリーが現れた。身長は百五十五センチというところだろうが、胸と腰回りはよく発達していた。ウエストもほどよくくびれている。
「わかった。服を着ろ」
おれはブラを外そうとしたミカを制した。
「着たままがいいのね?」
「なにを飲む?」
ミカは腰に両手をあてがっておれを睨んだ。
「ねえ、これはなんなの?」
「セックスをするために君を呼んだわけじゃない」
おれは日本語で言った。ミカの目が丸くなった。
「中国人だと聞かされてたわ」
「中国語が話せる日本人だ。なにを飲む」
「ガスなしの水を」
おれはうなずき、ミニバーからミネラルウォーターのボトルを取りだし、グラスに
「服飾デザイナーを夢見てるんだって」
ミカにグラスを渡した。
「そうだけど、それがどうかした?」
「娼婦に身をやつしてまで成し遂げたい夢なのか」
「ねえ、もう一度聞くけど、これはなんなの?」
「面接だ。どうしてミラノで娼婦なんかをやっているんだ?」
「このまま日本に帰るのが悔しいの。ミラノは家賃も高いし、普通の仕事で稼ごうと思ったら、勉強をする時間が足りなくなる。でも、この仕事なら、週に何日か働くだけでお釣りが来るわ」
「もっと稼げる仕事がある。やることは娼婦と変わりないが、相手をするのはひとりだけだ」
「だれかをはめるのね」
ミカは水を啜った。頭の回転は速い。
「娼婦と悟られないこと。相手に
「いくら?」
ミカはソファに腰をおろし、脚を組んだ。
「手はじめに一万ユーロ。うまくいけばさらに四万ユーロ」
「はめる相手は?」
「大森怜央」
「だれ、それ?」
おれは笑った。
「サッカー選手だ」
「サッカー選手は嫌い。昔、わたしの友達が遊ばれて捨てられたわ」
「やるのか?」
「なにをどうすればいいのか、教えて」
「OK」
おれは言った。
(このつづきは本書でお楽しみください)
▼馳星周『暗手』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000665/