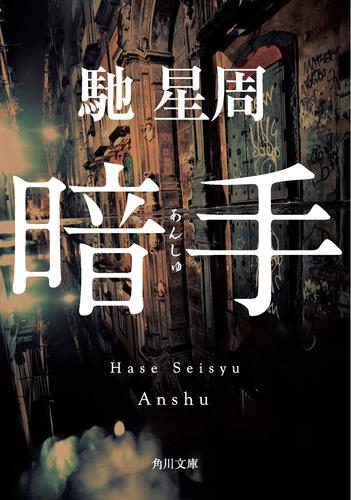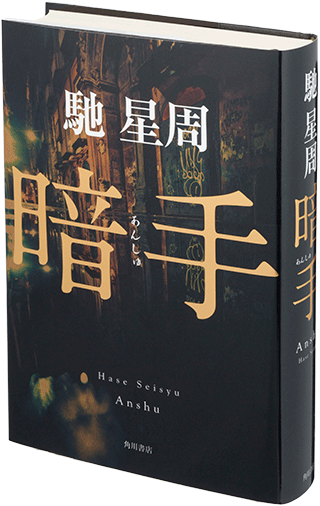『不夜城』で馳星周が鮮烈なデビューを飾ったのは一九九六年。その二年後に発表された長編『夜光虫』は、馳文学史上もっともダークという呼び声が今なお高い。主人公が、とことんまで堕ちていくからだ。約二十年の時を経て、「その後」を描いた続編『暗手』が世に送り出されることとなった。前作を読んでいなくても問題なく楽しめる。だが、前作を読んでいたら、より楽しい。最悪な状況下でも「生きる」ことを決断し続ける主人公の姿が、前作以上に、生命の輝きに満ち溢れていると感じることができるからだ。
ヨーロッパサッカーを巡る八百長 それに絡む加倉をすっとイメージできた

── : 台湾で野球賭博に関わり、のちに殺し屋となり復讐の鬼となる。『夜光虫』の主人公・加倉の転落人生と「その後」が、プロローグに当たる第「0」章で記されます。〈欲望に身を任せた。(中略)顔を変えた。名前を変えた。/そして殺した。/殺した。殺した。殺した。/殺しすぎて台湾にいられなくなった。/そしておれは今、イタリアにいる〉。最初の一ページで、一撃で、物語世界に引きずり込まれる感触がありました。第「0」章が最初に書いた文章だったのでしょうか?
馳: 小説を書く時は、出だしが最も重要なので、ここから始めましたね。さっき編集者と雑談していて思い出したんだけど、ミラノ取材の最終日に「出だしの文章はこれだ」って俺が話していたらしい。そこから何を書くかは、まったく構想していなかったと思うけどね(笑)。
── : 加倉はイタリア黒社会で、「暗手(暗闇から伸びてくる手)」という通り名を持っています。殺し以外の仕事ならなんでも請け負う彼のもとに、サッカー賭博の八百長のコーディネートをしてほしいという依頼が舞い込みます。台湾を出た加倉の居場所と職業は、どのように決められましたか?
馳: ミラノに関しては、馴染みのある街だったってことですね。十数年前までは、プライベートでよくヨーロッパへ遊びに行っていたんです。一番の目的は、サッカー観戦でした。俺は野球に関して門外漢なんで、『夜光虫』の時はかなり苦労して。でもサッカーに関しては、わざわざ調べる必要もないぐらい知っている。サッカー賭博や八百長に関しても、サッカー関連の情報を追い掛けている中で自然と耳に入っていたんだよね。「『夜光虫』の続編を書きませんか?」と編集者に言われた時に、その辺りを書くことになるんだろうなぁというイメージはすっと頭に浮かんできました。
── : ヨーロッパサッカーの賭博と八百長仕事にもかかわらず、中国系マフィアが大きく関わっていますよね。
馳: 昔から八百長めいたことはあったんだけど、二〇〇〇年代に入って中国人が金を持ち始めてからは、えげつないことになったんですよ。中国人ほど、博打好きな国民はいないから。インターネットで金をやり取りできるようになったことも、サッカー賭博が世界的に広がった下地ですね。
── : 加倉の新しいターゲットは、ミラノ郊外の田舎町ロッコのクラブチームで活躍する、日本人ゴールキーパー・大森怜央です。八百長組織はキーパーを真っ先に狙う……という記述に触れて、驚きました。
馳: 八百長絡みの資料ももちろん読み込みましたけど、サッカーを知っていれば、それ以外ないというのはすぐ分かるんです。フォワードやミッドフィルダーを買収したって意味がない。いくら「点を取れ」と指示したって、向こうのディフェンスが頑張っちゃったら取れないでしょう。ゴールキーパーにわざとミスさせて、相手に点を与えるのが最も確実な八百長のやり方なんです。
── : 協力者のひとりに、加倉はこう言っています。「レオは悪い時に悪いチームに所属していた。運がない」
馳: ビッグクラブに行くと、八百長からは完全に縁が切れるんです。でも、大森が所属しているのは、セリエAの降格圏にいるクラブ。シーズンの終盤は残留をかけて盛り上がるし、試合が賭けの対象になりやすい。八百長の組織は、その選手の人格のことなんか一切考えていないんです。儲かるからターゲットにしているだけで、本当に運が悪いだけなんだよ。自分の意思ではどうしようもないんです。
── : とはいえ、弱小チームの躍進を支える二十五歳の大森は、ビッグクラブへの移籍も噂される逸材であり、モチベーションも高い。どうやって八百長に手を染めさせるか? 読者は加倉に感情移入しながら読み進めていくわけですが、彼の言動は想像の一歩先を行く。できる男、ですよね。
馳: 『夜光虫』の時に、ハメられる側の心理を自分で経験して学んだんだよね。ハメる側に回った時は、その経験が活きる。こういう言い方が合っているか分からないけど、裏社会の人間として成長しているんです。
「完璧な作品」を狙って未来の自分にパスを出す
── : 大森をハメるシミュレーションは、書く前に細かく計画されていたんですか?
馳: 最初からきっちりすべてを構築して書くタイプの作家ではないので、書きながら、ですね。正攻法で考えると、女を使って落としていくだろうなと思ったので、加倉はまずミカという協力者を金で雇って、大森に惚れさせるよう指示を出す。でも、ミカにいいところを見せようとした大森が、神懸かり的なセーブを連発しまくる場面を書いた時に、このままだとシーズン途中でも、ビッグクラブからスカウトの声がかかる可能性が出てきたなって、本能的に気づいたんですよね。「やばい。ブレーキかけなきゃ」となったんですが、いきなりスランプに陥っちゃうのも嘘くさい。新しい展開を考えて、加倉に一手を打たせるようにしたんです。そういうことの連続でした。
── : 序盤戦のキーポイントは?
馳: どの作品も冒頭から百枚ぐらいまでは手探りなんですが、それぐらいまで書いてくるとだんだん先行きが見えてくるんです。『暗手』で言えば、ちょうど馬兵が登場したあたりですね。仇役が必要だなってなった時に、加倉を雇っている王天サイドの登場人物として、とにかくまずは出してみたんです。俺の場合、キャラクターも書いていくうちにどんどん固まっていくことが多い。ただ、馬兵と王天に関して言えば、登場させた時点である程度先のイメージまで見えていたかな。
── : 馬兵に対して加倉が抱く感情の中には、恐怖だけではなく、歓喜もあります。「馬兵ならきっと自分を殺してくれる」という期待から来る感情です。この感情はどのように発見されたんでしょうか。
馳: 『夜光虫』で描かれたような凄惨な経験をした人間が、「十数年経ってどうなっているだろう?」と考えた時に、「本当は死にたいんだけど、自分では死ねずに生きているんだろうな」と。誰かが殺しに来るのを待っているという設定はアリだなと、早い段階で思っていました。
── : 馬兵と加倉の関係には、一種の友情も通っているんじゃないでしょうか?
馳: 歪んだ友情はあるよね。磁石のプラスとマイナス的なイメージかな。最後に殺し合うってことが分かっているからこそ、それまでに二人の関係性をぐっと濃くしなければいけない、という算段もありました。アンドリュー・ヴァクスというアメリカの小説家の「アウトロー探偵バーク」シリーズに、主人公の幼馴染みで、冷徹な殺し屋の死神ウェズリーっていうキャラクターが出てくるんですよ。馬兵は、そこからイメージして自分なりに作り上げていったんです。バークとウェズリーの関係は、加倉と馬兵の関係にも近いと思う。「悪霊VS死神」の戦いですから。
── : とにかく、意外性の連続なんです。未来の自分に向かって、「スルーパス」を出し続けているイメージを抱いたんです。ボールが繋がるか繋がらないか分からない、ギリギリのところへ思い切ってパスを出す。その連続によってボールが前へ前へと進んでいく、という。
馳: そうかもしれないですね。サッカーの話をすると、チームっていうのは約束事、戦術が決まっているわけです。ボールがここにある時は、このポジションの選手はこう動け、ああ動けっていう決まりがあって、基本的に選手はその通りに動く。でも、いざ試合となると、約束事通りに進まないんですよね。思いもよらないところにパスが突然飛んできたりするわけ。小説も同じで、物語の約束事というか、ここでこの人物にこういう行動をさせたら話はこう動くだろうなって予想はできる。でも、連載で書いていたということもあって、この先どうなるかは何も考えてないけど、伏線を入れておこうと思って書くことがよくあるんですよ。ただ、次の原稿に臨む時にその伏線を忘れて、パスミスすることもある(笑)。だけどやっぱり、大事なパスは通すよ。
── : 未来にパスを出し、物語に新しい展開をもたらす時の指針は「より面白いものになるように」という感じでしょうか?
馳: それだとちょっとニュアンスが違うかな。なんだろう……。「より完璧な作品を」って考えているかもしれない。面白くなるかどうかって、意外と考えてなくて。だってエンターテインメントとして書いているんだから、面白くならないはずがないんです。
生きていくためにはどんなものにもしがみつく
── : 物語ががらっと変化するのは、大森の姉・綾の登場からです。大森の部屋で目にした写真立ての中の彼女は、加倉が台湾にいた頃愛していた女性にそっくりだった……。その後で実際に綾と会うことになるんですが、実物はそれほど似ていないんですよね。でも……という展開が絶妙でした。
馳: 昔の恋人とそっくりな女が出てくるって、物語ではありがちだよね。でも、それは俺の中の「リアリティ尺度計」が許さないんだよ。うちのかみさんが韓流ドラマにハマっていて、俺もたまに観るんだけど、また昔の恋人にそっくりの男が出てきたよ、いい加減にしろよって思う(笑)。あくまでも自分が書いているものはフィクションなんだけど、リアリティ、本当らしさは大事にしたい。そう考えた時に、こういう展開で進めていくのが正解かな、と。
── : 綾との関係が深まっていくと、「頭の奥の声」が聞こえてくる。その声は、『夜光虫』の読者にとっては馴染み深いものです。
馳: 欲望が首をもたげた時にどうなるのか、自分との戦いというモチーフは『夜光虫』から引き継ごうと思っていました。『夜光虫』の頃と違うのは、「それで一回ものすごく痛い目に遭ってるじゃないか」って、自分でも分かっていることなんですよ。欲望とエゴが強すぎたせいで堕ちていって、これだけ辛酸を嘗めて、生き地獄をさまよっているわけじゃないか、と。にもかかわらず、同じような状況になったら懲りずにまた同じことを繰り返してしまう。人間の愚かさ、悲しさを描きたかったんです。
── : その後、加倉はある決断をします。
馳: 加倉の生きている世界と生き方を考えると、その選択をすることでしか生き残れないんです。それが不可能であるかどうかっていうのは、彼の中では論外なんだよね。倫理なんかも一切関係ない。やるしかないから、やる。そういう考え方をするのが、加倉という男なんです。
── : 加倉という主人公の何よりの魅力は、生きる、という欲望の強さだと思うんです。例えば、愛した女からの罵倒さえも、生きる力に変えていきますよね。
馳: そうですね。相手はそういう意味で言ったつもりじゃないけど、加倉は罵倒の中から、生きるためのメッセージを受け取る。この男は、生きていくためには、どんなものにだってしがみついていく。それが俺にとっての「ノワール」なんです。
── : 『暗手』の連載開始キックオフインタビューで、「虚無を抱えて絶望の中にいながらも、『それでも生きている』姿を書いてみたい」と仰っています。「それでも」の部分が、本作では爆発したのではないでしょうか?
馳: そうじゃないと続編を書く意味がないですからね。連続性と、前作からこの男はどう変わり、変わっていないのか、意味を持たせて書かなければいけない。二十年も作家をやっているので、一個一個の作品に特別な思い入れを持っていたら次が書けないし疲れちゃうんですよ。でも、この作品に関しては今できる自分の最良の仕事をやったという満足感はあります。俺なりのノワールを、書き切ることができました。