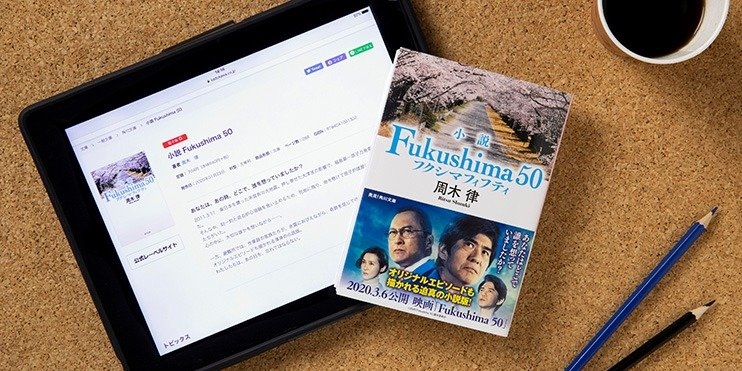小説 Fukushima 50

渡辺謙、吠える! メルトダウンに向かう福島第一原発での男たちの闘い『小説 Fukushima 50』試し読み⑥
刻一刻と迫るメルトダウンと闘う現場、本質を見誤ったまま突き進む本店。板挟みとなった福島第一原発所長・吉田は――。
>>前話を読む
作業は 、時間との闘いだった。
いつメルトダウンするかもしれないという制約に、伊崎が課した『1時間』ルールもある。何よりこれだけの線量がある環境に身を置くのは、短時間であるに越したことはない。
もっとも、だからといって作業そのものをおろそかにするわけにはいかない。せっかく危険を冒しても、肝心のバルブが開けられなければ元も子もないからだ。
確実さと、手早さ。今はどちらも求められている。
手袋の甲を見ながら、大森たちは2つめ、3つめ、4つめのバルブを開けていった。
全面マスクの奥に汗が滴り、鼻を伝う。
大森は足早に、最後の目的地へと向かった。
架台の上の高い位置にあるそのバルブの丸ハンドルは、直径60センチはある巨大なもので、かつ今までで最も原子炉に近い場所にあった。
大森は、梯子を上ると、バルブ番号を確認した。「……『25A』、これだ!」
早速ラッチレバーを上げると、手を伸ばしてハンドルを両手で握り、左に回そうとした。だが、
「むっ……」思わず、
当然だ。大プラントの大本の配管を仕切る弁が、そう簡単に開くわけがない。
「負けねぇぞ、こん畜生が」
「5……10……」当直副長が、開度計の目盛りを読み始める。
少しずつだが、バルブは回っている。大森はなおも力を込める。
「45……50……55……」
こめかみに血が集まる。食いしばった歯がギリギリと音を立てる。そして──。
「90……95……100! 弁番号25A、
「弁番号25A、開、了解! やった、これで水を入れられるぞぉ!」
大森は歓喜の声を上げた。
バルブは
5つのバルブを開けた大森たちは、速やかに中操へと戻ると、伊崎にバルブ開の成功を報告した。
「ありがとう! ありがとう大森さん!」
全身びしょ
だがその笑顔も、当直副長の報告にすぐ凍りつく。
「線量は二重扉付近で1・2ミリありました」
「そんなにあるのか」伊崎が、
そんなにあったのか、と大森も思った。サーベイが毎時で1・2ミリシーベルトというのは、尋常ではない放射線量だったからだ。
実効線量で500ミリシーベルトを被曝すると、人体は血中リンパ球の減少のような影響が出始めると言われている。これを踏まえ、原発で働く者については、年間50ミリシーベルト以下、5年間で100ミリシーベルト以下の実効線量でなければならないと法令で定められている。社内基準ではさらに低く、年間20ミリシーベルトが上限だ。
もっとも、そういった定めがあっても、運転員がこれまで被曝したことのある実効線量は、1年で高々1ミリシーベルトを少し超える程度だったのだ。
その1年間分を、たった1時間の作業で食らってしまうほどの線量。
何かが起こっているかもしれないという
大森は、伊崎に言った。「……もう、水位が
核燃料は常に水の中にある。その水位が燃料上端を切ったということは、燃料の上端が露出し、溶融が始まっている可能性があるということ、さらには放射性物質を含んだ水蒸気がどこからか外部に漏れ出しているということを意味する。
伊崎は、深く考え込むように
「1号建屋内、毎時1・2ミリシーベルト。1号機で何らかの異常が起きていると想定されます」
*
「1号建屋内、毎時1・2ミリシーベルト! 線量、上昇しています!」
緊対の吉田に、怪我人の状況報告を終えた真理は、背後で唐突に上がった野尻の大声に、思わず身体を
野尻の報告に、吉田は立ち上がると、
「1号
ゆっくりと本部長席に腰掛けると、吉田は顔を曇らせ、
技術的なことは、事務方の真理にはよくわからない。だが、1Fでこれまでになかった深刻な事態が起こっていることだけはよくわかった。何しろ真理は見たことがなかったのだ。いつも冷静な野尻があんな大きな声を出すところも、いつも笑っている吉田がこんな深刻そうな顔をするところも。
「そうだ野尻、電源車はどうした? ヘリで空輸する
「今、やってます!」
野尻が裏返った声を返すや、吉田は、
「スピード!」と、机を
*
家の中に、しんしんと寒さが染み入ってきていた。
地震の後、伊崎家はすぐに停電した。明かりもテレビも、もちろんエアコンも消えた。
外は3月とはいえまだ厳しい寒さが続いていた。遙香は石油ストーブを居間に持ち込み、母と祖父と、3人で暖を取りながらラジオを聞いていた。
まず飛び込んできたのは『
ただの揺れではないと思っていたが、まさか、それほど大きなものだったとは。
地震で散らかった居間を片付ける間もなく飛び込んできたのは、『大津波警報』だった。大丈夫かな。ドキリとしたが、遙香は思い直す。伊崎家は海岸からかなり離れていて、高台にある。原発も、津波対策は万全だろうから大丈夫なはず──。
だが、日が暮れてローソクに火を
「……どういうこと、おじいちゃん?」
首相官邸での記者会見。官房長官が伝えた福島第一原発に関する不穏な宣言に、遙香は思わず祖父を見た。
かつて、福島第一原発の建設に携わった祖父だ。何かを知っていると思ったのだ。
だが祖父は、
「『原子力緊急事態宣言』か……」と独り言のように呟いたきり、黙り込んでしまった。
不意に、遙香は嫌な寒さを覚えた。
祖父はきっと、この宣言の意味を理解している。その上で、何も言えなくなっている。おそらく、のっぴきならない事態が発生しているのだ。父が働くあの福島第一原発で。
「お父さんなら大丈夫よ。何十年もやってるんだから」
母が、遙香を
「そうだよね」遙香はわざと、口角を上げて答えた。
父なら大丈夫だ。長くあの仕事をしているのだし、何十年に一度の出来事くらい、きっと笑いながらでも対応してしまうだろう。でも──。
もし、百年、千年に一度の出来事が起きたとしたら?
「…………」
ローソクの炎が、身震いをするように揺れた。
遙香の不安は、ちっとも
2011年3月12日0時頃
正門付近 毎時0・06マイクロシーベルト
「電源車はまだこねえか!」
吉田が、マイクに向かって怒鳴っていた。
日付を
本来、本部のトップは社長であるべきだ。だが社長は11日から関西に出張していて不在らしく、そのため小野寺が代行として緊急時対策本部長を務めていたのだ。
吉田は、上長に当たる小野寺に
「電源がないと現場は計器も見られないんだぞ? 一体いつになったら届くんだ!」
その剣幕は、横にいた樋口からも、吉田が飛ばす
しかし小野寺は、「えー、それは今、そちらに向かっているかと」
「向かってたって着かなきゃ意味ねえんだよ!
「…………」小野寺が黙り込む。
「はっきりしてくれ!」
無駄な沈黙に、吉田が憤りを
だが、ディスプレイの向こうにいる小野寺は、左右の幹部とコソコソと何かを話してから、無表情のまま、「先ほども言いましたけれど、原子力安全委員会で決められているとおり、若い人は飲んでください。40歳以上の者は飲む必要はありま……」
「だから、それがおかしいってさっきから言ってるんだ!」
バン! と、小野寺の語尾を待たず、吉田は机に
あくまでも無表情を貫きながら、小野寺は両隣とまたコソコソ話を始めた。
悠長な東京の幹部たちに、吉田は、
安定ヨウ素剤は、特に原子力災害時に有効とされる、放射線障害の予防薬だ。
原子力災害が起こると、多くの放射性物質が大気中に
これを防ぐため、あらかじめ安定ヨウ素剤を飲んでおく。安定ヨウ素剤は、放射線を発しないヨウ素だ。先に飲んでおけば、甲状腺に安定ヨウ素が蓄積され、その後、もし放射性のヨウ素を吸引したとしても置き換わることはなく、結果として、放射性ヨウ素による内部被曝を軽減することができる。
一方、一定の年齢以上の者は飲まなくてよいとする判断にも、実は一理ある。ヨウ素剤の効力は年齢が上がるほど弱まることが知られているからだ。とはいえ、放射線被曝の可能性がある現場において、飲む者と飲まない者の差が生まれることは看過できない。だから吉田は強く進言したのだ。40歳以上の者も飲むべきだ、と。
にもかかわらず、本店はそれを渋った。なぜか?
理由は単純だ。飲んでよいとする根拠がないからだ。
原子力安全委員会は、40歳以上は飲まなくていいと言っているらしい。これに反してヨウ素剤を飲ませた結果、もし万が一のことがあったら誰が責任を取るのか? 本部に居並ぶ幹部たちは、それを恐れているのだ。
だから樋口は、ほとほと
「えー、吉田所長。少し時間をください。安全委員会に問い合わせて……」
「待ってらんねえよ、そんなことも決められないのか、本店は!」
怒り心頭の吉田が、また
直後、復旧班が報告した。「所長、電源車が到着しました!」
「やっとか、待ってたぞ!」吉田が笑顔を見せた。
しかし、報告した作業員が、
「どうした? 何か、あったのか」
「……使えないんです」
「使えない? どういうことだ」
「電圧が、違うんです。やってきたのは低電圧の電源車でした。でもこっちが欲しいのは、高電圧の電源車で……」
「クソッ!」
報告を聞いた吉田は、真っ赤な顔で立ち上がると、打ち合わせ用のテーブルを
「本店は一体、何をやってるんだ!」
(第7回へつづく)
▼周木 律『小説 Fukushima 50』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000667/