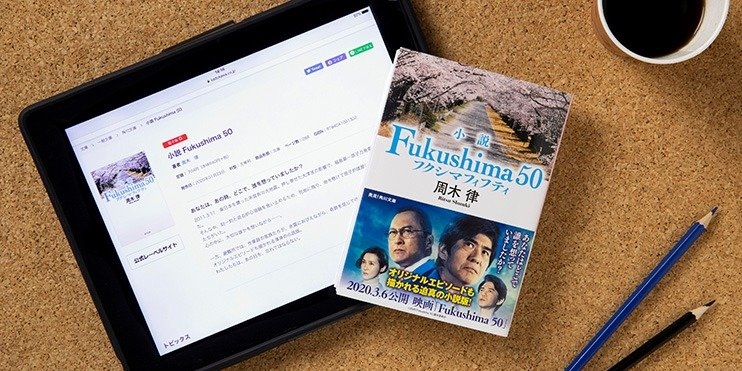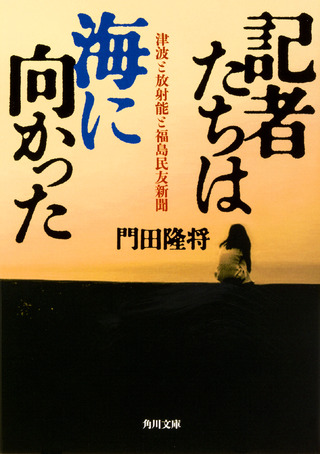小説 Fukushima 50

全電源を失った中、使命を胸に身一つで原子炉建屋に突入する男たち『小説 Fukushima 50』試し読み⑤
原子炉を冷やすためには、建屋内に入り、手動でバルブを開けるしかない。被曝の恐怖を抱えながら――。作業員たちは使命を胸に建屋内に突入した!
>>前話を読む
*
中操 の机には、どこかから持ち出された図面、緊急時マニュアル、そして懐中電灯やヘッドライトの
津波により電源が失われ、また原子炉建屋も津波に襲われた。冷却機能が失われ、原子炉がどのような状態にあるのか把握もできずにいる。まさしく五里霧中と言うべき状況の中、西川は、不安に押し
これは、夢だ。そうであってくれ。
何度もそう願い、目を閉じる。だがその願いも空しく、西川は、先輩たちが動き回る気配や、飛び回る蠅のような懐中電灯の光、制御盤が発する機械特有の臭い、何より、時折不気味な音とともに突き上げてくる余震によって、すぐ現実に引き戻された。
何度目かの余震が過ぎ去った後、不意に、それまでずっと考え込んでいた伊崎が、すっと立ち上がった。
「……皆、ちょっと聞いてくれ」
男たちが会話を止め、当直長に向き直る。
何条もの光に照らされながら、伊崎は、神妙な声色で言った。
「これから、原子炉建屋に入ろうと思う」
全員が、息を止めた。西川も、自分の心臓がドクンと脈打つ音を聞いた気がした。
原子炉建屋に入る。言うまでもなくそれは、制御盤では見ることができなくなった原子炉の状態を直接確かめ、または修繕していこうという意思表示である。
「原子炉の中で何が起こっているかわからない状況だ。俺たちにも何が起こるかわからない。だから、改めて、現場へ行くときのルールを徹底しておきたい」
ひとつ間を置くと、伊崎は続けた。「現場に向かうときは必ずペアで行動すること。それをまず第一に守ってもらう。もし、1時間経っても帰ってこなければ、救出に向かう。たとえ目的の場所に着かなくても、1時間を超えるようならその時点で戻れ。それから、出入りの時間をホワイトボードに書き込むこと。……いいな!」
「了解!」一同が、ほぼ同時に返事をした。
西川も返事をすると、心の中でルールを
1、必ずペアで行動する。
2、1時間経ったら帰ってくる。
3、出発した時刻と戻ってきた時刻を、ホワイトボードに書く──。
「1号は慎重にな。アメリカ製で手が掛かるぞぉ」
大森が軽口を
だが伊崎は、あくまでも真剣な表情のままで続けた。
「電源が復旧しなければ、いずれ原子炉内の水は干上がり、
「メ、メルトダウン……」西川は、冷水を浴びせられたような気分になった。
核燃料は放射性物質であり、
だが、このまま放っておけば、核燃料は崩壊熱によって摂氏何千度にもなる。やがて溶け落ち、容器を突き破り、外に出てきてしまう。
それが、炉心溶融。メルトダウンだ。至近にいる西川もまた、大量の放射線に
「だから、水を入れて冷やすんだ!」
伊崎の声に、西川ははっと我に返った。
「そのためにまず、原子炉建屋内の消火用配管ラインのバルブを開ける必要がある。水の通り道を作るんだ。水が通れば、炉心を冷やせるからな。開けなければならないバルブは5つだ……」伊崎が、バルブ番号を口にしながら、図面を指差した。
先輩たちが、素早くそのバルブ番号をメモする。西川も倣って、手元のメモに番号を書き留めようとした。
だが、書けなかった。手がブルブルと震えてしまったからだ。
西川は想像してしまった。開けなければならないバルブが5つもある。つまり、その数の分だけ、誰かがリスクを負わなければならないのだ。何が起こってもおかしくない原子炉のすぐ傍に、誰かが行かなければならないのだ。
西川の背筋を、冷たい汗がツーッと滴り落ちた。
2011年3月11日17時19分
正門付近 毎時0マイクロシーベルト
「なんでそんなことになってるんだ!」
首相は、
東北地方に襲いかかった
──福島第一原発が、津波に襲われ全電源を喪失、冷却機能を失っている。
昨年秋、首相は原子力総合防災訓練に参加していた。静岡の原発で冷却装置が故障し、放射性物質が放出されるおそれあり。そんな設定で行われた訓練は、予定調和のものではあったが、事前の説明もきちんとなされていた。
津波により、冷却機能が失われるおそれがあります。もし冷却機能が失われれば、原子炉がメルトダウンし、放射性物質が
そう、大丈夫だと
「一体、津波対策はどうなってたんだ!」
報告に来た原子力安全・保安院院長を、首相は怒鳴りつけた。
院長は恐縮しながら、「それが、その、想定外の大津波が襲ってきたもので……」
「冷やせなきゃ原子炉は空焚きだ、暴走するぞ? 放射能が出ちゃうだろうが! もっと細かい情報が下から上がってきてないのか!」
「そのう、すみません、まだ、何も……」院長は、これ以上ないほど身体を
頼りにならないと思いつつ、首相は問うた。「何か、手はないのか」
「それは今、色々と対策を練っているところで」
「どんな対策だ? 言ってみろ」
院長に詰め寄る。「俺にわかるように、きちんと説明しろ。君は担当庁のトップだ。原発を管轄する立場にあるんだぞ」
「ええと……私には、そのう」
院長は、気まずそうに目を
「お前、文系なのか」
「はい」
「…………」
原発のことが何もわからない男を、トップに据えたのか。日本全国の原発の安全を担う役所のトップに──。
いつもなら「馬鹿野郎、ふざけるな!」と
だが首相は、もはや怒鳴る気にすらなれず、ただ
*
大森は、驚いていた。
よく見知ったはずの松の廊下が、初めて訪れる場所のように感じられたからだ。
原子炉建屋とタービン建屋を結ぶ地下通路、通称『松の廊下』は、長さが50メートルはある長い通路だ。1Fで仕事をしていれば日常的に通る廊下であり、大森自身もこれまで何千回、いや何万回と往復している、見慣れた場所である。
それが、今はまるで別物に思えた。
懐中電灯の光を当てれば、見覚えはある。しかし、それは明らかに大森の知っている場所ではなかった。
暗いせいだろうか。それとも、放射線の恐怖によるものか。
いつメルトダウンが起きてもおかしくない現状が、俺をして
「へっ、ろぐなもんでねぇな」大森は、全面マスクの奥でわざと冗談めかして
そして、恐怖心を押し殺しながら、ペアを組んだ、一回り年下の当直副長とともに、松の廊下を進んでいった。
5つのバルブを誰が開けに行くか。大森はこの仕事に、真っ先に志願した。
理由は単純、放っておけば責任感の強い伊崎が「俺が行く」と言い出しかねなかったからだ。伊崎は地震が起きたときから中操にいる当直長であり、指揮官だ。あいつに線量を食らわせるわけにはいかない。それでなくとも大森は、中操にいる人間の中では最も年長だ。もし危険を冒すなら俺しかいないと、初めから思っていたのだ。
手を挙げた大森に続いて、当直副長も手を挙げた。こうして、自然とこの二人が『突入部隊』となった。
いつもなら空調の音が聞こえる通路が、不気味な静寂に包まれている。そのせいか、歩くたびにカサカサとタイベックが
タイベックは、不織布で作られた使い捨ての全身防護衣だ。防護するとは言っても、あくまで表面汚染を防ぐためのもので、ガンマ線など透過性の高い放射線は防げない。
胸につけた、タバコの箱ほどの大きさの
「くそっ、後だ後!」
できるだけ余計なことを考えないようにしながら、大森は、松の廊下を早足で進んだ。
突き当たりの重い二重扉を開けると、バルブのある原子炉建屋へと足を踏み入れる。
やはり、真っ暗だった。だが、松の廊下と異なり、少し空間の広がりを感じた。すぐ目の前に、原子炉を収める格納容器があるからだろうか。
「かなり線量が高いです」背後で、
メータの針はきっと、この場所の空間線量を示しながら、ゆらゆらと揺れているのだろう。一体何マイクロ、いや何ミリあるのだろう。もしかするととんでもない数字を
くそっ、また想像しちまった。
大森は心の中で毒づき、恐怖心を振り切ると、左手のゴム手袋の甲を見た。
『365、……、25A』
大森たちが開けるべき5つのバルブの番号が、油性ペンで書かれていた。
プラントの配管は把握している。バルブの場所も頭の中に叩き込んだ。だが「それが本当に開けるべきバルブか」は、必ずチェックしなければいけない。
水の通り道を作るんだ。水が通れば、炉心を冷やせるからな──伊崎の言葉が
右側の階段を下りていくと、ひとつめのバルブを見つけた。
「あったぞ!」バルブは図面どおり、両脇を配管に囲まれた窮屈な場所にあった。
身体を
大森はバルブの奥にある
鈍い
「10……20……」当直副長が、バルブの横にある開度計の
少しずつ、しかし確実に、大森はなおもハンドルを回す。
「……80……90……100! 弁番号365、
「弁番号365、開、了解! 次ぃ!」
当直副長に復唱するや、大森はすぐさま
(第6回へつづく)
▼周木 律『小説 Fukushima 50』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000667/