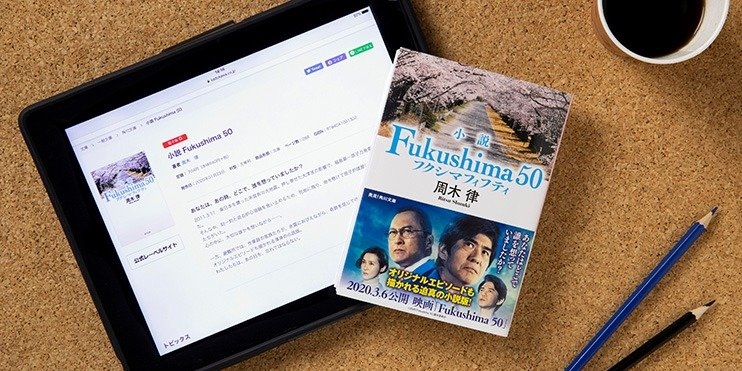小説 Fukushima 50

大地震、津波――あの日の福島第一原発が映画に『小説 Fukushima 50』試し読み④
どんな手段を使っても、原子炉を冷やすしか道はない――。全電源を喪失したなか、作業員たちは猛然と「今やるべきこと」に取りかかった。
>>前話を読む
*
発電 班席で突然鳴り出したホットラインの受話器を取った発電班長の
「なんだって? 非常用電源が……止まった?」
野尻の言葉に、緊対が一瞬、凍り付いた。
非常用電源、つまりDGが止まること。その意味は、第一運転管理部の部長職を預かるベテランの野尻だけでなく、今この場にいるすべての人間が理解できたはずだ。
原子炉はすべて、電気的にコントロールされている。それだけでなく、原子炉の状態も電気的に感知されている。つまり、電気がなければ、原子炉の運動神経も、感覚神経も働かないのだ。
それは目隠しされた上に、
『そうだ。今なんとか原因を調べてる。中操でも頑張ってみるから緊対でも……おい、どうした?』
野尻は、受話器を握ったまま絶句していた。
野尻だけではなく、緊対の人間はすべて手を止め、
ただひとり、吉田だけが猛然と野尻の傍に走り寄り、
「俺に貸せ!」
受話器をひったくるや、「吉田だ! 伊崎、非常用電源が止まったって、どういうことだ! もっと細かいことはわかんねえのか!」
そのとき、別のホットラインが鳴った。
すぐ傍にいた職員が、受話器を取り上げると、ややあってから裏返った声で叫んだ。
「さ、3号、4号、SBO!」
「なんだと……」
伊崎と繫がったままの受話器を持ちながら、吉田も言葉を失った。
1号機から4号機まで、すべての電源が失われた。
認めたくない現実が、今そこにあった。
だから野尻は、ごくりと
「所長、これは……『原災法10条』に該当します」
原災法。正式名称を『原子力災害対策特別措置法』という。1999年に発生した東海村JCO臨界事故を契機として作られた法律で、原子力災害が放射能を伴うという特殊性を踏まえ、国民の生命、身体、財産を保護することを目的とする。
この法律の10条には、施設敷地緊急事態として、一定の事象が発生した場合には直ちに主務大臣に通報すべきことを規定する。野尻はかつて、そういうふうに教わっていた。
そのときの野尻は、「まさか、この規定が使われるケースはないだろう」と高をくくっていた。この条文は、万が一のためのものだ。我々は万が一がないように、日々プラントをコントロールしている。だから、そもそも使う機会などあり得ない。
だが、現実は残酷だった。
その機会は今、きてしまった。あり得ないことが起こってしまったのだ。そして、起こってしまったからには
「所長!」
愕然としたままの吉田に、野尻は叫んだ。
吉田は、はっと我に返ると、本部長席のテレビ会議用マイクのスイッチを入れ、いつも泰然自若とした吉田には珍しい、上ずった声で言った。
「本部、聞こえますか! 1F……
*
真っ暗闇となった中操では、非常用の懐中電灯だけが、信じられる『光』だった。
伊崎たち14人はそれぞれ、制御盤に張り付き、その細い光を計器類に当てながら、今起こっていることを何とかして突き止めようとしていた。
SBOはなぜ起こったのか。その結果、原子炉に何が起こっているのか。
「冷却装置はどうなった? 1号のイソコン、動いてるか?」
伊崎は、暗闇に向かって叫んだ。
1号機も2号機も、原子炉そのものはスクラムし緊急停止が完了した。これによって、とりあえず核燃料の連鎖反応は止まっている。
しかし、これで核燃料の発熱が完全になくなるわけではない。
原子炉に収められた核燃料であるウラン235の原子核は、中性子を当てるとエネルギーを生み出す。原子炉は、この原子核反応を連鎖的に起こすことによりエネルギーを取り出すためのボイラーだ。ただ、連鎖反応がストップしても、核反応そのものは一定割合で勝手に起こる。その割合は
物理学的には『崩壊』と呼ばれる現象である。これにより、原子炉は発生した熱エネルギー、すなわち『崩壊熱』により、自然に温められていくことになる。原子炉は、完全に停止しても自然に熱を発するのだ。
問題は、この自然発熱を放っておくとどうなるか、だ。
微弱ではあっても、崩壊熱は継続的に発生する。時間が経てば崩壊熱により、原子炉内の温度は摂氏何百度、何千度まで上昇していく。当然、原子炉内の水は沸騰し、水蒸気に変わる。これにより原子炉内の圧力が高まり、燃料が溶け、メルトダウンに向かう危険性が生ずる。ともすれば高熱によって原子炉そのものが溶かされてしまうかもしれない。
止める、冷やす、閉じ込める──緊急時プロセスの2つめに『冷やす』があるのは、このためだ。有事の際にまず原子炉を止めることが最優先なのは当然だが、その後は、崩壊熱による温度上昇とそれによってもたらされる原子炉の破壊を抑えるため、確実に原子炉と核燃料を冷やしていくことが要求されるのだ。
この、冷やすための命綱となる装置が、
1号機の
つまり、イソコンが動いてさえいれば、原子炉は冷える。
伊崎が暗闇の中、何よりもまずイソコンの稼働状況を気にしたのは、このためだった。
だが、「……わかりません!」
「原子炉の水位も、圧力も、な、何も確認できません!」
と、ゼロを指したままの計器を懐中電灯で照らしながら、運転員たちが答えた。
「2号はどうだ? RCICは動いているか?」
「地震の後は動いていましたが、今はわかりません」
伊崎の問い掛けに、また誰かが答えを返した。
こんなときでも皆は機敏だ、と伊崎は思った。だが同時に、だからこそ状況が刻一刻と悪い方へ向かっていることも理解できた。イソコンやRCICが動いているか、あるいは原子炉の中がどのような状況にあるか、これらはすべて電気的センサーで感知している。したがって、電源が落ち、電気がきていない今、センサーは働かない。完全に目隠しをされた状態になっているからだ。
「……冷やさねぇと、大変なことになるぞ」と、大森が
わかっている。そんなことは、わかっている。
だが、そもそもなぜこんなことになったのか。状況を確かめる
「くそっ、何がどうなってるんだ……」
当直長席の机を
そのとき、中操のドアがバンと開いた。
二人の男が、つんのめるように転がり込んできた。
息を切らせながら、ずぶ
「工藤、お前どうしたんだぁ」大森が問う。しかし工藤は、
「やばい、やばいです!」とパニックを起こしたように、中操の男たちの顔を見回した。
工藤の前にゆっくりと座ると、伊崎は、
「落ち着け、工藤。一体、何があった?」
工藤は一度、ごくりと唾を飲み込むと、一拍を置いて、
「つ……津波! 津波です!」
「……津波?」
「そ、そうです! この建屋にも、か、海水が入ってきています!」
原子炉建屋に、海水だと──?
その瞬間、伊崎は理解した。
地震による巨大な津波。その津波が1Fを襲い、原子炉建屋を水没させる。同じ海抜に建てられたDG建屋も水没しただろう。だとすれば当然、非常用発電機はおじゃんになる。機能を停止する。つまり、電源が、止まる。
「SBOは、それでか……」伊崎は、
原因は津波だ。それで説明できる。しかし、説明できても納得はできなかった。
原子炉建屋もDG建屋も海抜10メートルの高さに造られている。その高さを超える津波が襲い掛かってきたなど、あり得ない!
だが、そのあり得ないことが、現に起こった。
だとすれば、これからもあり得ないことが起きてくるだろう。訓練もしていない、マニュアルにも書いていない出来事が、俺たちに襲い掛かってくる──。
「お前、津波に巻き込まれたのかぁ。誰か、タオル持ってこい!」と、大森が叫んだ。
*
「所長! 津波でした!」
ホットラインの向こうにいる伊崎の説明を聞きながら、樋口は大声を上げた。
樋口の報告に、緊対がどよめいた。本部長席にいた吉田も立ち上がると、
「信じられん、津波が、
「想定外の大津波です。中操も今、真っ暗で、計器も何も見えないそうです」
「だから、電気が落ちたのか」
険しい顔でしばし考え込んでから、吉田は続けた。
「とにかく今は電源だ。本店に電源車を要請してくれ!」
「了解です」
「あ、ちょい待て」
指示を受けるや本店に連絡を取ろうとした樋口を、吉田は呼び止めると、数秒の間を置いてから、
「……消防車だ。消防車もすぐ手配しろ」
「えっ、消防車ですか?」
そんなもの、火が出ているわけでもないのに、何に使うのか?
首を
「わかんねえのか、冷やすんだよ、原子炉を! ポンプを動かす電源がねえんだぞ、代わりに消防車を使って水を入れるしかないだろが」
「あっ!」
「構内に三台あったはずだ。今すぐ手配するんだ!」
「了解です!」
即座に身体を動かしながら、樋口は、先刻の伊崎の報告を思い出していた。
『津波だ。DGが沈んで電源が落ちた。とにかく今は早く原子炉を冷やさないといけない。方法は緊対でも考えてくれ』
原子炉を冷やす。緊対の吉田も、中操の伊崎も、同じことを発想していたのだ。
もちろん、これは偶然ではないだろう。百戦錬磨のプラントエンジニアである二人だからこそ、同じ結論に
あるいは、感傷的かもしれないが、これが『
だが、現場担当者からの報告に、樋口のそんな気持ちは打ちのめされた。
「消防車のうち二台が、津波にやられて使えません!」
「本当か?」愕然とした樋口の横で、吉田が、険しい声で問うた。
「もう一台はどうなってる」
「無事だそうです。で、でも」
「でも、なんだ」
「
「難しくてもやれ!」
吉田が、緊対中に響く大声で怒鳴った。「瓦礫が邪魔ならどけろ! 人が要るなら駆り出せ! ないものねだりしたってどうしようもねえんだ。知恵を使えよ、できることをやれ、
「は、はい!」
吉田の一喝に、担当者が緊対を飛び出して行った。
樋口は、ややあってから吉田に言った。「消防車一台じゃ、とても足りません」
「ゼロよりゃマシだろ」
「そりゃ、そうですが……」
「わかってるよ樋口。……本店を通じて、自衛隊に消防車を要請してくれ」
「了解です」樋口は、本店に繫がる電話を取った。
吉田が、フー、と長い
(第4回へつづく)
▼周木 律『小説 Fukushima 50』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000667/