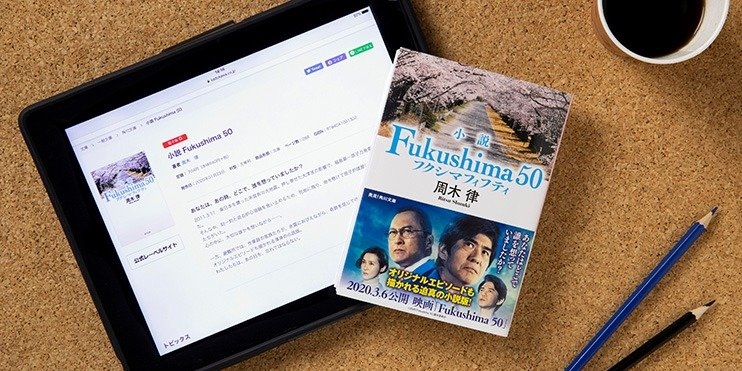小説 Fukushima 50

震災の日、非番だった作業員は妻と息子を置いて原発へ向かった『小説 Fukushima 50』試し読み③
福島第一原発を大津波が襲った! 中央制御室は全電源を喪失。真っ暗闇のなか、原発の暴走を止めるべく、命を懸けた闘いが始まった――。
>>前話を読む
*
DGが 起動してからの
西川はまだ若かった。と言ってももう26、キャリアも7年を超えるのだが、第一運転管理部にいる百戦錬磨のエンジニアの中ではまだまだ
だからかどうかはわからないが、信じられないほど大きな地震が起こり、1号機と2号機がスクラムし、停電し、DGが起動するという目の前で起こる一連の出来事に対して、なんだか現実感が乏しかった。
一体、皆は何をしているんだろう? 俺も何やってるんだろう?
災害時の訓練通りに動いてはいたが、西川はどこか上の空だったのだ。
その代わり、頭の中では今朝の出来事が思い出されていた。
「……だからね、こんな危ない仕事は、もう辞めてほしいの」
出勤しようとした西川に、ゆかりがそう言った。
理由は『危ない』から。原発のような放射性物質を扱う部署に恋人がいるのが耐えられない、だから他の仕事に就いてほしい、と懇願するのだ。
確かに、彼女が過去どんな経験をしたかを考えれば、そう言いたくなる気持ちもわかる。けれど西川にも、工業高校で優秀な成績を修め、推薦されてこの仕事に就いたのだ、というプライドがあった。放射線ごときで簡単に辞めるわけにはいかない。
辞めて。辞めない。堂々巡りの口論は、日増しに多くなっていた。
ただ、今朝のゆかりはやけにしつこかった。「辞めてくれなければ、もう付き合いを考え直す」とまで言い出した。だから西川も、思わずかっとなり、玄関口で怒鳴ってしまったのだ。
「うるさいな! ほっといてくれ。お前の顔なんかもう、二度と見たくないよ!」
──なんで今朝、あんなこと言っちゃったんだろうなあ。
あいつ、地震で無事かなあ。もし何かあれば、あれが最後の言葉になっちゃうんだ。それなら、あんなこと言わなきゃよかった。
自分が吐いた暴言に、西川は今さら後悔していた。
「大丈夫かぁ、応援にきたぞ!」
突然、中操に、数人の男たちが入ってきた。
作業管理グループの当直長、
「大森さん、ありがとうございます」
「
「今のところ順調です」
伊崎が
すかさず誰かが出て、伊崎に取り次いだ。「当直長、所長からです」
「代わってくれ……はい、伊崎です……うん、大丈夫だ。今のところ問題は……えっ? 津波?」
伊崎の顔色が曇った。
「うん……うん……わかったよ、ありがとう、
電話を切ると、伊崎は一同に言った。「大津波警報が出ているそうだ」
津波だって? 大丈夫なのか? と中操がどよめいた。
西川も一瞬ぎくりとしたが、それでも大丈夫だろうとすぐに思い直す。
このプラントは海抜10メートルの地盤に造られている。それを超えるような津波はまずないと考えられているからだ。津波が来ても、問題はない。それよりも──。
「……吉やん?」って、誰のことだ?
西川が
「そうだったんですか」だとすれば所長は随分、砕けた人なんだなぁ。
そう思う西川に、先輩が言った。「気ぃ抜くな西川! まだ終わってねえぞ。マニュアル、きちんと用意しとけよ」
「はい」西川は返事をしながら、ずれたヘルメットの位置を直した。
*
そのとき、
当直副長である拓実は、本当なら今ごろ1Fにいる予定だった。だが、たまたま病院での検査と重なり、他の当直副長とシフトを代わってもらっていたのだ。
天地を揺るがすような揺れに、拓実はとっさに、妻と息子の上に覆い被さる。
拓実は48歳、妻のかなは8つ年下だ。結婚が遅く、子供もなかなかできなかったが、5年前、待望の息子、
「かな、徹、お父さんの下に!」何よりも大事な家族だ。時計や置物が背中に落ちてくるのに耐えながら、拓実は必死に二人を守った。
揺れが収まると、家の中は変わり果てていた。
タンスは倒れ、食器もほとんど割れてしまった。だが幸いなことに、かなにも徹にも怪我はなかった。
だが、ほっとすると同時に、拓実の頭には職場のことが
1Fは、どうなってる?
この地震だ。プラントも無事では済むまい。復旧の人手がいるはずだ。だったら──。
「拓実さん、どこに行くの?」
突然ジャンパーを羽織り、出かける支度をし始めた拓実に、かなが不安そうに尋ねた。
拓実は、「かな、ごめん」と謝ると、
「俺、原発に行かなきゃ。きっと皆、大変なことになってる。行かないと」
「……わかった」拓実の職責を十分に理解する妻は、徹を抱いたまま、頷いた。
二人の姿に、ふと拓実の頭にためらいが過る。
今、この二人を置いていって、いいのだろうか? だが──。
拓実は、玄関に向かった。僕を必要としている場所がある。そこに行かなければ。
「……行ってくるね」
「行ってらっしゃい。気を付けてね」
妻と息子から離れることに後ろ髪を引かれながらも、拓実は、二人の顔をしっかり見つめてから、後ろ手に扉を閉めた。
2011年3月11日15時35分
正門付近 毎時0マイクロシーベルト
初めは小さな揺れだった。2日前にも少し大きめの地震があったから、それと同じようなものかなと思っているうち、揺れはあっという間に天地をひっくり返すほどの衝撃へと膨れ上がっていた。
「地震だぁ! どっかに
だがそう叫ぶ自分自身が立っていられず、すぐに、床に転がされる。
1号機から3号機まで、無事か?
51歳の工藤は、当直長という大役を任されている。もちろん、原子力を扱うプラントに万が一のことがあれば、破滅的な結果が待っていることも、嫌と言うほど知っている。
だから、揺れが収まってからしばらくして、目の前にあるDG建屋の発電機が起動したことに心底ほっとした。電源が確保されれば、原子炉は最悪の事態を免れる。
おそらく、中操にいる伊崎たちは、スクラムにも成功したに違いない。
DG建屋内の安全確認をひととおり終えた後、同僚と連れ立ち建屋を出ると、各所の運転員や協力企業の作業員たちも、あちこちで慌ただしく動いているのが目に入った。
うん、この雰囲気なら、致命的なことにはなっていなそうだ。
だとすれば俺ができることは、中操に加勢すること。あいつら大変だろうからな。
そう心に決めた工藤が、中操のあるサービス建屋に向かおうとしたとき、
「あ、ありゃ何だーっ!」
誰かが、絶叫を上げた。
振り向くと、DG建屋の向こう、海側から、何かが迫っているのが見えた。
何だ、ありゃあ? 工藤は目を凝らす──黒い壁?
湧き上がる疑問に、また別の誰かの絶叫が答えた。
「逃げろーっ! 津波だぁー!」
そうか、津波か! あの地震が引き起こした、大津波か!
だけど、こんなに大きな津波って、あるのか?
そう思ったときには、すでに、黒い壁は工藤の頭上に迫っていた。
はっと気づいた工藤は、反射的に、津波が来るのと反対方向に走り出した。だが、そんな工藤をあざ笑うかのように、ドドドドドと不気味な
「うわあっ!」
足を
工藤はそのまま、自分を飲み込んだのと同じ濁流が、DG建屋にも猛然と襲い掛かっているのを見ながら、しょっぱい水の中に引きずり込まれていった。
2011年3月11日15時40分
正門付近 毎時0マイクロシーベルト
まず、伊崎の頭上で輝いていた蛍光灯が、フッと消えた。
それを合図にしたかのように、中操の蛍光灯と制御盤のランプが、パタパタと消えていく。まるで壁に貼られていた
二百坪ほどの中操の暗闇に、1号機側の淡い非常灯と、腕時計の蛍光塗料が放つ青緑色だけが残った。
同時に、鼓膜が痛くなるほどの静寂が、伊崎たちを襲う。
光が失われたのと同時に、あれほど鳴り続けていたアラームもぱたりと消えたからだ。
「……な、なんだ?」静けさに耐えかね、誰かが言った。
「どうした?」伊崎も、きょろきょろと暗闇を見回した。
伊崎だけではない。きっと誰もが思っていただろう。なぜ明かりが消えた? 今、何が起こっている?
不安と不気味さを
「ディ……DG、トリップ!」
「電源が落ちましたぁ!」
「なんだと!」伊崎は
非常用の
だが、追い打ちを掛けるように、別の運転員たちが、
「1号、エ……SBO!」
「に、2号、SBO!」と、立て続けに現状報告を絶叫した。
SBO。ステーション・ブラックアウトの略。つまり、
伊崎は即座に理解した。制御盤はすべて電気でコントロールされている。電源が失われたのだから、照明も制御盤も作動しなくなって当たり前だ。
だが現実は、当たり前の一言では済まされない。
地震があり、主電源が落ちた。それをカバーするためにDGが起動した。だが、それも落ちた。さらにバッテリーさえも落ちた。そして、電源が完全に失われた。これから一体、何が起こるのか。
いや、そもそもDGに何が起こったのか。
「なんで、電源が落ちるんだ」
「どうなってる?」
「何があったんだ……」
運転員たちも、口々に疑問を発していた。海千山千の大森ですら、顔の下半分を手で覆ったまま、言葉を失っている。
「わ、わかりません。どうしてこうなっちゃってるんですか……」と、若手の西川も、助けを求めるような顔でおろおろとしていた。
もはや中操だけの問題ではない。伊崎はそう判断すると、中操の端に設置されていた非常時用のホットラインの封を切ると、赤い受話器と、その向こうにある緊対に向かって叫んだ。
「全交流電源、喪失!」
(第3回へつづく)
▼周木 律『小説 Fukushima 50』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000667/