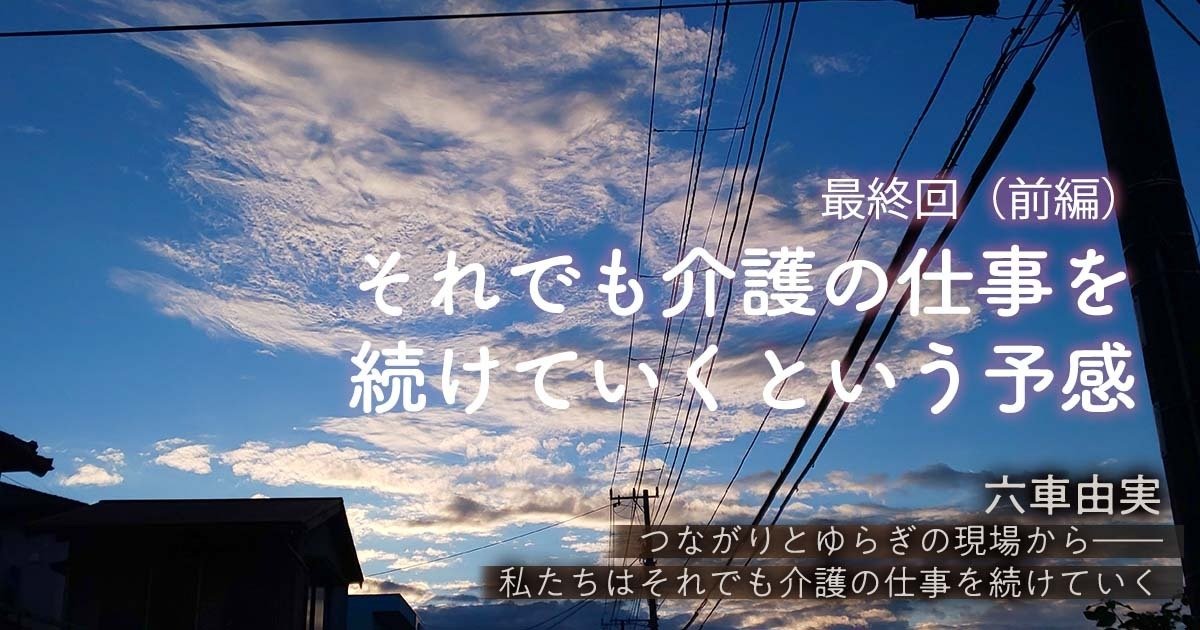
カドブン連載「つながりとゆらぎの現場から―私たちはそれでも介護の仕事を続けていく」 最終回 それでも介護の仕事を続けていくという予感(前編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
◆ ◆ ◆
再び「すまいる劇団」
今年も「すまいる劇団」によるお芝居の準備を始める時期がやってきた。「すまいる劇団」とは毎年一回起ち上げられる、利用者さんとスタッフとが参加してお芝居を作り、演じる劇団である。昨年は、10月下旬に開催した文化祭で、厨房を手伝ってくれている地域の方と私の母とを招待して、彼らの前で、「富士の白雪姫」を披露した(連載第5回)。みんなで何度も話し合いを重ねて出来上がったシナリオは、原作の「白雪姫」からは大きく逸脱してはいるものの、利用者さんたちの個性や経験が十二分に反映されたオリジナルのストーリーになったのだった。
今年の演目を何にするかは、初夏にはもう話が出ていて、どういう経緯だったか覚えていないのだが、「浦島太郎」がいいだろう、ということになった。ただ、お芝居を披露するのは、9月下旬の水曜日の予定で、水曜日は偶然にも男性が一人もおらず、女性の利用者さんのみの日。女性が浦島太郎(男性役)をやればいいのだけれど、そもそも浦島太郎が女性でもいいだろうということになり、「浦島 太郎」ならぬ、「浦 島子」が主役の物語を作ることになったのだった。
そこで、スタッフの亀ちゃんがお芝居「浦島子」のシナリオの下案を作ってきて、みんなの前で大きな声でゆっくりと読み上げた。ストーリーはだいたいこんな感じ。
浦島子が片浜海岸を通りかかると、浜で漁師が網引きをしていた。網には近海の魚とともに一匹の亀がひっかかっていた。浦島子が網にひっかかった亀を助けると、亀はお礼に駿河湾の海底にある竜宮城に連れて行ってくれた。竜宮城では乙姫様と魚たちが歓迎してくれ、歌や踊りを披露して浦島子を楽しませてくれた。宴会が終わり、浦島子が、「そろそろお暇します」と帰ろうとしたところ、乙姫様が玉手箱をお土産に持たせてくれた。亀に連れられて片浜海岸に戻ってくると、浜ではまだ漁師が網引きをしていた。浦島子が、玉手箱をお土産にもらったことを思い出して開けてみると……。
片浜海岸は利用者さんたちの何人かが住んでいる地域のすぐそばにある海岸で、夫がしていた網引き漁を手伝っていた、という話を何度も聞いている。そんなエピソードから亀ちゃんは、亀が子供たちにいじめられるのではなく、たまたま網にひっかかってしまったと設定を変えてくれたのだった。
亀ちゃんが悩んだのは、玉手箱の中身である。玉手箱を開けたら煙が出てきて歳を取ってしまった、というのではあまりにも悲劇的で、敬老会の演目のエピローグとしてはふさわしくないのではないか、と思ったのだそうだ。言われてみれば、確かにそうかもしれない。
亀ちゃんは、みんなに、「玉手箱の中身は何がいいでしょう? 最後はどう終わったらいいかな?」と問いかけた。すると、コロナ禍前まではボランティアとして朝のバイタル測定の手伝いに来てくれていて、今年の8月からは利用者さんとして参加している、元看護師の89歳のアイさんがこう言った。「若返った方がいいじゃない?」。歳を取ってしまう原作とは真逆の発想に、私は、「なるほど、それいいね」と嬉しくなった。そこで、「何歳ぐらいに若返ったらいいかな?」と聞くと、アイさんは少し考えた後に、「二十歳に戻りたいね。やり直せるじゃ」と笑いながら答えた。それを聞いたみんなも、「そうだね」「二十歳、いいね」と大笑いしていた。
浦島子は「未亡人の主婦」
そして、大体のストーリーが決まったところで、今度は配役へ。この時はみんな遠慮がちで、自分から何の役をやりたい、とはなかなか言ってくれない。そこで、まずは「二十歳に若返る」というエピローグを提案してくれたアイさんに、「浦島子、やってもらえます?」とお願いしたところ、「嫌だよ」と即答されてしまった。どうやら物語の案を考えるのと、その役を演じたいと思うのとは違うらしい。
「じゃあ、乙姫様は?」と尋ねると、「いいね。長いドレス着て、真珠のネックレス着けたりしてね」とアイさんは快く引き受けてくれた。そして、ずっとみんなのやり取りを聞いていたトウコさんも、「乙姫様なら……」と呟いた。というわけで、乙姫様は姉妹であるという設定に変更になった。
片浜海岸の近くに住んでいるタカミさんに、漁師役をお願いしたが、「網引きはやったことがないからできないよ」と断られてしまった。でもすぐに、「わたしゃ、亀でいいよ」と亀役を引き受けてくれた。すると、美砂保さんが、「うちの居間に、亀の甲羅が飾ってあるんです。使います? 持ってきましょうか?」と言い出すと、アイさんも「うちの玄関にもあるよ!」と、スタッフのまっちゃんも「うちにも小さいけど亀の甲羅がある」と、次々と亀の甲羅を持っているという話が出てきてしばらくその話題で盛り上がった。
さて、肝心の浦島子はどうしようか、と配役の話に戻し、その日の一番年長者であるきーやさんに浦島子役をお願いすると、意外にも、「いいですよ」と少し照れながらも快く引き受けてくれた。
ああこれで一安心、と思った矢先、たまたま用事があって1階に下りてきていて、みんなの話し合いを聞いていた母から、「浦島子さんの職業は何ですか?」という突っ込みが入った。「もともとの浦島太郎は漁師でしょ。だから、浦島子さんは何のお仕事している人なのかな?って思って」と。鋭い指摘である。
亀ちゃんが、きーやさんに、「浦島子の職業は何にしましょう?」と尋ねると、きーやさんは、「私は外では仕事したことないからね。ずっと家のことやってたから……」と悩み、一呼吸おいてから、「主婦だね。近所の主婦」と笑って答えた。みんな自分の経験にひきつけて一生懸命考えてくれる。本当に面白い。
テンさんとカナさんは、竜宮城で浦島子を歌や踊りで歓迎する魚役をやることになり、それぞれなりたい魚(タコやイカとかでも、カニ等の甲殻類でもOK)を選んでもらった。テンさんはアジ、カナさんはキンメダイになることに。なりたい魚というより、食べたい魚を選んでくれたようだが、特にカナさんは本格的で、「それじゃキンメダイの生態がわからないといけないわね。以前、息子が魚屋に勤めていたから聞いてくるわ」と意気込んでいた。
残る漁師役は最後に美砂保さんが引き受けてくれた。すると亀ちゃんが、美砂保さんが若い頃、よく宝塚歌劇を観に行っていたと語っていたのを思い出したのか、物語の終わり方についてこんな提案をしてくれた。
竜宮城から帰ってきた浦島子は、片浜海岸で漁師と再会し、二人で一緒に玉手箱を開けると、二人とも二十歳に若返った。そこで二人は結婚し、幸せに暮らした。最後に、みんなで「ふたりは若い」を歌って幕が下りる。
そして、更に亀ちゃんは、こう付け加えた。「だから、浦島子は未亡人の近所の主婦で、漁師は独身、ということにしよう」と。
きーやさんも美砂保さんも、手をたたいて大笑い。「いいんじゃないの」「笑えるね」とみんな賛成してくれた。
こうして、ストーリーも配役も決まっていった。今年も、物語も役柄も個性豊かで、面白くなりそうだ。
みんなで話し合って作り上げる幸せ
私は、お芝居を作るという一つの目的に向かって、みんなでワイワイ言い合い、大笑いしながら話し合うこの時間がたまらなく好きだ。
利用者さんたちもスタッフも本当にみんな活き活きしているし、思わぬ人が予想もしていなかった意見を出してくれるのもいい。突拍子もない意見やアイディアもあって、まとめ役の亀ちゃんは大変だと思うが、それでもそれぞれの意見をうまく取り入れながら、起承転結のある素敵な物語に仕上げていってくれる。
「すまいる劇団」のシナリオ作りだけではない。たとえば、8月下旬に行った納涼祭に向けては、女学校時代にフォークダンスを踊ったというトウコさんの思い出話から、まっちゃんが、「今年の納涼祭では盆踊りじゃなくて、フォークダンスを踊ろう!」と提案してくれた。そして、何日もかけて利用者さんたちと椅子に座ってできるフォークダンスの踊りを考えたのだった。選んだ曲は「オクラホマミキサー」と「コロブチカ」。体を動かし、こうしたらいい、ああしたらいいと話し合いを重ねて、リズムよく足を動かし、隣同士で手を打ったり、手を結んだりする愉快な踊りが出来上がった。当日は、テンポの速い曲に合わせて何度も踊り、息が上がりながらも、「ああ、楽しかった!」「懐かしかった!」とみんなの顔は満足そうだった。
お芝居や踊りといった作品をみんなで話し合って作り上げていく。そんな様子を眺めながら、「ああ、この感じ、いいなぁ。心地いいなぁ。すまいるほーむにこんな時間が流れるのって幸せだなぁ」と私はいい気持ちになりながら、やわらかな時間の流れに身を委ねている。
前回に触れた運営推進会議のように、「すまいるほーむの活動についてどう思うか」とか、「これからのすまいるほーむはどうあったらいいか」などといった課題について、意見を言い合い、真面目に議論することも、みんなですまいるほーむを作り上げていくための大切なプロセスだと思っている。けれど、何かの課題や問題に正面から向き合うのはとりあえず置いておいて、何か楽しいものを作ろうという目標に向かってみんなで話し合ったり、試行錯誤したり、練習したり、準備したりすること。それも、すまいるほーむに参加する人たちにとっては欠かせない時間なのだと思う。
すまいるほーむという場で起きている出来事に心を痛めたりすることや、それぞれが現実の生活で抱える苦しさや辛さといったことから解放され、身も心も軽やかに、自由に羽ばたける時間。それはわずかな時間ではあるかもしれないが、そのわずかな至福の時間があるからこそ、現実でまた生きていける、ということもあるのではないだろうか。
※次回は10月2日(土)に掲載予定
























