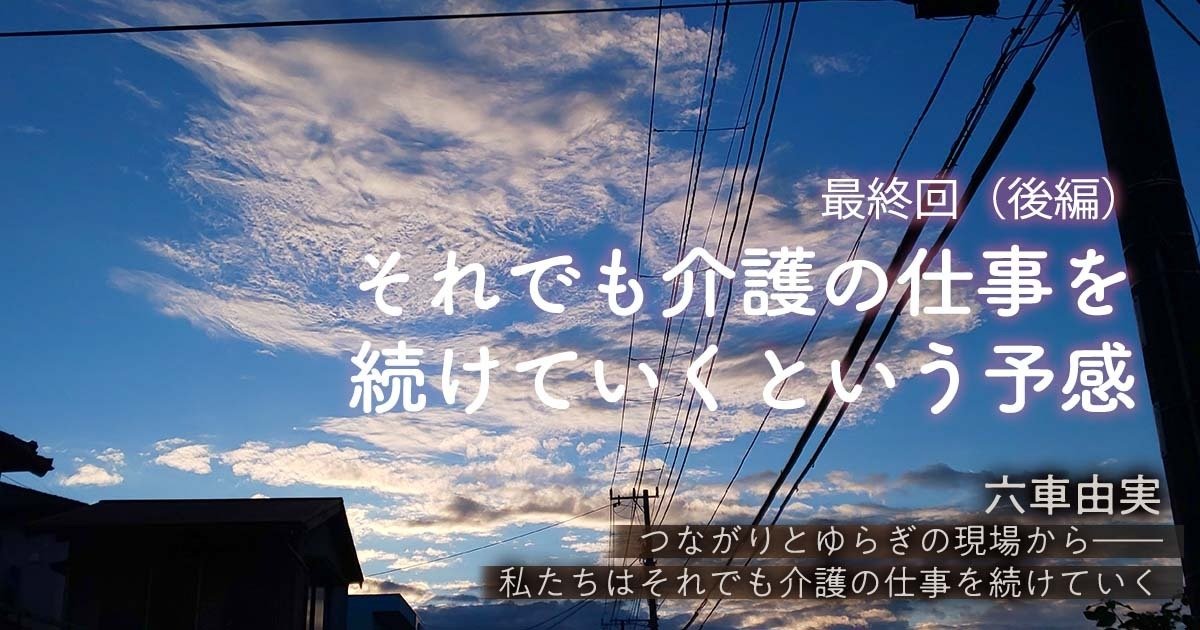
カドブン連載「つながりとゆらぎの現場から―私たちはそれでも介護の仕事を続けていく」 最終回 それでも介護の仕事を続けていくという予感(後編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
◆ ◆ ◆
決して否定されないという大前提
実際、私自身がそうなのだ。体の奥で今でも疼き続けている痛みを、みんなでこうして作品作りのために話し合ったり笑い合ったりしている時間は忘れて、ただただ幸せを感じている。疼き続けている痛みとは、あゆみさんのことである。再び飛び出していったあゆみさんの利用を中止にさせてもらったこと(第14回)。それが正しい決断だったのか。私たちにもっとできることはなかったのか。何をすれば、状況は変わったのか……。納得も理解も諦めもできないまま、ぐるぐると考えが迷走し続けているのである。私は疲れ切っていた。
そんな私も、「すまいる劇団」のシナリオの打ち合わせで、みんなでいろんな意見を出し合って、作り上げていく場にいることで、気持ちが緩やかにほどけていき、心から楽しいという気分を久々に味わうことができた。それが嬉しかったし、救われた気分だった。
でも、打ち合わせが終わり、おやつの準備をしながらまっちゃんがつぶやいた一言で、私は現実に引き戻された。
「あゆみさんが居たら、こんなふうに楽しく話し合いができなかったかもしれないね」
まっちゃんもまたあゆみさんのことをどう考えたらいいのか、悩み続けているのだろう。
「あゆみさんが居たら……」。幸せの中に浸っていた私は、そんなことは思いも浮かばなかった。けれど、まっちゃんの言葉で、ふと現実に戻って想像してみると、やはり私も、あゆみさんが居たらこんな楽しい雰囲気の話し合いはできなかっただろうし、ましてや、こんな愉快なストーリーは出来上がらなかったのではないか、と思った。
あゆみさんが認知症の進んだ方や高齢で介助なしでは歩行ができない方等の言動の一つ一つに敏感に反応し、拒絶的な言葉を発することに対して、他の利用者さんたちも随分と心を痛めていた。そして、なるべく彼女を刺激しないようにという気遣いをしていた。それは、運営推進会議でのみんなの意見で改めてわかったことだった。
あゆみさんが、実際にこの打ち合わせに参加していたら、どんなことを言ったのか、どんな反応をしたのかわからない。けれど、もし彼女がこの場にいたら、みんな委縮してしまって、あんなふうに自由に思ったことを言い合うことなどできなかったのではないか。
みんなが自由に意見が言えて、楽しく、心地よく、作品を作り上げていくためには、「何を言っても根本的なところでは否定されない」という大前提が保障され、参加者全員に共有されていなければならない、と私は思う。
すまいるほーむで積み上げてきた、みんなで話し合い、作り上げていくという時間は、まさにその大前提をみんなが共有していたからこそ成立していたのであり、自分が決して否定されないということにそれぞれが安心感や心地よさを感じてくれていたのだろう。
あゆみさんは、少なくとも今年になってからのあゆみさんは、そんなみんなの安心感と心地よさの大前提を崩してしまう存在になっていたことは確かなのである。
決定的に欠けていたのは対話、だけれど
では、あゆみさんは最初からそんな存在だったか、というと、そんなことはなかった。
私が強く印象に残っているのは、昨年の8月の納涼祭でのことである。納涼祭でのゲームを考える際に、あゆみさんは、他の人の意見を否定することもなかったし、自らも、こうしたらもっと面白くなるんじゃないか、と積極的に意見を言ってくれたりしていた。そしてみんなで遊んだのが、チラシを帯状に切ったものをテーブル中央に設置してあるアクリルボードの上に垂らして、アクリルボードのそれぞれ両側から団扇で扇いで、相手の方に落とす、というあゆみさんが考案したゲームだった。コロナの感染防止対策のためにやむなく設置し、テーブルの真向いに座った利用者さん同士のコミュニケーションにとって大きな壁であったアクリルボードという鬱陶しい異物を、逆手に取って遊びの道具に変えてしまう、ナイスアイディアだと私は感心したのだ。
そんなあゆみさんの様子が変化したのは、9月の下旬に起きた、すまいるほーむからの飛び出し以降だったように思う。飛び出すことになった直接のきっかけは、あゆみさんが汚してしまったトイレをスタッフが掃除しているところをあゆみさんが見たことだったが、その数日前の介護保険の認定調査の直後から、あゆみさんは心身ともに不安定になっていた。認定調査での様々な質問によって認知症の進行状況が評価され、本人も否応なしにその現実を突きつけられることになったのが相当に辛かったのかもしれないとも想像できる。
実際、何が変化のきっかけになったかはわからないが、その頃から、突然感情を爆発させて飛び出して行ってしまうことが繰り返されるようになり、そしてそれと呼応するかのように、他の利用者さんの人格を否定するような言葉を発するようになった。そして、今年になってから、その言葉を発する頻度も増し、内容もますます酷いものになっていったように思う。
経緯をそのように振り返ってみては思うのだ。早い段階で、あゆみさんが、他者の人格を否定するようなことをなぜ言ってしまうのか、あゆみさん自身と私が直接話ができていれば、違っていたのではないか、と。これまでも、そういう発言をする利用者さんはいなかったわけではない。でも、その度に、本人と話をすることで理解してくれ、そういう発言を控えたり、もしまた言ってしまった場合には相手に対して謝ったり、あるいは、相手を理解しようと努力したりしてくれていた。それで何とかなってきたのだった。
けれど、あゆみさんに対しては、私は、最初から最後までそれができなかった。理由を問われれば、いくつも挙げられる。あゆみさんがいつ逆上して飛び出してしまうかわからないという恐怖があったこと、私自身のトラウマに触れてしまったこと、コロナ禍で私自身が心のゆとりを失っていたこと……。
理由はともあれ、確かなことは、あゆみさんとの対話が決定的に欠けていた、ということである。7月の下旬にあゆみさんが5回目の飛び出しをした後、それからのことを考える際にも、スタッフや家族、ケアマネジャー、そして事後に他の利用者さんとは話し合いをしたが、あゆみさんの意見は一度も聞かないままに、利用中止を決めてしまった。
認知症当事者の団体である「日本認知症本人ワーキンググループ」が掲げている「本人抜きに本人のことは決めない」というスローガンや、精神科医療で近年展開されつつあるオープンダイアローグの大前提となっている「本人のいないところで本人の話はしない」ということに、私は心から賛同し、すまいるほーむでも意識して実践してきたつもりだったのに。そのことは大きな後悔として残る。
ではあの時、あゆみさんとどんなふうにすれば話し合いができたのか、あるいは、それほどまでにお互いに追い詰められる前に、彼女との対話を重ねていくには、どのような形がありえたのか。いくら考えても、今の私にはよい考えが浮かばない。
何かが見えてくるまで待ってみたい
私は疲れている。あゆみさんのことで思い悩んでいるからだけではない。収束の見えないコロナ禍の中で、私は再び押しつぶされそうになっている。
でも、それは1年前とはかなり違ってきている。1年前は、新型コロナウイルスという未知のウイルスに対して、その感染をどう防御していったらいいのかわからない不安と恐怖に慄いていた。このコロナ禍を1年半以上過ごしてきた今は、変異株の感染の広がりに対する不安はあるが、利用者さんもスタッフも希望者のワクチン接種は全て終わっているし、考えられる感染防止対策は続けている。そして、万が一、感染者が出たとしても、その対処方法は、様々な情報の蓄積によって学んでいるし、マニュアルを作りスタッフで共有することで備えている。
むしろ、私の心身を蝕んでいるのは、ウイルスへの恐怖ではなく、感染防止のために、買い物や通院以外の一切の外出を一年半以上も控えていることのストレスによるものだと思う。このことは、自宅が職場である、という私自身の抱える特殊事情によっても増幅されている。
コロナ禍以前は、何かストレスがあれば一人でお気に入りの喫茶店に出かけて、おいしいコーヒーとデザートを食べながら、一時間ばかり読書をして過ごしていた。用事のない日曜日や休みの日には、母と一緒によく食事に出かけたり、お芝居を観に行ったりしていた。年に1回程度は、マロンを連れて家族で泊りがけの旅行にも出ていた。地方に講演に呼んでいただいた時には、観光を楽しむ時間的な余裕はなかったが、帰りに駅弁を買って、車窓からの風景を楽しみながら駅弁を食べた。そんなたわいもない一つ一つのことが、どんなに自分の心を豊かにしたり、解放感をもたらしてくれていたのかと、改めて思う。
今は、朝にマロンの散歩をし、時間になったら1階の職場に下りて仕事をし、仕事が終わったら、マロンの散歩をして、2階で食事をして寝る。その繰り返しである。ストレスがたまっても、逃げ場がない。外出することができない、ということで、こんなにも自分の心が追い詰められてしまうとは思ってもみなかった。
それから、もう一つ、自分が外へ出られないというばかりでなく、利用者さんやスタッフ、家族、ケアマネジャーや利用希望の見学者以外は、すまいるほーむへの来訪者は断っているということも大きい。コロナ禍以前は、地域のボランティアの方や老人会の方たちが毎月の行事に参加してくれて、親交を深めていた。それに、取材やインタビュー、あるいは見学ということで、県内外からも毎月様々なお客さんがすまいるほーむを訪ねてきてくれた。そうした普段のメンバーとは異なる他者が時々すまいるほーむの活動に参加することによって、利用者さんと来訪者、スタッフと来訪者との間に化学反応が生まれ、予想もしない展開に発展したりすることもあった。また、利用者さんたちも、普段はスタッフには話さないようなことを、来訪者には話すといった新たな関係性も生まれたりしていた。私自身もそんな光景を見ながら、新しい発見をしたり、面白いアイディアが浮かんだり、前向きに考えられるようになることが度々あったのだった。
すまいるほーむも外部から閉ざされ、私自身の生活も家の中だけに閉じられている。このどうしようもない閉塞感の中にどっぷりと浸かっている現状はとても苦しい。この苦しみを抱えたままで、あゆみさんのことに向き合うことは私にはできそうにない。
私は、ここでいったん筆をおきたいと思う。連載として執筆することは、その時に起きている現実に向き合うための私の大切で欠かせない手段であったが、今は現実に向き合うことからいったん離れてみたい。そして、利用者さんとの日々のやり取りの流れに身を委ねることで、その中からまた何かが見えてくるのを待ってみたいと思う。
コロナ禍という、連載の構想の時点では予想もしなかった事態の中で、様々な出来事によって、人と人とがつながってはゆらぎ、ゆらいではつながっていく、そうして何とか生きている、介護という現場に集う人々の模様を描いてきた。私自身はゆらいでばかりであったが、必ず戻ってくるのは、「それでも介護の仕事を続けていく」という思いからである。それは、責任感や覚悟や決意とは違う、予感のようなものと言ったらいいだろうか。辛いことも苦しいことも山ほどある。けれど、私はやっぱりこの仕事が好きだし、この場で共に過ごすことで救われている。
だから、私はこれからも介護の仕事を続けていくだろう。そう予感している。
------------------------------------------------
ご愛読頂きどうもありがとうございました。本連載は小社より書籍化を予定しております。



























