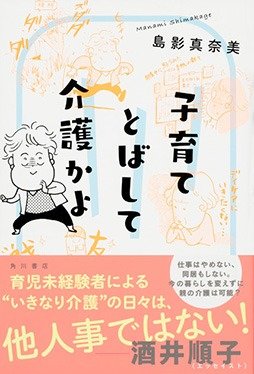「密閉空間」「手の届く範囲に多くの人がいる」「近距離での会話や発声」――クラスター発生の3条件に加え、重症化率の高い「高齢者」のいる介護施設。加速する新型コロナウィルス拡大の中、介護の現場ではどのような対応を取り、今後に備えているのか――。『神、人を喰う』でサントリー学芸賞、『驚きの介護民俗学』日本医学ジャーナリスト協会賞を受賞し、いまもデイサービスの管理者として介護の仕事を続ける、六車由実さんが緊急寄稿。全2回でお届けします。まさに今こそ、介護という仕事を考える時かもしれません。
変わらぬ日常
閉ざされた場となったすまいるほーむの中で、様々な不安を抱えながらも、私が救われるのは、利用者さんたちやスタッフたちの元気さと明るさである。
新型コロナウイルスへの感染を心配してデイサービスの利用を控える方も相当出てくるかもしれないとも想定していたが、糖尿病の疾患のある男性利用者さんが一人、予防のために一か月休んでいるだけで、他の方は通常通り利用してくれている。しかも、インフルエンザにも罹らず風邪もひかず、みんな元気である。たぶん、自宅でも手洗い、うがい、消毒等の感染予防をいつも以上に徹底してくれているのだろう。スタッフたちも今のところ発熱することはなく、休まず出勤してきてくれている。
3月上旬にゆうゆうクラブのみなさんにも参加してもらう予定だったひなまつり会は結局、利用者さんとスタッフだけで行ったが、地域の方たちと会えなくなった寂しさを吹き飛ばすかのように盛り上がり、デイルームの中は明るい笑いが溢れていた。
今年のひなまつりは、子供の頃に利用者さんたちが遊んでいたお手玉やあやとり等で遊ぶという企画。やり方、遊び方は、世代や地域によっても異なるので、互いに教え合いながら、みんなで再現して遊んでみよう、というものである。一番盛り上がったのは、あやとりだ。最初は、「どうやるんだっけ?」「子供の頃にやったきりだから覚えてないよ」と言いながらも、毛糸を手にしながら指を動かしていくと思い出す人も多く、特に、二人であやを取り合って形を作っていく二人あやとりは、「こことここを取るんだよ」とみんなでわいわいと言い合って、遊んだのであった。二人あやとりでできた「ぶんぶく茶釜」のあやを複数人でひっぱり合いながら唱う歌なんかも出てきて、盛り上がりは最高潮に。
「ぶんぶく茶釜が煮え立った。隣のばあさん屁をこいた。いくつこいた、10こいた。いち、に、さん、……」
10まで数えたところでみんなで手を放し、最後まで毛糸を持っていた人が負け。勝った人も負けた人も、キャーキャーと大騒ぎ。みんな童心に返ったようだった。
また、毎年、春と秋のお彼岸には恒例となっている塩おはぎも、今年もみんなで作って食べた。砂糖を使わない塩おはぎは、沼津や伊豆の一部の地域では昔よく食べられていたおはぎだったそうで、数年前に利用者さんの「塩おはぎが食いたい」という一言から始まった、もはやすまいるほーむの伝統行事である。この春のお彼岸には、90代の二人の利用者さんが中心となって、おいしい塩おはぎを作ってくれて、みんなでいただいた。
直接的な交流はできなくなったが、それでも地域とのつながりは今でも続いている。
たとえば、今までボランティアとして新聞を読みに来てくれていた鷲田さん。自宅の庭に咲いている花をデイルームに飾ってくださいと持ってきてくれて、利用者さんたちを気遣ってくれたり、逆に、利用者さんたちが、ボランティアさんやゆうゆうクラブの人たちが元気かどうか心配したりと、互いに互いを気遣い、気持ちのやりとりをしている。
それから、こんなこともあった。2月の中旬ぐらいから、マスク不足となることを予想して、裁縫が上手な利用者の好美さんに手伝ってもらって、ガーゼマスクを作り始め、利用者さんやご家族、スタッフたちにプレゼントをしていた。そんな時に、私が愛犬マロンの散歩をしていると、いつもマロンをかわいがってくれる近所の小学生の姉妹が寄ってきて、私がしていた手作りマスクを見上げ、「うちにはもうマスクないんだ」と不安そうにつぶやいたのだった。そこで、好美さんと協力し、すぐに子供用サイズのガーゼマスクを作り、彼女たちにプレゼントしてあげた。すると、翌日に、母親と共に姉妹がすまいるほーむにお礼の手紙を持って来てくれたのである。手紙には、「マスクを作ってくれてありがとうございます。すごく気に入りました。大切に使います」とかわいらしい字で丁寧に書かれていて、玄関先で手紙を受け取った好美さんは、「あれ、私が作ったんだっけ?」(認知症のため短期記憶が残らないので)と一瞬首をかしげたものの、「かわいいね。また作ってあげなくちゃね」と頬をゆるませていた。今までは、地域の子供たちとの交流はなかなかできていなかったが、これを機会に子供たちとのつながりもできていくかもしれない。
そして、好美さんに加え、新しい利用者である信子さんも手伝ってくれ、手作りマスク作りはまだまだ続いている。気持ちを少しでも明るく、穏やかにしてもらいたいと思い、明るい色合いやかわいらしい模様の布を使って作っているのだが、これが利用者さんたちに大人気で、「かわいいね」「私はこれがいい」と言って思い思いのマスクを持って帰り、使ってくれている。スタッフの子供たちや姪っ子、甥っ子たちにも、子供用マスクをプレゼントし、喜ばれている。それが、好美さんにも、信子さんにも励みになっているようだ。手芸だけは得意な私も、時間がある時にはマスク作りに励んでいる。材料探しやデザインの改良なども含め、私にとっては、マスク作りは暗くなりがちな気持ちをリラックスさせてくれるストレス解消法にもなっている。
みんなで過ごすことが力になる
コロナ以前も以後も、すまいるほーむの日常はこんなふうに変わってはいないように見える。というか、ますます元気に明るくなっているようにも見える。でも、もしかしたら、内心はそれぞれ不安でいっぱいなのかもしれない。自宅に朝お迎えに行くと、テレビを見ていた利用者さんたちから、「コロナで大騒ぎだな」「また、感染者が増えたってよ」と不安の声が聞こえてくる。私自身も、毎日、何度も新聞やネット、テレビで感染状況や国や自治体の対応を確認したり、厚労省からのコロナ関連のメールを読んだりしていて、不安がどんどん募っている。しかも、感染リスクを避けるために食料品や日用品の買い物や定期受診以外は外出を控え、職場でも家でもとにかく手洗い、消毒を繰り返し、家族が咳をしただけでも反応してしまうほど敏感になっていると、ストレスで圧し潰されそうになる。利用者さんたちだって、スタッフたちだって同じに違いない。
けれど、利用者さんたちが言うのだ。「ここに来ることだけを楽しみにしているの」と。一人暮らしの方もそうだが、家族と同居している方であっても、自宅や地域で孤立している方は少なくない。しかも、今は、利用者さんたちは、自宅ではほとんど自室に閉じこもって、息詰まるような日々をすごしている。そんな彼らにとって、すまいるほーむに来て、いつもの仲間といつもの日常を過ごし、お互いに愚痴を言い合い、励まし合い、笑い合うことは、たぶん唯一の希望であり、今の状況に負けずに生きていくための力になっているのではないかと思うのだ。
それはスタッフにとっても同じだろう。小学校の休校のために仕事を休んでいた谷さんが、子供をお姉さんに預けて、久々に出勤した時、スタッフも利用者さんもみんな彼女の元気な顔が見られたことを大喜びし、彼女自身も、「仕事に来られてよかった。楽しいです」ととても晴れ晴れとした表情をしていたのが印象的だった。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、クラスター発生のリスクが高い条件として、「密閉空間」「手の届く範囲に多くの人がいること」「近距離での会話や発声があること」を挙げていて、この3つの条件ができるだけ同時に重ならないように対策をとることが必要である、と訴えている。高齢者のデイサービスは、ほぼこの3条件に当てはまるだろう。すまいるほーむでは、できるだけ換気はしているが、14畳のデイルームで利用者さんが6~10人家庭用テーブルを囲んで座り過ごしている。利用者さん同士もよく話をするし、歌を歌うのも大好きだ。耳が遠い方には、スタッフは耳元で大きな声で話しかけてもいる。しかも集まっているのは、重症化リスクの高いとされる高齢者である。実際、名古屋市では複数のデイサービスでクラスターが発生し、3月6日には市長が市内2区の全デイサービスに休業要請を出した。全国のデイサービスの中には、感染リスクを考慮し、自主的に休業するところも出てきている。
デイサービスという場所が、今大きな危険をはらんでいるということは私たちも理解している。このまますまいるほーむを継続していってよいかどうか、今も悩んでいるし、常に不安でもある。それでも、私たちは、感染予防のためのできうる限りの努力をみんなで協力して続けながら、ここすまいるほーむという場を守りたい。なぜなら、介護の仕事とは、生命を守ることと共に、その人の「生きる」を支えることも大きな目的としていると考えるからだ。だから、私たちは、ここに集う人たちが生きる希望を持ち続けられることこそを一番大切にしたいのである。
今後起こりうる事態を想定して
ただ、新型コロナウイルスをめぐる事態は悪化の一途をたどっている。この原稿を書き終えようとする今日は3月26日。昨日の25日には、東京都知事が、「感染爆発の重大局面」だとして、都民に対して、不要不急の外出を自粛することを要請した。そして、今日、安倍首相は、新型コロナウイルス対策のための特別措置法に基づく「政府対策本部」の設置を決めた。これにより、「緊急事態宣言」を出すことが可能になった。あるいは、静岡県はまだ感染者が3名しかいないが、周辺の地域の感染の急激な拡大を考えれば、いつ県内でも感染者が爆発的に増加するかわからない。そうなった場合、デイサービスへの休業要請が出されることも予想される。
そのため、私たちは、それを想定して準備を始めている。名古屋市でデイサービスに対する休業要請が出された3月6日前後に厚労省から送られてきた通知によると、都道府県等から休業要請が出た場合、感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、デイサービスの事業所におけるサービス提供と、デイサービス職員による利用者宅への訪問によるサービス提供の両方を組み合わせて行うことができるとし、その場合の介護報酬の算定方法も指示されている。新型コロナウイルスの感染が広がり始めた当初は、デイサービスが休業となった場合は、その代替サービスとして訪問介護(ホームヘルパー)にサービスを切り替える、という案が浮かび上がっていたが、全国の訪問介護事業所から、人手不足で既にサービスの提供はいっぱいいっぱいで、デイサービス休業には対応できない、という批判の声が上がった。デイサービスの職員による利用者宅への訪問によるサービス提供は、その代わりの臨時的な取り扱いとして出されたと考えられる。また、一人暮らしや老々介護など、どうしてもデイサービスを利用せざるを得ない人たちが現実にはいるという状況を踏まえ、休業要請後もデイサービスは継続できる、とされたようだ。
3月18日付の朝日新聞デジタルの記事によると、休業要請が出された名古屋市では、確認できた113か所のうち休業したのは58か所、時間短縮や人数を限定する等で事業縮小して継続したのは53か所、従来通りに継続したのは2か所と、対応は事業所ごとに大きな開きが出たとのことである。デイサービスの職員が利用者宅を訪問し、入浴介助やリハビリをしたり、昼食用の弁当の配達サービスを行ったところもあったと記されている。いずれにしても、利用者にも家族にも、職員にも相当の混乱と困惑があったようで、事業所にとっては、休業や事業縮小等で報酬が減少することで経営面でも死活問題になっているということである。
この名古屋市の状況を見る限り、沼津市にデイサービスの休業要請が出された場合、すまいるほーむでも同じような混乱や経営面への影響は避けられないだろう。ただ、それでも、今は、すまいるほーむに集う利用者さんたちが、希望を持って生き続けられること、それを最も大切にして、今、できる限りの対応をしておかなければならない。
そこでまずは休業要請が出された場合のすまいるほーむの方針を法人内で話し合い、次の三つに決めた。
一つは、一人暮らしや日中独居であったり、認知症や他の疾患があって長期間一人で自宅で過ごすことが困難な方や自宅で入浴が難しい方等に限定し、利用人数を少なくしてデイサービスを継続すること。特に、認知症のある利用者さんの中には、毎週同じ曜日に来所して、同じ仲間と共に過ごすことによって、心穏やかな暮らしを続けられている方が何人かいる。もし、この生活パターンが急に変わってしまったら、心身ともに不安定になってしまうのではないかと心配なのである。
二つ目は、在宅で過ごすことになった利用者さんの希望に沿って、自宅を訪問し、入浴や食事、排泄の介助、体操等を行うこと。
三つ目は、デイサービスで提供している昼食をお弁当にして自宅に届けること、である。
この方針を、ケアマネジャーを通して、各利用者さんと家族に伝えていただき、休業要請が出た場合のそれぞれの希望をうかがっている。今のところ、デイサービスの継続的な利用を希望しているのは20人中7名で、各曜日、3~6人程度である。訪問によるサービス提供や弁当の配達については、現在は希望がある方はいないようだ。ただ、これらはあくまでも現在の希望であり、実際にその状況になったら、またそれぞれの希望も変わってくるかもしれない。
「つながり」を確信できるように
私たちが心配をしているのは、自宅で過ごす利用者さんたちのことである。というのも、休業要請時に自宅で過ごすことを希望しているのは、必ずしも利用者さん本人とは限らないからだ。中には本人が「自宅にいるからいいわ」と言ってくれた方もいるが、多くの場合、ご家族やケアマネジャーが、本人の健康状態を案じて、自宅で過ごすという判断を下している。ということは、もし休業要請が出されたら、利用者さん本人は何の心の準備もないままに、すまいるほーむの仲間たちとの関係を一時的とはいえ突然断たれてしまうことになる。しかも、その期間は2週間になるか、一か月になるか、あるいはそれ以上になるかもわからない。そうなった時の利用者さんのダメージは相当に大きいだろうことは容易に想像できる。
あるいは、どんなに感染予防に気を付けていても、すまいるほーむから感染者が出てしまうことだってありうる。そうなれば、事業の継続は難しく、一定期間の休業は余儀なくされるだろう。そうなった場合、今まで、すまいるほーむに来ることで希望を見出してきた利用者さんたちは、何を拠り所にこの危機的状況を乗り越えていくのだろう。そのこともあらかじめ考えておかなければならない。
今、私たちが準備していることのひとつは、自宅でできる体操のプログラムである。高齢である利用者さんが自宅に籠ることになって心配されることは、急速な身体機能の低下だからだ。感染を予防することができたとしても、身体機能が落ちてしまったら、今後の在宅生活の維持も難しくなってしまうかもしれない。そのために、機能訓練指導員とともに、自宅で一人でもできる体操やストレッチのプログラムを立てて、わかりやすく図式化して配布し、自然に覚えられるようにデイサービス利用時にも繰り返しみんなでやってみる、ということを考えている。
そして、もうひとつ重要だと思っているのは、デイサービスに休業要請が出た場合のことを、あるいは、すまいるほーむ自体が休業に追い込まれた場合のことを、利用者さんとスタッフと一緒に話し合っておくことである。すまいるほーむでは、行事の企画を立てる時や、何か問題が生じた時等、スタッフだけではなく、利用者さんにも参加してもらって、みんなで考えるすまいる会議を重ねてきた。どんなことでもみんなで共有して、みんなですまいるほーむという場所を作り上げてきた。それが、ここに集う仲間たちの互いのつながりを深めることにつながってきた、と言える。
だから、今回も、休業要請が出た場合のすまいるほーむの方針と、今現在把握できている利用者さんのご家族の希望とを、ざっくばらんに利用者さんに伝えたい。また、もし感染者が出た場合には休業せざるを得ないことも伝えたい。その上で、利用者さんたちがどうしたいのか、何を希望するのか、何が不安なのか、率直な意見を聞き、現実的に私たちができることは何かをみんなで考えたいと思っている。そのプロセスがあれば、たとえ、一時的にすまいるほーむに来られなくなったとしても、ここに集って共に過ごしてきた仲間たちとのつながりを感じ続けられるだろうし、いずれまた必ず再会できると確信できるのではないか、と思うのである。そのつながりへの確信と希望が、この危機を乗り切る力になってほしいと願っている。
この原稿がカドブンに掲載される頃には、新型コロナウイルスをめぐる事態は、また更に変化しているだろう。だから、これからも私たちの葛藤と格闘は続いていく。けれど忘れてはならないのは、この場に集う人たちにとって一番大切なことは何か、ということを、みんなで常に考え続けることではないかと思っている。
これまでにない程に、世界中が生命を脅かされる危機に直面する今、介護の現場はどうあるべきか、福祉ができることは何か、という問いが、それぞれの現場に投げかけられているのではないだろうか。