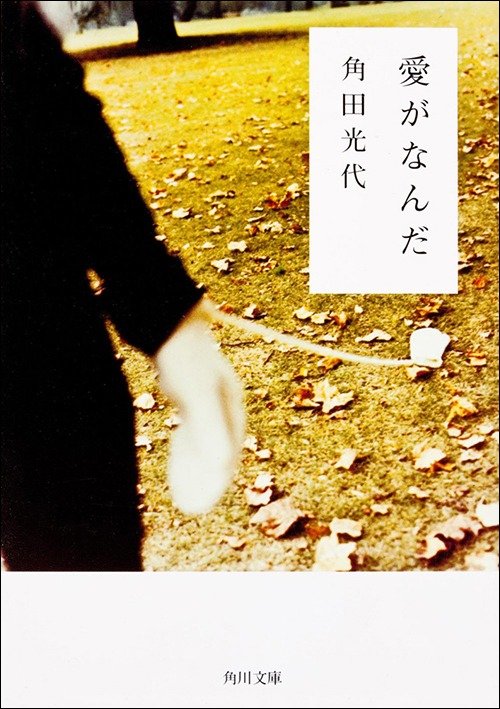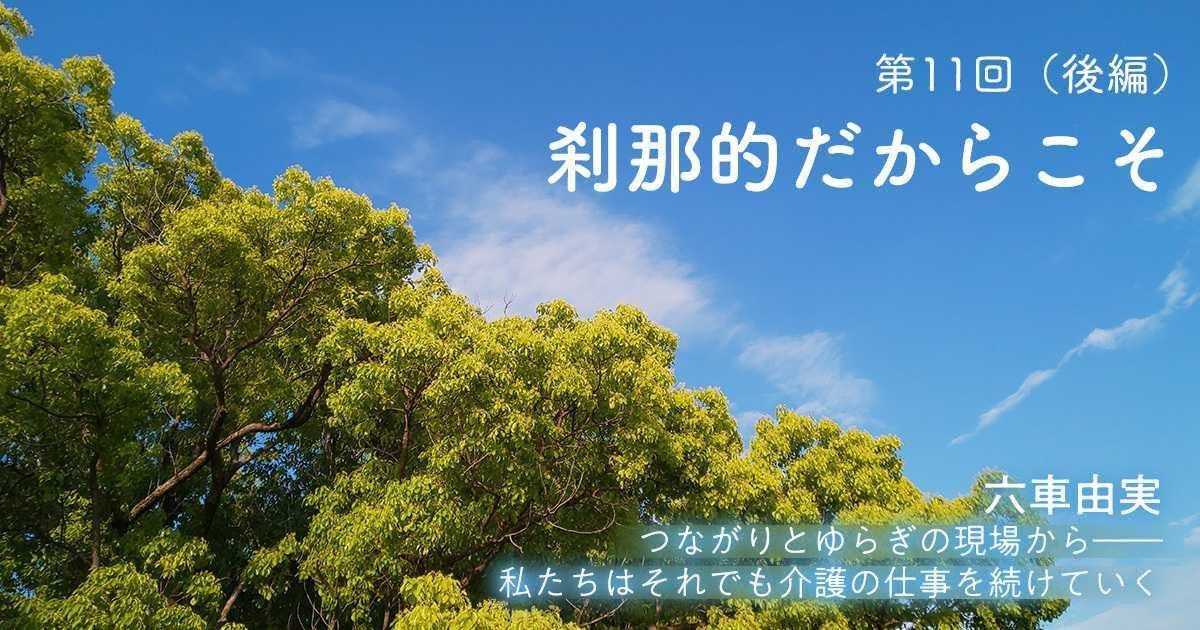
六車由実の、介護の未来11 刹那的だからこそ(後編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
>>前編はこちら
◆ ◆ ◆
人生最後の願い
では、ウーさんのしたいこととは何だろう。がんの告知をされていないウーさんに、それを直接尋ねることはできない。けれど、私は、昨年の秋にNHKで放映されていたドラマ「天使にリクエストを~人生最後の願い~」に触発されて、利用者さんたちやスタッフに、「人生の最後を迎える前にしたいことは何ですか?」という質問をして、それぞれが望むことを色画用紙に書いてもらっていたのだ。
そのドラマは、様々な事情を抱えた者たちが葛藤しながら結成した「サイレント・エンジェル」のチームが、病気の悪化によって人生の最後を迎えようとする人たちの秘めた思いや後悔の念に向き合い、その最後の願いを叶えようと奮闘するストーリーだった。そのドラマを観て、私は、私たちがすまいるほーむで共にしている利用者さんたちに対しても、あんなふうに最後の願いを叶えるお手伝いができたらいいな、と思った。そこで、みんなにドラマのことや質問の意図を説明して、人生最後の願いを書いてもらいたいとお願いしてみたのだった。
でも、実際は、利用者さんたちに人生の終わりについて考えてもらうのは、なかなか難しかった。自分の死や終い方に直接向き合うのは恐ろしいようだったし、年を重ね、若い時分よりは死を身近に感じているとはいえ、まだ切迫感のない今は、人生最後の願いと言われてもピンとこない、という感じでもあった。
それでも、みんなそれぞれ一生懸命考えて、願いを書いてくれた。
例えば、六さんは、「モーリシャスに住んで、昔の仲間と一緒に遊びたい、と書いてくれ」と言って、私が代筆した。六さんは若い頃、貿易船のコック長となって洋上へ出ており、中でもモーリシャスには一緒に仕事をした仲間がいて、思い出がたくさんあるのだという。
美砂保さんは、「はっきり記憶できる間に、生まれ育った故郷の親友○○さんに会いたい」と書いてくれた。美砂保さんが生まれ、幼少期を過ごしたのは中国地方の都市であり、その親友とは、もう何十年も会っていないのだそうだ。「はっきり記憶できる間に」というのは、自分の認知症の症状が進行していくことに対する不安もあるのかもしれない。
他にも、「実家に帰って、家族に会いたい」、「元気な内に、NHKののど自慢で歌いたい」、「東京に行ってお芝居を観たい」など。聞いてみると、人生最後とは言わずとも、それぞれしたい、やりたいと思っていることがあるんだということがよくわかって、いい機会となった。私たちでお手伝いして叶えられる願いであったら、叶えてあげたいとも思った。
では、ウーさんは、何と書いたのか。実は、ウーさんはなかなか書こうとしなかった。スタッフが、「誰か会いたい人とか、行きたいところとかないの? 食べたいものだっていいよ」と何度か聞いても、椅子の背もたれに寄りかかり、腕を組んだまま何も書こうとしなかったのだった。そして、最後に、こうつぶやいた。「仕事が好きで十分やってきたから、悔いはない」と。
そうか、なるほど。人生に悔いなし、と言えるなんてすごいことだ。でも一方で、少し寂しい気持ちもあった。というのも、実は、ウーさんは、家族間の複雑な事情によって、一緒に住んでいた妻のクミさんと2年前から別々に暮らすようなっていたからだ。だから、「死ぬ前にクミに会いたい」というようなことを書いてくれるのでは、という期待も私には少なからずあったのである。
変わらぬ日常を保ち続ける
ウーさんと一緒に住んでいる頃は、クミさんもすまいるほーむに通ってきていた。必ずしも仲睦まじい夫婦といった感じではなかったが、喧嘩したり、文句を言い合いながらも、互いが互いを気遣っているのがよくわかったし、薬の飲み忘れとか、ガスの消し忘れとか、ごみ捨てとか、それぞれの足りないところを自然に補って、何とか生活を成り立たせていた。ところが、クミさんは自宅で転倒したことをきっかけに、隣の市に住む娘さんに引き取られ、二人は別々に暮らすようになった。それ以来、ウーさんはクミさんに一度も会っていないのである。
私たちスタッフの目には、クミさんと別れて一人暮らしになってから、ウーさんの身体機能も意欲もだんだんと低下していったように見えていた。以前は、お花見だけではなく、すまいるほーむの活動にも意欲的に参加してくれることが多かったし、大好きなカラオケで「岸壁の母」など、セリフ付きの演歌をよくみんなの前で披露してくれたりもした。当時、隣に座ることが多かった高木さん(第2回に登場)が国政や市政への批判を演説し始めると、それに対して、「そうだそうだ。俺もそう思う」と相槌を入れたりすることもよくあったし、選挙があれば、期日前投票に行きたいと言うので、他の利用者さんと一緒に何度かその会場に連れて行ったこともある。
そんなウーさんは、一人暮らしになった頃から、自分からは自分の意見とか、望むことなどを言葉にすることはほとんどなくなっていった。すまいるほーむの活動にも参加はするが、楽しんでいる様子は見られなかった。政治談議をすることもなくなった。人生を諦めている、そんなふうにも見えた。それはもしかしたら、クミさんと別れて暮らすようになったことがきっかけであったのかもしれない。あるいは、もっと根っこにあるもの、長い家族の歴史の中でもつれ続けて、もはやほどくことなどできなくなってしまった家族間の糸が、最終的には断ち切られるような状態になってしまったことに原因があるのかもしれない。
でも、ウーさんは、クミさんに会いたいとか、家族への恨みつらみとか、後悔とか、そんなことは一切、本当に一切口にしたことはなかった。だから、そんなふうに想像するのは私の単なる思い込みなのかもしれないとも思う。
それに、たとえウーさんが、クミさんとの再会や、家族との和解を望む言葉を口にしたとしても、いったん断ち切れてしまった家族の糸を、私たちがそう簡単に繋ぎ合わせることができるわけではないこともわかっていた。ドラマのようにはいかないのだ。
結局、ウーさんが最後に何をしたいのか、何を望んでいるのかはわからなかった。それでも時間は過ぎていく。私たちは、ウーさんの病状の変化に注意しながらも、今まで通りの支援とかかわりを続けていく、それしかなかった。
朝、お迎えに行き、声をかけ、顔色を確認し、体温を測る。失禁していればトイレに連れていき、着替えを手伝う。汚れ物をまとめて持ち帰り、洗濯する。すまいるほーむに着いてからは、汚れた体をお風呂で丁寧に洗い、湯舟にゆったりと浸かってもらう。昼食には、できるだけウーさんが好きな麺類とか魚などを出して、おいしく食べてもらう。横になりたければ、ベッドを準備し、体が休まるまで寝てもらう。帰りの歌の時間には、ウーさんが好んで歌っていたセリフ付きの演歌をカラオケで流し、みんなで歌う。夕方には自宅に送り届け、夕飯のお弁当を温めて、すぐに食べられるようにテーブルの上に置いてくる。そして、また次の利用日にお迎えに来ることを伝えて、帰ってくる。
今までと変わらない日常を保ち続ける。私たちにできることはそれだけだった。その日常の中で、ウーさんが少しでも心地よいと思える瞬間があえばいい、みんなそんな思いでいた。
日常は永遠には続かない
いつ急変するかわからないという緊張感を持ちながらも、ウーさんへと今までと変わらぬ支援を続けていた4月下旬のある日の夜、思わぬ来客があった。タケコさんの娘さん夫婦が訪ねてきたのだ。その日はスタッフ会議でスタッフの多くが集まっていたので、タケコさんについての何かよい報告に来てくれたのではないかと、スタッフみんなで玄関まで出てきて、娘さん夫婦を迎えた。ところが、娘さんが語ったのは、全く想像もしていなかった、タケコさんが亡くなったということだった。誤嚥性肺炎による突然の死だったという。
タケコさんは、昨年10月下旬に自宅前で転倒し、大腿骨頚部を骨折し、緊急入院をして手術を受けた(第6回)。急性期を過ぎた後はリハビリ病院に転院し、3か月近くリハビリを行った後、娘さん夫婦の住んでいる地域の近くにある施設に入所していた。リハビリ病院から施設へ移る2月の上旬には、娘さん夫婦はタケコさんを連れて、わざわざすまいるほーむに挨拶に来てくれたのだった。タケコさんは車いすに乗っていたが、思ったより元気そうだった。利用者さんたちやスタッフが、「タケコさん、がんばってね」「また必ず会おうね」と励ますと、タケコさんは涙を流し、「ありがとう」と何度も繰り返していた。娘さんも、「また元気になって、歩けるようになったら、自宅に戻して、すまいるほーむに通わせたいと思っているんです。母も、それを望んでいるので」と言ってくれた。
タケコさんの元気な姿を見られたことで私たちは安心していた。だから、利用者さんたちと話をしていてタケコさんのことが話題にのぼると、誰ともなく、「タケコさん、元気にしているよ」「リハビリがんばっているよ」「きっとすまいるほーむに戻ってくるよ」と言って、また会える日が来るのを楽しみにしていたのだった。
それなのに、タケコさんが亡くなったなんて。私はとても信じられなかった。現実のこととは思えずに、目の前で涙を流して語る娘さんの声が何だか遠くに聞こえるように感じられた。娘さん夫婦が帰り、会議を再開し、タケコさんのお別れ会をしようと日程について決めている時も、どこか他人事のような感じで、私は淡々としていた。
でも、夜、ベッドに横になると、タケコさんの死の事実が私に重くのしかかってきた。私の心身に覆いかぶさってきたものは、哀しいという気持ち以上に、虚無感だった。タケコさんの死と、末期がんであるウーさんのこととが重なり合って、私の心は痛かった。「この仕事はなんて刹那的なんだ」と、虚しさだけが心に突き刺さった。
適切かどうかはわからないが、今も「刹那的」という言葉しか思い浮かばない。私たちが関われるのは、その人が生きてきた長い人生のわずかな時間にすぎない。しかも、死に近づいている人生の終盤の、ほんの一瞬なのである。
もちろん、そんなことはわかっていた。介護の現場にいる私たちは、利用者さんたちが死に向かって下っていくプロセスの伴走者であると、これまでも書いてきた。けれど、利用者さんたちと、楽しくて、穏やかな日常をすごしていると、錯覚してしまうのである。永遠にこの日常が続いていく、というように。そして、利用者さんの入院や死によって、ある時突然突きつけられる。永遠に続く日常などない、と。
利用者さんの言葉を聞き続けたい
ウーさんは、4月末に自宅でとうとう歩けなくなり、入院した。担当医師によると、自宅に戻って一人暮らしができるような状態ではないという。もうウーさんはすまいるほーむに戻ってくることはできない。ウーさんとの別れも、こうして突然やってきた。
やっぱり、介護の仕事は刹那的だ。でも、刹那的だからこそ、一人一人と向き合って、このわずかな時間を大切に共にすごしていきたい、と今は思う。利用者さんが何を望んでいるのか、何を思って過ごしているのかは、本当のところ私たちにはわからない。それは、言葉数の少なかったウーさんだけでなく、全ての利用者さんたちに対しても言えることだと思う。
わかるはずがないのだ。だって、私たちは、その人の人生の終盤のほんのわずかな一瞬を、偶然共にすることになっただけなのだから。では、その短い時間の中で、私たちができることとは何か。たぶん、それはスタッフそれぞれで違うだろう。お風呂で体の隅々まできれいにして気持ちよくなってもらうことも、刹那的な時間を共にする一つだし、編み物が得意な利用者さんに編み方を教えてもらうのもその一つだと思う。お花見をして、さわやかな春の陽射しを一緒に浴びたり、はしゃいだりすることだって、最後へと向かう時間においては大切な瞬間となるだろう。
では、私はどうか。私にできることは、やはり、利用者さんの語る言葉を聞き続けることだと思う。脈絡なく突然発せられる言葉を聞き、私がそれに反応する。そして、また利用者さんが語りだす。その人が本当は何を考えているのか、思っているのはわからないけれど、この言葉のやりとりをしている対話の時間だけは、何かを共にできているという確信が持てるからだ。
入院の前日、歩けなくなったウーさんはすまいるほーむを休んだので、私は夕方、スーパーでマグロのたたきの巻き寿司と稲荷寿司のセットを買って、ウーさんの自宅を訪ねた。ウーさんがベッドに座るのを手伝って、その前にテーブルを置き、お寿司とお茶を用意した。ウーさんは、「食欲がない」と言いながらも、おいしそうにお寿司を食べ始めた。私はほっとして、何となくウーさんにまた隅田公園のお花見の話を聞いてみたくなった。すると、ウーさんは、こんなことを語ってくれた。
「親父は頭のいい兄貴じゃなくて、出来の悪い俺のことばかりいつも連れて出たんだよ。出店の前で、『あれ買ってくれ』って寝転んで騒いだりしてさ。全く俺もどうしようもなかった。でも、親父はなぜだか、俺ばかりをどこへでも一緒にさ、連れまわしたんだよな。花見だけじゃなくて、祭りとかさ、銭湯とかさ」
「お父さんは、ウーさんを可愛がっていたんだね」
「結局、そういうことだね」
「ウーさんもお父さんのこと好きだった?」
「好きだったね」
それが、ウーさんとの最後の対話になった。
入院を翌日に控えた人と話す内容が、こんなことでよかったのかどうかわからない。でも、お寿司を頬張りながら、父親との思い出を語るウーさんの表情は、いつになく緩んでいるように見えた。私も、ウーさんの思いに少しだけ触れられたような気がした。
病院で過ごす孤独な時間の中でも、子供の頃の父親との思い出にうっすらとでも包まれてくれたらいいと願う。
※次回は6月19日(土)に掲載予定