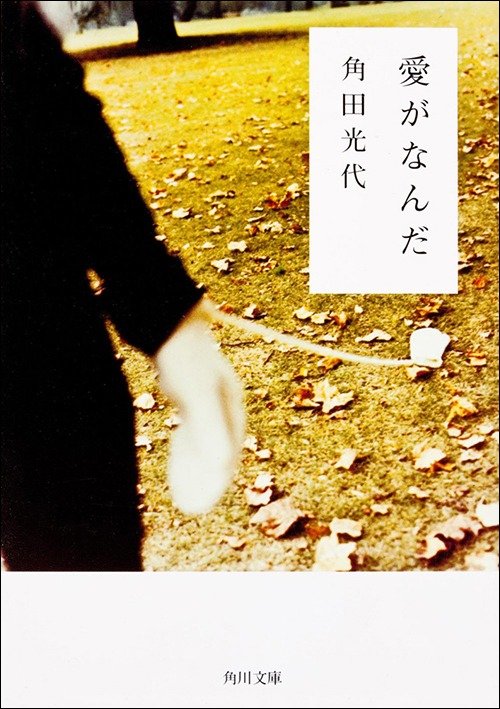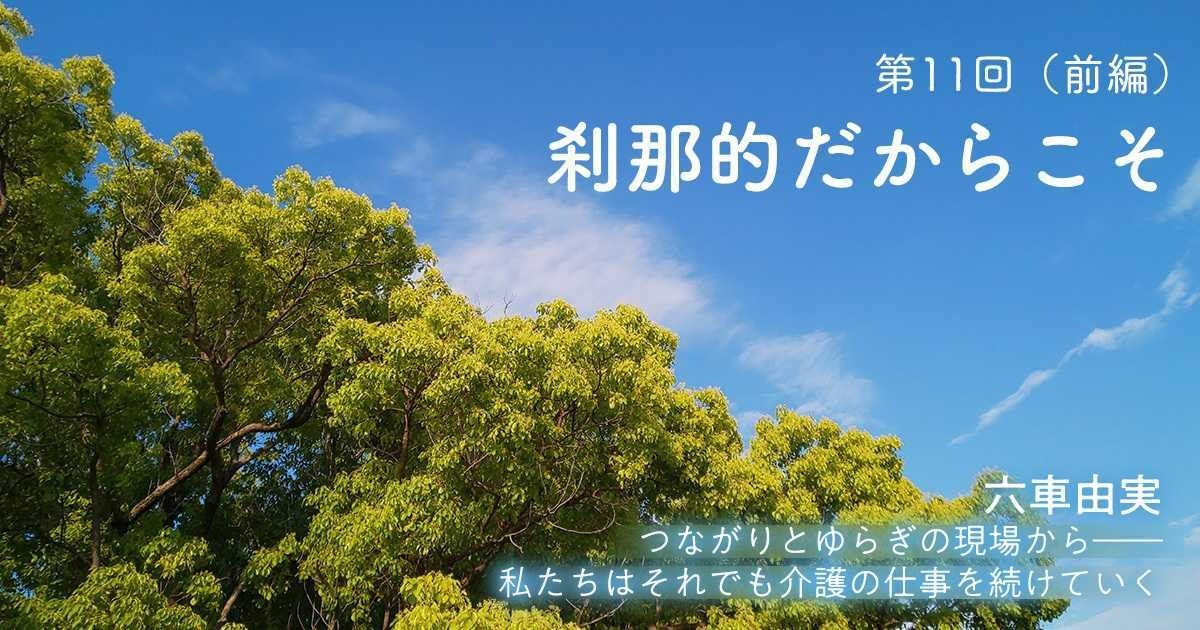
六車由実の、介護の未来11 刹那的だからこそ(前編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
◆ ◆ ◆
お花見の昂揚
すまいるほーむの裏を流れる沼川の土手に整備された遊歩道は、南側に河津桜、北側にソメイヨシノが植えられた桜並木になっている。だから、2月下旬から3月上旬には寒桜の河津桜が咲き、そして4月上旬から中旬になると今度はソメイヨシノが満開になる。遠くまで足を延ばさずとも、歩いて行けるごく身近に年に二度もお花見ができる場所があるというのは、本当に恵まれた環境である。しかも、観光地化されておらず、地元の人たちが散歩がてらお花見をする程度。今年も安心してゆったりと、利用者さんたちと二度のお花見を楽しむことができた。
一年以上続くコロナ禍の中で、すまいるほーむでも、昨年11月の紅葉狩り以外は、感染対策のために買い物等の外出は控えてきたし、それまで家族と一緒に外食や買い物、日帰り温泉旅行、美術館巡りなどを楽しんでいた利用者さんたちも、この一年はどこにも出かけていない方がほとんどである。だから、満開の桜並木の下を二度も散策できたことによって、利用者さんたちの心は、随分と明るく開放的になったようだ。
女性の利用者さんたちはみな少女のようだった。桜の花びらがさわやかな風に吹かれて舞い散るごとに、キャッキャと楽しそうに騒いだり、川面を流れていく無数の花筏を眺めてはうっとりとしていた。室内の活動では見られない表情がそこにはあった。
普段から青空に浮かぶ雲を眺めては、その雲の形から様々な物語を空想するのが好きな美砂保さんは、最近、お花見のことを思い出して、こんなことを笑いながら話してくれたのも、私には何だかとても嬉しかった。
「4月にお花見に行きましたよね。桜の花びらが吹雪みたいに何度もパーッと散ったじゃないですか。それを見上げていたら、マロンちゃんがね、楽しそうに(空中を)歩いているのが見えたんです。不思議だなぁ。カイさん(スタッフ)がそんな大がかりな仕掛けをして見せてくれたのかな、すごいなぁと思っていたんですけど、カイさん、そんなことしてないよって。私、おかしいのかな、って思ったけど、でもいいんです。私には、マロンちゃんが見えたんですから。可愛かったよ、マロンちゃん」
花吹雪の中に楽しそうにお散歩しているマロンが見えたなんて、なんて素敵な幻だろう。マロンの怪我の回復を誰よりも喜び、可愛がってくれている美砂保さんだからこそ見えた幻だったのだろう。そして、それが幻だったということを、美砂保さんは「いいんです」と前向きに受けとめて、私に話してくれた。家族との関係等でいろいろと悩んで眠れなくなったりすることもある美砂保さんが、そんなふうにありのままの自分を受け入れられたのも、澄んだ青空の下でのお花見のおかげなのかもしれない。
「花見に行きたい」
お花見を楽しみにしているのは、女性の利用者さんばかりではない。一人で散歩に出かけるのが日課で、時には自宅近くのコンビニまで行って買い物ついでにイートインでビールを一杯ひっかけて帰ってくることもあったウーさんは、すまいるほーむを利用し始めてからしばらくは、毎年お花見に行くのを心待ちにしていた。利用日ではない日にお花見が予定されていると、わざわざお花見の日に利用日の変更をしてまでも、お花見に参加するのを望んだほどだ。
だが、そんなウーさんは、ここ数年は、お花見に誘ってもあまり乗り気ではなくなった。杖をつきながらの歩行も、以前よりおぼつかなくなってきていることもあってか、車いすの利用者さんたちと一緒に、遊歩道のすぐ近くまで車で送っていくことを伝えても、「かったるいからいいよ」と言って行かないこともあった。
今年の2月下旬も、河津桜を見に行こうと誘うとその時は「うん」と返事をしたのだったが、いざ出かけようと食後の昼寝をしていたウーさんに声をかけると、「やっぱりいいよ、俺はここで寝てるから」と言って起きてこなかった。そのため、4月のお花見も行かないだろうと私たちスタッフは予想し、ウーさんの利用日ではない日にお花見を予定して、特にウーさんには声をかけなかったのだった。
ところが、4月の初めのこと。朝の送迎の途中、例年より早く開花し、満開となった桜並木の近くにさしかかったあたりで、ウーさんが後部座席から何か小さな声で言った。「何て言ったの?」と私が聞き返すと、「花見、行く?」と今度ははっきりと聞き取れる声で言ったのだった。予想もしていなかった言葉だった。「お花見、明日行く予定になってるよ。ウーさんも行きたかった?」と尋ねると、しばらく間があいた後で、「そうだなぁ、行けたら行きたいな」とつぶやくように言った。
お花見、行きたいんだ。意外な言葉に驚きながらも、それだったら、ウーさんをお花見に連れて行ってあげたいと私は思った。自分の希望を言葉にしたり、明確な意思表示をしたりすることが最近はほとんどなくなっていたウーさんが、はっきりと「行きたい」と言ったことも気になっていた。
朝のミーティングの時に、スタッフたちにそのことを伝えてみんなで相談し、午後、希望者を募ってお花見に出かけることになった。
午前中、入浴の順番を待っているあいだ、ウーさんはいつになく多弁だった。
「ウーさんは、よくお花見に行ったの?」
「行ったよ」
「どこに見に行ったの?」
「隅田公園だな」
「隅田公園って、東京の?」
「そう」
「子供の頃、疎開する前は隅田川の近くに住んでたんだもんね」
「親父が毎年連れてってくれたんだよ。人が多くてさ、迷子になりそうになったりしてさ。おふくろは、迷うから嫌だっていって留守番してた。だからいつも親父と二人で見に行ったよ。川沿いに桜がずっと咲いててさ、きれいだったな。あそこの桜が一番だな」
「沼津に来てさ、大人になってからはお花見には行かなかったの?」
「行かなかったよ。仕事が忙しかったから」
「家族とも?」
「行かなかったね」
昔から、何軒も飲み屋をはしごして最後には道端や公園のベンチに寝転んでしまい、よく警察の厄介になっていたというほど呑兵衛だったウーさんのことだから、大人になってからも飲み仲間と花見酒で盛り上がっていたのではないかと勝手に想像していた。でも、今ウーさんが大切にしている桜の思い出とは、子供の頃、父親に毎年連れて行ってもらった隅田公園のお花見だったことを、私は初めて知ったのだった。
ただ満開の桜を見上げていた
その日は利用者さんは男性三人だけだった。一人は翌日のお花見に参加予定なので、ウーさんとサブさんとの二人をお花見に連れて行くことになった。サブさんは外出が好きで、「今日お花見に行こうと思うんだけど……」と誘うと、「本当? 嬉しいなあ」と大喜びだった。朝からウキウキとしていて、午後からのお花見を楽しみにしていた。
午後2時になり、昼寝をしていたウーさんに「そろそろお花見に行こうか」と声をかけると、河津桜の時とは違ってすぐに目を覚まし、ベッドから起きて準備を始めてくれた。
二人とも歩行が不安定で、裏の沼川の遊歩道まで歩くのは難しいので、送迎車で移動。そして、折り畳み式のアウトドアチェアを桜並木がよく見える場所に二つ並べて置いて座ってもらった。サブさんは、「きれいだなぁ。幸せだなぁ」とニコニコ顔になり、「あっちの桜の木の方が枝が垂れているから、あそこで写真撮ってよ」と、立ち上がってそこまで杖を頼りに歩き、枝垂れ桜のように垂れた満開の桜の枝に顔を寄せ、ポーズをとったりしてはしゃいでいた。
ウーさんは、そんなサブさんの様子は全く目に入らないかのように、アウトドアチェアに深く腰をうずめたまま、ただじっと桜の木を見上げていた。午前中に隅田公園の思い出を語ってくれた多弁で楽し気なウーさんとは別人のようだった。「ウーさんも少し歩いてみる?」と誘ってみたものの、「いや、俺はいい」と言ったきり、陽射しが眩しかったのか目をつむってしまった。ただ、青空の下、暖かな陽射しを浴びて気持ちよさそうには見えた。
20分程お花見をしてすまいるほーむに戻ってきた後も、二人の様子は対照的だった。
「おかえり! 桜、どうだった?」と玄関で元気に出迎えてくれたまっちゃんに対して、サブさんは、「いやー、きれいだった、満開だったよ。ホント、行ってよかった」と興奮していたが、ウーさんは無言のまま、靴を脱ぐのにてこずっていた。「ウーさんも、楽しかった?」とまっちゃんが靴を脱ぐのを手伝いながら、顔を見上げて再び尋ねると、ウーさんは、声は出さずに、ただ「うん」とだけ頷いた。楽しかったのか、行ってよかったと思っているのか、それとも何か別な思いがあったのか、私たちにはウーさんの気持ちがよくわからなかったが、それ以上尋ねることはしなかった。
それから半月ほど経ったある日、受診したかかりつけの病院での検査で、ウーさんは、大腸がんであることがわかった。既に肺にまで転移が見られるステージ4。いつ容態が急変してもおかしくない状況であると診断されたというのだ。付き添いをしていた息子さんから連絡が入ったと、ウーさんのケアマネジャーである三国社長から電話があった。本人には告知していないという。
その電話を受けて、私はショックのあまり、「えっウソ!」と大きな声で叫んでいた。ウーさんが大腸がんだなんて、しかも末期だなんて……。涙が溢れてきた。
電話を切った後、気持ちを落ち着かせようとしばらく事務室に留まり、何度も深呼吸をした。その時、お花見の光景が私の頭を過ぎった。もしかしたら、ウーさんは、がんであることはわからないにしても、自分の体調が思わしくないこと、もしかしたら来年の桜は見られないかもしれないことを、何となく感じ取っていたのではないか。だから、おぼつかない足取りでも、体がだるくても、「お花見に行きたい」という自分の希望を明確に私たちに伝えてくれたのではないか。そう思うと余計に辛くなった。
ウーさんは、いったい何を考え、どんな思いで、満開の桜を見上げていたのだろう。
私たちの共通した思い
確かに、ここ半年程、ウーさんは足のむくみが酷く、歩行が不安定になっていたし、いつも体がだるそうで、すまいるほーむに来てもベッドに横になり、寝ていることが多くなっていた。また、一人暮らしのアパートで、夜間トイレに行くことができず失禁をしてしまったりすることもたびたびあったし、すまいるほーむの利用日やお迎えの時間を間違えたり、薬を飲み忘れてしまうといった認知機能の低下も見られるようになっていた。
そんな状態の中、昨年11月の定期受診の際には、極度の貧血状態であることがわかり、そのまま2週間入院し、輸血による治療を受けたのだった。家族が原因究明のための精密検査や積極的治療を望まなかったため、貧血の根本原因はわからなかったが、主治医は、骨髄の造血機能に問題があるのではないか、とその可能性を指摘していた。
退院後は、輸血と造血剤の服用で貧血状態は改善に向かっていた。食欲は旺盛だったし、相変わらず歩行は不安定だったが、何とか杖を使って歩いていた。失禁も続いていたが、お迎えに行くたびに、スタッフがトイレで紙パンツや衣類の交換を手伝って、汚れたシーツやタオル、衣類はすまいるほーむで洗ってから、帰りの送迎の時に一緒に自宅へ持っていくようにしていた。また、同じ法人内の訪問介護事業所のヘルパーのなっちゃんが自宅に入って身体介護や家事援助をする回数を増やして、支援を手厚くしていた。それにより、自宅での生活環境も何とか整えられていたから、まだまだこれから先も、ウーさんは在宅生活を続けていけると私たちは楽観視していた。
そもそも、トイレ介助時に排泄物に血が混じっていることは一度も確認したことはなかったし、痛みを訴えることもなかったから、大腸がんが進行していたとは私たちは考えてもみなかったのだ。だから、既にステージ4で、いつ急変してもおかしくない程の状態にあることを私が伝えると、スタッフたちはみな同様に言葉を失っていた。
ウーさんはあとどのくらい在宅生活を続けられるのだろうか。すまいるほーむにはいつまで来ることができるのだろうか。私たちスタッフの心は不安でいっぱいだった。
私たちは、これまでも、末期がんであることがわかった利用者さんたちとかかわった経験があった。しばらくは食欲があり、歩くこともできて、元気そうに見えていた利用者さんが、ある時急激に体調を悪化させ、自宅での一人暮らしが難しくなり、専門病院に入院して、それからまもなくして最期の時を迎えるのを目の当たりにしてきた。だから、今は食欲もあって、自力で何とか歩行もできるウーさんも、近い将来、全く歩けなくなったり、食べられなくなったりして、在宅生活が難しくなるということはよくわかっていた。
もしかしたら、すまいるほーむに来ている時に、急に大出血を起こすかもしれない。あるいは、朝、お迎えに行った時に亡くなっているかもしれない。それを想像すると怖かった。でも、今までの利用者さんの場合にも、主治医や訪問看護師などの医療職と連携して、乗り切ってきた。今回も医療機関と連携し、体調急変の時の対応を予め想定しておけば、まだ、ウーさんが在宅生活を続けるための支援を私たちもすることができる。いつか限界が来るかもしれないけれど、その日まで、できるだけウーさんのしたいことをさせてあげたい。それが、ケアマネジャーの三国社長、ヘルパーのなっちゃん、そして、私たちすまいるほーむのスタッフの共通した思いだった。
※次回は6月5日(土)に掲載予定