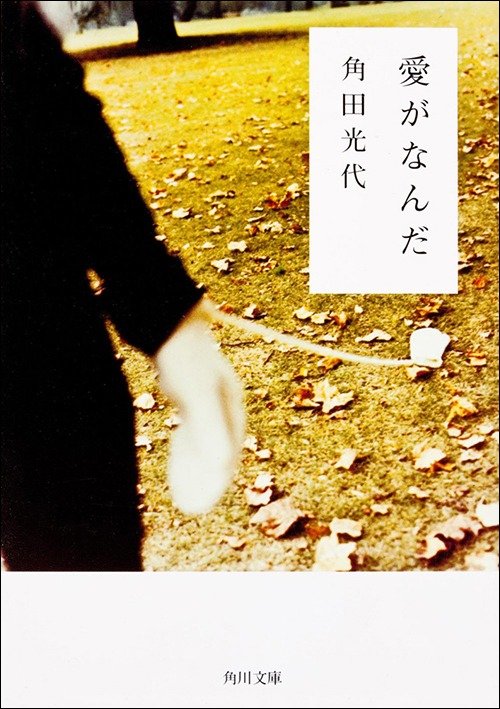六車由実の、介護の未来10 入浴は「気持ちがいい」だけじゃだめなのか?(後編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
>>前編はこちら
◆ ◆ ◆
自宅での入浴にはいくつもの困難が伴う
自宅での入浴が困難である理由は、きーやさんのように転倒への不安ばかりではない。認知症の利用者さんの場合には、また別の要因が困難さの一因になっている。
アルツハイマー型認知症の診断を受けていて、一人暮らしのみよさんは、すまいるほーむの利用を始める少し前から、自宅でお風呂に入らなくなっている。お風呂が嫌いというわけではない。保険の外交や観光ホテルの洗い場で仕事をしていたみよさんは、休みの度に、仕事仲間と伊豆や箱根等の温泉旅館に泊まりに行くほど、お風呂が好きだった。ところが、認知症の症状が進行し始めてからは、時々様子を見に来る娘さんが尋ねると、「お風呂に入っている」と本人は言うものの、入浴した形跡は浴室には全くなく、だんだん顔や体も汚れていくのがわかったという。短期記憶に障害のあるみよさんは、お風呂に入ったかどうかとか、お風呂の準備をしたかどうかということを記憶しておけず、入浴する方向へと行動を結び付けていくことは難しくなっていたのではないかと思う。
そんな事情もあり、みよさんは、すまいるほーむの利用開始とともに、入浴介助も受けるようになった。もともとお風呂好きであるし、近年まで続けていた観光ホテルでの仕事の時には仕事が終わるとホテルの大浴場に入っていたということもあって、みよさんは全く抵抗なく、すまいるほーむのお風呂にも入ることができ、そして入るたびにこう言ってくれる。
「昼間っからお風呂に入れてもらってさ、幸せだよ、本当に。頭を洗ってくれるのも気持ちがいいしさ。あんたっちはみんないい人だし、上手だし。私は本当に幸せだよ」
同じアルツハイマー型認知症の方でも、あゆみさんの場合はまた少し事情が異なる。あゆみさんは、自宅でも入浴しているのだが、一度入ると何時間も出てこないため、お風呂から上がった時にはのぼせてしまって寝込んでしまうという。あゆみさんによれば、湯舟に浸かっているうちに、浴室の壁とか天井の汚れやカビが気になってしまい、お風呂の大掃除をそのまま始めてしまって、疲れ切ってしまうのだそうだ。また、家族によると、入浴しても、髪の毛を洗わないことがほとんどだという。入浴しているうちに、髪の毛を洗うのを忘れてしまうのかもしれない。
そのため、あゆみさんも利用開始時から入浴介助を受けているが、彼女の場合は、毎回入浴できているわけではない。入ってしまえば心身ともにリラックスして、気持ちよくお風呂を上がることができるのだが、その時の天候や気になることなどに影響され、体調や気持ちが大きく揺らぐことが多いので、心身がすぐれない時には入浴することもできないのである。おそらく自宅でも同じ状況なのではないかと思う。
このように認知症の方たちは、デイサービスでの入浴介助時に訓練すれば自宅で自立して入浴できるようになるといった機能的なものとは性質の異なる、より複雑な困難さを抱えているのである。
更に言えば、脱衣や着衣、洗身や洗髪、浴室での歩行や浴槽の跨ぎ等、入浴にかかわる一連の動作ができるようになれば、自宅で入浴できるか、というとそうではないだろう。入浴する前には浴槽に湯を溜めたり、沸かしたりしなければいけないし、入浴後には、浴槽の湯を抜いて、浴槽や洗い場の清掃をしなければならない。もっと言えば、入浴後に着る衣類を準備したり、脱いだ衣類や使ったタオルは洗わなくてはならない。シャンプーや石鹸も用意しなければならない。こうした数えきれないほどの作業をこなして初めて、自宅で入浴ができるのである。そうした作業をこなすのは、利用者さんたちにとってどれだけ大変なことだろうか。
入浴介助時に打ち明けてくれたことでわかったのだが、美砂保さんもそうした作業が大変で、最近は自宅では入浴できなくなったという。
「すまいるほーむから帰ると、お父さん(夫)が準備してくれたお夕食を食べるでしょ。お父さんは食べ終わるとすぐに、お風呂に入って、さっさと2階の自分の部屋へ行ってしまうの。だから、私がお夕飯の片づけをしているの。パッパとやればいいんだけど、体が動かいないからのんびりやっていると時間がかかるのね。それから本当ならお風呂に入って寝たいけど、遅くなってしまうと疲れてしまうし。お風呂に入った後は、またその片づけもしなきゃと思うと気持ち的にも疲れてしまって、もういいやってなって、入らないの。だから、ここでお風呂に入れてもらえるのは本当に嬉しい。ゆっくり入れるし、スタッフのみなさんとも和やかにお話しできるし」
美砂保さんは、目に涙を浮かべていた。夫と二人暮らしの美砂保さんは、夫に家事を頼っていることに負い目を感じていて、自分でできることはできるだけしようといつも頑張っている。でも、頑張りすぎて、お風呂の跡片付けまでする余力はなくなってしまうのだ。
そんな美砂保さんに対して、「頑張って自宅で自立して入浴しよう」とは私には言えない。美砂保さんは、身体機能的には自宅で入浴することは可能だ。けれど、彼女が、すまいるほーむで介助を受けながらお風呂に入ることで、ほっとしたり、喜びを感じたり、スタッフとの会話を楽しめたりするのだったら、それでいいのではないか、と私は思ってしまう。
「自立支援」と「重度化防止」という「まやかし」
入浴介助加算の見直しは、今回の介護報酬改定での一つの大きなテーマとなっている「自立支援・重度化防止の取組の推進」の一環として行われたものである。今回ばかりではない。介護保険制度は制度改正や報酬改定の度に、「自立支援」と「重度化防止」が大きく掲げられ、重点化されてきているのである。ここで言う「自立支援」とは、利用者さんたちができるだけ公的サービスに依存しなくても生活できるように機能訓練を行ったり、環境を整えたりすることを指している。そして、自立支援による訓練を続けていけば、重度化が防げるとされている。
けれど、それらは幻想ではないか、あるいは、社会保障費の抑制を誤魔化すためのまやかしではないかと私は思っている。早い遅いの違いはあれ、人は誰でも平等に老いていく。できることもあれば、できないことも増えていくのである。そして最終的には心身ともに機能は低下し、つまり重度化し、死を迎えることになる。誰もが死に向かって人生を下っていくのであれば、私たちが目指すべきことは、その下りのプロセスをいかにその人らしく、人として尊重されて、穏やかに、希望を持って、最後まで生き切るか、そのための支援をしていくことではないだろうか。それこそが、本来の「自立支援」ではないかと思うのである。
連載第4回で触れたように、「自立とは、依存先を増やすこと」と熊谷晋一郎さんは言っている。人生の最後のプロセスを「自立して」(その人らしく)下っていくためには、何にも頼らないのではなく、公的サービスを含めた複数の依存先に思う存分頼れることが必要だと言えるだろう。すまいるほーむで私たちは、そのいくつもの依存先の一つとして、利用者さんたちの下りのプロセスの伴走者になっていきたいと考えている。
入浴介助も同じである。孤独や困難を抱えながらも在宅生活を何とか続けている利用者さんたちが、お風呂に入ることで、頑張って疲れ切った体や心を癒したり、コロナ禍で緊張した心身のこわばりを緩めたり、ひと時の幸せを感じられて、それがこれからの人生を生きる力に少しでもなるのであれば、私たちスタッフに大いに依存してもらいたい。私たちは、利用者さんが気持ちよくなるために髪の毛を洗ってあげたいし、さっぱり爽快な気分になるように体も隅々まで洗ってあげたい。そして、転倒を心配することなく、安心して、ゆったりと湯舟に浸かってもらいたい。それこそが、利用者さんの人生を伴走する私たちの喜びであり、やりがいなのである。そんな入浴介助という特別な時間を、利用者さんに更に頑張りを強いる訓練の場には使いたくないのである。
なぜ、人はお風呂に入るのか?
実は、今回、この原稿を書くために、私は利用者さんたちに、お風呂の思い出について聞き書きした。例えば、東京の下町で子供時代を過ごしたウーさんは、父親に連れられて毎日銭湯に行ったことを語ってくれた。普段は私たちが何か尋ねてもほとんど答えないウーさんが、浅いお風呂と深いお風呂の間の壁に開けられた穴を潜って遊んだことや、三助さんに背中を流してもらったこと、銭湯の後に蕎麦屋に寄るのが楽しみだったこと等、目を真ん丸に見開いて語ってくれたことが印象的だった。
90代のスズさんは、野良仕事で体が汚れるので、毎日自宅のお勝手の土間にあった木の風呂を焚いて入っていたことや、国鉄職員だったお舅さんや夫が持ち帰った石炭を、十能ですくってくべてお風呂を焚いていたこと、お風呂でお姑さんの背中を流したり、髪を梳かしたりするとわがままなお姑さんが喜んでくれたこと等、地域の生活史に関心のある私にとっては興味深いことをたくさん教えてくれた。
締め切りと私の残された余力からすると、ここではこれ以上詳しく紹介することはできないが、利用者さんたちはお風呂にまつわる鮮明な記憶を、それぞれが目を輝かせて楽しそうに、そして雄弁に語ってくれたのだった。そこから私は、苦労しながらも懸命に生き抜いてきた利用者さんたちにとって、お風呂に入るということは、心身を癒し、生きるエネルギーを回復させていく大切な時間と空間であり続けてきたのだということが改めて理解できたのだった。そうであれば、身体機能が衰えてきて、人生のプロセスを下りに向かって生きている段階になって、癒しとエネルギー回復の場であるはずのお風呂で、自立のための訓練を頑張らなければならないというのはどう考えても酷なことだし、理不尽な押しつけだと言えるだろう。
聞き書きの最後に利用者さんたちに私は尋ねた。なぜ人はお風呂に入るのか、と。すると、利用者さんたちは、その問いが少し唐突だったようで、戸惑っていたが、それでもそれぞれが考えて答えてくれた。
「やっぱり気持ちがいいからじゃないの?」
「さっぱりするからだね」
「俺は特に客商売していたからだと思うけど、対外的にきれいにしておくためっていうのもあるよね」
そして、それまでみんなの話を黙って聞いていたきよしさんが、この質問に対しては、はっきり、ゆっくりと答えてくれた。
「誰だってお風呂に入るのが好きなんだよ!」
「お風呂が好きだから入る」。単純明快な答えである。
「気持ちがいいから」「清潔になってさっぱりするから」「好きだから」。確かにお風呂に入る理由に、それ以上のものがあるはずもない。
「気持ちがいい」「さっぱりする」「お風呂が好き」、利用者さんたちがそう思い続けられるように、私たちはこれからも、私たちにとっても幸せを感じられる入浴介助の時間を大切にしていきたいと思う。
※次回は5月22日(土)に掲載予定