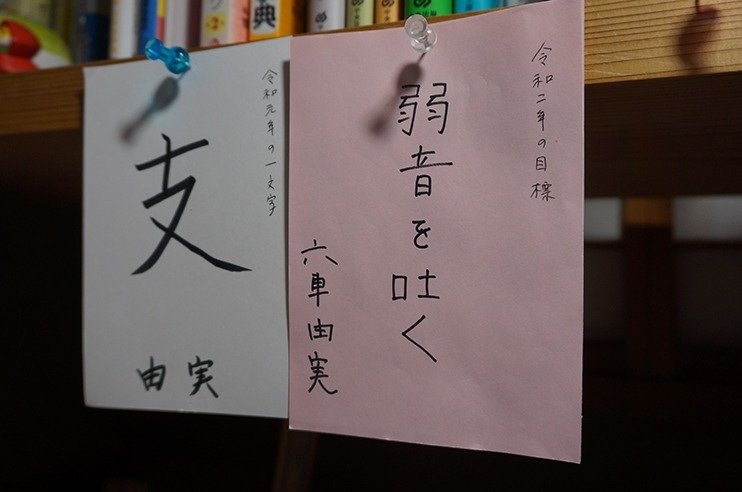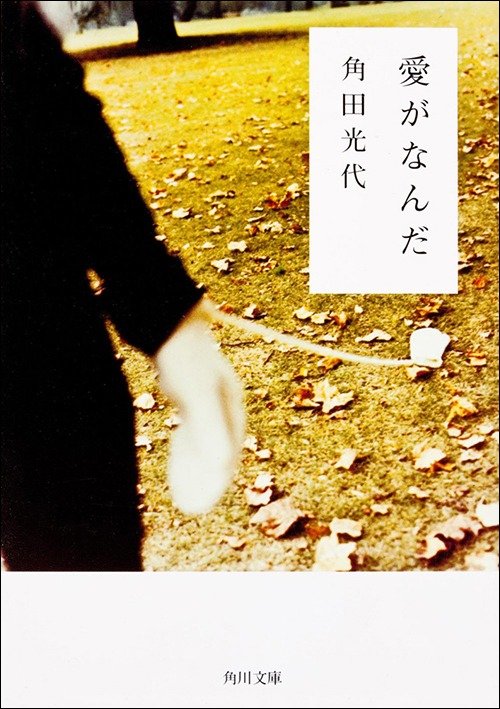六車由実の、介護の未来04 たくさんのつながりがあるということ(後編)
つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。
>>前編はこちら
◆ ◆ ◆
家族とつながりたい
私には苦い経験があった。認知症の親を介護している家族が、症状が進んでいくことを憂いて、本人の同意も本人への説明もなしに、突如施設への入所を決めてしまうというケースが何度かあったのである。いずれも、私たち現場のスタッフから見たら、まだまだ住み慣れた自宅での暮らしが続けられるだろうと思える方ばかりだったから、とてもショックを受けた。
でも、後から話を聞いてみると、家族は私たちが想像していた以上に追い詰められていたことがわかる。お嫁さんに宝石を盗まれたという被害妄想があったり、詐欺にあったと警察へ駆け込むことがたびたびあったり、家族を強い口調で責め立てたり。そして、それを信頼している主治医に相談するたびに薬が増えて、それでも症状が悪化していき(症状の悪化は薬の副作用とも考えられるのだが)、本人と家族の置かれた状況はあっという間に深刻化していく。そして、主治医からもう自宅で暮らすのは難しいと施設への入所を促されれば、家族がそれ以外の選択肢はないと思ってしまうのは当然かもしれない。
(ちなみに、認知症の方の「暴言」とか「暴力」とか言われる行動の背景や、認知症の方の服薬の功罪等について考える手がかりとして、認知症専門医の木之下徹さんの『認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由』(講談社+α新書)をお薦めしたい。本人にとっても、家族にとっても希望がもてる良書である)。
私は、施設への入所が悪いと言っているのではない。けれど、本人が置き去りにされたまま、家族が半ば騙すようにして本人を施設へ入所させてしまうというのは、本人にとっても、そしてそうせざるを得なかった家族にとっても、とても不幸であるように思うのである。
私たちはこれまで、利用者さん本人がいかに心地よく、そして安心してすごせる場をすまいるほーむに作っていくか、ということに注力してきた。本人がここでたくさんのつながりを結び、生きる希望を持つことができれば、自宅での暮らしに安心感や平穏を取り戻すきっかけになるのではないかと思っていたのだ。けれど、当たり前だが、デイサービスで私たちがかかわれるのは生活のほんの一部にすぎない。それ以外は、自宅で過ごし、家族とのかかわりや暮らしがある。家族には私たちとのかかわりができる以前からの長い歴史があり、それぞれの事情がある。だから、私たちは自分たちができることが限定的であることを自覚しながら、仕事をするよりほかはない。
でも、できれば、家族が孤立し、追い詰められて早急な決断を出す前に、一息ついてから、本人と向き合い、考えを共にめぐらせることができるように、僅かでも力になれればとも思う。たとえば、みよさんの娘さんのように、不安な気持ちの聞き役になってもいい。あるいは、少しでも前向きになれるような情報を提供したり、そう考えてもいいんだと力を緩められるような、ちょっとした発想の転換を促したりもできたら、行き詰った家族も、そして本人も少しは楽になるのではないかと思うのである。それは、私たちでなくてもいい。家族会に参加したっていいし、信頼できる医師やケアマネジャーに相談したっていい。とにかく、家族だけで抱え込まずに、いくつもつながりを頼ってほしいと思う。私たちもその一助を担えたら嬉しい。
実際、最近は、私自身の年齢が利用者さんを介護しているお子さんたちの年代とほぼ変わらなかったり、少し上になっているケースもあり、家族も電話だけでなく、メールやLINEでも気軽に連絡をくれたり、相談してくれたりすることも増えてきた。私の方も、自宅での様子を聞いたり、すまいるほーむでの様子を伝えたり、あるいはお願い事をしたり、メールやLINEで頻繁に連絡をとるようにしている。最後に押されるスタンプや絵文字で、互いを気遣う気持ちの交換がゆるくできるのも、メールやLINEのいいところだと思っている。
家族とのつながりが少しずつ結ばれてきている。それは決して、利用者さん本人をないがしろにしようというのではない。そうではなくて、利用者さんとスタッフとのつながり、利用者さん同士のつながり、スタッフ同士のつながり、利用者さんと家族とのつながり、そして、家族とスタッフとのつながりと、さまざまな方向に向かって交差したり、重なり合っているのだ。そして、そのようなつながりが多ければ多いほど、それぞれが困難を抱えながらも、行き詰って倒れてしまわずに、たとえ倒れても誰かとのつながりが支えになって、また起きて前を向いて歩いて行けるのではないかと、私は楽観的な希望を抱いているのである。
たくさんの依存先を頼りに逞しく生きる
すまいるほーむにかかわる人たちに、それぞれ複数のつながりがあり、そのつながりの束がこの場所にあればあるほど、利用者さんも、家族も、スタッフたちも生きやすくなる。だから、できるだけ多様なつながりが結ばれるように場を開いていきたい。そう私が思うようになったのは、小児科医で、自らも脳性麻痺の障害を持っている熊谷晋一郎さんが、さまざまな場面で繰り返し強調されている「自立とは、依存先を増やすこと」という言葉に影響されたことが大きいように思う。熊谷さんは言う。
一般的に『自立』の反対語は『依存』だと勘違いされていますが、人間は物であったり人であったり、さまざまなものに依存しないと生きていけないんですよ。(中略)健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違いされている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなものに依存できていて、障害者は限られたものにしか依存できていない
『TOKYO人権』第56号・インタビュー「自立は、依存先を増やすこと 希望は、絶望を分かち合うこと」
つまり、障害者とは、「依存先が限られてしまっている人たち」のことだという。だから、障害者が自立を目指すためには、親以外の依存先を社会に増やさないといけない。とはいえそれは、障害者本人の自助努力でできるわけではなく、社会が依存先の選択肢をたくさん提供していくことが必要だ、というのである(mugendai 2018.8.02インタビュー「『自立』とは、社会の中に『依存』先を増やすこと ――逆説から生まれた『当事者研究』が導くダイバーシティーの未来」)。
「自立とは、依存先を増やすこと」というこの熊谷さんの主張にまず救われたのは私自身だった。結婚もせず、親と同居して、80歳を過ぎた母親に家事を任せっきりで仕事と原稿執筆と講演活動に明け暮れている。そうした「自立できない自分」「依存している自分」に私は常に後ろめたさと申し訳なさと劣等感を抱いてきた。一方で、辛い時でも誰にも助けを求めることができず、倒れる寸前まで心身ともに自分を追い詰めて、結局母親に心配をかけるという事態をこれまで何度も繰り返してきていた。
けれど、熊谷さんのこの言葉に出会ってから、「依存している自分」を肯定してもいいのかもしれない、と思えるようになった。そして、実は私には、依存できる先がたくさんあるのではないかと気づくようになったのである。そのころから少しずつ、辛い時には弱音を吐いて、上司やスタッフ、それに利用者さんたちにも助けを求められるようになってきたように思う。職場以外でも、丁寧な説明で安心感と信頼感を与えてくれる主治医である婦人科の医師の存在や、定期的に通って体と心の緊張と疲れをほぐしてくれる鍼灸師の存在、私にいつも寄り添ってくれるマロンという愛犬の存在、そして毎日何度も繰り返し聴いて、心を落ち着かせたり、楽しい気分にさせてもらっている米津玄師さんのアルバム。すべてが私にとっては依存先だと思えるようになると、とても気持ちが楽になっていった。熊谷さんの言葉に出会って、私はやっと、「大丈夫、私は生きていける」と思えるようになったのである。
だから、熊谷さんのいう依存先を「つながり」と考えれば、すまいるほーむにもたくさんの多様なつながりがあった方がいい。そして、できれば、利用者さんにも、家族にも、スタッフたちにも、すまいるほーむの外にも、複数の頼れるつながりができてほしいと思う。
そういう視点でみよさんを見てみると、みよさんは実はたくさんの依存先とつながりを持っているように思える。すまいるほーむでの他の利用者さんたちやスタッフとの一つ一つのつながりはみよさんの心を支える依存先だと言えるし、そして、携帯電話もみよさんを外の世界へとつなげ、道にまよったりして困った時には命を救う依存先だと見ることができるだろう。携帯電話を通して、みよさんは昼夜問わず、娘さん、息子さん、かつての職場の同僚たち、そして私ともつながれる。私の部屋にはすまいるほーむの電話の子機が置いてあるし、私の携帯からかけた着信履歴がみよさんの携帯に残っている。だから、みよさんからの電話はだいたいとることができる状態にある。娘さんは、「迷惑をかけてすみません」と謝るが、明け方にかかってくる電話であっても、「ああ、みよさんが頼りにしてくれているんだ」と思えて、私は少し嬉しかったりする。確かに眠いけれど。
そして、みよさんには、自宅にいる時に、時々、亡くなったご主人や寝たきりで会えなくなったお姉さんの姿が見えている。認知症の症状の1つである幻視だと思われる。でも、みよさんはそれを怖がったりはしておらず、「姉さんがまた来て一緒にご飯を食べた」等と親しみをもって語ってくれる。だから、そうした幻視のご主人やお姉さんも、マンションに一人で暮らすみよさんの寂しさに寄り添ってくれる大切な依存先だと考えてもいいのではないかと思う。
みよさんは、たくさんの依存先を頼りに、今を逞しく生きている。「すごいよ、みよさん」と改めて思う。
さて、明日の朝も、みよさんから電話がかかってくるかな。「今日行く日だっけ? どうやって行けばいいかな」というみよさんのさわやかな声が聴けることを楽しみにして、今夜も眠りたい。
※次回は11月28日(土)に掲載予定