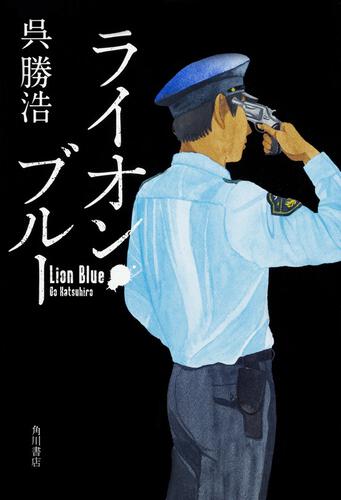さあ、選ぶんだ。次に誰を殺すのか。呉勝浩「スワン」#10
呉勝浩「スワン」

PM12:00
音楽が聞こえた。オルゴールのような音色だ。メロディは弾んでいる。音源は通路の先の突き当たり、黒鳥広場だ。
もうそんな時刻か、と丹羽佑月はゴーグルを外して捨てた。急がないと、そろそろ邪魔が入るころである。
歩を進めつつ、佑月は
そう考えると、笑えた。笑いながら、拳銃を撃った。とくに狙いもなく、気まぐれに。ほとんどの客が避難を終えている。有意義な獲物に出会う確率は低い。ガスの真似みたいで
ガス。図体だけ立派な腰抜け野郎。意気がってサントを撃ち殺していたが、肩は震えていた。目は泳ぎ、汗をだらだら流していた。途中で見かけた様子からも小心者ぶりがうかがえる。まったくもってピエロじゃないか。
ドン、ドン、ぽいっ。いよいよショルダーバッグが軽くなった。中にはあと四、五個くらいしか残っていない。
ドン、ドン。空の銃を放り捨てたとき、ひらけた場所にたどり着いた。眼下に黒鳥の泉が見えた。黒い衣装のオディールがくるくる回っていた。倒れている人間がいないか探してみるが、見当たらない。血の跡すらない。ふん。やっぱりな。しょせんガスはその程度の奴だ。
両手にひとつずつ拳銃をにぎる。ショルダーバッグは空になった。拳銃の残りはチョッキにおさめた四個と腰に差した一個だ。
佑月はエスカレーターで三階を目指した。用なしのバッグを宙に放る。妙に身体が軽くなった。同時に、ぽっかりとした気分になった。
初めその理由を、ゴーグルカメラの撮影が終わったせいだと解釈した。緊張が途切れてしまったのだと。映像に残そうと提案したのは、このドキュメントをたんなる記録ではなく「丹羽佑月の作品」にしようと思ったからだ。一方で、最後の最後は撮影しないと決めていた。名作や傑作には観客の想像力をかき立てる余白が必ず残っている。譲れない持論だ。
つまり、この虚脱の原因は、ほかにある。
何か、足りない。しびれるような快感、高揚。日常を超えた風景、研ぎ澄まされる五感。たしかにそれはあったけど、望んでいたとおりだったけど、けれどそれ以上じゃなかった。ゴヤの『マドリード、一八〇八年五月三日』やドラクロアの
こんなものか、という失望が否めない。虚空に銃声を響かせたところで『ポンヌフの恋人』がすくいとった解放感にはほど遠い。
エスカレーターに運ばれながら、何が足りないんだろうと考えた。やはり敵か。これがアクション映画なら、主人公に負けない魅力的な敵役が欠けている。いやこの場合、佑月たちが敵役か。すると求められているのは逆境に打ち勝つ、強烈な個性をもった主人公ということか。そんなもん、どうやって用意すりゃいいんだよ。
自嘲しているうちに、三階に着いた。
透明な筒が天空へのびている。その先にある、消失点。
物足りない気持ちはある。だが潮時だ。美しいものはたいてい、引きぎわを心得ているものだ。
佑月は拳銃を手に、透明な筒へ向かう。この上にあるスカイラウンジ。そこが佑月のラストステージだ。
ボタンを押す。けれどエレベーターはこなかった。
ああ、と察した。異変に気づいたラウンジの客たちが上階で停めているのだ。その可能性をすっかり見落としていた。
ふっと感情が込み上げ、佑月はエレベーターのガラスドアを
怒りにまかせドアを殴りつける。上空をにらむ。
しかしそこにエレベーターの箱はなかった。もしやと思い見下ろすと、箱の天井が見えた。一階に停まっている。
胸をなでおろし、もう一度ボタンで呼ぶが、やはり箱は動かない。電力が切られている? しかしエスカレーターは動いている。
疑問はあったが考えても仕方なかった。下りのエスカレーターを駆けおりる。
黒鳥広場に着き、やっと状況がわかった。エレベーターの箱とフロアにまたがるように、女性が倒れていたのだ。胴体の部分が邪魔をして、ドアが閉まらなくなっている。
くそっ。ガスのボケが。ほんとによけいなことばかりしやがる!
佑月はうつ伏せになったその障害物に近寄り、八つ当たり気味に拳銃を撃った。後頭部と背骨のあたりに一発ずつ命中した。運動靴を履いた両足をつかみ、引きずりだした。
箱に乗る。スカイラウンジ行きのボタンを押す。『四羽の白鳥』がやむ。黒いオディールが噴水の底へ沈んでゆく。
箱は無事に動きだした。息をつく。これじゃあドタバタコメディだ。シナリオライターは死刑だな。
ふたたび、佑月は
上昇しながら外の風景を眺める。貯水池が目に入る。水面は静止画のように穏やかだ。あの池を死体で埋めて、真っ赤に染めるほうが美しかったかもしれない。
貯水池の向こうに湖名川市の町並み。ずらりとならぶ建物は奇妙なほどおなじ背丈で、まるで人工の地平線だ。丹羽佑月が育った町。そして真っ青な空。
箱が停まった。束の間の物思いを切り上げる。
ドアが開き、佑月は思わずのけぞった。
ああ──、そりゃそうか。
エレベーターが動かなかったんだから。ならばここに客が残っていたって不思議じゃない。
ドアの向こうで、不安げにこちらを見る顔、顔、顔。
「あっ──」
佑月が構えた拳銃に、三人ならんだ女たちの、真ん中の子が反応した。「大丈夫だよ」と佑月は答えた。
「大丈夫だから、動かないで」
救助を待ち焦がれていたのだろう。真ん中の彼女が絶望とともに息をのむのがわかった。その姿に、佑月は心のなかで
なんてことだ。すごいギフトだ。ドタバタの
細長い手足、身体。派手さのない顔つき、気が強そうな目の感じ。そして可愛らしいポニーテール。何もかも彼女は、文句なく、佑月の好みにぴったりだった。
ここにいた。「物語」の主人公が。
スワンを見下ろす頂上で、ひとり孤高の死を遂げる──そんなエンディングはご破算となったけど、代わりにこのB級映画のフィナーレを飾る、とても素敵なアイディアが降ってきた。
佑月はにっこり笑い、箱の外へ一歩を踏みだした。