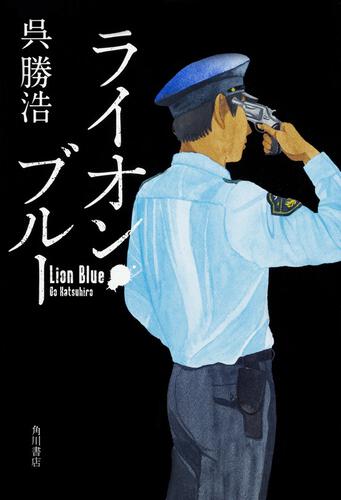死者21名、重軽傷者17名。ショッピングモールの日常は地獄絵図と化した。呉勝浩「スワン」#6
呉勝浩「スワン」

AM10:50
腕時計を見る。ふだんはスマホで済ませているが、今日は入学祝いの品を引っ張りだしてきた。
十時五十分。
チノパンのポケットからスマホを取りだす。着信もメッセージもない。
苛立ちが増す。すでに二十分、待ちぼうけをくっている。
なんだよ。昨日はあんなにはしゃいでいたくせに。
初めはムカついていた。カメ、カメと気安く呼ばれ、「うるせえな、ブス」と心のなかで悪態をついていた。それがいつの間にやら仲良くなって、気がつけば心
洋介はこれまで、女に困ったことがない。すらりとした長身に、すっきりした顔立ち、我ながら気が利くし弁もたつ。おかげで小学校のころから彼女が途切れたためしはなく、クラスや学年で、学校で、あるいは地域で、モテモテだった。それなりのランクを求める女の子が寄ってきて、こっちもランクを見極めて、付き合ったり離れたりを繰り返した。歴代の彼女のなかにはファッション誌の読者モデルになった子もいる。
そんな洋介だから、大学でもとっかえひっかえ、女遊びに精をだすつもりだった。じっさい新歓コンパで彼女を見つけ、サークルで愛人を見つけ、飲み屋でセフレを見つけた。愛人とセフレのちがいはよくわからないが、ともかくそういうふうに楽しんでいた。
ところが去年、三年生になったとき、急にすべてがつまらなく思えた。理由は不明だ。就職活動やら卒業やらが迫ってきたこととも無関係じゃないのだろうけど、はっきりはしなかった。仕送りで遊びほうけ、金が尽きれば女たちにおごってもらう生活に、ついに飽きがきたのかもしれない。
なんとなくはじめたバイト。やたらと活気のある居酒屋はサークルOBが店長をしている店で簡単に採用された。汗水たらすのはセックスのときだけと決めていた洋介は初日でうんざりし、二日目で辞めたくなり、三日目で辞める決心をし、四日目の休む理由を探していたところに、由衣が現れたのだ。
思い返すと当時の自分は「いらっしゃいませ!」の掛け声すら適当で、オーダーまちがいを謝りもしない典型的駄目バイトくんだった。そんな洋介に由衣は容赦なかった。次の日も洋介が出勤したのは、このくそ女を
それがどうして、こうなってしまったのやら。
由衣は十八で親もとを離れ、たったひとりで生計を立てていた。学校に通うわけでもなく、ふたつのバイトを掛けもちし、お金を貯めていた。いつか自分の店をもちたいのだと彼女は語った。小さな定食屋、あるいは弁当屋。五年がんばった、あと三年もすれば──。
付き合ってくれと頼んだのは洋介のほうだ。由衣はぽかんとしていた。なんだか急に可笑しくなって、思わずふたりで笑い合った。定食屋も弁当屋も、洋介にはダサい仕事に思えたが、なぜだか由衣といっしょなら悪くない気がした。
せっかくだから一度は就職してみろと由衣にいわれ、いまは外食チェーンを狙っている。学んだノウハウが、いずれふたりの店の役にたつかもしれないからだ。
メッセージが届いた。〈すまん。寝坊った。走る〉
走るって、池袋から何キロだよ──。
思わず笑ってしまう。そのことにあらためておどろく。昔の自分なら予定はキャンセルし、ナンパに繰りだしていただろう。
洋介の地元が湖名川だと知り、スワンに行ってみたいと誘ってきたのは由衣のほうだ。洋介は渋った。ここだと、知ってる人間に出くわす確率が高い。泣かせた女、恨まれている男。山のようにいる。
それでも由衣の願いなら応じてあげたい。ときめきや強烈な性欲とはちがう、何かこう、そばにいたいという感覚。そばにいてほしいという感覚。
緊張は、すきあらば由衣を家族に紹介しようと
人生ってほんと、何がどうなるかわからないな。
苦笑をもらした拍子に、ふと、目を奪われた。駐車場のほうから歩いてくる奇妙なロン毛の男。ごついゴーグルをかけ、重そうなレザーのショルダーバッグを担ぎ、ごつごつしたチョッキを着ている。そして腰に、時代劇のような刀をさしている。
イベントの出演者? そう思って広場を見渡すが、とくにステージなどは見当たらない。
時刻は間もなく十一時。噴水の前で屈伸運動をはじめたロン毛を、洋介はぼんやり眺めた。
ロン毛が、ごついゴーグルにふれた。辺りを見まわし、洋介に目を留めた。口もとが、ニコリと広がった。
知り合いだろうか。ゴーグルのせいでよくわからない。
ショルダーバッグに手を突っ込んだロン毛が、ゆっくりこちらへ歩きだす。なんだろう、誰だろう──洋介の疑問をよそに、どんどんどんどん、近づいてくる。
と、由衣からメッセージが届いた。
〈電車、乗った。楽しみ〉
ちぇっ。勝手いってらあ。でもまあ、そうだな。
楽しもう。
そんな返信をしよ、
ドン。
AM11:00
「ちょっとあなた、待ちなさい!」
呼び止めると、お団子頭のウェイトレスがふり返った。
不満げな表情を隠しもせず、相手がぼそりと答えた。「……ソーセージですけど?」
「ええ、そうね。びっくりだわ」大げさに、菊乃は肩をすくめた。「わたし、このお店のナポリタンが大好きなのよ。毎週のように食べてるの。もう数えきれないくらい」
毎週日曜日、たどり着いたスカイラウンジでゆっくり紅茶を飲んで疲れを
お団子頭の彼女の顔がどんどん曇ってゆく。それが菊乃の苛立ちに拍車をかけた。
「ソーセージはハムに替えてちょうだいといったはずよ!」
「──いつもの、としか伺ってませんけど」
「それが『いつもの』でしょっ」
ぶすっとしたまま、「じゃあ替えてきます」と皿を下げようとする。
「待ちなさい」堪忍袋の緒がぶちっと切れた。「その態度は何? お客さまは神さまだって教わってないの?」
「それはちがうと思います」お団子頭の彼女が、堂々と菊乃を見下ろした。「なんでもいうことを聞けるわけじゃないですし、『気に入らないからタダにしろ』とかいわれても困ります。できるサービスしかできません」
「まっ」
菊乃は目を丸くした。「できないことなんてひとつも頼んでいないじゃないっ」
「『いつもの』でぜんぶわかれっていうのが無理です。だってウチに『いつもの』なんてメニューはないですから」
絶句するよりない。なんだその
夫が興した物流会社で、菊乃は長年ばりばり働いてきた。取引先のわがままに付き合ったりご機嫌をとったりはあたりまえのこと。それが客商売だと性根に染みついている。
いくら若いアルバイトといえど、非常識がすぎるんじゃないか? こっちは毎週通っている上客なのに。
「店長さんを呼んでちょうだい」
はん、と鼻で笑われた。
「早くしなさい!」
怒鳴りつけると、ほかのテーブルに座る客たちがそっと眉をひそめる気配を感じた。まるでワイドショウでやり玉にあがるクレーマーの気分だ。怒りでフォークをにぎる手が震えた。せっかくのお出かけが台無しだ。
カウンターへ向かうお団子頭の背中が憎らしくてたまらない。いっそこの手で絞め殺してやろうか──。
ドン。
カチャン。
とつぜんの破裂音にびっくりし、にぎっていたフォークを床に落としてしまった。思わずといった調子で天井を見上げる。ガラスの向こうに、さわやかな青空が広がっている。
次の瞬間、下の階から、悲鳴。