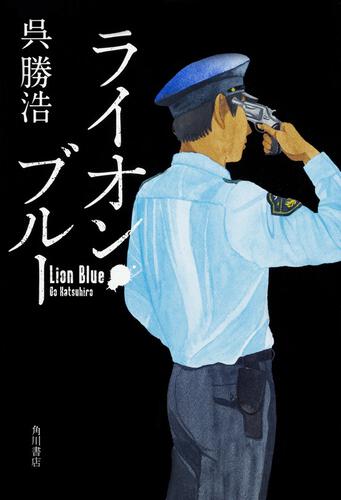死者21名、重軽傷者17名。ショッピングモールの日常は地獄絵図と化した。呉勝浩「スワン」#7
呉勝浩「スワン」

AM11:10
〈防災センターより連絡です。ただいま館内において火災が発生いたしました。ご来場のみなさまは係員の誘導に従い、速やかに安全な場所へ避難してください〉
火災ねえ。
ドン、ドン。二階へ上がるエスカレーターの上に立った丹羽佑月は、手すりに背中をあずけた体勢で、二階の通路を走る中年カップルに模造銃を連射した。一発目と二発目のどちらが当たったかはわからないが、夫らしき男性が肩口を押さえすっ転んだ。女性のほうが悲鳴をあげて駆け寄った。なかなか澄んだソプラノだ。
射程距離はそこそこあるが、遠くからでは威力が落ちる。あの男は大した怪我じゃないだろう。運がいい。
空の拳銃をぽいっと投げ捨てる。下から、カーンと音が響く。一階を見下ろすと、白鳥広場はひどいことになっていた。ベンチのそばで人が倒れ、床に人が倒れ、白いタイルに血が赤い染みをつくっていた。撃ち終えて捨てた拳銃がバラバラと黒い点を打っている。手当たり次第に撃ちまくった結果にしては美しい模様じゃないかと佑月は思う。
エスカレーターで運ばれるあいだ、ぐるりと周囲を見渡した。白鳥広場の中心を、天にのぼっていく感覚だった。悲鳴や泣き声に自動音声の館内放送が加わってうるさいことはうるさいが、意外に耳障りではなかった。天井から降り注ぐ四月の陽光。この巨大な円柱の、ひだまりのシェルターが、二十一世紀製バベルの塔が、あたかも丹羽佑月のためにあるみたいだ。
目の端を何人か、走っていく者がいた。素敵な気分なので見逃してあげる。
肩にずっしりと食い込むレザーのショルダーバッグから新しい拳銃を取りだす。二階に着く。すぐそばの携帯ショップの店先に、店員らしき女性が突っ立っていた。両手を胸におろおろしている。パニックで思考停止という感じだ。
佑月と目が合い、口をパクパクさせた。
「火事だそうですよ、お嬢さん」
構えた拳銃の引き金を、ボブカットの彼女の、
ガチッ。
引ききれずに固まった。弾詰まりだ。その場合はすぐに捨てろとガスはいっていた。製作者の忠告に従い拳銃を放り、あらためて新しいやつをにぎる。そのあいだも、ボブカットの女は腰を抜かして震えているだけ。楽なもんだ。
ドン。
額にしっかり銃口を当て、撃った。脳みそが飛び散るなんてことはない。しょせんは自家製、そこまでの威力はない。けれど彼女は糸が切れたように突っ伏した。それで佑月は満足し、ついでだから残った弾をお腹のあたりに撃って、空の拳銃をぽいっと捨てた。
二発しか撃てない模造拳銃は消耗品もいいところで、すでに佑月は十個ほど消費していた。仕留めた獲物は六体くらいか。いちいち確認していないから生き死にまでは定かじゃない。
ドン、ドン、きゃあ! ぽいっ。
出くわす獲物に銃弾を浴びせながらアンティークショップやカフェをやり過ごす。ゆるくくねった直線状の通路は中央が吹き抜けになっていて、左右にフロアがわかれていた。見通しはいいが人影は目につかない。まだ残っているのは、よほどどんくさい奴だろう。
獲物に逃げられても深追いせず、佑月は悠々と通路を進んだ。目的地に着くのは正午の予定だ。あまり早すぎると恰好がつかない。何より日曜日の真っ昼間にガラガラのスワンを闊歩するという貴重な時間を楽しまないのは罪だろう。
立ち止まってみたり、ふり返ってみたり。スワンという巨大で空虚なオブジェをじっくり観賞し、堪能する。佑月のためだけに存在するアートを。
やがて一階フロアの奥のほうから、ドン、ドンという音がした。きゃああ! という叫びがセットで聞こえた。黒鳥の泉からスタートしたガスにちがいない。思ったより距離がある。場所はちょうど白鳥広場と黒鳥広場の中間地点だ。とっくにすれちがってもいいころなのに。
一階の、花壇がある広場を、逃げ惑う客たちが猛然と走ってきた。映画のワンシーンを眺める気分で見下ろし、せっかくなので上空から狙い撃ちしてみたが、さすがにこの距離とあのスピードでは当たらなかった。老いも若きも男も女も、スプリンターみたいないきおいで走っている。火事場の馬鹿力ってやつかしら。
ガラスが割れる音がつづけざまに響いた。ガスはずいぶんのろのろやってるらしい。警察がくるまでだいたい十分間。防災センターもパニックになるだろうからもう少し猶予があるかもしれない。警備員は無視していい。奴らはしょせん飾りにすぎない──ガスはそう断言していた。半信半疑に思っていたが、事実、佑月たちを止めようとする勇者はただのひとりも現れていない。幸運に恵まれているのか、現実とはしょせんこんなものなのか。
と、体格のいい五分刈り頭の男が一階フロアに現れた。ガスだ。声をかけようかと思ったがやめておいた。取り
渡り廊下を使って左右のフロアを行ったりきたりしながら、通路沿いにならぶ店舗をのぞく。逃げ損なった者がいたりする。震える彼らや彼女たちに笑顔で近づき、「大丈夫ですよ」と声をかける。そして銃弾を浴びせる。
ドン、きゃあ! ドン、ぽいっ。
ひと気がなくなった通路に、ミリタリーブーツがコツン、コツンと気持ちよい音をたてる。
コツン、コツン、ドン、きゃあ! ドン、ぽいっ。
気がつくと佑月は鼻歌をうたっていた。『ワルキューレの騎行』から『密室の恐怖実験』へ。タランティーノは天才だが、少し才に
コツン、コツン、大丈夫ですよ、ドン、きゃあ! ドン、ぽいっ。
エスカレーターがある吹き抜けはガラス天井になっていて、やわらかな光が差し込んでいた。そこを通り過ぎるたび、得もいわれぬ崇高な気持ちになった。
コツン、コツン、大丈夫ですよ、ドン、ドン、嫌っ、やめて、お願い、ドン、ドン、 ぽいっ、ドン、ガチッ、ちぇっ、ぽいっ。
通路の正面から走ってきたカップルが、佑月を見て足を止めた。馬鹿じゃないの? なんで足を止めるんだ? そのままのスピードで駆けてこられるほうが弾を当てにくいのに。
白鳥広場でもそうだった。目の前で人が銃殺されているのに、ほとんどの客は動けずにぽかんとしていた。まったくの
ドン、ドン、ぽいっ。あれほど重たかったショルダーバッグが羽のように軽くなってゆく。
そろそろ目的地が見えてくる。この計画を思いついたとき、まっ先に決めた旅のゴール。丹羽佑月という登場人物のエンディング、消失点。