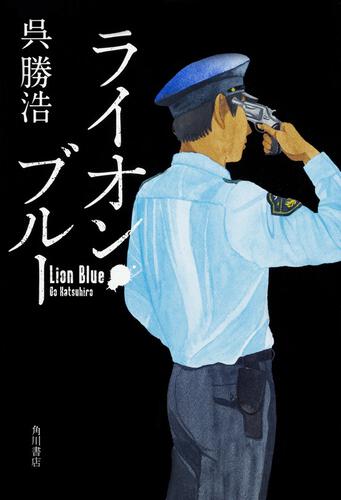さあ、選ぶんだ。次に誰を殺すのか。呉勝浩「スワン」#8
呉勝浩「スワン」

AM11:30
ちくしょう、あの野郎っ!
避難を促す館内放送がうるさかった。苛立ちをぶつけるように
ひたすら足を動かし、撃ちつづける。拳銃は使いきる。死んだサントのぶんまでぜんぶ。残したところで意味はない。
一時間はもつだろうと安和は踏んでいた。警察への通報が五分、到着まで五分。状況確認と来場者の安全確保、犯人にどう立ち向かうか、武器使用を許可するかどうか。そんなこんなで三十分は対応が遅れるはずだ。いざ制圧となったところで町のお巡りさんに思いきった行動はとれまい。県警本部に指示を仰ぐにちがいない。上層部とてこうした事態は不慣れに決まっている。無駄な時間が積み重なるだけ、被害者は増えつづける。事なかれ主義の帰結。平和ボケの末路。国民よ、思い知るがいい。これが我が国の現実なのだ。
吹き抜けの上空にぶら下がるバルーンを狙う。弾は当たらず、むなしく銃声が響いて終わった。空の拳銃を壁に向かってぶん投げる。背中の痛みが増してゆく。
視界の向こうに動く標的があった。ジーンズショップから転がるように、茶髪のチャラい少年が出てきた。べそをかきながら逃げだす背中を、撃つ、撃つ。銃声にびびったのか、少年は頭を抱えてうずくまった。弾は、またもや当たらなかった。さっきからぜんぜん当たらない。視力のせいか? ちゃんとコンタクトを着けてきたのに。
少年は腰を抜かしたように足をばたつかせながら、必死に動こうとしていた。ショルダーバッグに手を突っ込む。一個つかむと、バッグは空になった。残りはチョッキに差した一つだけだ。
銃口を向け、撃つ。少年は「ひい」とうめきながらよたよたと床を
しかし少年は死ななかった。亀のように丸まって
刀を構え、ふん、と突く。首の後ろにずぶりと刺さる。ぬるりとした手応え。少年は祈るように手を空中へ突きだし、だらんとなった。その様子を見下ろしながら、茶髪にしてるおまえが悪いんだと安和は思った。
首から刀を抜く。血があふれた。人間を斬るとその脂で刃の斬れ味が悪くなる。安和は少年の柄シャツで血のりをふきとった。自分には日本刀のほうが合っているのかもしれない。ぬるりとした手応えに、魂を洗われる感覚があった。
皮肉なものだ。時間もコストも労力も、拳銃づくりにいちばんかかった。試作品ができるまで三ヵ月、射程距離や殺傷能力を向上させるのに二ヵ月、量産に一ヵ月。3Dプリンタの購入費用と材料費、作業場として借りたガレージの賃料で総額五百万円くらい。金はヴァンが用意してくれたが、設計から量産まで、すべて安和が受けもった。
寝食を忘れ没頭した。防大受験よりものめり込んだ。実現可能性を優先し、なるべくシンプルな構造にする必要があった。しかし連射式はゆずれない。反撃された場合の対応速度が段ちがいだからだ。条件を満たすアイディアを求め片っ端から資料にあたった。言葉の壁は自動翻訳アプリとウェブ辞典で対処した。
苦労はこれで終わりじゃなかった。むしろ本体以上に弾丸がやっかいだった。海外とちがい日本で実弾にふれる機会などない。扱いをまちがえれば指が飛ぶくらいの事故は簡単に起こる。ここでも頼れるのは世界中に生息するマニアの先生たちだった。ネットを漁り試行錯誤を繰り返し、苦心の末に22LR弾を模したスチール製の弾丸をつくりあげた。火薬の入手はヴァンやサントに協力させて乗りきった。
命中精度、耐久性、射程距離、殺傷能力……。完成品の性能は、国内で可能なハンドメイドの最高峰にちがいない。その自負はあったし、愛着ももっていた。なのに結局、自分は日本刀に心を奪われている。
不思議と悔しさはなかった。これが日本文化の奥深さかと、むしろ誇らしかった。
茶髪の少年を踏みつけ、安和は進んだ。足どりは軽かった。まっすぐに歩けた。呼吸も整っている。
ずっと苛立ちにまとわりつかれていた。ヴァンと別れ黒鳥広場へ急ぎ、十一時、作戦決行ののろしを吹き抜けの上空に
つまらないミスをして、心がゆれた。多くの時間を無駄にした。あと一発でとどめを刺せたのに……悔やんでも悔やみきれない失態だ。その動揺が、射撃の精度に影響している。弾はろくに当たらず、標的には逃げられ、体温が上がる一方で足もとは冷えていった。
迷いがあった? あるいは恐怖? まさか。おれはヴァンの目の前でサントを撃ったじゃないか。あの下劣な餓鬼を粛清したんだ。安っぽいモラルは乗り越えている。そのはずだ。
あれはたんなる油断──。しかし苛立ちはふくらみつづけ、銃弾は
それがいま、すっかり消えた。疲れも痛みも焦りも。不純物を、きっと日本刀が浄化してくれたのだ。
ずらりとテーブルがならぶフードコートを横目に安和は歩いた。間もなく目的地だ。ゴーグルを外して投げ捨てる。こんなもの、もう要らない。
白鳥広場に着く。一瞬、立ちくらみを覚えた。ふだんならにこやかな人びとであふれる場所に、いまは傷を負って這いつくばる中年男性や息絶えた若者が転がっている。見渡すかぎり、十体近くあるだろうか。おびただしい死の場所へ、誘われるように踏み入った。
映画のように、美術のように──。ヴァンはそんな
偉そうにするな──。安和は倒れている人間を日本刀で突き刺した。次々と突き刺した。
背中を丸めた女性を刺す。深い手応えがあった。
ふと、噴水のほうから視線を感じた。警察という単語が頭をよぎった。力をこめて刀を抜き、身構えた。
制服警官も完全武装のSATもいなかった。いたのは男性だった。噴水のへりに、老人がちょこんと腰かけていた。小汚いポロシャツを着、手ぶらで、うつむきかげんにもにょもにょ口を動かしている。床に散らばる死体の山や、日本刀を携えた安和の姿に動揺するでもなく、彼のたたずまいは
安和は構えを解き、日本刀を左手に持ち替えた。チョッキに残った最後の拳銃を抜き、老人に向けた。老人は反応しなかった。よだれを垂らしていた。
しばし向き合った。
ドン、ドン。
銃弾は脳天とあごに命中した。老人は背中から噴水のなかへ落ちた。水しぶきがあがった。それを見つめる安和の手から、拳銃がこぼれた。
高揚はなかった。やはり自分には、手応えのない武器は向いていないらしい。
そのとき、噴水から音楽が流れはじめた。クラシックなど興味もないが曲名は知っている。かつて教えられたのだ。チャイコフスキー作曲、『四羽の白鳥の踊り』。
曲に合わせ、噴水から人形がせり上がってくる。白い衣装の少女像はつんと胸を張り、両手を広げている。まっすぐのびた右足でつま先立ちし、左足は直角にのびている。クラシックバレエの名作として有名な『白鳥の湖』、そのヒロイン、オデットだ。全身があらわになるや、彼女は回転をはじめる。別館ではジークフリート王子が、黒鳥広場では黒い衣装のオディールが、おなじように回っているはずだ。日に三度、決まった時刻に動く仕掛け人形。三十二回転のグラン・フェッテ。
束の間、安和は立ちつくした。くるくる回る人形から目が離せない。見飽きた光景だった。曲も聴き飽きている。たしかにひさしぶりではあるけれど、どうしてこれほど新鮮に感じられるのか、不思議でならない。
まるで演出みたいな絶妙なタイミングで、羽ばたきが聞こえた。天を仰ぐと、はるか頭上のガラス天井の、さらに上空、澄みきった青空を、数羽の鳥が横切った。
意識のなかから音楽が遠ざかり、静けさに包まれた。
なぜ、こんなことになったのだろう。
よくわからなかった。わかる必要もなかった。いまさら考えたところでしようがない。なのに考えてしまう。
おれは、この国の体制と治安に一石を投じたかったのだ。簡単に銃器を密造できる時代に、平和を壊すことはたやすいのだと、わからせたかったのだ。社会を守るとは何か。国を守るとは何か。それはきっとおれにしかできないことなのだ。この勇敢な
そう。これは私利私欲を超えた、愛国心ゆえの行いである。行いである。行いで──。
──後悔? 馬鹿な。だとして、三十七年の人生の、いったいどこまでさかのぼって悔いろというんだ。
頭痛がした。ズキッと背中に痛みが走った。うるさい。館内放送がうるさい。『四羽の白鳥』がうるさい。
あの夏の日がよみがえる。醜い面をした男たちにぶつけられた挑発、威嚇、女たちが放つ
正当防衛。教育的指導。何がまちがっている?
死ね。全員死ね。おれをなめた馬鹿どもはひとり残らず地獄に落ちろ。後悔するのはおまえらだ。
頭痛、苛立ち。どうして涙が──。
次の瞬間、後ろから組みつかれた。首に腕が絡みついた。反射的にあごを引いた。それでも絞めつけてくる圧力にめまいがした。
「動くなっ!」
上ずった男の声だ。警官? いや──。
相手の息が、頰にかかった。目が、こちらを見ているのがわかった。
わずかに、首にかかる力がゆるんだ。「おまえ──」相手の声がする。「──大竹?」
迷いはなかった。どうせ初めからそのつもりだった。背中の痛みが、決意を後押ししてくれた。
日本刀を両手で逆手に持ち直し、高くかかげる。いきおいをつけ、刃を、自分の腹部に思いきり突き刺した。その瞬間、安和は思った。
死ね。みんな死ね。そして後悔しろっ。
ざまあみやがれ──。
へその辺りから、刃がずずずと侵入してくる。かすんでゆく視界の中で、白いドレスの仕掛け人形が回りつづけている。