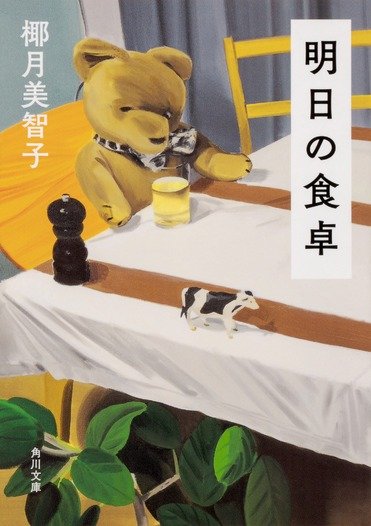【連載小説】男がお茶を汲むという古い考えはもうやめたほうがいいと思います。 椰月美智子「ミラーワールド」#1-6
椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
会長がいなくなった険悪ムードただよう会議室で、
「今度の総会のお茶いれ、池ヶ谷さんは来られなくていいですよ」
と、進は辰巳に伝えた。辰巳は進の顔をじっと見つめ、大きく息を吐き出して頭を振ったあと、よろしくお願いします、と蚊の鳴くような声で言い、みんなを残して会議室を出て行った。せっかくお役御免にしてやったのに、ぶすっとした辰巳の態度に、進ははっきり言ってムカついたのだった。
「池ヶ谷さん、めっちゃムキになってたよな。PTAの存在にまで話が及んで、びっくりしたよ」
水島が言う。
「本当だよな。五木会長が気の毒になったわ」
井上がうなずく。
「お茶いれのために、これから決議を取り直すなんて、そんなめんどくさいことできるかっての」
水島がうんざりしたように頭を振る。
「だけど、池ヶ谷さんが言ってたことも確かに、と思いました。男のお茶くみっていう古い考え方はもうやめたほうがいいと思います」
澄田が言う。澄田の年齢をはっきりとは知らないが、まだ三十代らしい。見た目もあきらかに進たちより若かった。本人もそれをわかっているのか、PTA役員で話すときはいつも敬語だ。
「そんなこといって、澄田ちゃん。妻さんの実家の理容室継いでるじゃん? 妻さんのために、結婚してから理容師免許取ったんでしょ? お茶いれどころのレベルじゃないよ」
井上が笑いながら言う。
「えー! そうだったんだ、澄田さん。やるねえ、内助の功じゃない」
水島がひやかす。
「いや、おれが理容師免許を取ったのは、べつに妻のためじゃないっすよ。理容師に憧れてたんですよ。だから、ちょうどよかったっていうか……」
最後のほうは言葉に詰まっていた。
「まあまあ。妻さんの実家の家業を継ぐのと、PTA総会でのお茶いれは、まったく違うことだから」
進はさわやかに微笑んで、井上と水島をやんわりと制した。
「男女平等はわかるけど、女を支えているのは男だって思えば、お茶いれなんて、たいしたことないって思わないか? なにをあんなにムキになっているんだろうね、池ヶ谷さんは」
それが進の本心だった。女が女でいられるのは、男のおかげだ。男がおだてて気分よく外で働いてもらい、サラリーを運んでもらう。
進の妻は勤務医である。内科なので急な呼び出しはないが、医者の不養生などと言われないように、夫の自分がしっかりと支えたいと進は思っている。
「池ヶ谷さんの仕事って、学童指導員だっけ?」
井上が言う。
「そうそう、昔は教師だったらしいよ。奥さんも教師みたいね」
水島だ。みんなよその家庭のことに詳しいなと思う。
「教師って保守的な人が多いけど、たまに変わり種もいるからね」
辰巳が教師を続けていたとしたら、入学式や卒業式での国歌斉唱に起立しないで、頑として座り続けているのではないかと想像した。
「保守的?」
澄田がきょとんとした顔で問う。
「新しいものより、これまで慣れ親しんだものを好むってこと。池ヶ谷さんはその逆だよね。進歩的っていうのかな」
なるほど、そういう意味か、と澄田がつぶやく。
「おれ、甘い物食べていいっすか」
澄田がチョコレートパフェを注文した。若いねえ、と水島が笑う。
今度のPTA総会でのお茶いれは、ここにいる四人と、もう一人は
「おかえり、鈴ちゃん」
鈴の帰宅に間に合ってよかった。誰もいない家に子どもを帰らせることは、なるべく避けたい。家族を出迎える。それが父であり夫である自分の務めだ。
「レアチーズケーキ作ってあるよ、食べるか?」
「うん、食べる」
着替えて手を洗っておいで、と声をかける。三年生の鈴はテニス部をこの夏に引退し、これからは高校受験一色となる。
子どもたちが小学生のとき、中学受験させるかどうかを妻と話し合ったが、中高大と公立で過ごしてきた妻としては、中学までは公立に通ってほしいという希望があった。さまざまな家庭環境や経済環境で育ってきた子どもたちと一緒に過ごして、偏見のない人間になってもらいたいというのが、その理由だ。進も地方出身で大学までずっと公立校だったので、妻の意見には賛成だった。
鈴は、県内でいちばん偏差値の高い公立の進学校を狙っている。成績は一年生のときから、ほぼオール5をキープできている。これまで三度ほど社会科が4だったが、三年生になってからは5以外をとっていない。滑り止めの私立校を一校、その他有名大学付属校を二校受験する予定だ。
「パパ、これめっちゃおいしい!」
「だろ?」
「お店開けるよ」
「まあな」
進が真面目にうなずくと、鈴は「調子に乗ってる!」と言って声をあげて笑った。
「塾の前に、少し食べていくだろ」
「うん」
六時半から九時半まで塾だ。塾の前に食べていくと眠くなってしまう。でも、なにも食べないとお腹が空いて集中できないというので、たいていはおにぎりを一つ食べさせてから行かせている。
帰宅後は炭水化物は食べずに、野菜とタンパク質だけだ。太ることを気にしているらしい。ついこのあいだまで小さい女の子だったのに、あっという間にすっかり年頃の娘になってしまった。自分も歳をとるはずだと思う。
鈴は女の子なのに、まるで手のかからない子だった。勉強しろと言わなくても自ら予習をし、テスト前には自分で計画を立てて勉強をしていた。部屋もいつもきれいに整理整頓できている。高校受験も、なんの心配もないだろう。進は陰でサポートするだけだ。
鈴が出て行ったのと入れ違いに、蓮が帰ってきた。鈴の塾は駅前にあり、自転車での通塾だが、女の子なのであまり心配していない。
「おかえり、蓮くん」
蓮は美術部だ。ただいま、とつぶやくように言って、二階にそのままあがる。
「うがい手洗いしろよー」
まだまだ頼りなげな薄っぺらな背中に声をかける。蓮は三月生まれということもあるせいか、身長も体重も平均より下回る。小学生といっても、当たり前に通用するだろう。色白で、かわいらしい顔立ちをしているので、ときおり鈴が冗談ともつかない口調で、ジャニーズに入れたほうがいいよ、などと言う。
少ししてから、妻の
「おかえり、千鶴さん」
「ただいま、進さん」
千鶴は進の一つ年下だ。「兄さん旦那は金のわらじを履いてでも探せ」といわれるように、我々夫婦はとてもうまくいっていると進は感じている。
「すぐご飯できるから」
「ありがと。でも汗だくだから、先にささっとお風呂に入っちゃうわ」
「ささっ、じゃなく、ごゆっくりどうぞ」
あはは、と笑って千鶴は手をひらひらさせながら、風呂場に向かった。お風呂を沸かしておいて正解だった。
▶#1-7へつづく
◎全文は「小説 野性時代」第205号 2020年12月号でお楽しみいただけます!