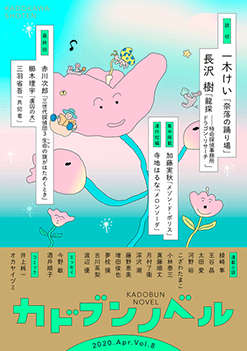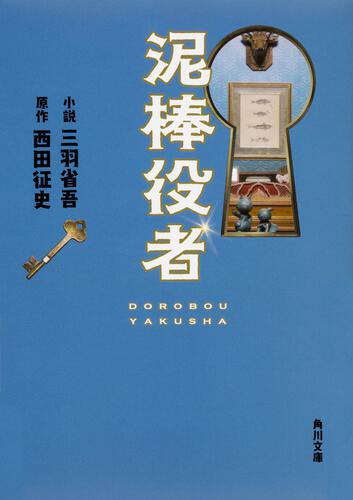死体遺棄事件の発端は、二十七年前の出来事だった――。報道の使命と家族の絆を巡るサスペンス・ミステリ。 三羽省吾「共犯者」#17-1
三羽省吾「共犯者」

※この記事は、期間限定公開です。
前回までのあらすじ
岐阜の死体遺棄事件を追っていた弱小週刊誌『真相 BAZOOKA』のエース記者・宮治和貴は、弟の夏樹が事件の被害者の実子であり、逃亡中である重要参考人・布村留美の兄であるという事実に辿り着く。宮治は、夏樹が殺人犯かもしれないと悩みつつも取材を続け、夏樹は布村を庇い、布村は息子の光を庇っているという結論に達する。事件を終結させるため、宮治は布村に向けた記事を書き、それがきっかけで布村は自殺を図るが、警察に保護された。
詳しくは 「この連載の一覧」
または 電子書籍「カドブンノベル」へ
七(承前)
夫妻の笑みには諦めの色が浮かんでいる。それに対して、恐らくは
幼い頃の生育環境を知らなかったとはいえ、娘がこんな事件を起こしてしまった以上、自分達の子育ては完全に失敗だった。
夫妻の笑みは、そういう意味だ。
謝るつもりだったのに、礼を言われてその機会を失った。そればかりか、罵倒されても仕方がないと覚悟して来たつもりだったのに、こんな悲しい表情にさせてしまった。
あなた方の育て方が間違っていたわけではない。声を大にしてそう訴えたかったが、宮治は感情的になりそうな気持ちを抑えて「裁判の話、少しいいですか?」と静かに語り掛けた。
夫妻は、布村
そして二人とも、これまで二度あった公判をいずれも傍聴していない。今後も、傍聴するつもりはないとのことだ。
被害者側の遺族は、施設に入っている
加えて、弁護人が言った言葉のせいでもある、と宮治は考えている。
夫妻は、布村留美が長年清掃を担当していた小さな法律事務所を通じて、優秀な女性弁護士を紹介して
女性弁護士は、殺人事件以外にDVやストーカー絡みの裁判経験も豊富だった。公判前整理手続きで、布村留美と宮治
「布村留美さんの判決に執行猶予が付く可能性は、ほぼ無いでしょう」
その優秀な弁護士は、正式に依頼を受ける際の条件として、そう明言したという。
そんなことがあって傍聴しないと決めたのなら、宮治もその判断を尊重したい。
だが、傍聴しなければ分からない事実もある。
「私は二度とも傍聴しています。これから先も、時間が許す限り傍聴するつもりです」
布村
「娘さんは警察の取調べの時点で〝しっかり罰を受けたい〟と言っていたそうなので、あの正直な弁護士のことを信頼しているのだと思います。それで、取調べでは言っていない──隠していたわけじゃなく、
宮治はそこで言葉を切り、冷めたほうじ茶に手を伸ばした。
上目遣いに
「光の小学校卒業を待つ、ということでしょうか?」
布村正雄が代表して訊ねた。これに宮治は「私もそれは考えました」と前置きし、説明を続けた。
未成年が法に触れる行為をした際、その取り扱いが大きく違ってくるのは犯行時十四歳以上である場合と、十八歳以上である場合だ。しかしたとえ十四歳未満であっても、いずれ補導されるなら一日でも早い方が本人の
また、彼女がすべて自分一人でやったことだと主張するつもりなら、それも一日でも早く出頭する方がいいに決まっている。
息子の小学校卒業は、出頭する前に見届けたいことと言えるかもしれない。だが宮治には、どうしてもそれだけとは思えなかった。
「留美さんは出生届も提出されていなかったので、正確な誕生日が分からず、こちらで正式に特別養子縁組が認められた十一月三十日を誕生日にしたそうですね」
我ながら回りくどい説明だと思いながらも、宮治は丁寧に言葉を選びながら話を続けた。
「その日は毎年ケーキでお祝いされ、クリスマスにはプレゼントを渡され、正月にはお年玉を貰う。そんな、普通の家庭に生まれ育った人々にとって当たり前の恒例行事も、彼女にとっては驚くべき経験だった」
温厚で我慢強い元県職員も、
「精神科医の先生に言わせれば、それもこれも、無駄な上書きだったということでしょう」
静かな、しかし確かに怒気のこもった声だった。
「それは違います。説明が足りず、申し訳ありません」
PTSDに根治はない。過去の記憶に上書きは出来ても、その下にある記憶を消去することは出来ない。
その女性弁護士が法廷に提出した精神科医の意見書は、確かにそういう内容だった。しかしそれには続きがあった。
「裁判には関係のないことと判断されたようで、検察側の異議によって記録には残されませんでした。でもその意見書には、こういう続きがあったんです。〝その上書きが素晴らしいものであればあるほど、それ以前の記憶を想起させるヒト・モノ・コトに出会った際、極端な拒絶反応を示す場合がある。本件は、その中でも特に極端な例と言えるかもしれない。逆に言えば、布村留美さんにはそれだけ、
宮治はそこで言葉を切り、湯飲みに手を伸ばした。上目遣いで夫妻を見ると、この話がどう三月に
「毎年の誕生日やクリスマスだけじゃありません。七五三、入学式、卒業式、成人式などは、
布村正雄が目を見開き、湯飲みを強く握り締めていた。薫の
来年の三月になにがあるのか、やっと思い当たったらしい。
「私が生まれ育った地域では一般的ではないので、ずっと気付きませんでした」
正雄が「十三
「そう、十三詣りです。五歳で引き取られ、完全に心を開くまで八年を要したということなのかもしれない。全国的とは言えない、地域によって知名度に差がある儀式だったので、より強く印象に残ったのかもしれない。理由はともかく、十三詣りは彼女にとって特別な経験だったようです。そして、来年の三月……」
宮治はそこで言葉を切り、布村夫妻の反応を待った。
「そうですか」
手にした湯飲みを見下ろしたまま、布村正雄が呟いた。
来年の三月、光の十三詣りが行なわれる。
宮治が調べたところによると、十三詣りは関西で古くから行なわれてきた行事だ。他にも行なわれている地域が点々と存在するが、それらは局地的で、規模も関西ほど大きくはない。富山県高岡市も近年では大きな寺が告知しているが、布村留美が十三歳を迎えた年、二十一年前は細々と行なわれていた筈だ。
かつては
「お詣りの中で住職から、ご両親に感謝しなさい、自分の言動に責任を持ちなさい、といった説法を聞くそうですね。普通の家庭に生まれ育った子には、当たり前過ぎてあくびが出るような内容かもしれない。でも留美さんの心には、その当たり前の話が深く届いた。自分が愛されているという実感を、改めて強く持った。だから実際にその目で見ることは
正雄は湯飲みを口に運んだが、空だった。中途半端な高さに湯飲みを止めたまま、視線がどこを見るでもなくさまよう。
薫の下瞼で、限界まで膨らんだ水滴がフルフルと震えていた。今にもこぼれ落ちそうだが、まだ奇跡的に
多分二人とも、二十年前の十三詣りのことを思い出しているのだ。
両親に感謝する、自分の言動に責任を持つ。普通なら聞き流してしまいそうなこれらの言葉を、布村留美は深く強く心に刻んだ。つまり彼女は十三詣りを境に、経済的な自立や社会的な立場よりも深遠な意味において、大人になるのだと静かに決意した。
宮治はそんなふうに思いつつ、同時に憤ってもいた。
十三詣りを境に大人になる。つまりそれ以前は子供だ。子供なら両親に感謝しなくてもいいし、自分の言動に責任を持たなくてもいい。布村留美が、そんなふうに解釈しているように思われてならないからだ。
だから、まだ子供である光の罪はすべて自分一人で引き受けるつもりだが、光の十三詣りだけは見届けたい。それまでは、なんとしても逃げ延びる。
それが逃亡の理由だったのだろうが、布村留美自身も気付いていた筈だ。彼女の望む通り、光が何事もなかったかのように十三詣りを迎えて大人になれば、両親に感謝し、自分の言動に責任を持つようになる。そうなれば、その瞬間に彼は自分の犯した罪の大きさに気付く筈だと。
しかし、それらのことを布村夫妻に伝えるべきでないことは、宮治も分かっていた。どれだけ憤ったところで、所詮は自分の頭の中の想像に過ぎない。
代わりに、二人に伝えておきたい言葉があった。
「こんな状況で不謹慎かもしれませんが、私はその時の彼女を祝福したい。来年三月の、光くんのことも」
正雄が深く息を吐き、
「ありがとう、宮治さん」
静かにそう呟いた。
その時、布村薫の瞳から、堤防が決壊したように涙がこぼれ落ちた。
▶#17-2へつづく
◎第 17 回全文は「カドブンノベル」2020年4月号でお楽しみいただけます!