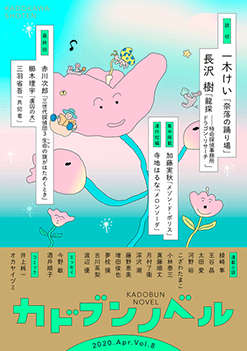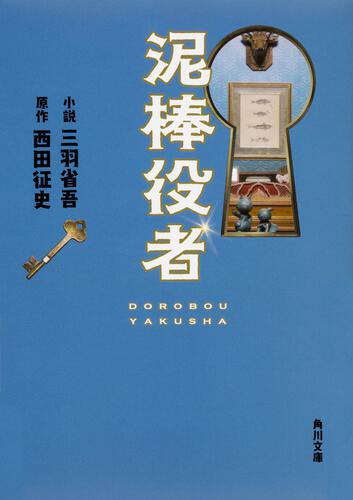死体遺棄事件の発端は、二十七年前の出来事だった――。報道の使命と家族の絆を巡るサスペンス・ミステリ。 三羽省吾「共犯者」#17-2
三羽省吾「共犯者」

※この記事は、期間限定公開です。
>>前話を読む
十二月。
「取り
彼が来ていることなどまったくの想定外だった宮治は、振り返ったもののなにも言えなかった。
この日、宮治夏樹に判決が言い渡された。罪状は犯人蔵匿及び隠避罪、判決は懲役一年六ヶ月、執行猶予三年。佐合優馬名義のカードの使用は、窃盗と詐欺、公務執行妨害に問われた。しかしカードを持ち去った布村留美が夏樹のコーポに預けていたこと、止められていることは承知で使ったことで、窃盗と詐欺には当たらないとされた。公務執行妨害の方も、夏樹のこの行為により捜査に支障は
「あの、色々とすみません。特にあの夜は、ありがとうございました」
やっと挨拶らしき言葉を発すると、可児は「なんやそれ」と笑いながら宮治の肩をポンと
「あんた、ちょっと瘦せたか?」
「いや、最近はあまり動いてないんで、むしろ少し太りました」
「ほうかい……まぁええ。時間あったら、ちょっとま付き合わんか」
宮治は実家の
「傍聴して頂き、ありがとうございました」
礼を言うのはおかしいと思いつつ、他に適当な言葉が見付からず、宮治は被告人の兄として頭を下げた。
「暇やったもんで、来ただけやて。それにしても、きょうだい
その「きょうだい」が宮治と夏樹ではなく、夏樹と布村留美を指していることはすぐに分かった。
夏樹は裁判の中で、布村留美が殺人死体遺棄事件の犯人だと知った上で、自らの判断で彼女を
布村留美も、殺意の有無を訊ねられ「いつの頃からか、もし実の両親が目の前に現れたら殺してしまうかもしれないと考えていた」と答えていた。
「当然どっちの裁判でも弁護側は止めたやろうに、言わな気が済まんかったみたいやの。どっちとも〝かもしれない〟っちゅうたのは、せめてそう加えるように弁護側が指示したんと違うか?」
布村留美の裁判では、彼女のこの発言が明確な殺意と解釈し得るか、彼女のような幼少期を経験すれば漠然と抱いていても不思議ではない感覚か、検察側と弁護側で今も論争になっている。
両方の裁判を傍聴して来た宮治も、答など永遠に出ないだろうと思いつつも、今でもずっと考えさせられている。
「監査、入ったわ」
たっぷり砂糖を入れたホットコーヒーを一口すすり、可児が唐突に話題を変えた。
岐阜県警が違法に入手したDNA型をデータベース化しているのではないか、という疑惑に関する話だった。
「正式な監査ですか? だったら、形だけ調査してお
「まぁ、そういうこっちゃろな」
警察庁が「監査です」と言って堂々と表玄関からやって来るということは、「大事にはしないから協力してくれ」という意思表示でもある。真に疑わしく、看過出来ない事態と判断すれば、まず潜入捜査員を送り込む筈だ。
「残念です」
宮治はコーヒーをブラックで飲んでいたが、一口目でその
「あの記事は、もう書かんのか?」
可児のその言葉に、宮治の舌は
DNA型データベースに関する疑惑の記事は、
「やるからには徹底的にやる。あんたは、そういうタイプの記者やと思うとったんやけどな。わしの勘違いか?」
「すみません。俺、今回のことで異動を命じられて、BAZOOKA編集部を外れたんですよ。今はファッション誌の編集者で」
可児は改めて宮治の服装を見て「そう言うたら、ビシッと背広やね」と口角を上げた。
金沢地裁でも富山地裁でも、宮治は傍聴する際は一応スーツを着ることにしている。しかし異動先はストリート・ファッション誌なので、今日の服装とは関係ない。
そのことを説明しようとしたが、やめておいた。口角だけ上げた可児の目が、まったく笑っていなかったからだ。
「あの疑惑、最前線にいる可児さんに言わせれば当たっていた。そういうことですか?」
「うん、まぁ、肯定も否定もせんとくわ」
「結構です……自分で書いておいてアレですけど、公に出来ない、つまり裁判で証拠として使えないとしても、被疑者を特定する為だけに使うのなら、県警が独自にDNA型データベースを蓄積することもアリだという声もあるようですが」
「たわけ、あかすか」
「え?」
可児は上着の内ポケットからショートホープを取り出しながら「すまん、口癖や」と謝った。
「三年……いや、もっと前からかな。わしらがなんぼ靴を
そんなことが繰り返しあり、公に出来ないDNA型データベースが存在する可能性については、可児ら末端の捜査員の間でも話題になっていた。
裁判で証拠として使えないにしても、まずは被疑者を特定し、その後で自白なり物証なり取ればいい。それで事件が早く解決するのなら、良いではないか。
可児の周りでは、そんな意見が大半だった。しかし可児は「たわけ、あかすか」と言い続けた。
「結局みな、目の前の仕事を手っ取り早く終わらせたいだけなんやて。違法捜査やとか倫理的に許されんとか、そんなご大層な理由と
可児の口から、ショートホープの煙と一緒に深い
もし被疑者特定のきっかけが、公に出来ないDNA型データベースであったことが明らかになれば、その捜査方法が問題になるだけでは済まされない。それ以降に得た自白や物証はもちろん、捜査自体がすべて無効になるかもしれない。可児はその可能性を恐れるとともに、とにかく仕事を楽に終わらせてしまいたいという同僚達の姿勢に憤っているのだ。
その気持ちを充分に理解しながら、しかし宮治は、ショートホープを挟んだ指で白髪頭を
「お力になれず、すみません」
カップを置き丁寧に頭を下げると、いつか捜査関係者に会う機会があれば訊ねてみたいことがあったのを思い出した。
「あの、一ついいでしょうか」
訊ねたかったのは、布村留美の現在の名前や住所、仕事のこと、離婚歴があり小学生の息子がいることなどを、佐合優馬がどのように知ったかということだ。
「あぁ、それな」
通常なら逮捕から起訴・送検までは二週間ほどだが、布村留美の場合は病院に搬送され、意識が戻り、自白をし、逮捕されるまでにプラス十二日を要した。可児も宮治と同じことが気になり、その一ヵ月弱を使って白川村の役場や児童相談所、児童養護施設『光の家』などを訪ね歩いた。
しかし結局は、誰が佐合優馬に情報を漏らしたかは分からなかった。
「まぁ、当然やお。佐合は得意の
「そうですか……」
「気になるんやったら、自分で調べたらええんと違うか?」
「えぇ、まぁ、そうなんですけど……」
そう答えながら、宮治は「ちょっと瘦せたか?」という可児の言葉を思い出した。
そうだ。
実際には少し太ったのに、瘦せたように見えたのだとしたら、ここ数ヵ月の宮治がずっと肩を落としているからだ。ひょっとしたら、顔にも生気がなくなっているのかもしれない。
この事件は終わった。それと同時に、事件記者としての自分も終わった。誰にもそんなことは言われていないのに、なんとなく自分でそう決め付けていたせいだろう。
可児の背後に見えるサイフォンが、ゴポゴポと音を立てていた。
「あの、可児さん」
「ん?」
異動になってから、BAZOOKA編集部では考えられないほど、時間に余裕があった。ホウオウ時代も
そのおかげで、
しかし沙知にも言われた。「大変だったのは分かるけど、なんか最近、あなたらしくない」と。
彼女の目にも、最近の宮治はやるべきことが見付からず、ぼんやりしているように見えるのだろう。
やるべきことが見付からないわけではなかった。薄々気付きながら、自ら気付かないふりをしていたのだ。
そう認めざるを得なかった。
「誰が佐合優馬に伝えてはならない情報を漏らしたかなんて、犯人探しをしたところで、しょうがないことなのかもしれない」
「まぁ、そういうことなんかな」
「けど、DNA型データベースの件は違う。俺、取材し直します」
可児は「ほぉ」と
「ファッション誌にそんな記事書いても、意味ないやろ」
そう言った。
「それでもやります、今回は」
「今回?」
「あ、いえ。とにかく、最後までやりますんで」
きっとホウオウを辞める原因となったあの件だって、そうだったのだ。担当を外されようが干されようが、個人的に取材を続けようと思えば出来た筈だ。
発表する場があるかないかは、後から考えればいいことなのだ。
鳥内
「〝たわけ、あかすか〟ですよ」
自らを鼓舞するように、可児の方言を
カップを口元で止めたまま、可児が再度「ほぉ」と呟く。
隠れて見えない可児の口元は、きっと笑っていた。
▶#17-3へつづく
◎第 17 回全文は「カドブンノベル」2020年4月号でお楽しみいただけます!