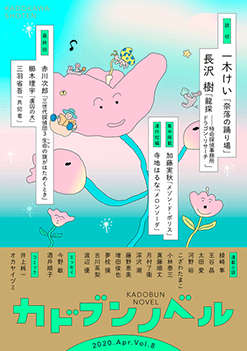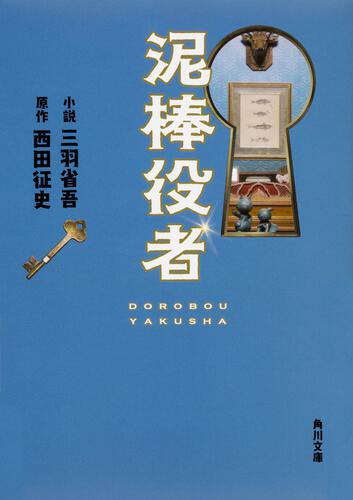死体遺棄事件の発端は、二十七年前の出来事だった――。報道の使命と家族の絆を巡るサスペンス・ミステリ。 三羽省吾「共犯者」#17-3
三羽省吾「共犯者」

※この記事は、期間限定公開です。
>>前話を読む
・
「よかった……ううん、ぜんぜんよくはないんだけど、でもあれ以上は誰も死ぬことはなかったんだし、やっぱり感想としては〝よかった~〟よね」
宮治夏樹に背中を向けたままそう言ったのは、
バケツ一杯のイワシを手際よく
夏樹に判決が下され、三ヵ月が
貯金が尽きたのは、三月に入ってすぐのことだった。
そして夏樹は今日、平塚の実家へ帰って来た。
そのことを結子は喜んでいるようだが、直接言葉にすることは避け、事件の決着に置き換えて「よかった」と繰り返しているようだ。
「お
階段の方から、沙知の声がした。
「あの部屋の本、全部居間と寝室に運んじゃっていいんですか? かなりの量ですよ」
かつて夏樹が寝起きしていた二階の部屋は、現在では弘貴の書庫になっている。その片付けをしていた沙知は、あまりの本の量に戸惑っていた。一冊ずつ本を運んでいる莉菜も「じいじ、本だらけ~」と文句を言っている。
タロウも手伝っているつもりのようで、二階の踊り場で「ウ~」と
夏樹はハッとして「ごめん、
「あとは自分でやるからもういいよ。莉菜ちゃんも、ありがとな」
居間の縁側で足の爪を切っていた弘貴が「夏、なにサボってるんだ」と怒り、ふと気付いたように傍らにいた
和貴はさっきからずっと、ノートPCを膝に置いてキーボードを叩いている。
「ってぇな、こっちは仕事してんだよ」
「仕事と家族、どっちが大事なんだ」
「その言葉、
「親に向かって〝あんた〟とはなんだ!」
二階に上がろうとした夏樹だったが、「まぁまぁ」と止めに入らなければならなかった。
土曜日の夕方だが、居間にも庭先にも
和貴は東京の賃貸マンションを引き払い、年明けすぐに平塚に引っ越していた。購入を検討する物件に適当なものはなく、結局新居は駅に近い賃貸マンションになった。転居後は毎週末、夕食を実家で食べているという。
床の間には、弘貴と結子が買った真新しい莉菜のランドセルが飾られていた。
莉菜が通う予定の小学校は、新居のマンションとこの実家の、ちょうど中間にある。
和貴も沙知も忙しい時は、莉菜は学校帰りに祖父母の家に寄って遊び、宿題をし、なんならそのまま泊まってもいい。既にそんな取り決めも出来ていた。
都心なら考えられないような恵まれた環境だ、と夏樹も思った。
「取り敢えず寝る場所だけ出来れば、充分だから。ホントにもういいよ、ありがとう」
夏樹のその言葉に、沙知も「そう?」と居間に運び込んだ書籍の整理に取り掛かった。莉菜もタロウと一緒に、後ろむきで一段ずつゆっくり階段を降りて来た。
「お義父さん、これ借りていい?」
「おう、沙知さんは旅行関係の仕事だったな。名所・旧跡の本なら、もっといいのがあった筈だぞ」
沙知と弘貴がそんな会話をし、
「和、あんたの古い雑誌や映画のパンフレット、少しずつでいいから持って行きなさい」
「え~、置かせといてくれよ。新居、そんなに広くないし」
「ウチは物置じゃないのよ。まったく、断捨離も出来やしない」
「え、終活?」
「断捨離って言ってるでしょ。あんたより長生きしてやる」
「マジっぽくて恐いよ……」
結子と和貴がそんな漫才みたいな会話をしながらの、
加圧鍋で骨まで食べられるようになったイワシの
だが、どうにも落ち着かない。
裁判中、弘貴と結子が
だがやはり夏樹としては、今日改めて和貴夫妻もいる場で謝るべきだと思っていた。
しかし、そのタイミングを与えないという意図でもあるかのように、六人と一匹の夕食は賑やかに進む。
午後八時。たまに事件や裁判以外の話題を振られ、適当に返していたら、夕食は終わってしまった。
弘貴は二階から下ろされた本をパラパラめくり、和貴は缶ビール片手にPCに向かい、結子と沙知は洗い物と風呂の準備に取り掛かった。莉菜はテレビで
「リンゴむいたよ~」
沙知が皿に山盛りのリンゴを持って来たが、弘貴も和貴も莉菜も、本とPCとテレビから目を離さずに「おう」「うん」「ん~」と曖昧に答えただけだった。
読むでもなく新聞を広げていた夏樹がリンゴを一口かじると、タロウが鼻をヒクヒクさせながら近付いて来た。夏樹は「食べるか?」と差し出したが、タロウは匂いだけ嗅いでプイと顔を背けた。
だが、タロウはそのまま夏樹の側に居て、あぐらをかいた膝に顎を乗せた。よく弘貴の膝でやっている、完全に
「莉菜~、お風呂入るよ~」
「え~、まだ八時半だよ~」
「小学校に入ったら、規則正しく生活するって約束でしょ。来月はもう一年生だよ」
「はぁ~い」
莉菜がテレビを消し、沙知と一緒に浴室へ向かった。莉菜と入れ替わりに、結子がポットとグラス、自家製梅干しが入った小皿を手に、居間にやって来た。
「はい、お湯割りの人はどうぞ」
弘貴が老眼鏡を外して「おう」と答え、和貴も「サンキュ」と言ってノートPCを閉じた。
「夏も
そう言って、和貴が三人分の焼酎お湯割りを作った。
「和、私にも薄いの作ってくれる?」
「お、珍しいじゃん。今更、キッチンドランカーか?」
結子は「うるさい」と言いながら、和貴の隣に座った。
四人で改めて乾杯をすると、結子が微かな笑い声を立てた。
「タロ、あんた珍しいわね。そんなに夏のことが気になる?」
タロウは首を上げて結子に視線を向けたが、またすぐに夏樹の膝に顎を乗せた。
「和、この間はあんただったけど、今日はさすがに負けね」
「あぁ、あの日は特別だったみたいだ」
砂糖や蜂蜜を使わない宮治家の梅干しは、塩分濃度が高い。梅を
「食べ物はもちろんだけど、傷や病気にもにおいがあるみたいでね。タロちゃんはそれを感じると〝大丈夫?〟って、側に寄ってくの」
「俺、
「あら、そう? だったら、傷や病気だけじゃなくて、悲しみにもにおいがあるんじゃないかしら?」
夏樹の膝に顎を乗せたまま、タロウがクルンとした
タロウの頭にそっと手を置き、夏樹は「ごめん……」と呟いた。
「
気を利かせて席を外してくれた沙知にも、子供心になんとなく変な雰囲気であると感じつつなにも言わなかった莉菜にも、感謝の意を込めての「ごめん」だった。
「なんの〝ごめん〟よ、馬鹿馬鹿しい。こんなこと、大きな声では言えませんけどね、私は夏が間違ったことをしたとは思ってませんよ。もしご近所さんが〝あそこは犯罪者を出した家だ〟とか言って付き合ってくれなくなるなら、私はそれでいいと思ってますからね」
威勢のいい言葉とは裏腹に、結子は
「それにね……」
更に言葉を継ごうとする結子を、ずっと黙っていた弘貴が「よさんか」と止めた。そして、
「まずは目前の問題だ。夏、仕事はどうするつもりだ」
マドラーで梅を潰しながら、訊ねた。
「うん、まぁ、近いうちにハローワークに登録して教職系を探そうと思ってるけど、ちょっと難しいかもしれない」
「だろう。だったら、郡司に頼ってみたらどうだ」
「郡司さんって、自称板前のサーファーだったよな。俺、料理なんか出来ないけど」
「あいつ、顔だけは広いんだ。市場であまり力を必要としない仕事を、探してくれている」
夏樹の口から無意識に「え?」という音が漏れた。すると弘貴は先回りするように「俺が頼んだわけじゃない。あいつが勝手に、探してるんだ」と言った。
夏樹は
長い沈黙が続いた。
浴室から、はしゃいでいる莉菜の声が聞こえる。
お湯割りとは抜群に相性が悪そうなリンゴをかじり、和貴がじっとこちらを見詰めていた。
その視線に気付きながら、夏樹はなにも言えない。ただ黙って、タロウの首筋を
莉菜の声が大きくなり、二人が浴室から洗面室に出たことが分かった。その時、
「来週、どうする?」
和貴が、唐突に訊ねた。
意味が分からず夏樹が顔を上げると、弘貴と結子も和貴に目を向けていた。二人にも、どういう意味か分からなかったらしい。
「来週の土曜だぞ。高岡の十三詣り」
弘貴が「なんだ、それは」と訊ね、結子は「じゅうさんまいり?」と首を
二人の問い掛けは無視し、和貴は「分かってるんだろ、夏」と訊ねた。
「うん、行きたい……けど……」
やっとの思いでそう答えると、即座に「行けよ」と返って来た。
二週間ほど前、布村留美には懲役八年九ヶ月の実刑判決が言い渡されていた。
罪状が殺人死体遺棄なら、最短でも十五年から二十年の筈だった。しかし布村留美の場合、その殺人の部分が過剰防衛による傷害致死だと判断された。
「早ければ、六年から七年で仮出所出来るよ」
和貴のその言葉に、夏樹は「うん、それはよかったけど……」と答えた。
「出て来る頃は、光くんの成人式だな」
「あぁ、そうなるな」
「布村留美……樹理亜の代わりに、十三詣りを見届けろよ。行くべき、と言うか、お前には見届ける責任があるんじゃないのか?」
タロウが「クゥ~ン」と鳴き、夏樹を見上げていた。
夏樹はお湯割りをゆっくりと吞んでから、「そうなんだろうな」と呟いた。
▶#17-4へつづく
◎第 17 回全文は「カドブンノベル」2020年4月号でお楽しみいただけます!