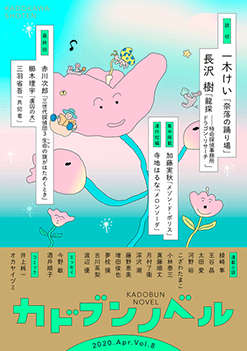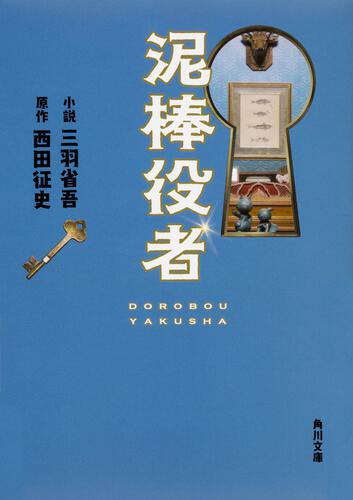死体遺棄事件の発端は、二十七年前の出来事だった――。報道の使命と家族の絆を巡るサスペンス・ミステリ。 三羽省吾「共犯者」#17-4
三羽省吾「共犯者」

※この記事は、期間限定公開です。
>>前話を読む
三月某日。
富山県高岡市の
古式に
だが
二十一年前、樹理亜もここで参拝した。どんな服装だったのだろう。振り袖だろうか、小袖だろうか、中学校の制服だろうか。
そんなことを思いながら、夏樹は門前から晴れ着姿の少年少女達を見詰めた。
「俺は遠慮しとくよ。コレもやりてぇし」
和貴はそう言うと、
和貴が「十三詣りに、弟を連れてお邪魔してもいいでしょうか?」と布村夫妻に伺いの電話を掛けたのは、平塚の実家で夕食を共にした日の翌朝だった。
夫妻から了承の電話があったのは、その二日後のことだ。和貴が言うには『是非』とか『喜んで』という言葉があったそうだが、二日という時間は、光に考えさせる時間だったのだろう。
この寺に来る前、夏樹は和貴に連れられて布村家を訪ねた。布村夫妻は「やっとお会い出来ました」と、歓待してくれた。光は参拝の列に並ばなければならないとかで、先に一人で出掛けており、自宅では会えなかった。
「参拝を終えた後で、改めてご紹介しますんで」
布村夫妻にそう言われ、夏樹は和貴とともに寺にやって来た。
参拝者は、ざっと見て二十人以上いる。それぞれに両親や祖父母が同伴しており、決して広いとは言えない境内は賑やかを通り越して騒々しかった。
布村夫妻によると、光は参拝を待つ列の最後尾近くに並んでいるとのことだ。本堂で受付を済ませ、好きな漢字を書いた半紙を奉納し、五人ほどを一組として経と説法を聞き、
その一時間、夏樹は
一通り済ませた少年少女が「やれやれ」という表情を浮かべて、それぞれの家族の元へ向かう。一八〇センチを超えた子、派手な化粧をした子もいれば、まだまだ小学四年生くらいにしか見えない子もいる。
夏樹はそんな少年少女の中から、まだ会ったことのない光を探そうとした。
樹理亜に似た顔は見当たらない。
だが夏樹は、一人の少年を見て「彼だ」と確信した。
思っていた通り、その少年は手洗い場近くにいた布村夫妻の元へ向かった。少年の唇が「ありがとう」と動き、夫妻のそれは「おめでとう」「これからが大変だぞ」と動く。
鐘撞堂からの距離、約十五メートル。夏樹は人込みをかき分けながら、その十五メートルを一歩一歩、これまでの来し方を踏みしめるように歩いた。
「あ、夏樹さん」
布村薫が気付き、手招きをした。
布村正雄は少し神妙な顔をして「なぁ、光」と、詰め襟を着た少年の両肩に手を置いた。
「ご挨拶しなさい」
光少年は、戸惑っているようだった。
「ねぇ、光」
薫が優しく声を掛けるが、光は
その反応を見て、夏樹は気付いた。布村夫妻は、光に母親の兄が来ることを伝えていないか、伝えたものの会うことを拒否されたのだ。返事をするまでに掛かった二日間は、夫妻が悩みに悩んだ時間だったに違いない。
そりゃそうだよ、戸惑って当然だよ。
そんなふうに思う夏樹もまた、戸惑っていた。
布村光は、驚くほど疋田
隔世遺伝とは言うけれど、肉体的な近似性は一代置きだとは言うけれど、それにしても残酷な話だ。
そう思わざるを得なかった。
光を育てながら、日に日に疋田亮二に似ていくその外見を見ながら、樹理亜はなにを思い、なにを感じ続けていたのだろう……。
「おめでとう」
しかし夏樹は、己の個人的な感情などどうでもいいと思い、光にそう声を掛けた。
「初めまして。僕は君のお母さんの兄、つまり君の伯父さんです」
疋田亮二によく似た目が、ハッと見開かれた。
布村夫妻が、光と夏樹を見詰めていた。
「さぁ、お祝いしましょう。一席、ご用意してますんで」
「あれ、宮治さんは? 変な気ぃを使いんなさって、もう」
布村夫妻が言い、夏樹はスマホを取り出して和貴に電話をした。
「光くんにとって、俺も一応は伯父になるのかな?」
和貴がそんなふうに言いながら、ふと気付いたように「
五人で、高岡駅近くの料亭でお祝いをしていた。
主役である光は、チビチビ煮魚や天ぷらを口に運んでいた。まだ慣れなくて苦しいのだろう、詰め襟の制服は第二ボタンまで外されている。
「制服が決まってるってことは、進学する中学は決まっているんだよね」「部活はまだ決めてないの? 恵まれた体格をしてるんだから、なにかスポーツはすべきだよ」「え、足もレフティー? なら、個人的には是非サッカーをやって欲しいな」「今日はお父さん、お仕事?」
酒も入っていないくせに和貴は不自然なくらい雄弁で、その内容は主に光への質問だった。光は小さな声で答え、YES・NOで答えられない質問には、布村夫妻が代わって答える。
坪内
坪内は自分が光を引き取り、姓も坪内に戻すべきだと言ったが、結局、光は布村姓のままで祖父母の家で生活を続けることになった。
進学先は、以前通っていた小学校と同じ学区の公立の中学校だ。なにも隠さず、以前の同級生達と中学校生活を送ることになる。
これらは光本人の意志で決めたことで、坪内も「本人が決めたのなら」と、その考えを尊重した。
自転車通学で片道一時間ほど掛かることや、他の生徒達の中に心ない言葉を浴びせる者がいる可能性については、布村夫妻と坪内が学校側と何度も話し合い、なにか問題が起きた時は夫妻と坪内で対処すると約束した。
「あの
光の反応があまりに鈍いせいか、和貴はウーロン茶を飲みながら布村夫妻を質問攻めにし始めた。
その間も夏樹はまだ、驚くほど疋田亮二に似た光の顔を見詰めていた。
その席で主役の一人が、『舞』と書かれた半紙を「じゃ~ん」と披露した。もう一人も
親族の会話によると、『舞』の字を書いた子はダンスを習っているようだった。もう一人は「令和初の十三詣りだし、ウケるかなと思って」と笑っている。
「そう言えば」
衝立越しに隣をチラリと見た和貴が、久々に光に水を向けた。
「十三詣りって、半紙に好きな漢字を書いて奉納するんだよね。京都辺りじゃそのままお
光は無言で上着のポケットに手を突っ込み、小さく畳まれた紙片を取り出した。広げられた半紙には『光』と書かれていた。
やや右肩上がりの癖のある筆跡で、決して達筆とは言えないものの、太く伸びやかで、止めも払いも跳ねも力強さが感じられる。
だが、全体的に小さい。半紙の中央やや右寄りに、決してはみ出さないことだけに腐心して、その中で出来る限り暴れようとしている。
夏樹の目には、そんなふうに見えた。
「色々と考えてたようやけど、結局は自分の名前にしたそうです」
無言の光に代わって、布村正雄が説明した。
「まぁ、無難な字ぃと言えば『絆』やとか『縁』やとか『志』やとか、なんぼでもあるのにねぇ」
布村薫も、補足するように言う。
和貴は「とてもいい字だと思います」と、大きく頷いた。そして、無表情のまま半紙を畳もうとする光に「ごめん、ちょっと貸して」と手を伸ばした。
数十秒、改めてその『光』という字を見詰め、和貴は「いい字……って言うか、すごくいい名前だ」と呟いて半紙を光に返そうとした。
「ちょっと、ごめん」
無意識だった。
気付いたら夏樹は和貴の手を止め、半紙を手にしていた。
和貴よりもずっと長い時間、夏樹はその一字を見詰めた。
隣の座敷は、退屈したらしい幼い弟がワーキャーと騒ぎ出し、別種の賑やかさになっていた。
「お、なんだよ夏。教員目線でなにか言いたいのか?」
茶化すような口調で和貴が言った。
「こいつね、今は無職透明なんですけど、元々は高校の非常勤講師とか塾の講師をやってたんですよ。俺と違って、お勉強も出来るタイプで」
布村夫妻と光にも、そんなふうに説明をする。
それを和貴らしい気の遣い方だと分かりつつ、しかし夏樹は自分を止めることが出来なかった。
「書くべき漢字が見付からないわけじゃない」
和貴が「え?」と言い、数秒後に布村夫妻も「え?」と揃って首を
「ただ、書いちゃいけない漢字がいくらでも思い付くだけだ。『絆』や『縁』はもちろん『志』『感謝』『友情』なんかも、光くんにとってはなんだか白々しい。ましてや『家族』なんて、書ける筈もないよな」
和貴が「おい、夏」と止めようとした。なにを言おうとしているのか、分かっているらしい。
さすが和兄だ、と夏樹は思う。思いながら、だがやはり自分を止められなかった。
「光くん。いま君に見えてるものは、幻じゃないんだぞ」
大人三人が夏樹の言葉に
「児相の人に、聞いた」
かみ過ぎて先端が潰れてしまった爪楊枝を、お造りのツマの上に放り投げ、光が言った。自ら口を開くのは、初めてのことだった。
「僕と母さんが殺したあの人……」
布村薫が「やめなさい、光!」と叫んだが、すぐに布村正雄が「おい」と止めた。光は「ごめん、
十四歳未満の光は警察に身柄を確保されることはなく、児童相談所で事件に関することを聞かれた。その中で、死んだあの男が母の実の父、つまり自分の血縁上の祖父であったことを知った。
「そんなに驚かなかったし、悲しくもなかった。正直それがなに? って感じだった。なにしろその存在自体、知らなかった人だし」
隣の座敷では、弟くんのグズり方が激しくなったのをきっかけに、全員が「帰ろう帰ろう」「他で吞み直そう」などと騒々しくわめきながら席を立った。
その騒動が収まるのを待ってから、光が「だらちん」と呟いた。
布村薫がはっとして光を見詰め、正雄はなにか言い掛けたものの口を
「やめろよ」
二人の反応を見て、夏樹が言った。
俯いていた少年が、上目遣いで夏樹を見た。口元が
「自分以外を〝馬鹿〟で
歪んだままの口から「はぁ?」と、大人を小馬鹿にする時の定番の音が出た。
「不幸な生い立ちを持つ者は、少々のことをやっても許されるという意味で、普通に生まれ育った人達より優位な立場にある。君は、そんなふうに勘違いしてるんじゃないのか」
「決め付けんでよ。初対面の人に、そんなこと言われたくない」
更に言葉を継ごうとした夏樹だったが、布村薫に「ごめんなさい、夏樹さん」と止められた。
隣の座敷に、新たな団体客が入って来た。今度は、一三〇キロはありそうな巨漢の少年を囲む集団だった。
少年以外も全員、
「光も、ごめんね」
布村薫が涙声で言い、
「お前が謝ることはない」
布村正雄がそれを止めた。
夏樹が「すみません、こんなめでたい筈の席で」と謝ったが、これには布村夫妻も和貴も、なにも言わなかった。
だが、
「こちらこそ、その、すみませんでした」
光が、外していたボタンを上まではめ直して、深々と頭を下げた。
▶#17-5へつづく
◎第 17 回全文は「カドブンノベル」2020年4月号でお楽しみいただけます!