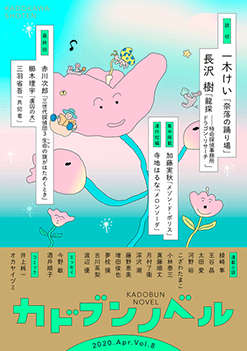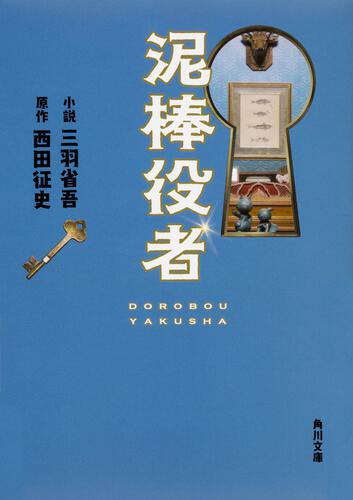死体遺棄事件の発端は、二十七年前の出来事だった――。報道の使命と家族の絆を巡るサスペンス・ミステリ。 三羽省吾「共犯者」#17-5
三羽省吾「共犯者」

※この記事は、期間限定公開です。
>>前話を読む
「最悪だ。これ以上の最悪、見たこともねぇ」
料亭を出て光達と別れると、和貴が何度も溜め息を
「今後もなんとか布村家と繫がりを持ちたいと、俺は思ってたんだ。布村留美の為でも、お前の為でもない。あの布村光の為にだ」
地雷を踏まないように注意深く話題を選んでいたのに、夏樹はどこに埋まっているのか分かっていながら、それらすべてを踏みまくった。
和貴はそう言って、夏樹を責めた。
SUVを
「ごめん。でも……」
「デモもストもねぇよ」
まだ午後二時過ぎで日もしっかりと高いのに、そんなやり取りは、なんだか吞んだくれたサラリーマンのようでもある。
「俺と樹理亜の刑が確定したことで、事件は終わった。でも俺は、むしろ始まりだと思ってる」
「なんだよ、関係ない話をするなよ」
「関係なくない。俺だって、光のことを第一に考えてるってことだよ。こういうことに終わりはないんだ。俺と樹理亜も優しい養父母に恵まれたからといって、それ以前がなかったことにはならなかった。それと一緒だ」
和貴は、やけにゆっくりとした動きで熱い缶コーヒーをアスファルトの上に置き、「聞こうか」と言った。
「和兄にも聞こえたよな。隣の客が帰った後、光が〝だらちん〟て言ったの。あれ、こっちの言葉で〝馬鹿〟って意味だ」
「まぁ、ニュアンスとしては分かったよ。だからなんだ。騒々しかったし、つい口にした言葉だろう」
「俺が気になったのは、光というより布村夫妻の反応だ。ああいう言葉を口にしたら、大人は
夏樹が思うに、夫妻のあの反応は今日に限ったことではない。何度か似たような状況があり──ひょっとしたらそれは、事件後に始まったことかもしれない──夫妻は黙ってしまうことが、その場をしのぐのに得策だと、間違った判断をしてしまったのではないか。
「なんで、そんなことを言い切れるんだ」
「他者に対して歪んだ優位性を持ってるって感覚は、俺にもあったから」
「え?」
「いや、俺の場合は口にも態度にも出すことはなかった。だけど、確かにそういう感覚は持ってたんだよ」
口に運び掛けていた缶コーヒーを中途半端な高さで止め、和貴が夏樹の横顔を見詰めていた。彼にとっては、思ってもいなかったことのようだ。
その視線を感じながら、夏樹は「いや、まぁ……」と照れたように首を振った。
「布村夫妻を否定はしないよ。あの人達は、光には絶対に必要だ。けどね、光の周りに物分かりのいい大人が増えるだけなら、俺達が彼の人生に関わる必要なんかない。俺はそう思う。それにね……」
光が夏樹に対して、あんな反抗的な態度を取ったのは、あの席で夏樹が唯一の血縁上の縁者だと分かったからだ。本人は意識的にそうしたわけではないかもしれないが、血縁のある者に過剰な拒絶反応を示すことは──自分には幸か不幸か一度もその機会がなかったが──感覚的には分かるような気がする。
「いや、しかし」
「うん、そうなんだ」
夏樹と布村留美は、血縁上のきょうだいではなかった。光とも、実際は赤の他人だ。つまり今日、光の十三詣りの祝宴に集った五人は、誰一人として血縁上の繫がりがない。
ブロックから腰を上げ、和貴はまるで気付いていなかったかのように「そうか……そうだな……」と呟いた。
夏樹も腰を上げ、空き缶を自販機横のゴミ箱に捨てに行った。
「でもね、俺、今日は来て良かったと思ってる」
少し遅れて空き缶を捨てに行った和貴の背中に、夏樹はやや声を張って言った。
まだ三月中旬。高岡市街地のコインパーキングには、思い出したように乾いた寒風が吹き抜ける。
「やっぱ、和兄は
「え? 俺のなにが?」
「ほら……」
料亭を出て光達と別れる直前、和貴は光にこう言った。
「今度、平塚にも遊びに来いよ。あ、お祖父さんとお
その言葉に、布村夫妻は深々と頭を下げた。光は形だけ頭を下げていた。
和貴は口元を歪め「あんなのは挨拶みたいなもんで、たいした意味はねぇよ」と言った。
そうかもしれない、と夏樹は思う。
同時に、だがしかし、とも思っていた。
たいした意味はない挨拶みたいな言葉が、その後の人生を左右することもある。自分や樹理亜、そして恐らく光のような人間には。
夏樹にとってそれは、弘貴の説教や結子の小言、和貴や郡司や鳥内のちょっとした悪い遊びへの誘いの言葉だったりした。樹理亜にとっては、十三詣りで聞いた住職の「ご両親に感謝しなさい」「自分の言動に責任を持ちなさい」という言葉だったかもしれない。
心の中では「お前に俺のなにが分かる」と他人を馬鹿にしながら、その思いを口にも態度にも出さずに育ったのは、きっとそれらの言葉があったからだ。
やがて成長し、他人に向けられた「お前に俺のなにが分かる」という思いは、そのまま自分に返って来た。「俺に彼らのなにが分かる」と。養父母や兄、鳥内や配島や郡司が、どのような思いで自分に接してくれていたのか分からない、分かろうともしていないではないかと。
ある日突然ではない。徐々に徐々に、そんなふうに考えるようになった気がする。
七月まで、あと四ヵ月。
その間、光がどのような中学生活を送るのかは分からない。
けれど夏樹は、一学期の期末試験を目前にした忙しい時期に、彼がフラリと平塚へ遊びに来るような気がしてならなかった。
「来るよ、光は」
「どこから来るんだよ、お前のその自信は」
和貴が
「さぁ、幸さんが待ってる。行こうか」
「あぁ、そうだったな」
「けど明日のこともあるから、今夜は早いとこ切り上げて寝ようぜ」
「うん、悪いな」
「家族に謝るんじゃねぇよ」
今夜は、富山市内で鳥内幸次郎に会う予定だった。
その後、二人でビジネスホテルに泊まり、明日朝は夏樹一人で布村留美に面会する予定だ。
SUVの助手席に乗り込む直前、夏樹は誰かに呼び止められたような気がして、辺りを見回した。
なんの変哲もない、かつてテナントビルかなにかが建っていたであろう、市街地にポッカリと空いたコインパーキングだった。
人と人は、完全に分かり合うことはない。血縁があろうとも、戸籍上の家族であろうとも、どれだけ親しい知人や友人であろうとも、一〇〇パーセント分かり合うことは出来ない。
だが、だからこそ、人は自分にとって大切な人のことを分かろうとする。
そこには、血縁も戸籍も介在しない。
いま布村光に必要なのは、彼のことを分かろうとする人間の存在だ。あの優しい布村夫妻のように、彼のすべてを肯定するような存在のほかに、時には彼を強く否定するような……。
春の気配はまだ遠い、北陸の三月。
七月。この立山連峰の雪が頂辺りに僅かに残るだけになった頃、もし光が平塚に来られないなら、こちらから来てもいい。
「どうした、行くぞ」
「あぁ」
白い
了
※本作は単行本として小社より刊行予定です。
◎第 17 回全文は「カドブンノベル」2020年4月号でお楽しみいただけます!