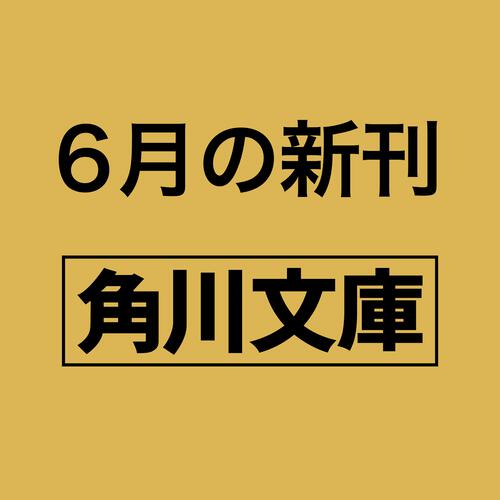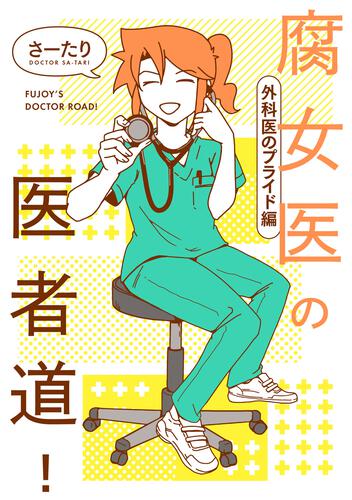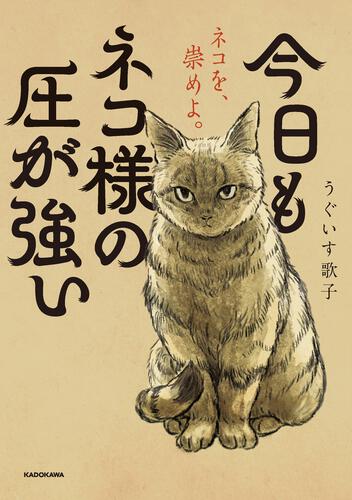米澤穂信『黒牢城』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!
米澤穂信『黒牢城』文庫巻末解説
解説 ジャンルを超える知的浸透圧、その底力について
マライ・メントライン(ドイツ公共放送プロデューサー)
『黒牢城』に接したのは、書評家の杉江松恋氏とクイック・ジャパンウェブで行う「直木賞全候補作読んで受賞予想」のときだった。いくら日本語が達者とはいえ私はガイジンさんである。正直なところ「時代物」系の小説は苦手だ。文体・用語に独特のクセがあったり、マニアックな史実を知らないと充分に楽しめなかったりしがちだからだ。でも最近の直木賞候補って、なぜか必ず時代物が入ってるんだよなぁと、本作についても正直、読み始めはあまり前向きな気分ではなかった……のだが!
まず、ページを眺めると確かに漢字密度が高くてザ・時代劇な雰囲気なのに、なぜか読みやすい。リズム感が良く、見かけ以上に意味と背景を汲み取りやすい文章なのだ。著者が意図しているかどうかは不明だが、これは背景知識を持たない、あるいは薄い読者にとって凄い推進力になる。実にありがたい。しかも読むほどに、進むほどにオモシロイ。いや、オモシロさが加速する。読む傍らで「荒木村重」「有岡城」などを検索して背景知識を得るのもまったく苦ではない。作中、思いっきり大胆に『羊たちの沈黙』のオマージュパロディを(シリアスタッチで)盛り込んでしまう遊び心も素晴らしい。な、なんなんだこれは……!? と怒濤のごとく読みふける。まさに作品世界との圧巻の接続体験。そしてその勢いゆえというべきか、実際のところ『黒牢城』についての端的なインプレッションとしては、読んだ直後、杉江松恋氏との対談で自ら述べた以下の言葉以上のものは出てこない。
今回のイチオシ作品です。ミステリと思想・軍事の融合小説としてもピカイチでしょう。歴史的知識がさほどなくても話の骨格だけで読めてしまう言霊力があります。また、読み進むにつれて内容が拡大深化することに驚かされます。スペック紹介は「包囲下の城で続発する難事件を描く連作短編」とミステリー文脈に沿ったものになっていますが、それだけではない。最初のエピソードこそ単なる不可能殺人ぽい感触ですけど、次第に戦術→戦略→政治→哲学レベルへと底なしに緻密な深みとおもしろ味を増していきます。それゆえに王道のエンディングも実に効く。
読み終えたとき、脳内で万雷の拍手が轟いたのをよく覚えている。ていうか読書人たるもの、ここで拍手しないでどうするよ。
本作は、その独特の読みやすさを根拠に他の時代小説よりも価値が高い、などと不遜なことを言うつもりは毛頭ないが、やはりこの美点は内容の「一般論化」による知的効果とリンクしているように思う。特に物語の後段、戦国乱世の「権謀術数」「サバイバル」「価値観の食い合い」「カルトの台頭」といった要素が複合的に展開して、登場人物を、というか作品世界を深く侵蝕してゆく場面で実感できるだろう。その絵巻的情景には、単に戦国の史的要素の再構築というにはとどまらないイメージ誘発力がある。ありていにいえば私は、近現代のイデオロギー戦争の多面的な力学をまざまざと想起させられていた。これはおそらく、読者が自らの知識を意図的に眼前の読書に結びつけた結果ではない。作品の筆致が普遍的な知性に接しているため、深くひそかに連関する情報どうしの関係が活性化するのだ。実に興味深い。
そうやって蓄積したエネルギーが最大の劇的効果をもって炸裂するのが有岡城内で展開するクライマックス場面であり、ここで本作はミステリでありながら、ある意味ミステリを超越してゆく。
ときに私は、ミステリが好きであっても、そのジャンルのお約束めいた点に一種の知的ポテンシャルの縛りを感じていた。根本的には小説ではなくパズルを起源とするのではないか、的な。しかしそれは「エンタメ」として市場形成するのに必要なリミッターなのだろう、と自分を納得させていた面がある。
この葛藤を明快に暴く傑作描写が、2011年に翻訳ミステリランキング三冠を成し遂げた(ということはつまり、ドイツの天才作家シーラッハの『犯罪』による三冠を阻止しよった)デイヴィッド・ゴードンの長篇『二流小説家』の結末付近に存在する。
推理小説を書くにあたっていちばん厄介なのは、虚構の世界が現実ほどの謎に満ちてはいないという点にある。(中略)だからこそ、ぼくは大半の推理小説に落胆してしまうのだろう。そこに示される解答が、みずから蒔いた途方もない疑問に答えているとはとうてい思えないからだ。
好き嫌いはあるだろうけど、じつに至言である。
この強力な言霊が、まさか『黒牢城』で見事に崩されるとは。
『黒牢城』のクライマックスは、実は古典的な演出だ。テレビのサスペンスドラマ的といってもいい。主人公と真犯人が一室で対峙し、真犯人が長広舌を振るうという例のアレである。「断崖絶壁で犯人に逆襲されてピンチに陥るヒロイン」と同様、現実でそんな展開ゼッタイ無いでしょというツッコミを誘いがちな、どちらかといえばダサいお約束シーン……となるはずだが本作の場合、まるで感触が違うのだ。
主人公はそこで、「真の道理とは何か。それは真の救済と両立し得るのか」「恐怖を突き詰めるとどこに行きつくのか」「その中で自らが拠って立つ伝統的価値観、特にマチズモはどこまで正当性を維持できるのか」といった因果律の問題を極限まで突きつけられる。特に、ホロコーストをめぐる議論でもしばしば語られる「理不尽な極限の暴力から生還してしまった人間は何を信じればよいのか」という問いが持つ観念的威力は絶大で、密室というシチュエーションにありがちな不自然さはまったくない。そしてさらに恐るべきは、それまでの各章で発生した「大小さまざまの怪事件」の真相が、すべて主人公の人間的座標を深く問う心理的凶器として機能し、人類史的宿業としての権力マチズモを少しずつ削いで切り刻んでゆく情景だ。ここにはまさに、自ら蒔いた疑問をはるかに超える途方もない解答が展開している。落ち着いた筆致ではあるが鬼気迫る、無限の闇を湛えながら「道理」の矛盾が主人公と読者に迫る。デイヴィッド・ゴードンも納得であろう。凄いぞ米澤穂信すごすぎる!
日本の戦国末期という舞台設定でありながら、その疑似宗教性と疑似哲学性から発する強大な倫理の倒錯は例えば、東欧・ソ連に侵攻したナチスドイツの「観念を現実よりも優先させる」世界改変の信念にもとづく殺戮や、中世フランスのカタリ派異端討伐の凄惨さ、シトー会修道院長アルノー・アマルリックの「異端派信者も正統派信者も皆殺しにせよ。死後、神が正統派信者だけを天国に送ってくれるから問題なし!」といった異様かつリアルな価値基準と、ダイレクトにつながっている。
そのように狂った世界に対抗しうるのは、果たして「正気の」救済思想なのか?
あの告発のクライマックスで、私は読みながら、NHKスペシャル『映像の世紀』のビジュアルとサウンドを自然に脳内再生していた。実は主人公も、私とともにスターリンの恐怖支配、ヒトラーの怒号、文化大革命、ホロコースト、ベトナムの村落に投下されるナパーム弾、原爆の惨禍などを、朧にも視てしまったのかもしれない。時代と国境を越えて果てしなく続く、真摯で狂った偽りの向上思想による「地獄」のヴィジョンの圧倒的な連なりを。
彼のその後の人生行路からして、それは何かふさわしいことのように思えてしまう。
そんなわけで(いやそれだけではなく黒田官兵衛の大仕掛け等もあるけれど)本作は、通例「ミステリの守備範囲」とされる領域をはるかに超えて世界と人間の本質と宿業を描き抜く凄い作品なのだが、ミステリ成分を薄くして通常小説に寄せてそれを成し遂げたのではなく、あくまでミステリの作法やお約束をしっかり守り、メインデバイスとしてミステリ的な要素を駆使しつつ「成し遂げた」という点が実に凄い。なんとなく、ミステリというジャンル自体の価値が上がった気がして私は大変嬉しいのだ、とまで言ってしまうと業界コア層からお叱りを受けてしまいそうだけど、そういう面はたぶん確実にあるはずだ。
というかそれは「米澤穂信」という知的システムの秘密&おもしろさを読み解く大きなカギでもあるのだろう。すっごくいいなぁ。
ちなみに直木賞と本作について、対談時の杉江松恋氏による事前観測では「傑作であることは疑いないけれど、史実や人物をいじりすぎる作品を拒絶する選考委員がいそうだから受賞は厳しいかも」とのことで、確かにその可能性はあるけれどちょっと理不尽なのでは、と思ったのだが、結果的に第166回直木賞を受賞できてよかった。ほんとうによかった。
本音ベースで、これからの執筆展開にも大いに期待なのだ!
作品紹介
書 名: 黒牢城
著 者: 米澤穂信
発売日:2024年06月13日
第166回直木賞受賞! ミステリ史に輝く金字塔
本能寺の変より四年前。織田信長に叛旗を翻し有岡城に立て籠った荒木村重は、城内で起こる難事件に翻弄されていた。このままでは城が落ちる。兵や民草の心に巣食う疑念を晴らすため、村重は土牢に捕らえた知将・黒田官兵衛に謎を解くよう求めるが――。
事件の裏には何が潜むのか。乱世を生きる果てに救いはあるか。城という巨大な密室で起きた四つの事件に対峙する、村重と官兵衛、二人の探偵の壮絶な推理戦が歴史を動かす。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000514/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら