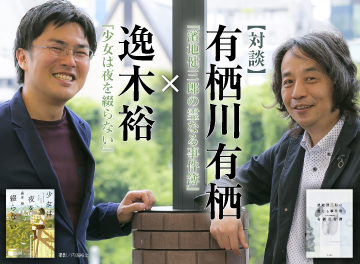【連載小説】謎が解かれ、仲間が加わる。残るメンバーは1人。少女の死の真相は? 青春ミステリの最新型! 逸木裕「空想クラブ」#12
逸木 裕「空想クラブ」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
6
「うわー伊丹くん、背伸びたねえ。もうすっかり大人の男性だなあ」
真夜は感激したように言って、圭一郎の隣でジャンプをした。
運動神経の悪い真夜のジャンプは小さくて、圭一郎の背丈に届かない。小学生のころのふたりは小柄で、並んで歩いていると双子みたいだったのに。
「背が伸びたって、喜んでるよ、真夜」
圭一郎は、焦げ茶のダッフルコートとジーンズに着替えている。当の本人は、ぼくに指差された空間を見ながら、困ったような表情をするだけだった。
「真夜はそこにいる。信じてくれる?」
「……さあ。何の気配も感じないし」
「信じてくれないなら、それでもいい。でも真夜はいるから、ひどいことは言わないでよ」
「もともとぼくは、ひどいことなんか言わない」
圭一郎は、自分の右隣の空間をじっと見る。その視線に目を合わせるように、真夜が下から覗き込む。
「真夜がいるかは判らないけど、あんな推理を吉見や小瀬ができるとは思えない。それは紛れもない事実だ」
「どこが事実だ。ただの偏見だろそれ」
隼人の言葉を、圭一郎は眼鏡の位置を調整しつつ、黙殺した。
「伊丹くんは、たぶん右手を骨折してる」
昨日、真夜が出した結論は、それだった。
「最初におかしいと思ったのは、伊丹くんが変な恰好をしていたことじゃなくて、絵を描こうとしなかったこと。あの子は昔から、頼めば絵を描いてくれた。それが難しいお題であればあるほど、闘志を燃やすタイプだった。そんな彼が、なんで依頼を断ったんだろう。それが、推理の出発点だったの」
真夜は右手を開いてみせた。
「利き手を怪我してて、物理的に描けない。そう考えれば、彼の行動の理由は判る。絵が描けないほどの怪我ってことは、骨にひびが入ってるか、折れてるか。伊丹くんはそれを隠してるから、絵を描いてくれないんだ」
「でも、なんで隠す必要がある?」
隼人の疑問に、真夜は当然答えを用意していた。
「その通り。手の怪我なんか、普通は隠す必要はない。じゃあ、普通じゃない場合って、どんな場合だろう? 怪我してることが発覚したら、不利益を被る場合だよね。でも、不利益を被る場合って? 伊丹くんが運動部のレギュラーで、怪我がバレたら試合に出られないとかなら判るけど、彼は美術部なんだし。となると──怪我がバレたら、誰かに迷惑がかかる場合なのかもしれない。伊丹くんにとって、そこまで大切な他人って誰?」
「美術部?」
真夜は頷いた。それが、美術部を調べてほしいと言った理由のようだ。
「でも、手の骨折を隠すのは大変だよね。ギプスをしてたら一発でバレちゃうけど、ギプスをしないで手を晒してても判っちゃう。そこで伊丹くんは、特殊な方法をとった」
あっと、隼人が声を上げた。
「ミトン、だよ」
核心に触れる真夜は、生き生きとしていた。
「エスキモーの恰好をしてたのは、別の理由があったんだ。伊丹くんは手の骨折を隠す必要があった。右手に巻かれたギプスを隠すには、ずっと手袋をしているしかない。ミトンを常にしていてもおかしくない服装……それを逆算して、伊丹くんはたまたま持っていたエスキモーの衣装を着ることにしたんだ」
すごい洞察力だ。半径二十メートル以内でしか活動できないのに、自由に動けるぼくよりも多くのことが見えている。
「で、なんでそこまでして隠そうとしたか、なんだけど……ここからは推測。たぶん、伊丹くんは、美術部の活動中に骨を折ったんだ」
「部活に迷惑をかけたくないから怪我を隠したってことか? でも、うちの部でも骨折くらいあるぜ。そんくらい、お
「普通はそう。でも、いまの美術部は、ちょっと特殊な状態だった」
確かに、いまの美術部は、生徒会や先生から、目をつけられている。
「弓場くん、っていう子がいたでしょう?」
カンバスを切り刻む、前衛的なアートを作っていた子だ。
「九月にあった小火の件、たぶんその子の仕業なんだと思う」
「なんでそんなことが判るんだ?」
「伊丹くんが部活のために骨折を隠すほど美術部が大切なら、美術室で煙草なんか吸うわけがない。見つかったら活動停止になっちゃうからね。つまり、小火は、部活動の中で起きたことなんだよ。たぶん、火を使って作品を作ろうとしたんじゃないかな。何かを燃やして作るようなアート……そういう
ぼくは、ナイフで切り刻まれたカンバスを思いだしていた。
「九月、弓場くんが美術室で小火を出しちゃって、伊丹くんはみんなを帰らせた。そこに間の悪いことに生徒会の人がきた。その場ではなんとかごまかせたけど、先生や生徒会に目をつけられることになった。その矢先に、最近また部内で何か事故が起きたんだよ。その結果、伊丹くんは骨折してしまった。公にすると、九月のことを改めて追及されて、真相が露見するかもしれない。だから伊丹くんは、骨折自体を隠すことにした。美術部の存続のために」
真夜は、嬉しそうにぼくたちを見た。
「前言撤回するよ。伊丹くんは変わらない人だって言ったけど、変わったんだね」
「え?」
「仲間を守る、立派な部長になった。小学校の彼には、なかったものだよ」
孤独な、オランウータン──。
その閉ざされた檻の
「弓場は、めちゃくちゃなんだよ。思いついたことを試さないと気がすまない。九月にあいつがやったのは、フュマージュっていう技法だった」
水彩絵の具で描いた紙の表面を
「それからしばらく落ち着いてたんだけど、この前、何を思ったか突然
圭一郎は慌ててそれを押さえようとして、落ちた石膏像と床の間に手を挟んでしまった。
骨折のことを報告したら、美術部全員が聴取されるかもしれない。そこで小火のことを蒸し返されたら、弓場くんは口を割ってしまう可能性がある。美術部は処分を受け、責任を感じた弓場くんはやめてしまう──圭一郎はそういうシナリオを恐れたのだそうだ。
「でも、美術室じゃなくて、家で折れたってことにすりゃよかったんじゃないのか」
「それは無理だった。あのとき、部員がみんなで悲鳴を上げて、隣の吹奏楽部とかが覗きにきたから。すぐに骨折してたって判ったら、あのときに折れたんじゃないかって勘ぐられる。二日くらいズル休みしてたんだけど、それも限界があったしね」
ぼくと隼人は目を合わせた。
そういえば、サッカー部の一年生が、陸上部のトラックにボールを蹴り込んでしまったとき、悲鳴のようなものが聞こえて足元が狂ったと言っていた。あれは、そのときの美術部員の悲鳴だったのだ。
「一週間くらい時間を稼げればいいんだよ。あとは家で折ったことにすれば、あのときの悲鳴と
弓場くんが和服を着て校庭を歩いていたのは、そのせいだったのだ。
「でも、そこまでしてかばうのはいいことなのか? 小火を隠すのはよくないと思うぜ」
「判ってるよ。ぼくのやってることは、間違ってるかもしれない。でも──あいつらに、自由に創作をさせてあげたいんだ」
圭一郎は、真剣な声になる。
「みんな──大助も含めて、個性的で面白い才能を持ってる。あいつらに、
「美術部はバラバラなんだと思ってた。みんな好き勝手に活動してて、全然まとまりがないって」
「まとまりなんかないほうが面白いだろ。去年もそうだった。先輩たちは色々なアートを作ってて、ごちゃまぜだったから面白かった。それが、笹倉東中美術部の伝統だ」
ぼくは、認識を改めた。
圭一郎は、オランウータンの群れにいるわけじゃない。
もっと多様な、ボノボやゴリラやチンパンジーといった、色々な種族がいる生態系の中にいるんだ。そこで、集まった個性的なメンバーを、ゆるやかに統率している。
猿山を檻の中から見つめていた孤独なオランウータンは、もうどこにもいない。彼は、自分の居場所を見つけたんだ。
「……全治まで、あと三週間くらいかかる」
圭一郎がミトンを取ると、右手の人差し指と中指にギプスが巻かれていた。
「治ったら、描くよ。真夜のためになるんなら、喜んで」
「かったいい」
真夜が声を上げる。かっこいいって意味、とすぐに補足を入れながら。
とりあえず、一歩前進だ。真夜が自由に動けるようになるための、強力なメンバーが加わった。
「三週間ってことは、ちょっと時間ができるな」
隼人が口を開く。
「それまで、三人であちこち〈子供〉を捜してみるよ。部活もあるから、毎日はできないけど」
隼人はそこで、ぼくの肩を叩く。
「あと、俺たちで真夜を支えてあげようと思ってるんだ」
「支える? どういうこと?」
「本を読ませてあげたり、映画を観せてあげたり」
「えっ? ほん! えいが!」
真夜が奇声に近い大声を上げて、ぼくは思わず耳に指を突っ込んだ。
「圭一郎と三人でローテーション回せば、毎日誰かしらここにこられるだろ。読みたい本とか見たい映画があったら言えよ。持ってきてやるから」
「すごいすごい、さすが小瀬くんだ。きまめだなあ。小瀬くんとふたりで映画が観られるなんて、こてらんねえ。吉見くんもそう思うだら?」
興奮しているのか訛りが強くて聞き取りづらいけど、とりあえず喜んでくれているようでよかった。「そう思うだら」と答えると、「ちょっと発音が違うんだよな」と苦笑された。
「真夜、ほかに何かやってほしいことがあったら言えよ」隼人が言う。
「会いたい人がいたらつれてくるし、欲しいものがあったら持ってくる。お父さんとお母さんには、会わなくていいのか?」
「会いたいけど……お父さんとお母さんに、私がまだ生きてるなんて話をしたら、怒られると思うよ。無駄に動揺させちゃう気もするし……」
「じゃあ、旅行はどうだ? カメラ持ってって、旅先から中継してやるよ。真夜に画面見てもらって、言う通りに動けば旅行みたいになるだろ。どっか行きたいとこ、ないのか」
「それだと、
言ったそばから、真夜は首を振る。
「やめた。たぶん画面を見てるだけだと、却って
「光害調査は?」ぼくが口を挟んだ。
「真夜、ずっと空の明るさを調べてたんでしょ? なら、ぼくたちが引き継いであげるよ。どこに行けばいいか指示してくれたら、出向いて明るさを測ってくるし」
「ほんとに? それはぜひ、お願いしたいな。ああでも、専門の機械が必要なんだよね。私の遺品はいま、お父さんが持ってるのかな」
真夜はそこまで言ったところで、はっと口を閉じた。うきうきとした様子が、一瞬で霧散した。
「涼子……」
「涼子がどうかしたの?」
「光害調査は、涼子と一緒にやってたんだよ。だから、専門の機械も、涼子をあたれば貸してくれるかも……」
告別式での涼子の態度を思いだした。昔とは別人のようにぼくを睨んできた、あの冷たい目のことを。
「涼子に会いたいの?」
真夜は、迷ったように唇を引き結んだ。会うのをためらっているのか、ぼくたちへの依頼を増やすことをためらっているのか、どちらだろう。
「会いたいなら、つれてくるよ」
真夜に、頼ってもらいたかった。
「涼子に手伝ってもらって、一緒に光害調査を完成させようよ。真夜のことを信じてもらえるように、説得してみるからさ」
真夜は、何かが引っかかっているように考え込んでいる。
ふたりの間に距離ができてしまったことを、改めて感じる。空想クラブにいたころ、ふたりは姉妹のように仲がよかったのに。
「真夜、遠慮しなくていいからさ。涼子もきっと、真夜に会いたいと思うよ」
「……そう思う?」
「うん。だって、親友だっただろ。会って話せば、きっともと通りになるよ」
「そうだよね……」
真夜はじっと、考え込むように黙っている。
答えを出さない彼女を見て、なぜか胸の奥が疼いた。ちくちくと、細い針で刺されているような痛みが身体の奥に走る。なんだろう。ぼくは真夜の役に立ちたいだけなのに──。
「判った、ありがとう」
結論を出すように、真夜が言った。
「やっぱり私、涼子に会いたい」
「ほんとに?」
「うん。しばらく会ってなかったけど、また昔のように話してみたいよ。色々頼んじゃってごめん、でも、お願いできるかな」
真夜はそこで、ぼくに笑顔を見せてくれた。
よかった、と思った。吹っ切れたような表情を見ていると、真夜の力になれたことに嬉しさを感じる。
先ほど感じた疼きは、どこかに消えていた。ぼくは応えるように、真夜に笑いかけた。
▶#13へつづく
◎前編の全文は「カドブンノベル」2020年8月号でお楽しみいただけます!