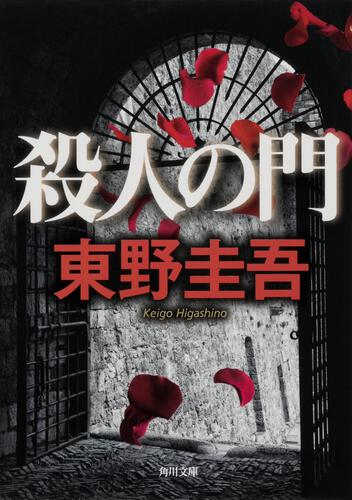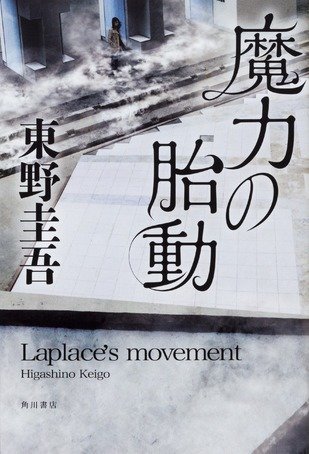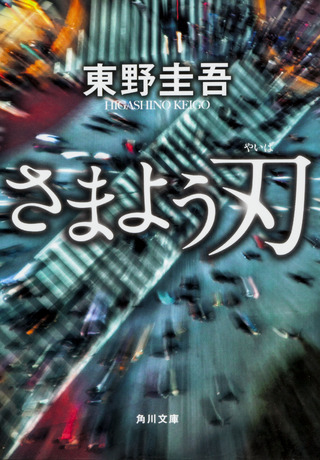あいつを殺したい。でも殺せない。『白夜行』と表裏をなす、歪んだ友情の物語。東野圭吾の11作品、怒濤のレビュー企画④『殺人の門』
全部読んだか? 東野圭吾
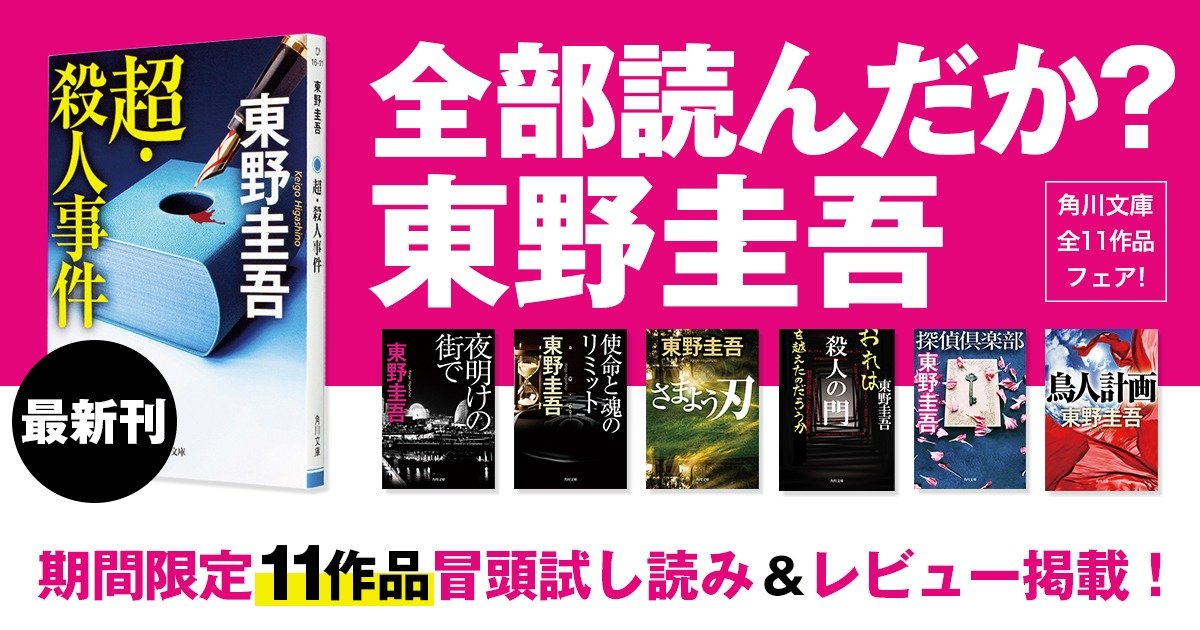
全部読んだか? 東野圭吾――第4回『殺人の門』
数ある東野圭吾作品。たくさん読んだという方にも、きっとまだ新しい出会いがあります。
『超・殺人事件』刊行に合わせ、角川文庫の11作すべてのレビューを掲載!
(評者:西上心太 / 書評家)
『たぶん最後の御挨拶』は、東野圭吾の肉声を聞ける貴重なエッセイ集である。苦労して取材を重ねたのに、自著がまったく評判にならなかったことへの落胆や、作家になってからの自著に関する売れ行きや評価などが、赤裸々に記されているのだ。
だがようやく1990年代の後半から、売れ行きも世間一般の評価も上向いていく。98年には『探偵ガリレオ』と『秘密』、翌年以降は『白夜行』、『片想い』、『時生』、『手紙』など代表作といってもよい作品を次々と発表し、誰もが認めるベストセラー作家に駆け上がっていった。
『殺人の門』は『手紙』と同じ2003年に発表された、脂の乗りきった(現在もその状態は続いているが)時期の作品だ。ある意味、『白夜行』と表裏をなすと言ってよい作品でもある。作者自身も同エッセイ集の中で、「『白夜行』は客観描写だけで主人公を描こうとしたが、この作品では、一人称にすることで、主人公の歪んだ思い込みの世界を描けるのではないかと思った」と述べているからだ。
田島和幸は小学校5年生の時に祖母の死に直面し、人の死に強い興味を覚える。ところが祖母は母親によって毒殺されたという噂によって、歯科医を開業していて裕福だった彼の家庭は傾きだす。両親は離婚し、父の女遊びによる浪費とトラブルにより歯科医院は廃業に追い込まれる。自宅を処分し、父は別の土地でアパート経営に乗り出すがうまくいかず、再会した女にまたも金を貢ぎはじめる。転校先の中学校で和幸はいじめに遭う。いじめを切り抜け高校に入学した和幸は、バイト先で初恋を経験するが、その相手は自殺。さらに借金まみれになった父は失踪してしまう。親類を転々とし、ようやく高校を卒業した和幸はなんとか就職したが……。
キーになる人物が和幸の小学校からの友人である倉持修だ。この男は和幸の人生の節目に現れては、彼の進む道をねじ曲げていく。最初は小学生時代に賭け五目並べに誘ったことだ。修はサクラで和幸の金を巻き上げる手伝いをしていたのだ。そして高校時代には初恋相手を奪い自殺に追いやる。和幸が就職すれば、またも彼の前に現れて、マルチ商法に誘う。それが原因で会社を退職させられた和幸に、今度はペーパー商法の会社へ入社を勧めるのだ。
和幸はそのおりおりで修の悪意ある行為を知り、何度も殺意を覚える。だが、そのたびに人好きのする修の弁舌に巧みに懐柔されてしまう。
何度ひどい目に遭っても学習しないダメ男が和幸という男なのだ。とはいえ、修に騙され悪事にも手は染めるが根は真面目なのだ。だが殺人へ強い関心を抱いている複雑な心性も有している。
こんな男の一人称で物語を進めていく試みが本書第一の特徴であり、作者の冒険である。第二が言うまでもなく倉持修という男の存在だ。幼いころから一攫千金をねらう根っからの詐欺師体質の男だが、彼の心情は一切描写されない。すべて和幸が見たり話したりしたことから類推するしかないのである。これは『白夜行』の中心キャラクターに使った方法である。内面を描くことなく、周囲の人間の言動や心情から、そのキャラクターを浮かび上がらせる手法を用いているのだ。生半可な技量ではできることではない。
真面目だがあまり人好きのしない主人公と、根っからの詐欺師だが人好きのする男。こんな二人の間の微妙な距離感のある関係を、感情移入しにくい男の一人称と、もっと魅力的な存在にできるであろう男の内面を描かないという二つの〈手かせ〉を用いて描いた〈殺意〉をめぐる物語。それが本書である。「歪んだ友情の物語」(北上次郎・本書文庫解説より)をたっぷりと味わってみてはいかがだろうか。
▼『殺人の門』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/200512000208/