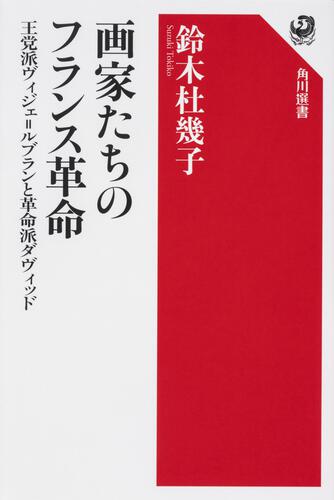鈴木杜幾子『画家たちのフランス革命』(角川選書)を、西洋美術史家で国立西洋美術館長の馬渕明子さんがレビューしてくださいました。
この本はフランス革命期を生き延びた2人の画家を取り上げている。一方は革命派からナポレオンの宮廷画家となったジャック=ルイ・ダヴィッド、もう一人は王妃マリ=アントワネットの肖像画家エリザベト・ヴィジェ=ルブランである。美術史でなくとも西洋の近代史を知っている人にとっては、前者は高校の教科書に出てくるなじみの名前であり、後者はほぼ知られていない。新古典主義という美術史の大きな流れを作った人物と、現在は無名の肖像画家を並べて論じることに、どんな意味があるのかと思う人もいるだろう。しかしこの対比は絶妙というほかはない。というのも、当時、二人はヨーロッパで最も高い知名度を誇った二人であったからである。一方が教科書に載り、一方が忘れ去られたのはなぜか? それぞれが残した作品と生涯を辿ることで、その謎を解くことができ、また数少ない女性画家がどのような社会的制約を受けていたかを、最も恵まれていたと考えられるダヴィッドと彼女を比べることで明るみに出そうとした試みと言える。
そもそも誰かの評伝を書くときは、筆者はその人物に寄り添い、時にその人物になったつもりで周囲を叙述し、感情移入しながら筆を進めるものである。特に鈴木氏はダヴィッドに関する著作が多数あり、正面からヴィジェ=ルブランを取り上げるのは初めてであろう。ダヴィッドの視点で筆を進めてもおかしくない。いっぽう、ヴィジェ=ルブランは詳細な『回想記』を残しているが、こうした文献は当然本人に都合の良いことしか書いていないし、書いたのは晩年で40年も前のことだったりする。しかも彼女の人生についてはほぼこれしか典拠がない。著者はその限界を意識しつつも、すでに築き上げたダヴィッドに関する伝記的史実と比較しながら、生き生きしたヴィジェ=ルブラン像を描きあげてゆく。
二人を描き分ける文体の違いが面白い。ダヴィッドについては、硬質な美術史の用語を駆使し、社会的環境と造形の意味を解説するいっぽう、ヴィジェ=ルブランについては、彼女の私的な好みや生活の好悪からでてくる感覚に沿って書く。カジュネック嬢の肖像画のヘアスタイルについて当時としては『カジュアル感』を感じさせたと思われるこのヘアスタイル
(232頁)とか、彼女と財務総監カロンヌの愛人関係を噂する小冊子をダヴィッドが来客に見えるように椅子に置いていた件についてダヴィッドがしたことは、同じ業界の女性の同僚のつまらぬ噂が載った週刊誌を自宅のリヴィング・ルームに置いて、訪れてきた友人たちに見せた
(78頁)に等しいと、卑近な例を出してかみ砕いて述べるが、ダヴィッドが主人公の場面にはそうした表現はまずない。その理由は『回想録』の内容と文体に引き寄せられたからかもしれないが、心理的には明らかに女性であるヴィジェ=ルブランを、内側から理解しようとする意欲が感じられる。革命によって崩壊した王制の御用画家であり、ヨーロッパじゅうの金持ち貴族の肖像画を高い値段で引き受け、顧客を求めて宮廷を転々とした女性画家、自らの美しい容姿を最大限に利用して、モデルをも現実よりはるかに美しく描くことで人気を得た画家、と今日では考えられているヴィジェ=ルブランを、貴顕と交際しても中流の出身であることを忘れず、身なりにあまり構わず、浪費家の夫も含めた家族を絵筆1本で支え、芸術家としての衿持を失わず、生涯マリ=アントワネットへの敬愛を持ち続けた強い女性として描き直す。もちろん著者は彼女を世界史の流れのなかに置けば、「政治音痴」で新思想は流行のファッションのようなもの
(176頁)、美しいもの大好き、貴族の生活が民衆を搾取することで成り立っているという反省もないと指摘することも忘れない。
一方ダヴィッドは王政と貴族階級に強い嫌悪感を抱き、革命の最中は次第に過激化して、ロベスピエールが失墜したのち、それでも運よく命は長らえて、美術に関心のないナポレオンに仕えて帝政時代とその後を生き抜いた。彼は明らかに美術の新様式を打ち立てようとし、その政治的信条がそれを導いたのか、芸術的信念が政治姿勢を選ばせたのか、双方に齟齬のない、また内的な葛藤のあまりない芸術家だったと言えよう。まさにダヴィッドは革命と政治を視覚化した類まれな人物だったわけだが、意外なことに、ヴィジェ=ルブランもまた、自信に溢れて仕事に邁進する精神をダヴィッドと共有していることを指摘する。つまり二人の芸術活動を辿れば片方からだけでは見えない「画家たちのフランス革命」が見えるはずで、筆者はそれに成功した。
芸術家と社会を語るとき、芸術家という存在が自立したものとしてあり、社会を「背景」と見なす場合が多いように思われるが、彼らの例をみると社会的価値観は外にではなく内面化されており、仕事をすることで自らの存在価値を生み出し、この混乱の時代を生き抜いたと考えられる。この二人の例は他の時代、他の社会でもありうるのか、それが近代へとシフトしようとしていたフランスの特別な例なのか。ダヴィッドが名を残し、ヴィジェ=ルブランが忘れられた理由、それは一方が偉大で他方がそうでないとか、一方が男性で他方が女性だからといった理由だけではない気がする。ダヴィッドの精神は人間の平等を謳った革命の側にあり、ヴィジェ=ルブランは民衆を敵とした王政の側にあった。今日の私たちにも基本的人権の遵守という点で革命側の価値観は共有されている。美術史を書くものも、そうした価値の選択を当然ながら行っており、そこで忘れられたヴィジェ=ルブランを闇から救い出して語らせたこの本の功績は大きい。
▼鈴木杜幾子『画家たちのフランス革命』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321708000028/