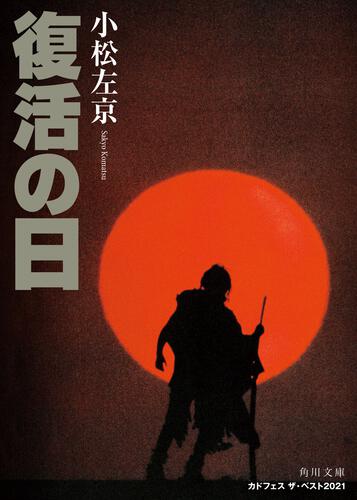文庫巻末に収録されている「解説」を公開!
本選びにお役立てください。
(解説者:小谷真理 / SF・ファンタジー評論家)
本書は、2016年にKADOKAWAから刊行された『失われた過去と未来の犯罪』の文庫版である。人類全体に、記憶が約10分くらいしか
以下、少々ネタバレを含むので、読者諸兄姉には、あくまで本書を読み終えたのちに、笑いすぎて痛くなった腹筋を優しく伸ばしながら、お読みいただきたい。
第一部では、まず、人々がいかにこの異変に気付いたかというプロセスが語られる。ただし、それは例えば、エリートたちの群れ集う政府中枢や秘密めいた軍部といった舞台では全くない。ごくごく普通の女子高生の、とぼけたループな独り言から始まるのだ。タメ口の微笑ましい女子高生の独り言が、いかにオソロシイ異変を物語っていたか。そして、その危機的異変に、この女子高生が誰よりも早く適応して打開策を打ち出していったかが語られる。左様。今時、サバイバル能力に
ところで、災厄といえば、現代こそ「ポスト東日本大震災」の時代。誰もが、
なぜなら、その昔、核の危機といえば、核兵器による人類滅亡の危機がジャンルSFにおける定番だったからである。軍需産業の中で超もてはやされていた冷戦の頃、日本では
21世紀の現在、消費期限を過ぎた食物のごとく、ゴミと化した核兵器は、放置された場所とともに人の定住不能地帯を増殖させるという新たな恐怖のエピソードを生んでいるそうだが、そんな核兵器と双子のように生まれた原子力発電所は、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとの触れ込みで、日本では50基以上も作られたものの、想定外の地震や津波といった自然災害にはあまり強くはなかったという弱点が明らかになった。
そして、今まさしく、本書で扱われている一次災害にも、原子力発電所は、どうも強くはなかったようである。何しろ、人類全体に降りかかった記憶障害は、原子力発電施設の職員の脳にも、もれなく降りかかったからだ。物語は原発施設が制御不能設備となる危機を的確に描いている。つまり、本作品は、核の恐怖を描くジャンルSFのテーマに、新たなページを付け加えるものである。そこに目をつけた作者の
ただし、本作品は、いわゆる緊迫感漂うノンフィクション的なサスペンスとして描かれているわけではない。恐怖の物語というより、ブラック・コメディの傑作なのである。
実は、非常事態直後から、地球上でもっとも知的で崇高な生命体として、常に
なぜ手作りかというと、人類全体が記憶障害になり、10分程度しか記憶が保たない、などという状況は、人類史始まって以来の珍事で、とにかく前例はないからなのだ。とすると、手始めは、ちょっと無防備でも、素手でかかっていくしかないではないか。
かくして、くだんの女子高生を始め、勤勉で真面目な典型的技術者たちは、とても真面目に危機に立ち向かう。具体的には、記憶障害を起こしている人の意識や対話がストレートに描かれ、この恐怖の状況から、なんと黒い笑いが漏れ出していく。
そう。本書は黒い笑いのSF作品なのだ。
あまりにも痛烈なブラック・ジョークの数々に、ここは笑うしかない。というか、あまりにも面白すぎる事態になる。かなり悲惨な状況だというのに!
記憶障害に悩まされているのは、何も本書の登場人物だけではない。複雑な現代は、情報過剰社会なので、現代人は常に覚えきれない情報に悩まされている。そこで本書でも、メモで残せばいいじゃない、という比較的古典的でよく使われる解決法が登場する。この辺のささやかな外部記憶装置のありようはかなり身近なので、長らく家族の認知症介護に関わってきた評者などは、確かに、記憶が保たないんじゃ、紙に書いて、あちこち貼り付けていくしかないよねー、と素朴に思いあたった。かなり切実に。
もちろん、そこは、集積回路やらなんやら、高度な外部記憶装置を使用することにかけては類を見ない21世紀感覚。モタモタといつまでも素朴なところにとどまらず、賢い人類なら高度な外部装置に頼って生きのびることに成功するよね、との希望的観測に行き当たる。しかし、そこにも著者は意地悪な落とし穴を用意する。第二部は、外部記憶装置が近未来的世界に根付いた後の珍騒動を描き尽くす。黒い笑いも健在どころか、いよいよ底知れない深さを見せる。
はたして珍騒動の水面下に、パニックSFだとばかり思っていた本書が、人類進化テーマや人類以外の高度生命体との接近遭遇テーマといったSFの王道としか言いようのないネタを隠し持っていることが明らかにされる。
いやー、驚いた。評者は笑いで顔をシワだらけにしながら、心から感服した。
何度でも失敗する人類。しかし何度でもへこたれず、緊急措置を発案してしまうしぶとい人類。七転び八起き的なイタチごっこは、申し分のなく気の触れたような展開になっていくので、そこは作者の本領発揮に感嘆していただこう。
その結果、読者諸兄姉は認識の変革を体験するだろう。著者は、日本ホラー小説大賞短編部門でデビューし、(お上品な恐怖物語ではなく)19世紀からホラージャンルのメインストリームを席巻し続けたスプラッター・ホラーの現代における代表的作家のイメージが強い。が、本書は、そんな固定観念を吹っ飛ばす。彼こそは狂った世界をダイナミックに描き続ける、
この世には、バカなのか利口なのか全くわからない天才がいて(褒めてます)、あるジャンルに固まって存在している、という伝説がある。主に、出版界の話だが。彼らの知性というのは、衝撃性バツグンとしか言いようのない創造物を輩出しているにもかかわらず、どこがどうすごいのか、説明するのがいつも難しい。
最近の日本のやや嘆かわしい風潮によると、知的評価基準は、何かが役に立つか立たないか、金になるのかならないのかが重要視され、しかもそれが、比較的近い未来の時空間に達成できるかどうかにかかっているらしい。ところが、そんな近視眼的(失礼)評価基準では全く計り知れない知こそ、彼ら天才たちの武器なのだ。
持って回った言い方をしてしまったが、なんの役に立つのか(今は)わからない知は主に現実を逸脱させる
そうした問答無用の才能を、本書は痛感させるのだ。記憶障害という、たった一つだけ起きた想定外の出来事が、律儀に思考を積み重ねていくと、いかに壮大で異常な世界へと
この狂った世界の素敵な異常感覚を、存分に楽しみ、未来の危機管理とサバイバルのために、どうか役立てていただきたいと、わたしは切に願う。
ご購入&試し読みはこちら▶小林泰三『失われた過去と未来の犯罪』| KADOKAWA