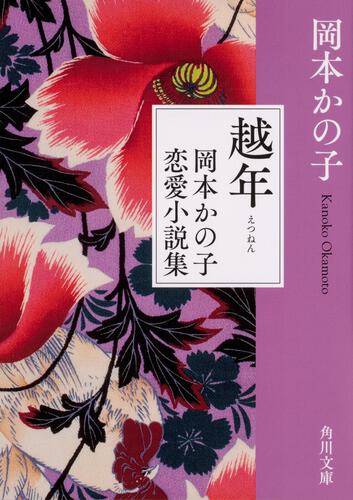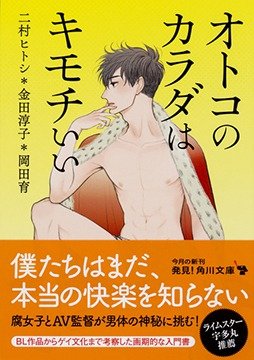文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説者:銀杏BOYZ・峯田和伸 / ミュージシャン)
この度、岡本かの子さんの作品を原作とした日台合作映画「越年・Lovers(仮)」(グオ・チェンディ監督)に出演させていただくことになりました。そのご縁で今回、原作小説の解説をお引き受けしたのですが、普段はミステリーばかり読んでいる人間で、恋愛系の小説は久しぶり。正直、心配でした。
しかし、結論から言えばどのお話もとても面白かったです。短歌をやっていた方だけあってなんといっても言葉の選び方が繊細。代表作の「老妓抄」はもちろん、今回の映画の原作(原案)にもなっている「越年」や「家霊」も読みやすい短編ですし、かの子さんのことを知らない人でも、とっつきやすい作品が揃っているように思います。
先日たまたま、夏目漱石の「三四郎」を読み返してみたのですが、久しぶりに読むと言葉の使い方が独特で、文体も歯切れがよく、さすが漱石だなと感心しました。一方、かの子さんの文体はそれともまた違います。なめらかで軽やかさがあって古くない。それから、ちょっとした滑稽さがあるのも魅力でした。「しかつめらしく」とか「きつきつと述べる」とか、語感も面白い。音楽をやっている人には特に読んでみてほしいです。
例えば、「家霊」に出てくる彫金師の老人がどじょうを食べるシーン。「ぽきりぽきり」という擬音が見事です。それから、この老人についての描写も独特。
今度は、この老人は落語家でもあるように、ほんの二つの手首の捻(ひね)り方と背の屈め方で、鑿(たがね)と槌を操る恰好のいぎたなさと浅間しさを誇張して相手に受取らせることに巧みであった一五二頁
この「いぎたなさ」という言葉にはショックを受けました。「うわ、目も当てられないんだろうな、これ」っていうのが、この一言でイメージできますよね。「だらしない」とか「見苦しい」という言葉なら今の人も使えると思うのですが、それとは違う。独特の感触があります。
「三四郎」を読んだ時にも思ったのですが、かつて日本人が培ってきた美しい言葉や優れた表現は、現代ではずいぶん埋もれてしまっています。でも、初めて見た表現、言葉遣いでも、「あれ? なんかわかる」と思える時がある。DNAに訴えかける表現とでもいうのでしょうか。古い時代に生まれた言葉なんだけど、現代に生きる自分にも、その意味合いが即座にニュアンスとして伝わってくる。かの子さんの小説にはそういうところが何箇所もありました。これは音楽的な体験に近い感覚でした。
今どきは多くの作品がスマホでも読めますが、僕は漫画でも小説でも紙の本を好みます。スマホだとメールやその他の情報にいちいち遮断されてしまいます。その点、本の場合は、開けばすぐその世界に戻ることができる。漫画の場合も、見開きで一枚の絵になるようコマ割りされていたりして、その迫力や読後のカタルシスはスマホではなかなか得られないものです。
映画も同様です。スマホの画面だとディテールが見えないので、どうしてもストーリーを追うだけの見方になります。でも、映画やドラマってストーリーだけではないですよね。照明の当たり方だったり、間合いや空気感だったり、そういういろいろな要素が含まれてこその作品だと思うのです。
今回、僕が出演させてもらった映画は故郷の山形が舞台です。CGかと思うくらいの猛吹雪や、美しい樹氷、空気の冷たさなども含めて楽しんでもらえたらと思います。
岡本太郎さんは僕の故郷の山形にとても
もちろん、山形でロケをして、山形出身の人たちが山形弁で出演するというのもいいなと思いましたし、それを日本人の監督ではなく、台湾の女性監督がやろうとしているというのにもとても興味を惹かれました。
グオ・チェンディ監督の演出は日本の監督とちょっと違うんです。台本を読んでなんとなく「こういう風に撮るかな」と予想していると、裏切られる。共演者の橋本マナミさんと僕が、雪の中で絡み合って、もみくちゃになった後、二人の距離が縮まるというシーンがあったのですが、「いいシーンだし、いいセリフもあるし、きっとアップでも撮るだろう」と思っていると、引きのカットだけ撮って「あれ、もう終わり?」なんてこともありました。
役者を撮りたいというより、その役者がいる状況を撮りたいという感じ。緩急のリズムで撮っていたようにも思います。もともとドキュメンタリー映画などを撮っていた方だと伺ったので、何か独自の方法論があるのかもしれません。そのあっさりした演出は、ジャン=ピエール・メルヴィルみたいで好きでした。
僕の出演している日本パートは、「越年」を原作として台北とマレーシアで撮影された物語と、「家霊」にインスパイアされた台湾の海辺の町が舞台の物語の間に挟まれた、オリジナルストーリーです。故郷の山形から逃げるように出てきて、東京で暮らすプログラマーの青年。何年も故郷と連絡を絶っていたのに、ある大晦日にかかってきた幼馴染からの電話で、ついに地元に帰ることになります。
実はとても自分に近い役どころでした。僕も、故郷の山形を飛び出して来てしまったという感覚がどこかにあるんです。生まれた場所が嫌いというわけではないのですがどうにも息苦しいという感覚。多かれ少なかれ、皆さんも持っている感覚なのではないかと思います。今思えば、そう悪い街ではないのだけど、当時は、ここにいて自分のやりたいことが果たせないのが辛くて、逃げ場所として東京に来たという面もあると思います。
そういう立場からすると、一度出てしまった街においそれとは帰れないというのがありますね。いまだに実家の玄関をまたぐ時は緊張しますし、仏壇に「じいちゃん、ごめん。帰ってきちゃった」と手を合わせたりします。
「老妓抄」や「家霊」でも、男は放蕩者でほっつき歩いていて、女性はじっとその場所にとどまっている人として描かれます。一見、「女は家にいろ」みたいな男尊女卑っぽいお話なのですが、現代の女性上位とかフェミニズムとかとは全く違う目線で、女性側の、そこに居続ける強さみたいなものを描いている。そこが、かっこよかったです。男を否定するわけでもなく、「男ってこんなものよ」と達観している強さ。しかも、それを昭和初期の女性作家が書いているということに感動しました。
かの子さんは、その生き方も含めて、「均一化されていないものが産み出せる人」だったのだと思います。必ずしも広く世間に受け入れられるとは限りませんが、そういう人が作るものはやっぱり面白いし、貴重だなと思います。
彼女の作品から感じる強さが、僕たちだけでなく、海を越えて台湾の方までをもいいな、と思わせるのかもしれません。
ご購入&試し読みはこちら▶『越年 岡本かの子恋愛小説集』| KADOKAWA