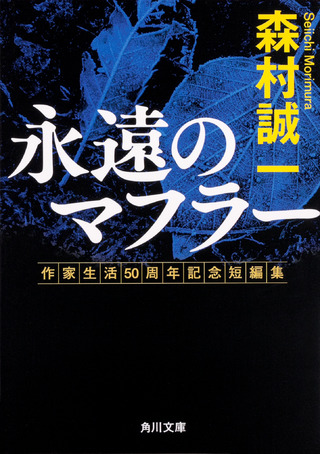文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開! 本選びにお役立てください。
(解説者:山前 譲 / 評論家)
物理的にはまったくほかの年と変わりないにもかかわらず、西暦二〇〇〇年と聞くと、なにやら特別なことのように感じてしまう。西暦、すなわちグレゴリオ暦では大きな区切りとなるだけに、なにかと話題の多い二十世紀最後の一年だが、森村誠一氏にとっても、最初の著書である「サラリーマン悪徳セミナー」の刊行から三十五年目と、ひとつの節目の年となっている。
まだホテルに勤務していた一九六五(昭和四十)年、池田書店から新書サイズで刊行されたサラリーマン向きのエッセイ書が、作家・森村誠一の第一歩だった。二十世紀の出来事のなかでも特筆される一九六九年の月面着陸に倣って言えば、それは出版界にとっても森村氏にとっても小さな一歩だったかもしれないが、その後の森村氏の活躍ぶりを見れば、とてつもなく大きな一歩だったとも言える。二年後には、ホテルを辞めてビジネス・スタイルの講師となった。そのかたわら本格的に執筆活動をはじめ、最初の長編小説「大都会」を刊行している。
さらに二年後、「高層の死角」によって江戸川乱歩賞を受賞し、推理作家としてより新たな一歩を踏み出した。当時、推理小説界における最大の登竜門であった乱歩賞の受賞は、出版界にとっても森村氏にとっても間違いなく大きな一歩だった。その後の歩みについては詳しく語る必要はないだろう。日本推理作家協会賞を受賞した「腐蝕の構造」ほかの推理小説はもとより、「忠臣蔵」「平家物語」といった時代・歴史小説にも意欲をみせ、「悪魔の飽食」のような
その森村氏の世界を
なかでも興味を引かれたのは創作ノートである。作者の脳髄の片隅にモチーフが芽生え、ひとつの作品として形を成していくまでの経過がそこに凝縮されていた。完成して
では、この「棟居刑事の断罪」の創作ノートは、はたしてどのようなものだったろうか。幾つものエピソードが重ねられた重層的な構造と、時と場所を違えて関係していく登場人物を整理していくだけで、ノートに書かれた構想メモはかなり複雑なものになったに違いない。
発端は男女の偶然の出会いである。ホテルのラウンジで、恋人の矢代昭に待ちぼうけを食わされた松葉絵里子は、声をかけてきた鮫島と名乗る男とベッドを共にしてしまう。一度きりとすぐに別れたが、その日の深夜、
横領してまで金を貢いだ矢代と手を切り、勤勉で実直な夫との幸せな結婚生活を手にしたはずの絵里子だったが、分け前を使いはたした共犯者からの電話が彼女を不安に陥れる。警察も着実に捜査をすすめていた。忘れたはずの矢代から電話がある。すっかり拭いさったつもりの過去が、再び黒い影となって迫ってきた。しだいに追い詰められていく絵里子の心理がサスペンスを高めていく。
すでにお
いわゆる男女雇用機会均等法など、男女間の差別を解消していく流れはこのところ顕著である。もちろん一個の人間として、男であるか女であるかは区分の基準とはならないが、肉体的に、そして心理的に、依然として男女に違いの見られるのも否定できない。長年の社会的な慣習と経済的な環境から、どうしても女性は従の立場に追い込まれやすいのだ。本書の絵里子も最初は、男性に対する隷属的関係を自ら認めていた。二度も妊娠中絶を行い、なにかというと金をせびる矢代と、結婚までは望んでいない。独り暮らしを紛らわせてくれるだけで満足していたのだ。二十七歳という年齢もハンディと思ってしまう。その絵里子が、大金を手にしたことで、一度は大きく変身する。金銭的な余裕が、心の余裕となったのだ。自分を捨てて結婚してしまった矢代に未練はない。新たな出会いがこれまでの人生を一変させる。
だが、やはりそれは
本書にはもうひとつ、男と女の関係が内包されている。棟居刑事と本宮桐子の歯痒いほどのプラトニックな恋愛である。妻子を何者かに殺されて独身となった棟居は、穂高連峰を登山中に桐子と知り合う(「棟居刑事の情熱」の冒頭)。はからずも上高地のホテルで同室となるが、ふたりの間には何事もなかった。互いの素性も知らぬまま別れたものの、桐子の父親が殺人事件の被害者だったことから、再会の機会が与えられる。
以来、忙しい刑事生活の合間を縫ってデートは重ねてきた。しかし、まだプラトニックなままである。桐子の思いを棟居は十分知ってはいたが、もう二度と家族をつくるまいと決心した彼が一線を超えることはなかった。〈捜査に行きづまったときや、荒涼たる独り暮らしに精神が渇いたとき桐子に会うのは、桐子に甘えているのであろう〉と、棟居は本書でその心情を吐露している。しかし、桐子もまた、棟居に甘え、精神的に満たされているのだ。
こうした互いに相手を尊重しあう棟居と桐子の恋愛関係がベースにあるだけに、絵里子をキーパーソンとする打算にまみれた男女関係が本書ではいっそう際立っていく。男の思惑と女の思惑。歪な男女の関係が、日常生活のなかに潜む邪悪な心までも
この「棟居刑事の断罪」は、一九九五(平成七)年四月十四日から九月十五日まで『ザテレビジョン』に「棟居刑事のラブアフェア」の題で連載され、森村誠一氏の作家生活三十周年を記念して、同年十月に角川書店より刊行された。一九九八年一月、カドカワ・エンタテインメントの一冊として刊行されたとき、現在のタイトルに改題されている。男に頼り、そして男に翻弄されていく絵里子と、冷静に捜査をすすめていく棟居刑事とのコントラストが印象的な長編推理である。
森村誠一氏の創作ノートは、かつて「創作ノート『プロ作家の心構え』とは」(エッセイ集「ロマンの珊瑚細工」に収録)のなかで一部紹介されたことがあった。それは「死海の伏流」のもので、構想初期の苦闘期、構想中期の登場人物関係図、そして構想が煮詰まったものと、二ページを目にすることができる。なにが書いてあるか、作者本人にも判読できない字が多い。これが読めるようになってくると、いくらか固まってきた証拠である。と書かれているように、他人がきちんと判読できるようなものではないが、森村氏の創作過程の一端を
いま、なにかと時代の変化がマスコミで報じられている。既存のシステムの崩壊がいたるところで起こっているようだ。小説の世界も、CD‐ROMやインターネットを利用したものなど、従来からの「書籍」とは別の形で読者に提供される機会も増えてきた。しかし、どのような形態をとろうとも、書くのはあくまでも作家である。それぞれ独自の作品を創り出し、読者を楽しませていく小説の世界はまだ揺るぎないのだ。森村誠一氏の創作ノートも、これからさらに何十冊、何百冊と積み重ねられていくに違いない。
書籍のご購入&試し読みはこちら▶森村誠一『棟居刑事の断罪』| KADOKAWA