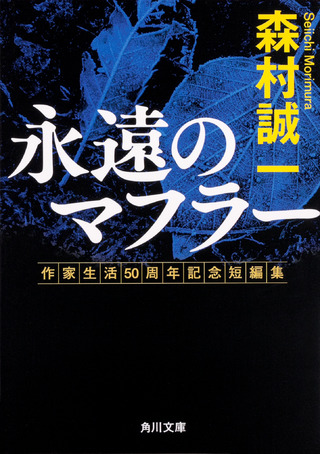二〇一五年は森村誠一氏にとって、作家生活五十周年という大きな節目の年となった。エンタテインメントの作家にとって、読者はかけがえのない存在である。どんなに面白い作品であっても、それを読んでくれる人がいなければ無に等しいからだ。
森村氏の作家活動を支えてきたその読者に、五十周年を迎えたとき、ビッグなプレゼントがあった。八作の短編が特別に書かれたのである。この『永遠のマフラー』はその八作に初期短編の三作を加えた文庫オリジナルの短編集だ。五十年にわたる森村氏の作家活動のエッセンスがここに集約されている。
一九五八年、青山学院大学を卒業した森村氏はホテルに就職した。いきなりフロント業務を任されて慌てたというが、そこで実感したのは、自身が企業のなかで歯車のひとつにしかすぎないことだった。個々のアイデンティティはなかったのである。
「社奴」というのは森村作品の大きなキーワードだが、そこから脱したいという強烈な思いが森村氏の作家活動の原点となった。大学の同窓生の紹介で「総務課の実務」にサラリーマン向けの小文を発表し、それを一冊にまとめて『サラリーマン悪徳セミナー』と題して刊行する。一九六五年十一月のことで、それが記念すべき作家生活の最初の一冊となった。
「ラストウィンドゥ」(二〇一五・三 角川文庫『腐蝕の構造』に書き下ろし収録)の野崎は、森村氏のように社奴から逃れることはできなかったのである。会社のために粉骨砕身し、実績を挙げてきた。しかし、定年を迎えたときには、会社の管理下から完全に離れた余生を送りたいと思うのだった。自由な時間を得て自宅近くを〝探険〟しはじめる。そこにはサラリーマン時代には気付かなかったさまざまな発見があった。かねてより気になっていたのは、通勤電車の窓からちらりと視野に入ったアパートに住む、若い女性だったが……。
大都会の一期一会の出会い(それは一方的なものだとはいえ)の結末にはきっと癒やされることだろう。一方、会社の業績不振で希望退職に応じたサラリーマンを主人公にした「虫の土葬」(一九七五・六 「オール讀物」掲載)では、社奴の悲哀が強調されている。
元商社マンで今は英語を中心にした私塾を開いている平を主人公にした「オアシスのかぐや姫」(二〇一五・三 角川文庫『終着駅』に書き下ろし収録)も、都会の片隅の喫茶店にまつわる癒やしの物語だ。もしかしたら誰もが、オアシスという異次元を求めているのかもしれない。
一九六七年刊の『大都会』を最初に小説にも意欲を見せた森村氏は、一九六九年、『高層の死角』で第十五回江戸川乱歩賞を受賞する。以後、謎解きの興趣と社会性豊かな作品で日本のミステリー界を牽引した。そして、『人間の証明』(一九七六)以下の棟居刑事や『駅』(一九八七)以下の牛尾刑事を主人公にした作品を中心に、現代社会の闇のなかで育まれた犯罪を描いてきた。けれど、「オアシスのかぐや姫」のようなロマンチシズムをいつも忘れてはいない。
「永遠のマフラー」(二〇一五・一 「小説 野性時代」掲載)は太平洋戦争にまつわる余情豊かなストーリーだ。一九四五年八月十五日の終戦の前夜、森村氏の郷里である熊谷は空襲で焼け野原となってしまった。特攻を描いた「神風の殉愛」や「紺碧からの音信」のような短編、元零戦操縦士が殺人事件の被害者となる『火の十字架』(一九八〇)、戦争から逃避する純粋な若者の姿が鮮烈な『青春の源流』(全四冊 一九八三―一九八四)、元兵士が旧日本陸軍の兵器で暴力団に挑む『星の陣』(一九八九)など、多くの作品で戦争をテーマにしている。一九九一年刊の『ミッドウェイ』では、太平洋戦争の局面を一変させた海戦を軸に、無念の青春を描いていた。
そして、『死の器』(一九八一)のテーマから発展して、七三一部隊の実相に迫るノンフィクションの『悪魔の飽食』(一九八一)が書かれる。さらには『新・人間の証明』(一九八二)、『エンドレスピーク』(一九九六)、『南十字星の誓い』(二〇一二)、『戦場の聖歌』(二〇一五)と、さまざまな形で戦争の悲劇と非人間性が描かれてきたのである。
さらに時は遡って、『忠臣蔵』(一九八六)や『太平記』(一九九一―一九九四)など、歴史・時代小説にもその作品世界を拡げる森村氏だった。『人間の剣』(一九九一―二〇〇一)で「剣」をキーワードに日本の歴史を描き、二〇一一年、元禄時代にダイナミックなストーリーを展開させた『悪道』で第四十五回吉川英治文学賞を受賞する。
そうした時代小説にも猫がよく登場しているが、猫派と犬派に分けるならば、森村氏は明らかに猫派だろう。公式サイトには「ねこ特集」があり、二〇一七年には『ねこの証明』と題したエッセイと小説からなる猫本をまとめているほどだ。人生の不思議な縁が語られる「春の流氷」(二〇一五・二 角川文庫『高層の死角』に書き下ろし収録)でも、その猫が物語の重要なアクセントとなっている。
森村氏がサラリーマン生活を送ったホテルが作家活動のベースとなってきたのは、乱歩賞受賞作の『高層の死角』、第二十六回日本推理作家協会賞受賞作の『腐蝕の構造』(一九七二)、そして大ベストセラーとなった『人間の証明』と、創作活動の節目となる作品の舞台がホテルだったことで明らかだ。「初夜の陰画」(一九七一・二 「別冊小説宝石」掲載)に描かれているホテル業界の非情さもまた、実体験に裏打ちされているのだろう。
「深海の隠れ家」(二〇一五・一 「小説 野性時代」)の主人公の真美は、真っ先にお客様をおもてなしするホテルの「グリーター」である。ホテルは人間の見本市のように多様な人々が集まる。真美がそんな〝人間の海〟である東京で、初めて自由を得た気になった。その東京でみつけたオアシスでの奇妙な体験……。これもまた大都会に潜む異次元に誘っていくストーリーだ。
「遠い洋燈」(二〇一五・三 角川文庫『吉良忠臣蔵 下』に書き下ろし収録)の舞台は、秩父山系に属する深山のランプの宿である。これもファンタジックな物語だが、ベースにある詩情もまた森村作品ならではのものだ。学生時代から山に親しんだ森村氏にはロマンチックな体験もあったらしい。『分水嶺』(一九六八)、『虚無の道標』(一九六九)、『密閉山脈』(一九七一)、『日本アルプス殺人事件』(一九七二)、『白の十字架』(一九七八)……山を舞台にした森村作品を挙げていくときりがない。
「北ア山荘失踪事件」(一九七二・一 「別冊小説現代」掲載)は、舞台は架空であっても、その圧倒的なリアリティに引き込まれていくことだろう。作家生活五周年のサイン会での再会で主人公が遠い青春に思いを馳せる「台風の絆」(二〇一五・二 角川文庫『超高層ホテル殺人事件』に書き下ろし収録)も、山というこれもまたある意味で異次元の舞台がロマンチシズムを誘っている。
やはり作家を主人公にした「人生のB・C」(二〇一五・三 角川文庫『吉良忠臣蔵 上』に書き下ろし収録)は、大学時代の同窓生だった女性にまつわるちょっとほろ苦い物語だ。ベース・キャンプとは高い山に登るときのスタートとなる基地である。自身のベース・キャンプはどこにあるのだろう。読後、深い余韻に浸ることだろう。
二〇一五年の作家生活五十周年はもちろんひとつの通過点にしかすぎない。『運命の花びら』(二〇一五)、『涼やかに静かに殺せ』(二〇一六)、『戦友たちの祭典』(二〇一七)、『深海の寓話』(二〇一七)など、森村氏はさらに新たな物語を紡いでいる。読者は森村作品でまさに至福の時を得ることだろう。
>>森村誠一『永遠のマフラー 作家生活50周年記念短編集』
レビュー
-
レビュー
-
レビュー
-
特集
-
レビュー
-
レビュー