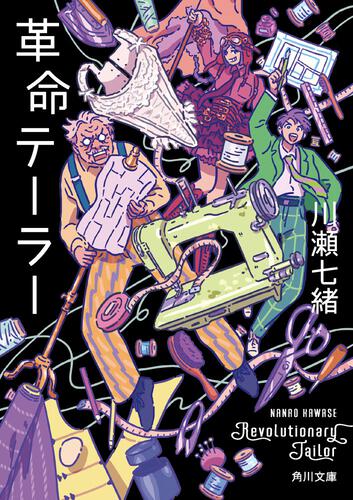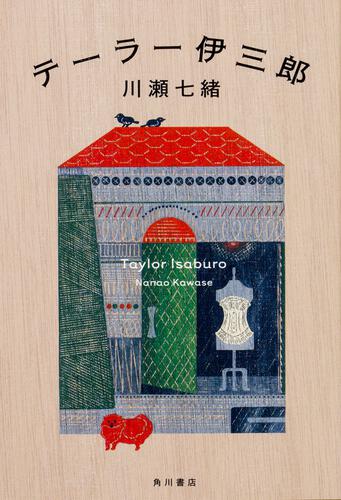3月1日に刊行された川瀬七緒さんの書き下ろし長編小説『四日間家族』。帯の「徹夜必至」という言葉どおり、圧倒的一気読み小説だと評判になっています。
好評御礼企画として、第一章「最悪への扉」を全文公開!
『四日間家族』第一章公開#04
4
後部座席のわたしと陸斗の間に赤ん坊の寝床を用意した。千代子がふわふわした素材のカーディガンを持ってきており、それがいいあんばいのベッドになっている。わたしは持参した何枚かのタオルを赤ん坊にかけ、陸斗もパーカーを出して小さな足許に置いた。
「しかし、本当に赤ん坊がいるとは神の思し召しじゃないだろうか」
千代子は厳かな調子で言った。
「たぶん、この子は生まれてから三ヵ月ぐらいだと思うよ。首の据わりがまだ甘い。だが、少し小さいかもしれないね。男の子なのに五キロもなさそうだろ?」
初めは置き去りにされた恨み節を捲し立てていた千代子だったが、赤ん坊を見るなり怒りを消していた。彼女はこの四人のなかで唯一子どもを産み育てた経験者だ。今までとは目つきが違い、紡がれる言葉には迷いがない。
それにしても、乳児の月齢というのはよくわからない。わたしは赤ん坊の顔を覗き込み、まるで小動物のような丸い目に釘づけになった。まだ表情は曖昧だが、わずかながら意思を感じることができる。赤ん坊が忙しなく目を動かしているのを見るに、環境が変わったことを悟っているようだった。
わたしは白くてすべすべした小さな足におそるおそる触れた。するとあたりまえのことが口を衝いて出た。
「……ちゃんと五本の指がある。ちっちゃいけど爪もある。すごい」
「ホントにな。こんなにちっこいのに、大人とおんなじものが全部ついてんだ。赤ん坊ってのはそこにいるだけで奇跡の存在なんだよ」
こんな大げさな表現も、すんなりと受け入れてしまう自分がいる。四人は互いに顔を寄せ合いながら赤ん坊を見つめ、それぞれに湧き上がっているであろう複雑な感情に振りまわされていた。
しばらくしてから陸斗が血色のいい赤ん坊の頰に指を当てると、母乳を探すかのような素振りで顔を傾けた。続けざまに首筋に指を当て、スマートフォンの時計に目を向ける。
「心拍数は正常」
「いや待て」と長谷部が口を開いた。「おまえさんは医者でもねえのにいろいろと詳しいような口ぶりだな。さっきの心臓マッサージの件もそうだしよ。はったりか?」
「違う」
「だとすれば、今どきの高校ではこんなことを詳しく教えてんのかね。やけに人を食った物言いといい、おまえは得体が知れねえから気持ちわりいんだよ」
長谷部はずばりと言い放った。確かにその通りで、どことなく警戒心が刺激されるのは間違いない。三人が説明を求めるように少年を見ていると、陸斗は左目をこすりながら小さな吐息を漏らした。
「赤ん坊の心拍数は一分間に百二十から百六十。呼吸数は四十から六十ぐらいで腹式呼吸かどうかを確認する。月齢にもよるけど、これはだいたいの目安」
千代子はたちまち感嘆の声を漏らした。
「たいしたもんだ。もしかして、あんたは医者の息子なのかい?」
「違う。僕は小さいときからずっとボーイスカウトの活動をしてたから、こういうのはそのなかで覚えた」
「ボーイスカウトか……」
長谷部は納得したように腕組みした。
「俺も甥っ子に勧めようと思ってたんだよ。うちの町内にボーイスカウトの指導員だかなんだかをやってる男がいてな。ひきこもりを家の外に出すにはいい集団だって熱心に勧誘されて、入れる方向で頼んでたんだ」
「やめたほうがいい」
陸斗は間髪を容れずに返した。
「スカウトは甘くないし性格悪いやつが多すぎる。いや、偽善者って言ったほうがいい。活動は自発的という名の強制だらけ。もちろん団にもよるけど、僕がいたとこは最悪の連中の集まりだった」
「だが、おまえさんみてえに人の役に立つことも覚えられるだろ」
「だとしてもデメリットのほうが上だと思う。自分の時間を食い潰されるし、特に人付き合いが苦手な人間からすれば地獄。まあ、稀に覚醒する人もいるけど」
陸斗はこの話はもう終わりとでも言うように、横で眠る赤ん坊に目を向けた。
「そんなことより、こいつをどうする?」
「どうするって、しかるべき場所へ預けるしかねえだろう」
「しかるべき場所?」とわたしが繰り返すと、長谷部はいつもの調子で煙草をくわえた。が、三人が非難の目を向けていることに気づいてしぶしぶ箱に戻した。
「警察に渡すしかねえよ。これはれっきとした殺人未遂だからな。俺らが気づかなけりゃ、こいつはあと半日も生きられなかったはずだ」
「そうだな。あの鬼のような母親には裁きを下す必要がある」
千代子も賛成だと相槌を打ったが、わたしは顎に指を当てて考えた。
「この子を捨てにきた女はスマホでだれかに電話してたよね。なんとなくだけど、あの女が母親だとは思えない。それに電話口の人間が何か指示してたみたいだし、組織的な犯罪じゃないの?」
わたしは鞄からスマートフォンを出して最寄りの警察署を検索した。けれども、通信状態が悪くてインターネットにつながらない。アプリを終了し、わたしは三人の顔を順繰りに見た。
「警察に行けば事情を聞かれるけど、まさか集団自殺をしにきたとは言えない。そのあたり、口裏を合わせたほうがいいよね。それか、長谷部さんだけで警察へ行くか」
長谷部は腕組みしてしばらく考え込んでいたが、いや、と声を出して顔を上げた。
「俺ひとりだと怪しすぎる。蒲田に住む人間が、夜更けの岩國山にいた理由が説明できねえよ。人が集まりゃドライブってことにできるだろ」
「むしろ、ひとりで自殺しにきたってぶっちゃければいい。でも、赤ちゃんを見つけて思いとどまったとか」
長谷部はわたしの提案を少し考えたが、やはり首を横に振った。
「こんなことでおまわりにマークされたくねえな。妹が手にする保険金の件もあるし、工場も計画倒産してる。倒産前に取引先から商品を入れてよそで売り捌いたんだよ。身元を照会されれば詐欺罪でしょっぴかれる可能性もある」
長谷部は肉付きのいい大きな顔を両手でこすり上げた。
「警察にはおまえら三人で行ってくれ」
「ちょっと待ってよ。このなかで運転できるのってわたしと長谷部さんだけだよね。そうなるとわたしが出頭確実になるんだけど」
「まあ、そういうことになるわな。まさかとは思うが、ねえちゃんもおまわりに追われるようなことをやってんのか?」
わたしはたちまち口ごもった。わからないからだ。過去にかかわった人間が、もしかして警察に訴え出ている可能性もなくはない。
重苦しい沈黙が車内を包んだとき、陸斗が唐突に声を出した。
「僕もパス。警察へ行った時点で保護されるし、学校も巻き込んだ騒ぎになりそう。今さら説教とか呼び出しとか面談とか激しくめんどくさすぎる」
「そんなこと言ったらあたしだって嫌だよ。いんたーねっとに名前も顔も出てんだぞ?」
「ある意味、ばあさんは有名人だからな。だが、考えようによっちゃこれ以上の最悪はないとも言える。七十三だし未来もない。よし、ここはあんたが行ってくれ」
長谷部が堂々とそう切り出すと、千代子は目を血走らせて食ってかかった。
「み、未来がないのはあんただって同じだろ! よくも年寄りをそこまで侮辱できるな!」
「侮辱してるつもりはない。代弁したんだよ、ほかの連中の胸の内をさ」
そうやって常に責任回避をするこの男は最低だ。なのにリーダーと呼ばれたがる。そもそも、今の複雑な状況を千代子に任せることはできなかった。出頭したところで間違いなく余計なことを口走るだろうし、ある意味、いちばん適さない人間だと言える。
「勝手に代弁しないでよ。わたしは千代子さんを行かそうなんて思ってない」
そう口を開いたとたんに「それ見ろ!」と老女はいきり立ち、長谷部は深々とため息をついた。
「結局、だれもおまわりにはかかわりたくないと。だが、このままにはできんだろ」
「人のいる場所にこの子を置いてくればいいじゃないか。手紙でも添えてさ」
千代子は名案だとばかりに声を上げたが、長谷部はすぐに否定した。
「防犯カメラを避けられねえよ。しかも赤ん坊を置き去りにしたら、もっとヤバい罪を着せられかねない」
わたしは安心しきって眠りに落ちている乳児に目を落とした。子どもを保護して警察へ訴え出る。そんなあたりまえのことをできる人間がここにはひとりもいないというわけだ。それぞれが自死という結論に至ったのも頷ける。陸斗のことはまだよくわからないが、少なくとも自分たち三人はまともな生き方をしてこなかったのだ。
長谷部は手慰みに煙草を指に挟み、真っ暗な森の中へ目を向けた。八方塞がりを感じているようで、いつもの適当さが消えて途方に暮れている。みなが自然に押し黙ったとき、遠くからエンジン音が聞こえて四人は一斉に国道のほうへ顔を向けた。蛇行する山道をあり得ない速度で飛ばしてくる者がいる。あの無謀さには見覚えがあった。わたしは慌てて手を伸ばし、車のルームライトを消した。
「さっきの女じゃない? たぶんそうだよ!」
「とりあえず伏せろ。声を立てなければ見つからない」
額に汗の玉を浮かべた長谷部は、おろおろしている千代子に落ち着けと目配せを送っている。そうしているうちに、車体を揺らしながら急角度で左折した赤いミニバンが自分たちのいる空き地に突っ込んできた。砂利を蹴散らしながら急ブレーキを踏んで土埃を上げている。そしてハイビームのヘッドライトを点けたまま、女はドアを蹴破るようにして姿を現した。
「お、鬼のような形相だよ……」
千代子は背中を丸めて拝みはじめている。煙草を口の端にくわえた女は、目の前にある真っ黒い森を憎々しげに睨みつけていた。風でなぶられている長い髪を鬱陶しそうに払い、大股で一歩を踏み出した。
わたしは動きを止めたまま女の行動を窺った。猛烈な喉の渇きに襲われ、思わず首許に手を当てた。舞い戻ってきた理由はひとつしか浮かばない。
「こ、この子を確実に殺すために戻ってきた?」
言葉を出さずにはいられなかった。女は横を向いて煙草を吐き出し、今さっきわたしたちが下りてきた斜面を駆け上っている。赤ん坊をそのまま置き去りにしたことが不安になり、途中で引き返してきたのか? わたしはそう自問したが、すぐ違うという結論に達した。共犯者に咎められたのではないのか。それでなければ、これだけ時間をかけて戻ってくるわけがなかった。女は確実にとどめを刺せと言いつかっている可能性が高い。
わたしは額の汗を手の甲でぬぐった。張り詰めた空気のなかで、長谷部がくぐもった声を出した。
「まさかヤクザ絡みじゃないだろうな」
「ヤ、ヤクザ」と千代子が繰り返した。
「とどめを刺しに戻ったんならカタギとは思えない」
長谷部は乾燥してひび割れている唇を震わせた。
「まさかとは思うが、この森はヤクザの死体処理場なのか……」
「いや、そんな話よりまずは逃げようよ!」
わたしは赤ん坊のほうへ目を向けた。今さっきまでぐっすり眠っていたはずの目は開いており、むずがるように体をくねらせている。
「この子が泣き出すかもしれない! 早く車を出して!」
「だ、駄目だ」
長谷部はだらだらと汗を流しながら声を絞り出した。
「さっきも言っただろ。このバンはバッテリーが弱ってんだ。エンジンを落とすとなかなかかからねえんだよ」
「そんなこと言ってる場合じゃない! この子がいなくなってることにはすぐ気づかれるんだよ!」
「そうだとしても、車を出すよりあの女が下りてくるほうが早い。エンジンをふかす音も聞こえるだろうし、ここで息を殺してたほうがいい」
長谷部は作業着の襟まわりに汗染みをつくり、一瞬だけ後部座席のほうに目を向けてきた。尋常ではないほど顔が赤黒く、緊張で体が強張っているのがわかる。千代子は背中を丸めて一心に拝んでおり、涙が頰を濡らしていた。
そのとき、赤ん坊がわずかに声を出し、本格的に泣く準備をはじめているのが見えてわたしは目を剝いた。咄嗟に体をさすってあやしにかかったが、次の瞬間には陸斗がさっと抱き上げて小さな背中を叩きはじめた。蒼白い少年の顔にも汗がにじみ、いささか息も上がっている。が、今にもパニックを起こしそうな三人に視線を送ってきた。
「……あっちは女ひとり。こっちは四人。いくら凶暴でも向かってくるわけがない」
すると長谷部が押し殺したようなかすれ声を出した。
「おまえは頭のネジが外れた人間を見たことなんてねえだろう。ああいう手合いは、相手がだれだろうがかかってくるんだ」
「それはおっさんの想像だよね」
「こっちは実際に見てんだよ! 銃をかまえたおまわりにだって躊躇なく向かっていくんだ! きっとあの女は何人も殺してるぞ。人の命なんてなんとも思ってねえ。恐怖心なんてもんがこれっぽっちもねえんだよ!」
わたしはぞっとし、大きな身震いが起きた。陸斗も赤ん坊を抱いたまま固まり、千代子は嗚咽を殺しながらむせび泣いている。ではどうすることが正解なのか? 必死に答えを導き出そうとしても、頭のなかが上滑りして考えがまったくまとまらない。ぐずる赤ん坊に翻弄されて恐怖に苛まれているとき、雄叫びのようなものが聞こえて四人は一斉に体を震わせた。森の入り口から女がぬっと姿を現し、手に持ったスマートフォンに怒鳴り声をぶつけている。
「だからいねえんだって! 聞こえてんのか! あのガキがいねえんだよ!」
女の怒声に叩き起こされたカラスたちが次々と飛び立ち、わたしたちの乗るハイエースの屋根に木の葉がばらばらと落ちてくる。千代子が肩を震わせて声を上げそうなのを見て、長谷部は素早く口を手で塞いだ。
「もしもし? だから、犬かなんかの動物が持ってったんだろ! そうに決まってる! もしもーし! くそっ! マジで電波がゴミだな!」
女は乱杭歯を剝き出しにして足許の枯れ葉を蹴散らし、ポケットから出した煙草にライターで火を点けた。ぼうっと浮かび上がる顔はまさしく鬼だ。腫れぼったい一重の細い目が吊り上がり、色の抜けた長い髪は傷んで束になっている。何がいるかもわからない真っ暗な森を怖がる素振りのない姿は、長谷部が語った「頭のネジが外れている」としか言いようがなかった。
そのとき、赤ん坊が弱々しい声を上げて背筋が凍りついた。煙草をくわえた女がぴくりと反応し、じっと動きを止めているのがわかる。わたしは陸斗が抱きながら揺すっている赤ん坊に顔を近づけ、むりやり笑みらしきものを作った。トートバッグのポケットからアパートの鍵を引っ張り出す。
「い、いい子だね。ほら、これは何かな。うさぎさんがついてるよ。か、かわいいねえ。ふ、ふわふわの尻尾がついてるねえ」
わたしは小声でたどたどしくあやしながら、キーホルダーのマスコットを赤ん坊の顔の前で揺らした。しかし乳児は見向きもせず、顔を真っ赤にして声を上げた。
「ほ、ほら、泣かないで、お願いだから。どうしてほしいの、な、泣かないでよ」
わたしのほうが涙ぐみながら必死にあやし、頭を低くして女の方へ目をやった。あいかわらず動きを止めており、一瞬だけ聞こえた声の正体を探ろうと耳をそばだてている。しかし夜空で鳴きわめいているカラスや木々のざわめきが壁となり、聞こえた場所を特定するにはいたらなかった。
「おい、後ろに段ボール箱があるだろ。今だけ赤ん坊をその中へ入れろ」
長谷部が流れる汗を払いながら言ったが、陸斗がすぐ首を横に振った。
「こっから手を伸ばしても届かない」
「いいからやれ。赤ん坊の口を手で塞ぐわけにはいかねえんだ。少しでも声を遮らねえと……」
その言葉の途中で、千代子が息を吸い込みながらおかしな声を発した。少しだけ顔を上げると、女が空き地をうろうろと歩きまわっているのが目に飛び込んできた。そしてあろうことか、わたしたちがいる桜の大木のほうへ向かってくるではないか。
四人は一層頭を下げて、陸斗は赤ん坊の上に覆いかぶさった。が、忙しない泣き声は止まらず、音を遮る手段がない。このままでは見つかる。だれもがそう思ったとき、長谷部がドアの取っ手に手をかけたのが目に入った。女にドアをぶつけて不意打ちをくらわせるつもりだ。砂利を踏む足音がすぐそこまできている。心拍数が暴走して吐き気が込み上げた。汗みずくの長谷部がドアを開けるタイミングを計っているとき、急に騒がしい音楽が鳴り響いてわたしは思わず声を出しそうになった。
わたしは両手でぎゅっと口を押さえ、少しだけ顔を上げて外の様子を窺った。女は立ち止まってジーンズのポケットからスマートフォンを抜いており、画面に目を落として舌打ちをしている。今の音楽は着信音だったらしい。女は短くなった煙草を無造作に吐き出し、電話を耳に当てた。
「何? またすぐ切れるって。マジで疲れたからもう帰るわ。どうせ動物に喰われて骨も残んないよ。今回は諦めろっつっといて」
すぐそこで通話している女は、新しい煙草をくわえて火を点けた。
「あ? だからもうやだって。今回ばっかりは割に合わない。話が二転三転しすぎだろ。つうか声が途切れて何言ってっかわかんねえんだけど。もう切るわ」
女は盛大に息を吐き出し、踵を返そうとした。わたしは汗みずくになりながらも鞄のポケットからスマートフォンを抜き、フラッシュがオフになっていることを確認してから何度かシャッターを切った。それと同時に、女は車のほうへ歩きはじめた。
「だから、聞こえねえんだって。電波が入るとこまで山を下りるしかない。もしもし?」
通話が切断されたらしいスマートフォンを尻ポケットに戻した女は、「だりい」と何度も毒づきながら荒々しく車に乗り込んだ。そしてとんでもない速度でバックし、方向転換をしてから急加速で走り去っていく。とたんにみな力が抜けたようにうなだれて息を吐き出し、わたしはむせて長々と咳き込んだ。
しばらくはだれも口を利かず、車内には赤ん坊がぐずる声しか聞こえなくなった。極度の緊張のせいで思考停止状態だ。身をよじって泣いている赤ん坊を見つめていると、陸斗がぽつりと言った。
「もう警察に通報するしかない」
その言葉にみなは無反応だったけれども、それ以外にできることがないのは百も承知だった。こんな小さな赤ん坊を夜の森に捨てた人間たちがおり、あまつさえ確実に殺すために戻ってきた。もう自分たちの手には負えない。
重苦しい空気のなか、助手席から千代子が振り返った。化粧が落ちて蒼褪めた顔には深いシワが目立ち、ここ数時間で一気に老け込んだ印象だ。千代子は一向に泣き止まない赤ん坊を覗き込み、そして手を出してきた。
「ちょっとあたしに貸してみな。赤ん坊ってのは抱き方ひとつで機嫌がよくも悪くもなるんだよ」
陸斗は首の据わっていない赤ん坊を慎重に抱え直し、千代子の腕にそっとゆだねた。老女はたちまち表情を緩め、泣き通しの赤ん坊と目を合わせた。
「いったいどうしたんだい? 虫の居所が悪いんだねえ」
そう言いながら、おくるみの前を開けて紙おむつを手で触る。
「ああ、おむつが濡れてて気持ち悪かったんだな。かわいそうに。すぐ取っ替えてあげたいとこだけど、おむつに使えるようなボロはないもんな」
「タオルは?」
わたしは鞄の中から大きめのタオルを取り出した。
「何があるかわかんないから、タオルとハンカチを多めに持ってきたの。あとこれ」
ウィルス用の除菌剤も手渡した。千代子は頷きながらスプレーした消毒液を手になすりつけ、赤ん坊を座席に寝かせて手早く紙おむつを取った。ティッシュでお尻を拭いてから素早くタオルをあてがっていく。さすがに手慣れており、安心して見ていられた。
「あんたすっと鼻筋が通ってるし、きっとものすごい美男子になるねえ」
千代子はおくるみを整えてから赤ん坊を縦に抱き、背中をぽんぽんと叩きながら低い声色で語りかける。そこには嫉妬深くて二面性のある老人の姿はなく、目を奪われるほどの慈しみしかない。とても静かで優しい光景は、荒んだ自分の心に毒のように沁み込んだ。
何をやっても泣き止まなかった赤ん坊はうとうととしはじめ、千代子は体を揺らしながらさらに深い眠りへといざなっている。それを見ていたわたしまで眠気が押し寄せ、長谷部は大口を開けてあくびをしていた。みながひとときの平穏をむさぼっていたが、陸斗の声で我に返ることになった。
「さっきの女、電波が入るところまで行くって言ってた」
「確かに」
「今度は仲間引き連れて戻ってくるかも」
その言葉と同時に現実に引き戻された。
「あの女はこいつをリュックに入れて森に置いてきただけ。でも女に指示してるやつは、たぶん確実に殺せって命令してる」
陸斗は左目に手を当てながら憑かれたように喋り続けた。
「人殺しを商売にしてる連中がかかわってる。割に合わないと言ってた」
確かにそうだ。さっきの女は森をひとりで捜しまわることを断固拒否するだろうから、頭数をそろえて舞い戻ってくる可能性はおおいにある。
わたしは運転席の長谷部に言った。
「長谷部さん、すぐ車を出して。とにかくエンジンをかけて」
長谷部は真顔でハイエースのイグニッションキーをひねった。
(つづく)
作品紹介
四日間家族
著者 川瀬 七緒
定価: 1,870円(本体1,700円+税)
発売日:2023年03月01日
誘拐犯に仕立て上げられた自殺志願者たちの運命は。ノンストップ犯罪小説!
自殺を決意した夏美は、ネットで繋がった同じ望みを持つ三人と車で山へ向かう。夜更け、車中で練炭に着火しようとした時、森の奥から赤ん坊の泣き声が。「最後の人助け」として一時的に赤ん坊を保護した四人。しかし赤ん坊の母親を名乗る女性がSNSに投稿した動画によって、連れ去り犯の汚名を着せられ、炎上騒動に発展、追われることに――。暴走する正義から逃れ、四人が辿り着く真相とは。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322210001445/
amazonページはこちら